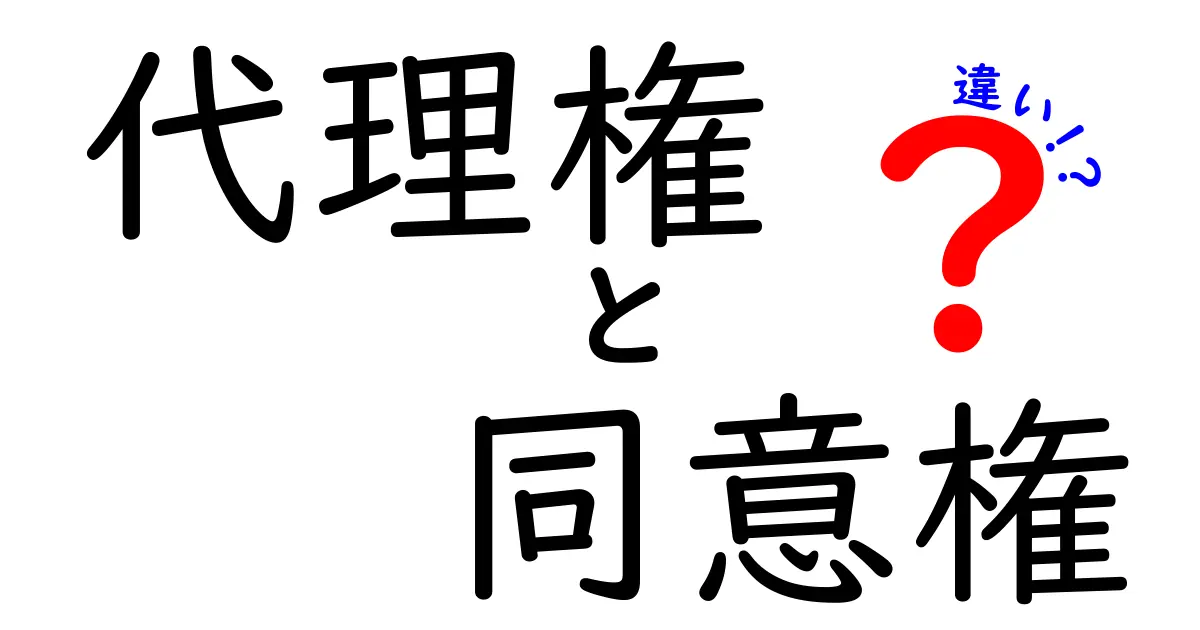

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
代理権と同意権の基本を押さえる
代理権とは、ある人が別の人の名において法律行為を行う権限のことです。たとえば、会社の社員が社長の代理として契約を結ぶとき、この権限が働きます。代理権は契約書を取り交わしたり、物を受け渡したり、法的な申請を代行したりするなど、具体的な行為の範囲を定められています。代理権には「事前に決められた範囲内で行為を行う」そして「その範囲を超える場合には別途同意が必要」というルールがしばしばあります。代理権を持つ人が被代理人の意思と異なる行為を行おうとすると、その行為は原則として無効になる可能性が高く、被代理人はその責任を負いません。これを理解するには、日常生活の例が役立ちます。たとえば、親が未成年の子どもに代わって美術品を購入する場合、親には通常代理権があり、子どもに代わって契約を結ぶことができます。もちろん、未成年者保護の観点から、契約の一部には同意権の確認が必要です。ここでいう同意権とは、相手の提案や契約の成立に対して「よいか/いけないか」を判断する力です。親が相談に応じる、あるいは法的代理人が定める代理権の範囲内での判断を指します。結果として、代理権は“行為を実行する力”であり、同意権は“その実行を許可する力”だと整理すると理解しやすいです。
この区別が重要なのは、実際のトラブルを避けるときにも役立つからです。代理権の範囲を超えた行為は法的責任の問題を引き起こす可能性があり、同意権を持つ人が存在しなければ意思決定自体が進みません。したがって、契約の場面では「誰が代理権を持つのか」「その代理権の範囲はどこまでか」「同意権を誰が有しているのか」を明確にしておくことが、後の混乱を防ぐ鉄則になります。
代理権と同意権の使い分けと具体例
このセクションでは具体的な場面を想定して、代理権と同意権がどう働くかを見ていきます。まずビジネスの場面。会社の取引では、社長が直接契約を結ぶ時間が取れない場合、法的に有効な代理権を持つ役員が社長を代表して契約します。ここで重要なのは「代理権の範囲」が明確であること。契約の金額、取引内容、期間など、事前に定められていなければ後で紛争の原因になります。次に家庭内の場面。未成年の子どもが重大な医療行為を受ける場合、医療行為には同意権を持つ保護者の同意が必要です。医師は保護者の同意があることを前提に治療を進めますが、保護者が迷っているときは専門家の説明と本人の意思を照らし合わせて判断します。学校行事の計画でも、代表者が提案を採択する際に「同意権を持つ人の承認」が必要になることがあります。ここで注意したい点は、代理権と同意権が別物であるため、誰がどの権限を持つかを明確にしておくことです。
最後に、覚えておくべきポイントを整理します。代理権は行為を実行する力、同意権はその行為を許可する力という基本を軸に、場面ごとに権限の所在を確認しましょう。もし誰かが権限を勝手に超えると、後日法的責任や契約の取り消しなどのトラブルが生じる可能性があります。本文を読んだ後、あなたが生活の中で遭遇する場面を思い浮かべ、誰が代理権を持ち、誰が同意権を持つのかをノートに整理してみてください。
この整理こそが、複雑な判断をスムーズに進めるコツです。
ねえ、代理権って友だちの代わりに先生に伝えものを渡すみたいなものだよね。先生と約束を結ぶ権限が代理権。つまり、私が言葉を代わりに発することで、相手は私ではなく“相手”と契約していることになる。リアルな場面で考えると、プリントを先生に提出するよう頼まれたとき、あなたが担任の許可を代わりに得る権限を持つことになる。ここでポイントは“範囲と責任”で、代理権の範囲を超えて行為をすると、元の人に迷惑がかかることだよ。こんな感じで、代理権は“動く力”、同意権は“合意を出す力”とセットで覚えると混乱しづらい。





















