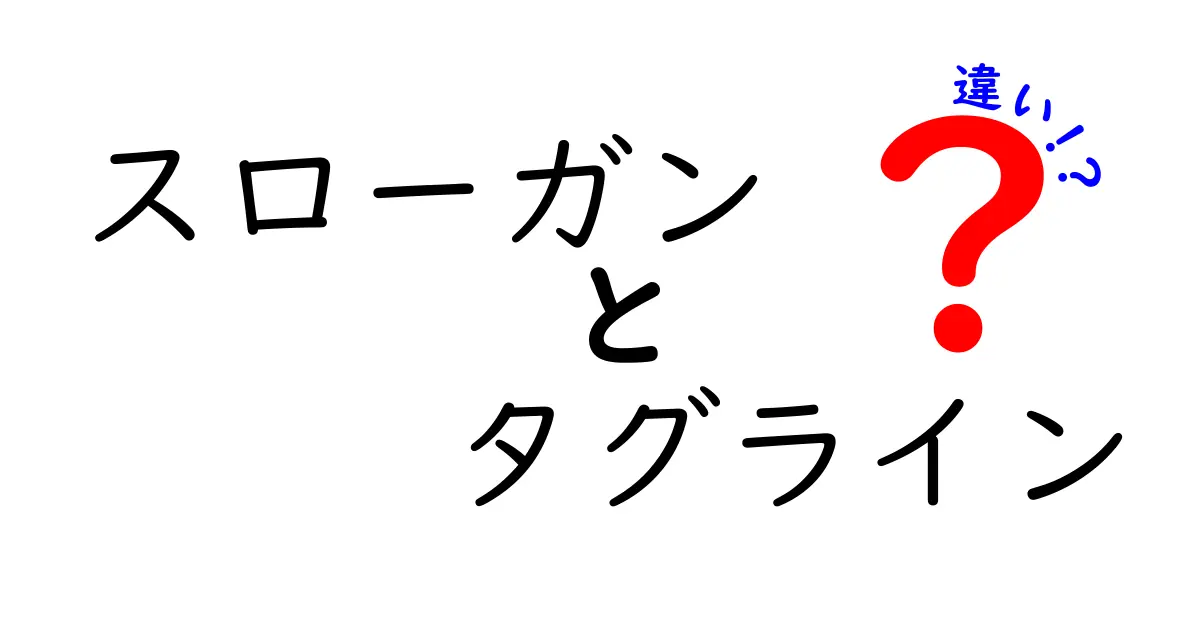

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
スローガンとタグラインの基本を理解する
スローガンとは企業や商品が伝えたい大きな意思や価値を、長めのフレーズで表す言葉のことです。長くても記憶に残るフレーズで、キャンペーン期間中に繰り返し使われることが多いです。対してタグラインはブランド全体を象徴する短くて覚えやすい一文です。一言でブランドを思い出させる力があり、名刺・ロゴ・Webのヘッダーなど、いつでも視界に入る場所で活躍します。
この2つは似ているようで役割が異なります。スローガンはムーブメントを作る力、タグラインはブランドを象徴する看板のような役割と考えると理解しやすいです。用途が違えば言い回しの長さやトーンも変わります。スローガンは情熱的・鼓舞的な語り口になることが多く、タグラインは端的で冷静な印象を与えることが多いです。
例を見てみましょう。スローガンの例として「より良い明日をつくる」というような未来志向の表現は、キャンペーンの旗印として力を持ちます。タグラインの例として「Just Do It」や「Think Different」は、企業のコア価値を一瞬で伝える短い言葉です。もちろん国や文化によって適切さは変わりますが、考え方としてはこの違いを押さえるだけで、文章の切り口と使い道が見えてきます。
この違いを理解していれば、広告だけでなくWeb、包装、動画、イベントなど、さまざまな媒体で一貫性のあるメッセージを作りやすくなります。
特に初心者の方には、まず「スローガンはキャンペーンの旗印、タグラインはブランドの顔」という基本を覚えると、作業の優先順位が見えてきます。
スローガンとタグラインの違いを具体例で見る
まず、ここでの目的は、覚えやすさ、伝える場の長さ、継続性、ブランドの一貫性という4つの要素です。スローガンは「パワフルに広がる言葉」を使い、イベントや広告の熱量を高めます。タグラインは「ブランド自体」を象徴する短い文として、長い年月にわたって使われることが多いです。
以下の表は、違いを一目で理解するための簡易比較です。
使い分けのポイントが見えやすくなります。
このように、スローガンとタグラインは異なる役割と適用期間を持ちます。言い回しの工夫次第で、読者が感じる印象は大きく変わります。企業のブランド戦略を設計する際には、まずこの2つの役割を混同せず、使い分けることが大切です。
また、若い読者や初心者の方には、それぞれの用語を混ぜずに使い分けを意識することをおすすめします。
使い分けの実務的なポイント
実務で迷ったときの判断軸をいくつか挙げます。ブランドの一貫性を重視するならタグラインを核に据えます。キャンペーンを強化したい時にはスローガンを前面に出して、製品の魅力を情熱的に訴えます。さらに、マーケティング資料の統一感を保つには、まず社内で「タグラインはブランドの顔、スローガンはキャンペーンの旗印」というルールを共有します。これにより、広告だけでなく、Web、包装、動画、イベントといった多様な媒体で整合性を保つことができます。
注意:
スローガンとタグラインを混同してしまうと、受け手に混乱を与え、ブランドの信頼性が低下するおそれがあります。必ず役割と長さ、用途を事前に決め、必要に応じて専門家の意見を取り入れましょう。
言葉の力は強力ですが、適切な場と適切な表現を選ぶことが成功の鍵です。
結論として、スローガンはキャンペーンの炎を灯す熱い言葉、タグラインはブランドの顔として長く支える冷静な言葉と覚えておくと良いでしょう。
昨日、教室で友達とスローガンとタグラインの話をしていて、私は『短い方が覚えやすいし、ブランドの顔として長く使える』派でした。一方の友だちは『キャンペーンでは長めのスローガンが記憶に残るはずだ』と言い、二人で熱く議論しました。結局、言葉の力にはタイミングが大切だという結論に落ち着きました。私たちが学んだのは、同じ意味を伝える言葉でも、使う場と長さによって伝わり方が全く違うということ。今後、授業の発表資料を作るときには、それぞれの役割を分けて設計し、スローガンはキャンペーンの火をつける旗印、タグラインはブランドの顔として長く支える柱として使い分けたいと考えています。もし友人と再びこの話題になるなら、現場の例を交えながら、短い表現でどう印象を変えられるかを雑談形式で深掘りしてみたいですね。





















