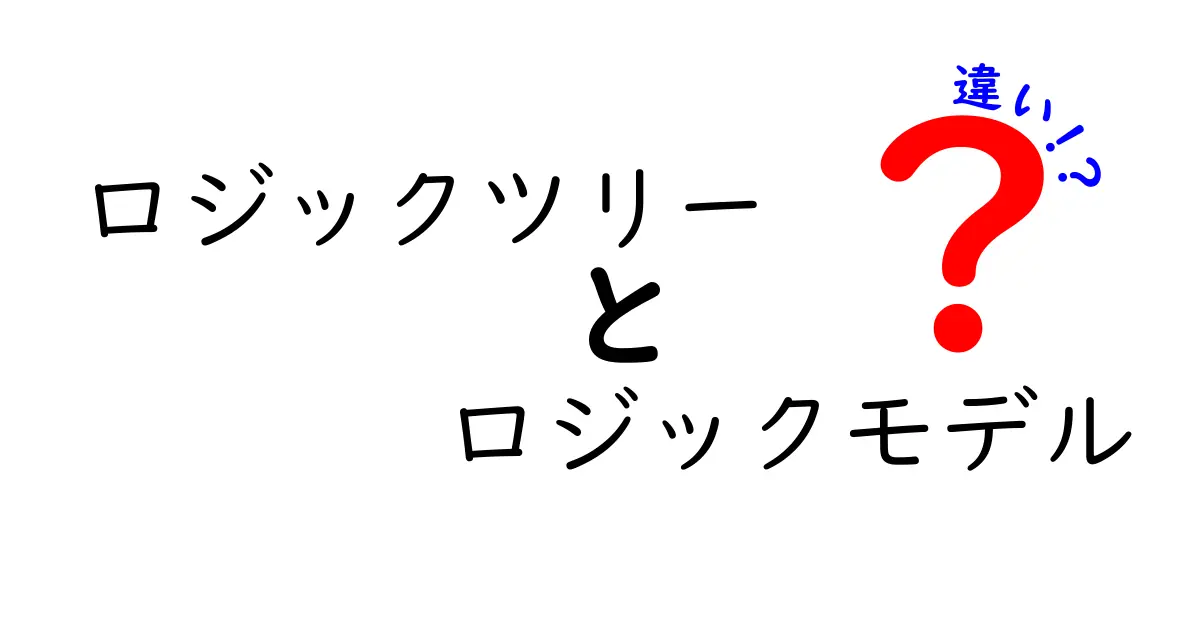

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ロジックツリーとロジックモデルの違いを知るための完全ガイド
このガイドでは、ビジネスや教育の現場でよく使われる「ロジックツリー」と「ロジックモデル」の違いを、中学生にも伝わるやさしい日本語で解説します。まず結論から言うと、ロジックツリーは問題を分解して原因や要因をつかむ道具、ロジックモデルは活動と成果をつなぐ因果関係を示す設計図です。これらは似ていますが、目的と使い方が異なります。この記事では、両者の基本的な仕組み、作り方の手順、実務での使い分け方、そして実際の例を詳しく紹介します。読み進めると、問題解決の場面でどちらを使うべきかが自然と分かるようになります。
それぞれの特徴を一言でまとめると、ロジックツリーは「分解と原因追究の地図」で、ロジックモデルは「入力から成果までの道筋を描く実行計画」です。
この差を押さえることが、あなたの企画や分析を一段と強くします。では、具体的な説明に入ります。
ロジックツリーとは何か
ロジックツリーは複雑な問題を“木の形”に分割していく思考の道具です。まず大きな問題をトップに置き、次にその原因や要素を複数の枝として分解します。枝分かれを繰り返すと、最後には解決の糸口となる要因が見えるようになります。作り方のコツは、大きな問題を「もし〜ならば」という仮説で分解し、各分岐を具体的な要因へと落とすことです。例えば「売上が伸びない」という問題を扱う場合、「市場要因」「製品要因」「顧客要因」の3つに分け、それぞれをさらに細かく掘り下げます。こうすると、誰が、いつ、どのように影響しているのかが見える化され、原因の連鎖を追いやすくなります。ロジックツリーは、議論のすれ違いを減らし、共通の理解をつくるのに特に役立ちます。
実務ではホワイトボードに描く、あるいはデジタルツールで図として保存することが多く、組織全体で共有する際にも理解が速く進みます。
ロジックモデルとは何か
一方、ロジックモデルは「入力(リソース)⇄活動(プロセス)⇄アウトプット(成果)⇄アウトカム(影響)」といった因果関係を全体として図にする設計図のようなものです。これを作る目的は、プログラムや施策がどんな順番で動き、どんな成果が生まれるのかを事前に描くことです。まずは使える資源や人、時間といった入力を整理し、それを活かして何を行うのか(活動)、その結果何を出すのか(アウトプット)、最終的にどんな良い状態(アウトカム)を期待するのかを順序立てて書き出します。ロジックモデルは評価設計と深く結びついており、評価指標をどう設定するか、成果をどう測るかといった問いに答えを用意します。教育プログラムや地域活性化の施策など、結果を可視化したい場面で特に力を発揮します。
また、関係者へ「何を、なぜ、どうして行うのか」を説明する際にも、因果関係が明確で理解しやすいという利点があります。
違いの要点と使い分けのコツ
ここまでを踏まえると、両者の最も大きな違いは目的と視点です。ロジックツリーは問題の原因を特定し、解決策を具体化する「分析の道具」です。対してロジックモデルは施策の設計図であり、誰が、いつ、何をするのかを計画し、成果を測る仕組みを作ります。使い分けのコツとしては、問題の段階に応じて使い分けることが大切です。問題の原因を洗い出して原因関係を整理したいときはロジックツリー、施策の全体像と評価の枠組みを作りたいときはロジックモデルを使います。実務で両者を組み合わせると効果が高く、最初にロジックツリーで問題を均一に分解した後、分解した要素をロジックモデルの中で具体的な活動に結びつけていくと、説得力のある計画と評価設計が同時に整います。最後に一つだけ覚えておくべきポイントは、どちらを先に使っても構わないが、最終的には「現状を変えるための具体的な行動」と「その行動の評価基準」を明確にすることが重要だということです。これを意識するだけで、資料作成の時間を短縮し、関係者との合意形成を加速させる力になります。
ある日、友達とカフェでロジックツリーとロジックモデルの話をしていた。私はツリーの分解力が好きで、友達はモデルの全体像の設計力に惹かれていた。結局のところ、ツリーで問題を「どこが悪いのか」を深掘りし、モデルで「どう実行して成果を測るのか」を計画する、この二つを組み合わせるのが最強だと気付いた。ツリーは原因追究の道具、モデルは成果達成の設計図。だから、現場ではまずツリーで現状を整理し、それを元にモデルを作って実行と評価の両方を整えると、伝えたいことがずれて伝わるリスクを減らせる。次の課題にもきっと役立つはずだ。
そんな雑談が示してくれるのは、いかに実務で使い分けが自然にできるかという点だ。さあ、あなたも日常の課題に両方の視点を取り入れてみよう。





















