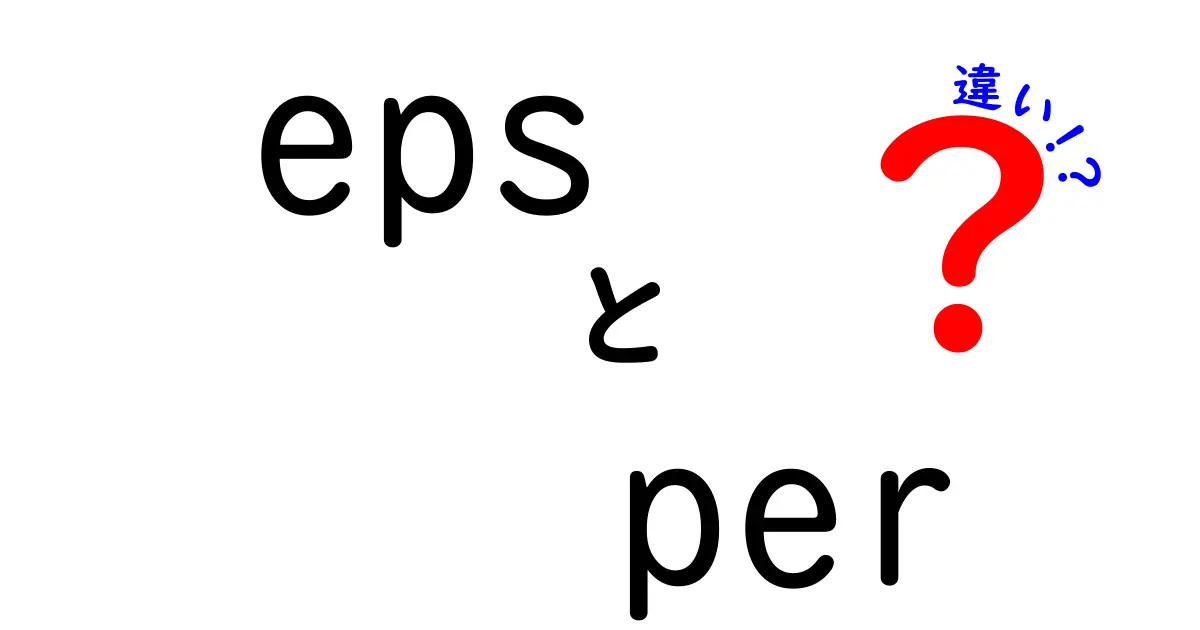

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
EPSとPERの違いを理解する基本
株式投資を始めたばかりの人にとって、EPSとPERは似たような言葉に見えますが、実は役割がまったく違います。EPSは企業の内部的な利益の大きさを1株あたりで示す指標であり、PERは市場がその利益をどの程度評価して株価を決めているかを示す指標です。これを混同すると、株を買うべきかどうかの判断が鈍ってしまいます。
EPSは企業の“本当のお金の動き”を映す鏡のようなものです。会社が1年間でどれだけ純利益を稼いだのか、そしてそれを何株に分けているのかを知ることで、株主に対してどれだけのリターンが期待できるかを想像できます。PERはその利益を現在の株価と結びつけ、株価が“その利益の何倍に相当するか”を教えてくれます。PERが高いと市場がその企業の成長を強く期待していることを意味する場合が多く、低い場合は市場の期待が低いことを示します。ただし、EPSが高くても株価が高騰しているだけで、実際の投資妙味が少ない場合もあるので、EPSとPERを併せて見るのがポイントです。次のセクションでは、EPSとPERそれぞれの特徴を詳しく解説します。
重要なポイントは以下のとおりです。
・EPSは株主に対する“実際の利益”を示す指標です。
・PERは株価の割安感を測る市場の目安であり、成長期待が高い企業ほど高くなる傾向があります。
・EPSとPERは単独では判断しにくく、業界比較や財務健全性、キャッシュフロー、配当政策などと組み合わせて判断します。
この2つは“相互補完的な関係”にあり、両方を見なければ、企業の価値を正しく評価することは難しいのです。
EPSとは何か:一株あたりの利益の考え方
EPSは Earnings Per Share の頭文字を取ったもので、日本語では「一株当たり利益」と訳されます。会社が一定期間に稼いだ純利益を、発行済株式数で割って算出します。
この指標は「会社が株主にどれだけの利益を還元できているか」を、1株あたりの数字で示してくれるので、株価の比較がしやすいのが特徴です。
ただしEPSは会計上の利益の取り扱い方や発行株式数の変動で大きく動くことがあります。
つまり、EPSが高くても株価が高騰しているだけで、実際の投資妙味が少ない場合もあるので、PERと併せて見るのがポイントです。
以下の例も参考にしてください。
例1:A社のEPSが1株あたり100円、発行株式数が100万株の場合、EPSは100円です。
例2:B社は株式の分割で発行株式数が増えた後、EPSが下がったように見えますが、純利益自体は増えているケースがあります。こうした変動にも注意が必要です。
PERとは何か:株価と利益の関係を測る指標
PERは Price Earnings Ratio の略で、日本語では「株価収益率」と呼ばれます。株価を1株あたりの利益(EPS)で割った値で、株価が“今の企業の利益に対して高いのか安いのか”を示す目安です。
計算式は「PER = 株価 ÷ EPS」です。PERが低いほど株価が利益に対して安く、の価値が高い可能性があると考えられます。ただし、低いPERが必ずしも良い投資を意味するわけではなく、成長性の低い企業や景気が悪い業界ではPERが低くても割安とは限りません。
PERを見て重要なのは時系列の変化と業界比較です。同じ業界の企業と比較することで、相対的な評価がしやすくなります。
さらに、PERは市場の期待を反映する指標でもあるため、成長が見込める企業は高いPERを正当化するケースが多いです。
次に、EPSとPERの「使い分け」を具体的に紹介します。
EPSとPERの実務的な使い方と注意点
実務では、EPSとPERを一緒に使って企業の実力と株価のバランスを見ます。
まずは企業の成長性を評価する際にはEPSの推移を追うことが大切です。年々EPSが増えていれば、純利益が株主価値として増えている可能性が高いです。
次に株価が妥当かどうかを判断する際にはPERを用いることで、同業他社と比較でき、過大評価か過小評価かを判断できます。
ただし、PERだけに頼ると危険です。業界の成長性、企業の財務健全性、キャッシュフロー、配当方針など、複数の指標と組み合わせて判断することが重要です。
このように、EPSとPERは互いを補完する関係にあります。適切に使い分けることで、株式投資の判断材料を増やすことができます。
表で見る主な違いと使い方
以下の表は、EPSとPERの違いを整理するのに役立ちます。
指標 意味 計算方法 EPS 一株あたりの利益。株主価値の“実力”を示す指標。 純利益 ÷ 発行済株式数 PER 株価が利益に対して高いか安いかの目安。市場評価の相対指標。 株価 ÷ EPS
ある日、友だちとカフェで株の話をしていたとき、彼が『EPSが高いと株価も上がるんだよね?』と得意げに話してきました。私はちょっと待ってと笑い、EPSは“一株あたりの利益”の数字だが、それだけが株の価値を決めるわけではないと説明しました。EPSが高くても、株式の発行数が増えれば一株あたりの利益は薄まることがあるし、利益の質(特別利益の有無や非現金項目の影響)にも左右されます。だからEPSだけを追いかけるのは危険です。次にPERの存在を持ち出して、株価がその利益に対して高いのか安いのかを判断する仕組みだと伝えました。彼は少し反省して、決算資料を一緒に読み解く約束をしました。結局大切なのは、EPSとPERをセットで見ること。数字の裏にある“物語”を読み解く力を養えば、株価の動きをより理解できるようになります。





















