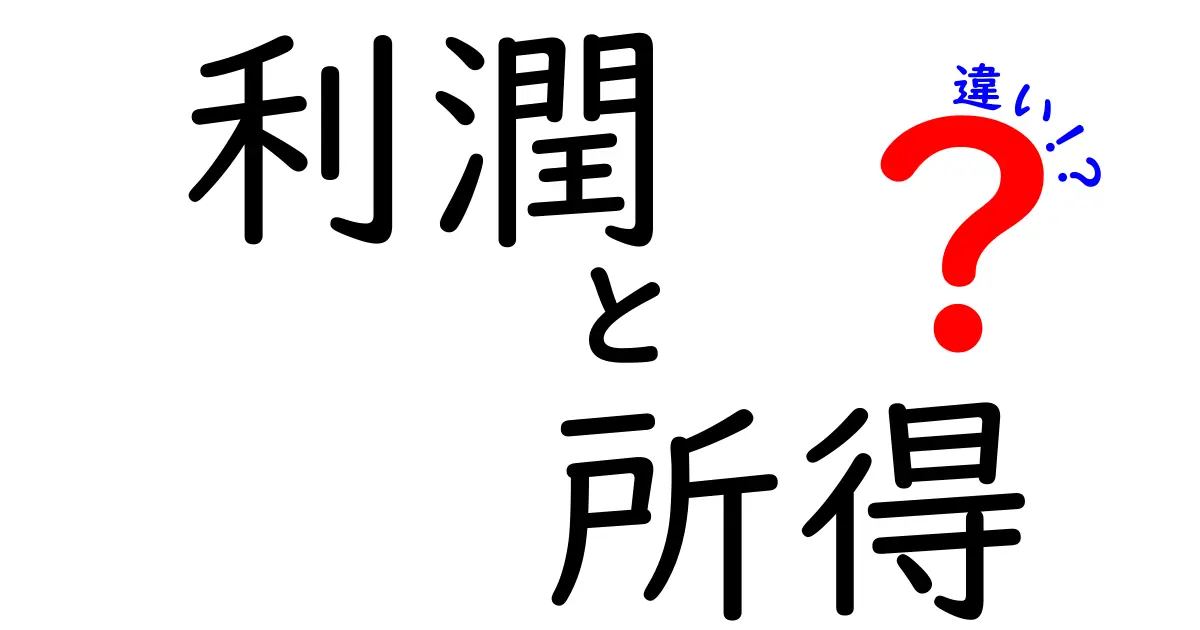

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
利潤と所得の違いを知ろう:基本の基礎
まず基本を押さえましょう。利潤とは、企業や事業が本業で生み出した儲けのことを指します。具体的には売上高から直接費用と間接費用を差し引いた残りの金額です。ここでいう費用には材料費や人件費、家賃、光熱費、広告費、減価償却などさまざまな出費が含まれます。利潤は企業の健全さを示す指標として使われることが多く、税金を払う前の“計算上の利益”と考えると分かりやすいです。例えばアイスクリーム店が1日で売上が1万円、仕入れや人件費などの費用が6千円だった場合、1万円から6千円を引いた3千円が利潤です。ここから税金やローンの支払いが引かれることがあります。つまり利潤はあくまで事業の成果を表す数値であり、必ずしもオーナーが受け取る“お金”をそのまま意味しません。
一方、所得は“個人が手にするお金の総称”です。給料やアルバイトの収入、事業を自分で行う場合の利益の一部など、個人の生活に使えるお金を含みます。所得にはさまざまな形態があり、利潤の中から個人に渡る分だけが所得となります。所得には税金や社会保険料がかかることがあり、年末調整や確定申告で変わることもあります。したがって利潤と所得は同じ金額を指すものではなく、利潤は企業の成果、所得は個人の生活費を支えるお金という風に覚えると混乱しにくいです。
この二つの違いを図解で見ると理解が深まります。下の表を見ながら、売上高や費用、利潤の関係を頭の中で整理しておくとよいでしょう。
ポイントを整理すると、利潤は企業の結果、所得は個人の生活費という別の視点でとらえることが大切です。
1) 利潤とは何か
利潤の定義をもう一度丁寧に整理します。利潤は売上から必要な費用を引いた金額で、企業の本業がどれだけ効率よくお金を生み出しているかを示します。ここでの“必要な費用”には原材料費、労働費、賃貸料、光熱費、広告費、減価償却、税金の前のちょっとした費用も含まれます。実務では会計上の粗利や営業利益、経常利益など、いくつかの指標があり、目的に応じて使い分けます。利潤を高く保つには、売上を増やすだけでなく、費用を抑える工夫、在庫の回転を早くする工夫、無駄な広告費を見直すことも大切です。日常の学校生活に例えると、部活動の「収支」を安定させる作業と似ています。もし売上が増えても費用が増えすぎれば利潤は減ってしまいます。だからこそ効率よくお金を回す仕組みづくりが大切なのです。
さらに実務上は、粗利、営業利益、経常利益など複数の指標名が出てきますが、基本的な考え方は同じです。売上高から費用を引くと利潤が残り、そこから税金や借入金の利息などを差し引く前の“純粋な儲け”として扱われることが多いです。ここをしっかり押さえておくと、ニュースで決算を見たときにも話の筋をつかみやすくなります。
また、企業の形態によって「利潤の見え方」が少し変わる点も覚えておくと良いです。個人事業主と法人では、税金の計算の考え方が異なり、同じ売上高でも手元に残る金額は違います。つまり利潤は企業の「お金がどれだけ残ったか」を示す指標であり、所得は個人の「生活に使えるお金」を示す指標という二つの軸で捉えるのが正解です。
この表を見れば、用語ごとの意味の違いが視覚的にも分かるようになります。
大切なのは、利潤と所得の関係を「企業の結果」と「個人の生活費」という二つの軸で捉えることです。
次のセクションでは、実生活で役立つ考え方のコツをいくつか紹介します。
2) 所得とは何か
所得は個人が手にするお金の総称です。給与所得、事業所得、配当所得、雑所得などさまざまな形があり、生活のために使えるお金として実際に手元に入る金額は所得控除や税金の影響を受けます。パートタイムの給料や自分で小さなビジネスをして得た利益は、すべて所得として扱われ、税務上の扱いが決まります。ここで重要なのは、所得は「個人の生活を支えるお金」であって、企業の利潤そのものではない点です。たとえば夏休みに友だちとボランティアでイベントを開き、収益が出ても、それを個人の生活費として使えば所得となりますが、企業の利潤としての話とは別の枠組みで考えます。
所得の計算では、控除や税率がかかわってくるため、同じ給与額でも手取りが変わることがあります。学校の授業だけだと「儲け」という感覚が強い利潤と混同しがちですが、所得は「生活に使えるお金」を指す点で別物です。現実の家計管理や学校の部活の費用分担を考えると、利益がどのくらい出ても個人の所得がどうなるかは別の問題として考える癖がつくと理解が進みます。
このように、利潤と所得を別々の視点で見ると、ニュースで見る企業の決算説明や税制の話題がずいぶん分かりやすくなります。理解のコツは、売上高から費用を引く算式をしっかり覚え、所得は個人の生活費としての実際の受け取り額であることを意識することです。
3) 実際の例で比べてみよう
ある会社がある月に売上高が100万円、原材料費が40万円、従業員の人件費が25万円、家賃や光熱費が10万円、広告費が5万円、その他の経費が5万円かかったとします。ここまでの費用は85万円なので、利潤は15万円です。次にオーナーがこの会社の代表として自分に給料を月20万円支払うとします。すると個人の所得としては20万円が生まれます。この場合、商売の利潤は15万円ですが、オーナーの所得は20万円になります。このように利潤と所得は別物であり、税金の課し方も変わってきます。売上高から費用を引くと利潤、個人の手取りとして使えるのは所得という別の概念です。
この考え方を押さえておくと、ニュースや授業で「儲け」について語られるときに、どの部分を指しているのかを見分けやすくなります。
次に、この日のまとめとして利潤と所得の関係を整理します。下の表は覚えやすい要点を並べたものです。
| 項目 | 意味 | 覚え方のコツ |
|---|---|---|
| 利潤 | 売上高から費用を引いた後の企業の儲け | 企業の成果を示す指標 |
| 所得 | 個人が使えるお金として手元にはいる金額 | 個人の生活費の元になる金額 |
| 売上高 | 商品の総販売額 | 規模感を測る指標 |
| 費用 | 事業活動にかかる出費 | どこでお金を使っているかを把握 |
この表を見れば、利潤と所得の違いが一目で分かります。
最終的には、利潤が企業の「結果」、所得が個人の「生活費」という別の枠組みだと理解しておくことが大切です。
昨日、友だちとカフェでこんな話をしたんだ。利潤と所得の違いって、なんとなくは知っていても実感が湧かないよね。僕はアルバイト先で働いているけれど、その給料は所得として入ってくる。ところが友だちはゲーム会社の株を持っていて、株の配当が入るときも所得になる。でも会社の“儲け”である利潤とは別の話。話が進むうちに、利潤が上がるには売上を伸ばすか費用を抑えるか、所得は税制の影響で額が変わることがあると知って、現実的な話だと思った。こういう現実と教科書の区切り方は、学校の勉強にも役立つ気がする。





















