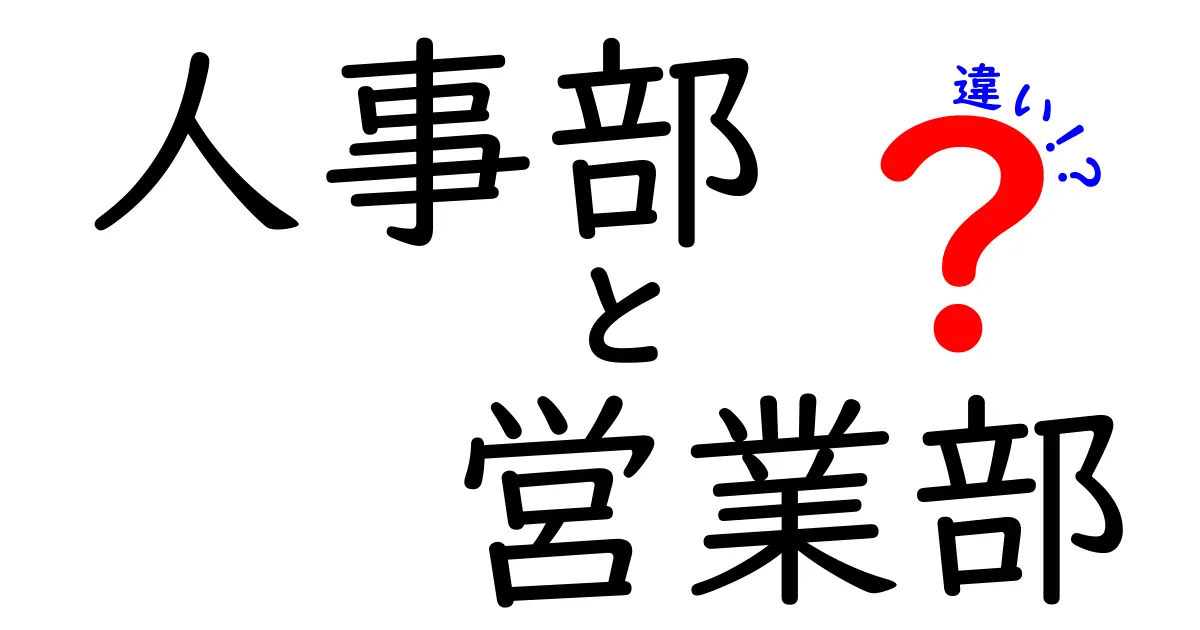

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
人事部と営業部の違いを徹底解説:役割・評価軸・日常のポイント
この章では、企業の中で「人事部」と「営業部」がどんな役割を担い、どんな視点で評価され、日々の業務はどう違うのかを中学生にもわかる言葉で説明します。まず前提として、どちらの部門も「組織を動かす力」を持っていますが、目標と手法が大きく異なります。人事部は社員全体の幸せと成長を支え、営業部は市場と顧客を動かして売上を作り出します。この二つの部門は、組織の“心”と“体”のように相互補完的に機能します。ここを理解することは、就職活動や職場の人間関係をスムーズにする第一歩です。
次に大事なのは、彼らが使う言葉の意味の違いです。人事部は「人材の採用」「教育・研修」「評価・異動・制度設計」などの語彙を中心に使います。一方の営業部は「顧客」「商談」「成約」「売上目標」といった、外部の市場と顧客に向けた語彙を多用します。日々の業務も、社員の成長を支援する制度運用と、顧客の課題を解決して利益を生み出す実務という点で異なります。これらを押さえると、上司や同僚が何を求めているか、何を達成したいのかが見えやすくなります。
最後に、働く人の視点から見た“組織での居場所”の違いについて触れます。人事部は長期的な組織の健康を守る役割であり、従業員全体の満足度やエンゲージメントといった指標を通じて、離職を防ぐことにも関心を持ちます。営業部は短期間の成果を出すプレッシャーを抱えつつも、顧客との信頼を築く力を養います。このような違いを理解しておくと、転職時の適性判断にも役立つでしょう。
1. 目的と評価軸の違い
人事部の目的は「人材の確保・育成・活性化・組織文化の最適化」です。これは社員が長く働きやすい環境を作り、組織全体の力を底上げすることを意味します。評価軸としては、離職率の低下、教育投資の効果、エンゲージメントの向上などが挙げられ、数字だけでなく社員の声や制度の利用状況も重要なデータになります。
対して営業部の目的は「売上を伸ばすこと」と「市場へ積極的にアプローチすること」です。指標は受注件数、成約率、売上目標の達成度など、外部の成果に直結する指標が中心です。日々の業務は商談の準備、顧客リストの管理、提案資料の作成といった実務が多く、数字のプレッシャーと顧客のニーズへの対応が日常の中心になります。
2. 日常業務と関係者の接点
人事部は社員と上司の橋渡し役として“人”の問題を解決します。1on1ミーティングを行い、キャリア設計や研修の案内、福利厚生の説明を丁寧に行います。制度設計や運用は組織の未来を決める大切な仕事であり、管理職や経営層と連携して方針を決める場面が多いです。社員の声を集める仕組みづくりも重要で、アンケートやフィードバックの活用を通じて職場環境を改善します。
営業部は直接的に顧客と接点を持ち、商談の準備・実施・フォローを行います。市場動向を読み解き、提案資料を作成し、価格交渉や条件調整を経て契約へとつなげます。顧客の課題を深掘り、解決策を示すことで信頼を獲得する力が求められます。社内の他部門と連携して、製品の仕様変更や価格戦略を共有し、より良い提案を作り出します。
この表を見れば、どの部門が何を重視しているのかが一目で分かります。人事部は人の育成と組織の健康を守る役割、営業部は市場の機会を捉え売上を作る役割というのが大きな違いです。もちろん、協力し合えば組織全体のパフォーマンスは高まります。例えば、人事部が新人研修のカリキュラムを整え、営業部がその知識を現場の商談で活用する、といった連携が実際の企業ではよく起こります。これを意識して動くと、あなたが所属する部門がどんな価値を生み出しているのかを理解しやすくなります。
この小ネタは“人材育成”についての雑談風解説です。友達同士がカフェでふとした話をしている想定で進めます。A君が言いました。「人材育成って、単に新人に研修を受けさせるだけじゃないよね?」Bさんは笑いながら答えます。「うん、単発の講義だけで終わらせず、長期的なキャリア設計、メンタリング、失敗からの学び、そして組織の価値観の共有まで含むんだ。新しいスキルを教えるだけでなく、成長の機会を作り続ける文化を作ることが本当の育成になるんだよ。」この視座を持つと、どんな仕事でも自分の成長軌道と組織の成長軌道を重ねて考えられるようになります。





















