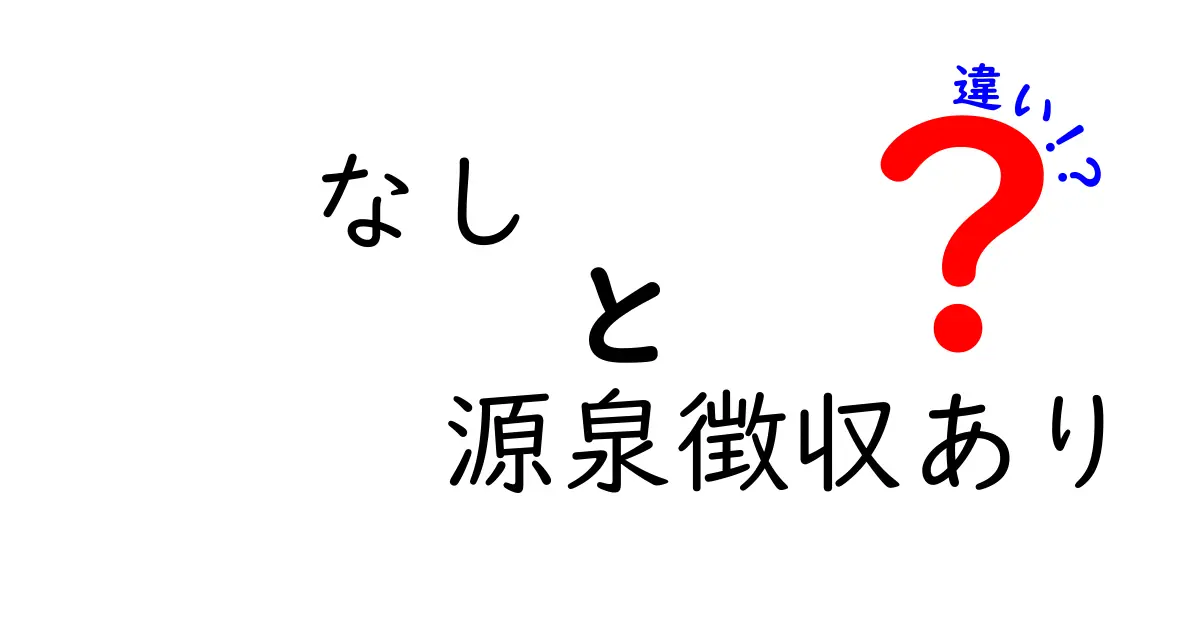

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
なしと源泉徴収ありの違いをざっくり把握
この節では「なし」と「源泉徴収あり」の違いを、給与の扱いを軸に整理します。まずは結論から言うと、なしは自分で税金を計算して納付する必要がある状態、源泉徴収ありは雇用主が給与から税金を天引きしてくれる状態です。税の仕組みは学校の算数とは違い、控除・扶養控除・配偶者控除など複雑ですが、要点だけ覚えれば日常の給料の見かけと実際の手取りがどのように変わるかが分かります。
「なし」は副業(関連記事:在宅で副業!おすすめ3選!【初心者向け】)や特定の所得がある人、または一定の条件を満たす個人事業主などに見られるケースです。所得の合計が増えると、納税額が増え、確定申告の義務が発生することがあります。年末調整の仕組みが働かず、税の計算を自分で行う必要が出てくるため、申告の手間が増え、注意すべき控除や経費の取り扱いも増えます。
一方で「源泉徴収あり」は、雇用契約を結んで給与を受け取る人に多く見られます。雇い主が毎月の給与から所得税を天引きして税務署へ納付します。そのため確定申告が不要になるケースが多く、年末調整で過不足が清算されます。もちろん副業がある場合は別途確定申告が必要になることもあります。ここでのポイントは、実際の手取り額と税金の支払いタイミングが分かりやすく整理される点です。
要点としては、源泉徴収ありの仕組みは「税の納付タイミングを先送りにせず、毎月の給与で分割して支払う」仕組みであり、なしは「年間での所得と税額を自分で計算して納付する」形です。
制度の仕組みと日常の影響
このセクションでは、仕組みをさらに詳しく見ていきます。源泉徴収ありの場合、給与からの天引きはどのように計算されるのか、控除の適用はどのように行われるのかを具体的に説明します。所得控除には基礎控除、扶養控除、社会保険料控除、医療費控除などがあり、年末調整で最終的な税額を決定します。実務上の流れとしては、会社が毎月給与とともに源泉徴収票を作成し、年末には年末調整が行われ、過不足を調整します。これにより、確定申告が不要になる場合が多いですが、副業がある場合や医療費控除が大きい場合には自分で申告する必要も出てきます。
注意として、源泉徴収ありでも所得が一定額を超えると追加の税金がかかることがあります。所得税だけでなく住民税の天引きにも影響します。年末調整の対象になる期間や、控除の適用順序、住宅ローン控除の適用の有無など、細かい条件が結果を左右します。
以下の表は、ざっくりとした違いを比較したものです。
今日は友達とのおしゃべり風に、キーワード「源泉徴収あり」について深掘りしてみるよ。税金の話は難しそうに思えるけれど、実は毎月の給料と深く結びついているんだ。源泉徴収ありだと、会社員は給与をもらうたびに税金が天引きされて、年末には年末調整で“払いすぎ”か“足りなさ”が調整される。この仕組みのおかげで、私たちは自分で税額を計算して納付する手間が減る反面、副業を始めたり医療費控除が増えた場合には、自分で申告する必要が出てくる。つまり、日常の手取り額は安定しつつも、思わぬ控除の変化で最後の税額が動くことがある、ということ。友だちと話していて、スマホの給与明細を一緒に見ながら「この分は天引きされた税金だね」と笑い合うと、税金の世界も身近に感じられる。税務の仕組みは難しく見えるけれど、実は自分の生活と直結していることを知れば、日々のちょっとした選択が税金の未来を変えるかもしれない、そんな感覚を大切にしてほしい。





















