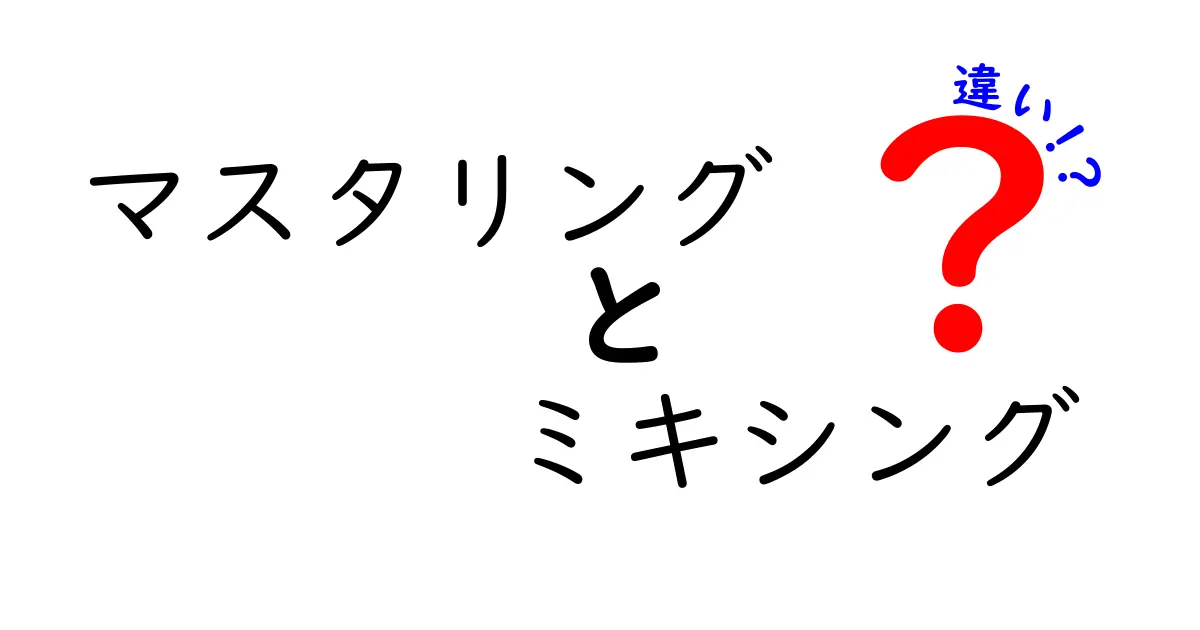

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
マスタリングとミキシングの違いを徹底解説:音楽制作の流れを理解しよう
音楽制作ではいくつもの工程がありますが、特に「ミキシング」と「マスタリング」は名前が似ているので混同されがちです。まず大切なのは、それぞれの役割が別の段階で行われるという点です。ミキシングは「個々の楽器や声のバランスを整える作業」で、パンニングやイコライザー、コンプレッションなどの道具を使って音をまとめます。楽器ごとの音量や定位を調整し、曲全体の雰囲気を作ります。対してマスタリングは「完成した音源全体をひとつの作品として最終調整」する工程です。音のダイナミクスを整え、音圧を適切に上げ下げし、再生環境の違いにも対応できるように仕上げます。
この二つの工程の違いをイメージで整理すると、ミキシングが部活でいうと演奏会のリハーサル、マスタリングが放送用の最終リハーサルと考えると分かりやすいです。リハーサルでは楽器同士の喧嘩や小さな不具合を直しますが、放送用リハでは音の厚さや聴きやすさを全国の人が聴く環境で均一にする調整をします。ここで重要なのは、聴こえ方の違いを理解することです。公園のベンチで聴くときと車の中で聴くときでは聴こえ方が違います。ミキシングとマスタリングは、その違いを補正して最適な音を作るための技術です。
- ミキシングは各トラックの音量・定位・時間差を整え、曲の「じゃぱっと聞こえる」ところを作る作業
- マスタリングは全体の「音の一体感」と「再生環境への適合」を高める作業
- ミキシングはソース音の個性を活かしつつ他の音と競合しないようにする
- マスタリングは音の統一感とノイズの最小化を図る
- どちらも聴き手の環境を想像して作業することが大切
初心者の方へアドバイスとして、リファレンス曲を用意して聴き比べることをおすすめします。自分の曲と同じジャンルのプロの音源を聴いて、どの帯域の音がどれだけ前に出ているか、どの程度のダイナミクスが保たれているかを学ぶと、ミキシングとマスタリングの両方の感覚がつかみやすくなります。さらに基本道具として、EQやコンプレッサー、リミッターなどの名称と役割を覚えると、実務の現場で迷うことが少なくなります。
実務での流れとポイント:現場での作業順と相互作用
制作現場では、まず曲のアイデアとデータをそろえ、録音素材を整えます。録音時のノイズやテクニックの違いを踏まえ、ミキシングで全体のバランスを取ります。ここでのコツは、見た目の音量だけではなく、聴感上の「空間の広がり」や「楽器の明るさ」を意識して調整することです。パンニングの微細な動きや高解像度の音をどう保つかが、曲の印象を大きく左右します。ミキシングが完了したら、作品全体をマスタリングへと繋ぎます。マスタリングでは、ラウドネスのガイドラインに合わせ、個々のトラックのダイナミクスを整え、フォーマット別の仕様に合わせて出力します。
また実務では、リファレンス機材と呼ばれる特定のヘッドフォンやモニター、再生環境を基準に判断します。音楽は機械的に再現されるものではなく、聴く場所や機材で聴こえ方が変わります。そこで重要なのは、環境に依存しない仕上がりを作ることです。適切なリファレンス曲を選ぶことで、あなたの作品が車内、家庭用スピーカー、スマホ、スタジオモニターといった多様な環境でどのように聴こえるかを想像しながら作業できます。最後に、納期と品質のバランスを取ることも大切です。
マスタリングという言葉は、音楽制作の中で巧妙な騙し討ちのようにも感じることがあります。ミキシングが細部の音を合わせる作業なら、マスタリングは作品全体の呼吸を整える儀式みたいなものです。ミキシングでバランスを作った後に、音が大きくなりすぎたり薄く感じたりしないよう、全体の音の厚みと粘りを整える。音楽は同じ曲でも聴く場所で聴こえ方が違うから、マスタリングはその差を小さくして、どんな機材でも聴きやすいように仕上げる作業。





















