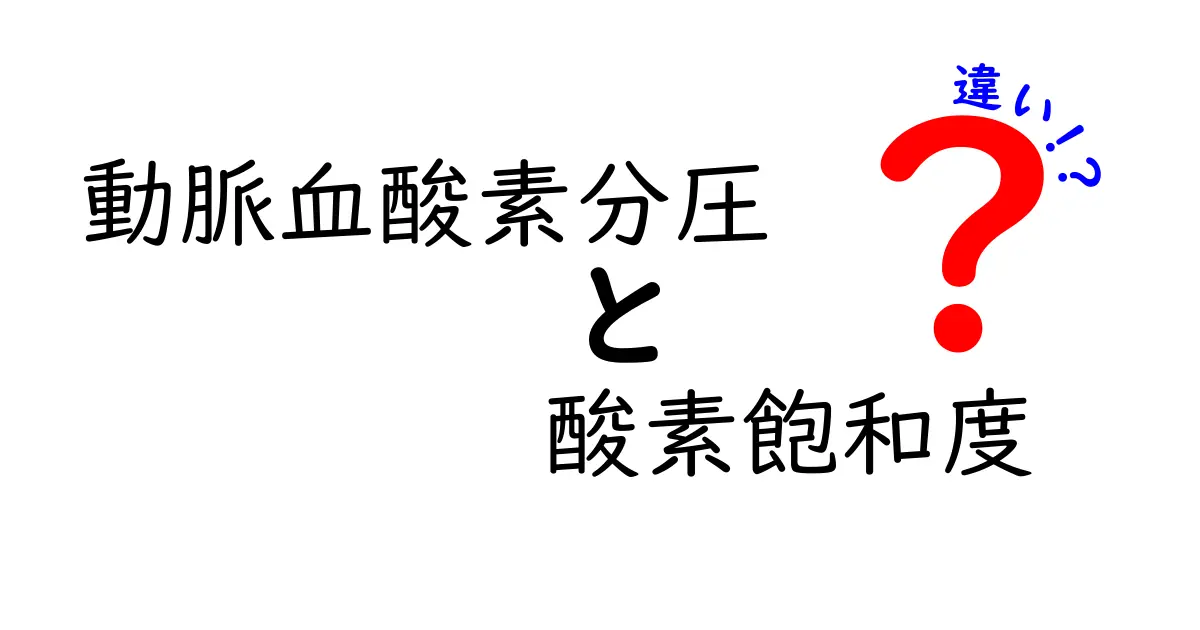

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
動脈血酸素分圧(PaO2)とは何か?その意味を噛み砕いて解説
動脈血酸素分圧、英語では PaO2 と呼ばれます。まず大事なのは、酸素は血液の中で二つの形で運ばれるということです。ひとつは 溶けている酸素、もうひとつは ヘモグロビンというたんぱく質に結合して運ばれる酸素です。PaO2 はそのうちの「溶けている酸素の圧力」を指します。つまり、血液がどれだけ酸素を“圧力として持っているか”を表す指標です。肺で取り込んだ酸素が動脈血に入るとき、酸素は肺胞の空気と血液の間の境界を通って少しずつ溶け出します。このときの圧力が PaO2 です。
PaO2 が高いほど酸素がしっかり溶けている状態、低いと溶けている酸素が不足している状態と考えます。健康な成人では海抜0メートル付近で PaO2 はおよそ 95〜100 mmHg 程度が目安とされますが、年齢や体調、呼吸の状態で前後します。PaO2 は肺と血液の“換気と血流のバランス”を反映する指標であり、体の酸素供給を直接的に感じる手がかりになります。
ただし PaO2 を正確に測るには動脈血を採血して分析する必要があり、非侵襲的な測定ではありません。臨床の現場では酸素治療の必要性を判断する重要なデータとして使われます。対して酸素飽和度 SaO2 は「ヘモグロビンが酸素を結合している割合」を示します。PaO2 は酸素の圧力そのものを測るのに対し、SaO2 は血液の中で酸素がどれだけしっかり運ばれているかを示す指標です。
この二つは互いに関係していますが、必ずしも同じ動きをするわけではありません。例えば PaO2 が少し下がっても SaO2 が急に下がらないことがあります。
ここがポイントです。 PaO2 は換気の状態を、SaO2 はヘモグロビンの酸素結合の様子を、別々の角度から教えてくれるのです。
酸素飽和度(SaO2)とは?PaO2との違いを図解で理解
酸素飽和度、SaO2 は「動脈血中のヘモグロビンが酸素と結合している割合」を示します。文字どおり 100 のうち何割が酸素をくっつけているかを表す数字です。正常値はおおむね 95〜100 % で、100% に近いほど血液が酸素でいっぱいの状態を意味します。SaO2 は非侵襲的に測定できることが多く、脈拍計を使うパルスオキシメータという機械で日常的に調べられます。
SaO2 が重要なのは、ヘモグロビンが酸素をどれだけ運べるかを直感的に示してくれる点です。ただし SaO2 には制限もあり、二酸化炭素の量や体温、pH、亜硝酸化物などの影響を受けることがあります。また、一酸化炭素中毒やメトヘモグロビン血症があると SaO2 の読みが誤解を招く場合もあります。
SaO2 は肺機能と血液の結合力の両方を反映しますが、PaO2 のように「溶けている酸素の圧力」を直接測るわけではありません。図で見ると、PaO2 は血液がどれだけ酸素を“溶かしているか”の圧力、SaO2 は酸素がヘモグロビンにどれだけ結合しているかの割合です。
この違いを覚えると、医師がどうして ABG(動脈血ガス検査)とパルスオキシメトリの両方を使うのかが理解しやすくなります。ABG は PaO2 などを詳しく測れるので、酸素投与の適正量や酸塩基平衡の状態を詳しく見るのに役立ちます。パルスオキシメータは SaO2 を手軽に知るための道具で、日常的な状態観察に向いています。
要するに PaO2 は「酸素の圧力」、SaO2 は「酸素を運ぶ力(結合率)」を示す別々の視点です。
この2つをセットで見ると、呼吸器系の病気や高齢者の体調変化など、さまざまな場面で酸素の供給状態を正しく読み解く手がかりになります。
日常の例と臨床での使い分け
日常生活の中では SaO2 の数値を見て“今の酸素がどれくらい体に行き渡っているか”をイメージします。スポーツや高地登山、風邪やインフルエンザの時など、呼吸がいつもよりしんどくなると SaO2 が低下することがあります。
臨床の現場では PaO2 を測るために動脈血の採血を行い、酸素をどれだけ血液に溶かしているか、また血液の酸性・アルカリ性のバランス(pH)とどう連動しているかを詳しく調べます。これにより、酸素をどのくらい補うべきか、人工呼吸や酸素療法が適切かを判断します。SaO2 は noninvasive、つまり体への負担が少ない方法での継続的な監視に最適です。
補足として、表で PaO2 と SaO2 の違いを整理しておきましょう。
指標 意味 正常値の目安 臨床での使い方 PaO2 動脈血中に溶けている酸素の圧力 約95–100 mmHg 肺換気と血流の状態を詳しく評価 SaO2 ヘモグロビンが酸素を結合している割合 約95–100% 非侵襲的に酸素供給の目安を把握
このように二つの指標は、医療の場で互いを補完する役割を果たします。
もし体調が悪いと感じたとき、自己判断で酸素を過剰に取るよりも、まず SaO2 を測って現在の状態を把握するのが安全です。さらに深刻な不調がある場合は医療機関を受診して、PaO2 や他の検査結果も含めて総合的に判断してもらいましょう。
結局、PaO2 と SaO2 は同じ“酸素”というキーワードを別の角度から説明する二人組です。肺の機能や血液の状態を正しく理解するためにはこの二つをすり合わせることが大切です。
SaO2 という指標を深掘りした雑談風の解説です。友達と喋るように、酸素の結合と圧力という二つの観点を結ぶイメージを使って説明します。例えばスポーツの後に呼吸が早くなる理由を考えると、酸素が足りなくなる瞬間と、血液が酸素をどれだけ抱きしめられるかの関係が浮かび上がります。SaO2 は“今この瞬間の酸素の送られ方”を直感的に示してくれる数字であり、PaO2 は“酸素が血液中でどう溶けているか”というもう少し詳しい話を教えてくれます。二つをうまく組み合わせると、体の酸素事情が頭の中で自然とつながっていきます。





















