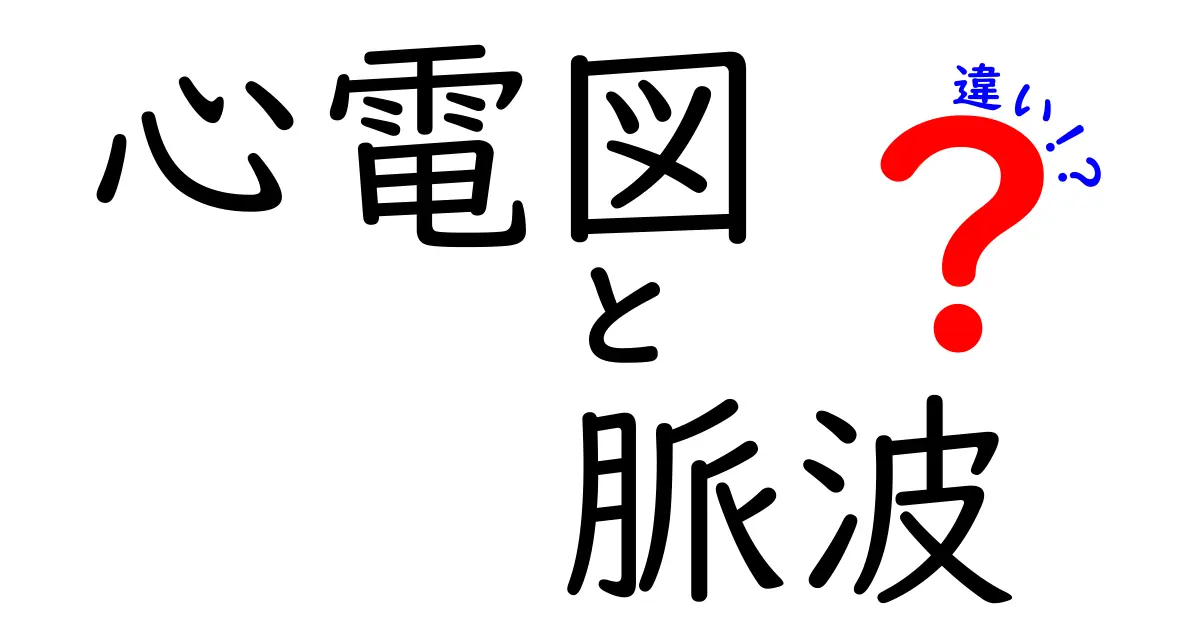

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
心電図と脈波の違いをざっくり掴もう
心臓には2つの側面があり、それを測る指標が「心電図」と「脈波」です。いずれも心臓と血管の情報をくわしく伝えますが、何を測っているのか、何を読み取れるのかが大きく違います。
この違いを知ると、医療の現場でどの検査が必要か、日常生活で自分の体をどう観察するのかが見えてきます。
本記事では、中学生にも分かる言葉で、心電図と脈波の基本、測定の仕組み、実際の臨床での使い方、そして日常生活で覚えておくべきポイントを丁寧に解説します。
まずは大枠のイメージをつかんでいきましょう。
心電図と脈波は、それぞれ別の情報を提供しますが、同時に見ると体の状態を総合的に理解できる強力な組み合わせです。心臓が電気信号で指示を出し、血管がその力を波として伝える。この2つの視点を覚えるだけで、体の仕組みがぐっと身近に感じられます。日々の健康チェックにもつながる、基本の考え方を身につけましょう。
この節のポイントは、どちらが「電気の流れ」を、どちらが「血管の波」を表しているかを明確に区別することです。
心電図(ECG)のしくみと役割
心電図は、体の表面に貼った電極を通じて心臓の電気活動を読み取る検査です。
心臓には「心臓の動きを指令する電気信号」があり、それが伝わる順序で心房が収縮し、心室が収縮します。この伝導の順序を図にしたものがECGの波形で、P波、QRS波、T波と呼ばれます。
これらの波形の形や間隔を見れば、心臓のリズムが正しいか、伝導の乱れがないか、心筋に痛みや損傷の兆候があるかなどを判断します。ECGは痛みを伴わず、短時間で実施できるため、日常的な健康チェックから入院時の診断まで幅広く使われます。
ただし、ECGは心臓の「電気の地図」であり、筋肉の力強さや血液の量といった機械的な情報は直接測れません。これらは別の検査(例:心エコー)と組み合わせて総合判断します。
ECGは医療現場での基本的なツールです。不整脈の発見、伝導障害の有無、虚血性心疾患の兆候などを把握するのに役立ちます。さらに、長時間のモニタリングを行うことで、日常生活では見つけにくい異常なリズムの痕跡を拾うことも可能です。
この検査は、心臓の「時刻表」を読み解く作業に似ています。どのタイミングで心臓が動くかを正確に把握することが、診断と治療の第一歩となります。
ただし、心電図だけで心臓すべての状態が分かるわけではありません。心臓は機械的にも働くため、収縮の強さや血液の動きといった情報は別の検査で確認します。心電図と他の検査を組み合わせることで、より正確な診断が可能になります。
この理解を持つと、医療の流れや患者さんの説明がずっと分かりやすくなります。
脈波(血管の波)についてのしくみと役割
脈波は、心臓が収縮して血液を動脈へ押し出すときに生じる「血管側の波」です。心臓の拍動とともに動脈が膨らみ、波となって体の末端へ伝わります。手首の脈を触れるのはこの波が指先まで伝わるからで、脈拍として日常的に感じることができます。
脈波の特徴には、波形の形、波が伝わる速さ、波の強さなどがあります。特にPWV(脈波伝搬速度)は、動脈の硬さを表す指標として注目され、年齢とともに硬くなる血管の状態を推測するのに役立ちます。血圧の状態や動脈硬化のリスク評価にもつながる重要な情報です。
脈波は心臓の電気信号そのものを測るものではなく、体内を流れる血液の力の伝わり方を示します。だからこそ、全身の健康をみる別の角度として広く使われています。
脈波を読み解く際には測定部位や環境の影響を考慮することが大切です。手首や頸動脈で測る場合、姿勢・温度・手の冷えなどが結果に影響します。家庭用デバイスを使う際も、リラックスした状態で同じ場所を数回測ると安定したデータが得られやすいです。脈波は、体の内側の健康状態を示す「外観」情報として、医師が他の検査と合わせて判断する材料になります。
違いを日常と医療でどう使い分けるか
日常生活では、脈拍を測って自分の体の「今のリズム」を知ることが一般的です。風邪気味や運動後の回復、疲労の程度をざっくり判断する目安になります。これは健康観察の第一歩であり、体調の変化に早く気づく助けになります。
医療の現場では、心電図を使って心臓のリズムや伝導の状態を詳しく調べ、必要に応じて治療の方針を決めます。例えば胸の痛みや息苦しさがある場合、ECGを通じて不整脈や虚血のサインを探します。
脈波は高血圧や動脈硬化の評価に用いられ、血管の硬さを知ることで長期的な健康管理の指針を得ることができます。—このように、心電図と脈波はそれぞれ別の情報を提供しつつ、同時に使うことで体の全体像をより正確に理解できるのです。
両方を組み合わせる意義は、病気の早期発見だけでなく、日常生活の健康管理を支える点にもあります。
この理解は、中学生のみなさんが体の仕組みを学ぶ上で大切な基礎となります。心臓の電気の流れと血管の波の両方を意識する癖をつければ、将来医療の仕事につながる道を考えるときにも、専門的な説明がより身につくはずです。
今日は友達と放課後の雑談で、心電図と脈波の違いについて深掘りしてみた話。僕らは心臓がビートを刻むのを電気信号で知るECGと、血管の波として感じる脈波を混同しがちだけど、実は別々の現象なんだよね。心臓の電気はSA結節から出て、P波QRS波T波と形を変えながら伝わる。これを見れば不整脈や伝導の乱れを探せる。一方、脈波は血液が動脈へ送られる瞬間の圧力の波で、指で触れる脈拍にも現れる。PWVという指標は血管の硬さを反映する。運動習慣や年齢で変わるから、測定の仕方を工夫すると変化が見える。僕らが日常で意識しておくべきは、心電図と脈波の違いを「心臓の電気の地図」と「血管の波の動き」というふうに分けて考えること。それができれば、体の変化に気づきやすく、将来医療に関わるときにも誰かの気持ちを考えた説明ができると思う。





















