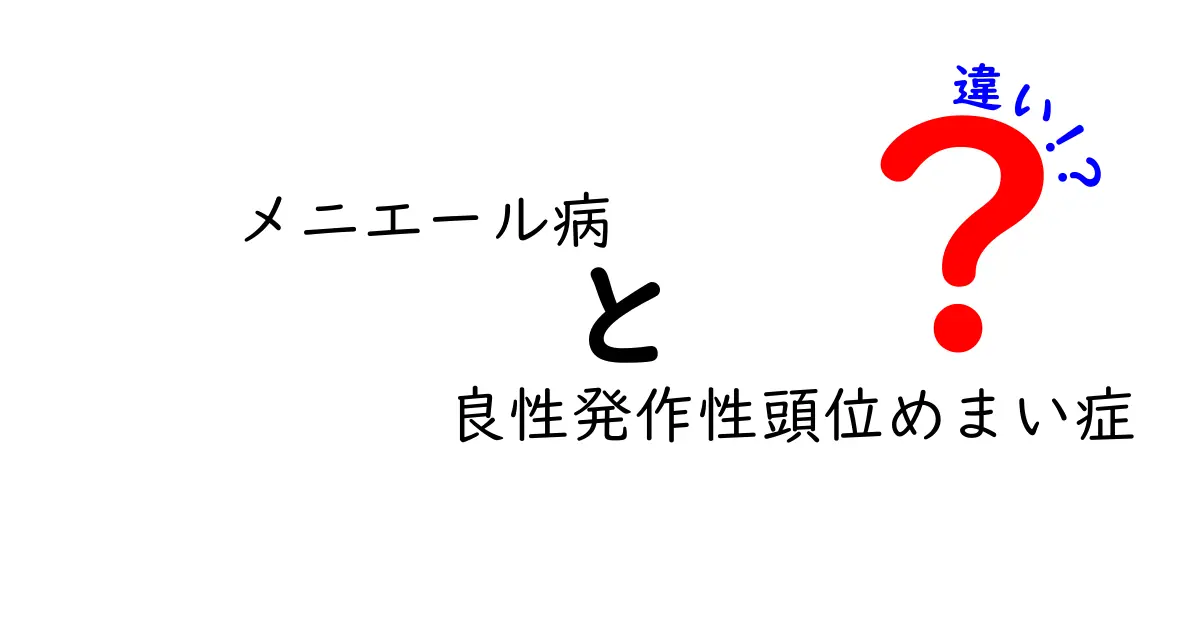

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
メニエール病と良性発作性頭位めまい症の違いを正しく理解する
日本では「耳の病気」としてよく耳にする2つの病気、メニエール病と良性発作性頭位めまい症(BPPV)は、めまいを引き起こす点で似ているように見えますが、原因・症状・日常生活への影響・治療法が違います。まず基本を押さえることが大切です。
1つ目の特徴は、原因の違いです。メニエール病は内耳の内部で液体の量や圧力のバランスが崩れることにより聴覚の細胞が影響を受け、長時間続く回転性めまいと聴力の低下、耳鳴りが同時に起こることがあります。これに対して良性発作性頭位めまい症は、耳の中の小さな石(耳石)が本来の場所からずれて前庭に刺激を与えることで、頭の位置を変えたときだけ急に激しいめまいが生じる病気です。
2つ目の特徴は、症状の持続時間とパターンです。メニエール病の発作は数十分から数時間に及ぶことがあり、発作の間はぐるぐる回るような強い回転感が続き、症状は時間とともに波のように現れます。聴力の低下は数日から数週間で回復することは珍しく、長期的な聴力の影響が残る場合もあります。これに対してBPPVは、頭を特定の方向に傾けたり寝返りを打つときに限ってめまいが起こり、数十秒から数分程度で落ち着くのが一般的です。聴力の影響は基本的にありません。
3つ目の特徴は検査での違いです。メニエール病では聴力検査で難聴が見つかることが多く、耳の奥の機能を測る検査(聴力検査、内耳の機能を調べる検査)や鼓膜の反応、聴覚と平衡の両方を評価する検査が重要です。一方、BPPVの診断には頭の位置を変えてめまいが出るかを見る「頭位眼振検査」や前庭機能を測る検査が使われ、補助的には耳石の移動を意図的に元の位置へ戻す治療(エプリー法など)を通じて診断が確定します。
このように、同じ“めまい”という症状でも、原因や症状のパターン、治療方針が異なります。誤ってどちらも同じ病気だと判断すると、適切な対処が遅れて生活の質が下がってしまうこともあります。どちらか不安がある場合には、専門の医療機関を受診して、医師の診断を受けることが大切です。
ポイントとしては、「長引く聴力の変化があるか」「頭の位置で起こるめまいかどうか」「日常生活での動作が影響するかどうか」をチェックすることです。
原因と症状の違い
メニエール病は内耳の内リンパ水腫と呼ばれる状態が背景にあり、内耳の液体のバランスが崩れることで回転性のめまいと聴力の低下、耳鳴りがセットで現れやすくなります。具体的には、発作時には体がぐらつき、頭がクラクラする感覚が数十分から数時間続くことがあり、発作が治まっても耳の音がしばらく響くことがあります。生活習慣の影響もあり、塩分の多い食事や過度のストレス、睡眠不足などが発作を誘発することがあるため、日常のケアがとても大切です。対照的に良性発作性頭位めまい症(BPPV)は、耳の石(耳石)が異常な位置に移動することによって、頭を動かしたときだけ発作的に強いめまいが起こるのが特徴です。聴力には通常影響がなく、数十秒程度でおさまるケースが多いです。前庭神経の刺激が強くなるため、頭の位置を変える動作がきっかけとなりやすく、日常の動作を意識することで予防・対処がしやすくなります。項目 メニエール病 良性発作性頭位めまい症 原因 内リンパ水腫など内耳の液体バランスの乱れ 耳石の移動・前庭刺激 主な症状 長時間の回転性めまい、聴力の変化、耳鳴り、耳の詰まった感じ 頭位変換時の短時間の激しいめまい、聴力変化なし 検査の特徴 聴力検査で難聴、内耳機能の評価、平衡機能の検査 Dix-Hallpike検査などの前庭検査、聴力には通常影響なし 治療の方向性 低塩分食・利尿薬・必要に応じた薬物療法 エプリー法などの前庭リハビリ・生活習慣の調整
この表は、2つの病気を一目で比較する際の目安になります。実際には医師の診断に基づく個別の治療計画が最も重要です。
診断のポイントと生活への影響
診断では、発作の頻度や持続時間、聴力の変化の有無、頭位で起こるめまいの有無を総合的に判断します。聴力検査の結果が出ると、メニエール病の可能性が高まる一方で、聴力に変化がなく、頭位変化でのみめまいが起きる場合はBPPVの可能性が高くなります。検査以外にも、日常生活の様子を医師が伺い、めまいが起きた際の導入動作(急な頭の動き、頭を後ろに倒す、長時間の睡眠不足など)を見直す指導が行われます。日常生活への影響としては、発作中の転倒リスクの増加、運転や自転車などの移動時の安全確保、睡眠の質の低下などが挙げられます。発作が起きたときには、静かな場所で安静を保ち、水分と塩分の管理を意識することが大切です。医師の指示に従い、薬物治療を受ける際には副作用にも注意を払う必要があります。
治療の考え方と日常生活のコツ
治療方針は病気のタイプにより異なります。メニエール病では、塩分制限、薬物療法(抗めまい薬・利尿薬など)、ストレス管理、睡眠の改善、必要に応じた聴力の回復を目指すリハビリなどが中心になります。日常生活のコツとしては、塩分を控えめにし、水分を適度にとり、カフェインとアルコールの摂取を控えること、定期的な運動とストレス解消法を取り入れることが推奨されます。BPPVの場合は、エプリー法と呼ばれる前庭リハビリを中心に行い、耳石を正しい位置へ戻すことで多くの場合、発作を抑えることができます。再発を防ぐためには、睡眠を十分にとり、体を急に動かさない習慣をつけることが有効です。いずれの場合も、急なめまいが強いときには車の運転を避け、転倒を防ぐ工夫を日常に取り入れることが大切です。医師と相談しながら、自分に合った生活リズムを見つけていきましょう。
ねえ、聴力の変化ってさ、どうして起きるんだろう。メニエール病の友だちは、発作のとき耳がぐるりと鳴る感じがすると言っていたよ。聴力が落ちても、時間が経つと元に戻ることもあるみたいだけど、それって内耳の水の量が関係しているのかな。私たちは日常で“聴こえ方”が急に変わる経験は少ないから、聴力の変化が体の中でどうつながっているのか、想像するとちょっと不思議だよね。大事なのは、聴力の変化だけで判断せず、頭の位置とめまいのパターンを一緒に見ること。もし発作が起きたら、焦らず休むこと、塩分を控える生活を心がけること、そして専門の人に相談すること。私たちの体は複雑で、耳の奥の小さな変化が生活のリズムを左右することがあるんだ。
前の記事: « カタツムリと蝸牛の違いを徹底解説!クリックしたくなるポイント満載





















