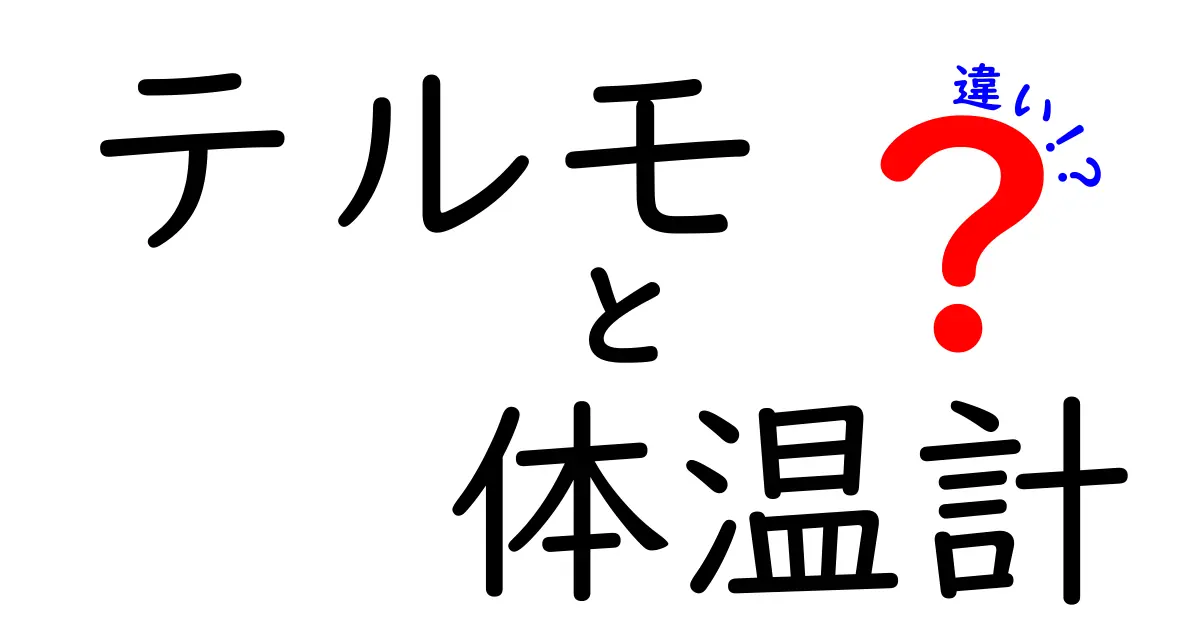

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
テルモの体温計にはどんなタイプがあるのか
テルモは日本の代表的な医療機器メーカーとして、家庭向けの体温計を複数モデル展開しています。ここで押さえておきたいのは、大きく分けて デジタル電子体温計 と 赤外線体温計(非接触・額・耳などの測定) の2つのタイプがある点です。デジタル式は内部のセンサーで体温を読み取り、測定部位ごとに使い分けることができます。赤外線式は額や耳から一瞬で温度を読み取るタイプで、測定時間が短くて便利ですが、場所や表面温度の影響を受けやすいという特徴があります。
この2タイプは目的や年齢、使用場面によって向き不向きが変わるため、まずは自分の使い方を想定して選ぶことが大切です。
デジタル電子体温計には、口内用・腋下用・直腸用 など、測定部位を切り替えられるモデルが多くあります。これらは測定部位ごとに正確な読み取りを追求しており、長時間の測定でも安定した値を出しやすいという利点があります。対して赤外線体温計は、額や耳 からの読み取りが主で、特にお子さんの機嫌を損ねず測定したいときに便利です。最近は non-contact(非接触)タイプも普及しており、距離をとって測ることができる点が魅力です。
さらに、どちらのタイプにも 機能の差 がいくつかあります。記憶機能(過去の測定値の保存)、 fever アラート(発熱の有無を知らせる機能)、バックライト、オートオフ、生活防水など、ニーズに合わせて選ぶと良いでしょう。年齢別のおすすめもあります。乳幼児には短時間で結果が出るモデル、日常の健康観察にはデジタル式の安定性、集団検査のような場面には非接触の利便性といったように、使うシーンを想定して選ぶのがコツです。
最近、友だちと話していて 赤外線体温計 の話題になったんだけど、正直最初は“一瞬で測れるから便利”と思っていました。でも実際には環境の温度や額の状態、汗の有無などが結果に影響することが多くて、「測定場所の条件を整えること」 がとても大事なんだと気づきました。例えば、寒い場所で測ると正確さが落ちることがあるので、測定前に部屋の温度を少し安定させる、額を軽く拭く、測定距離を守る、という基本を守るだけで精度がぐんと上がります。
デジタル式は時間がかかる反面、測定部位ごとの適正値 に対して安定した読み取りが期待できます。だから、家に小さい子がいる家庭や、じっくり体温を記録したい人にはデジタル式がおすすめです。最終的には、使い勝手と正確さのバランスを自分の生活スタイルに合わせて選ぶのが一番楽です。私自身、急いでいるときには非接触タイプの便利さに助けられましたが、夜間の発熱チェックにはデジタル式の安定感が安心感につながりました。





















