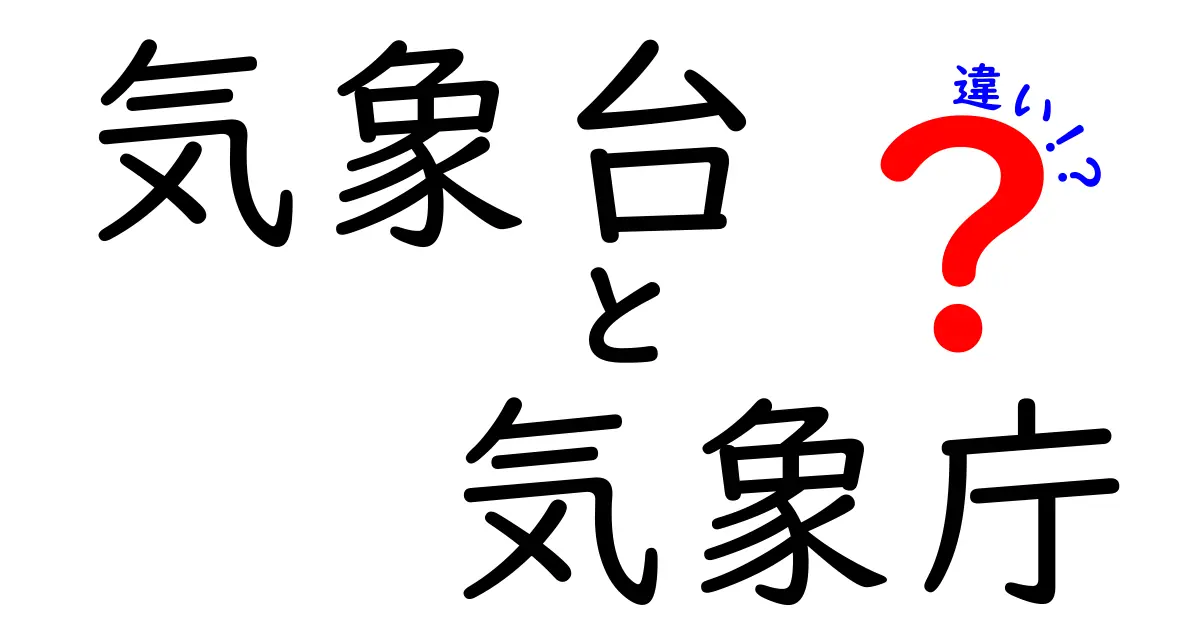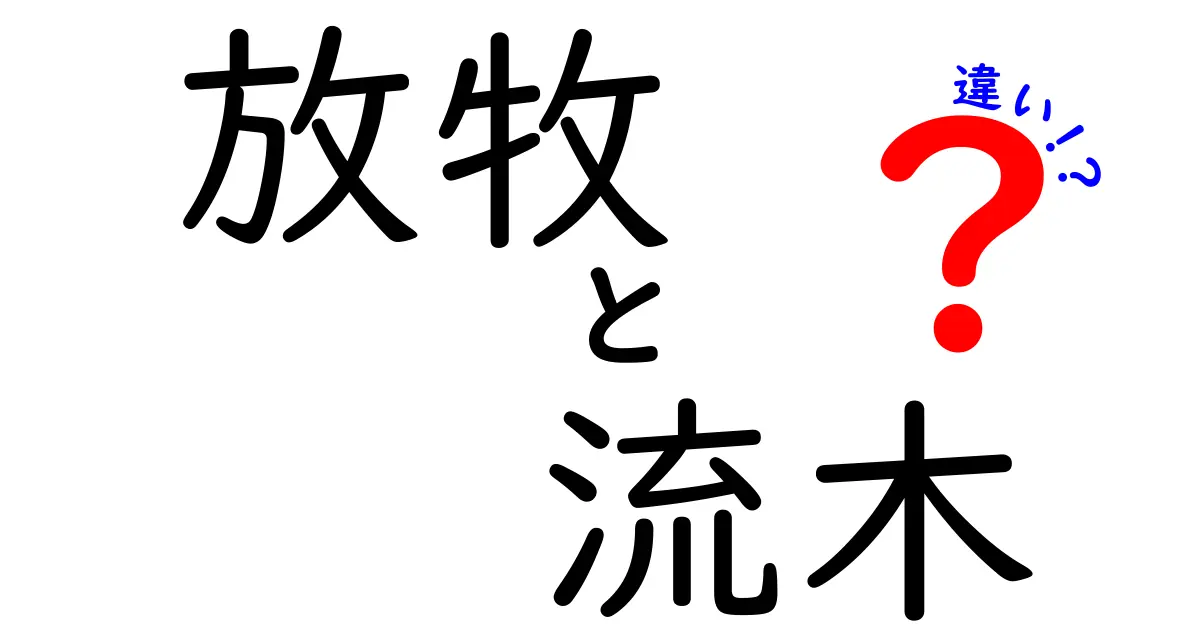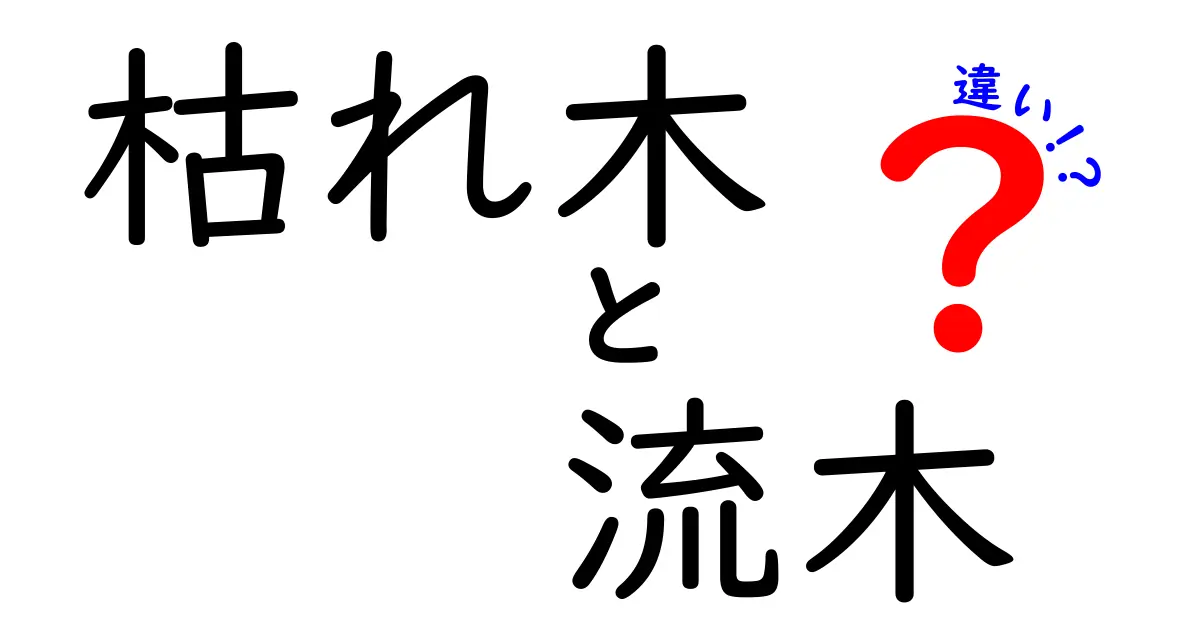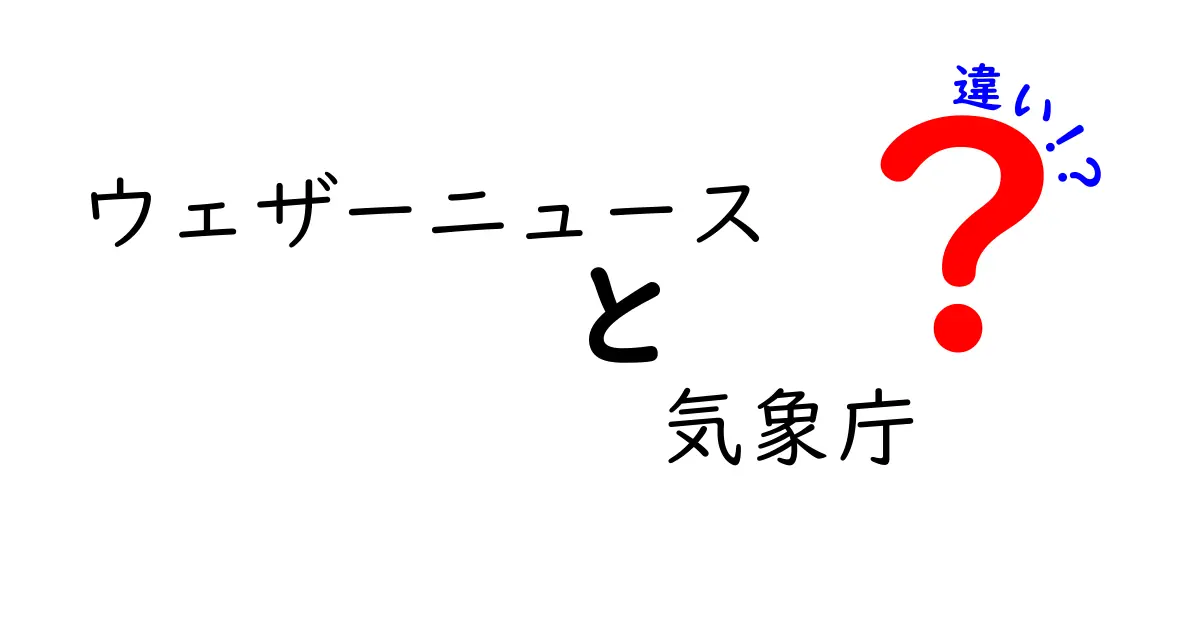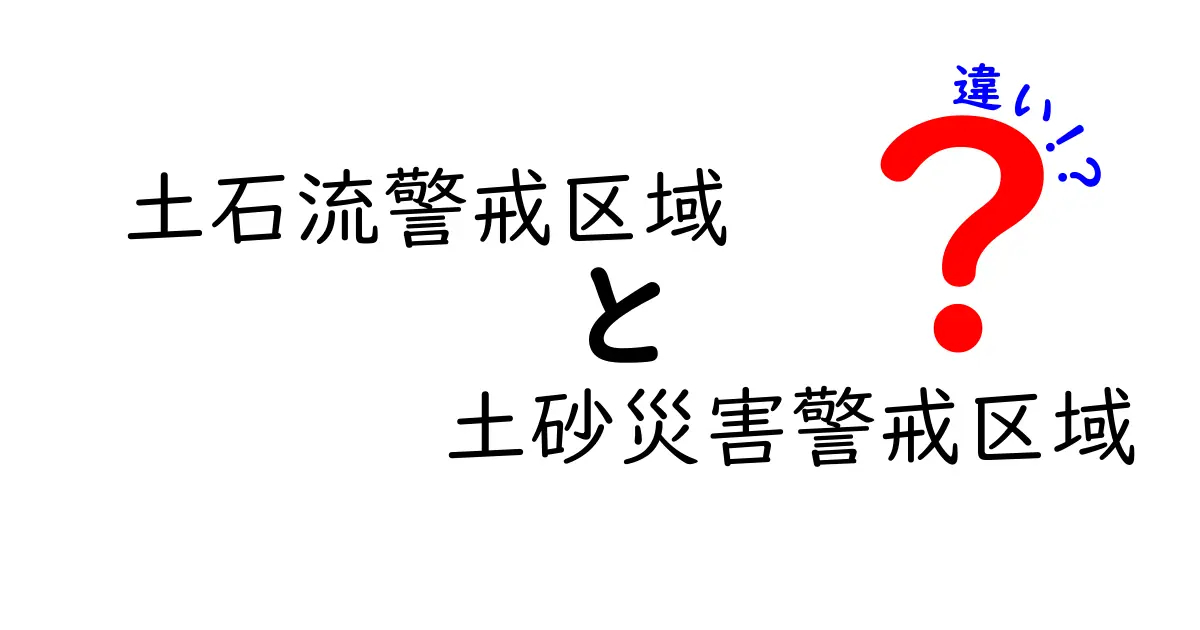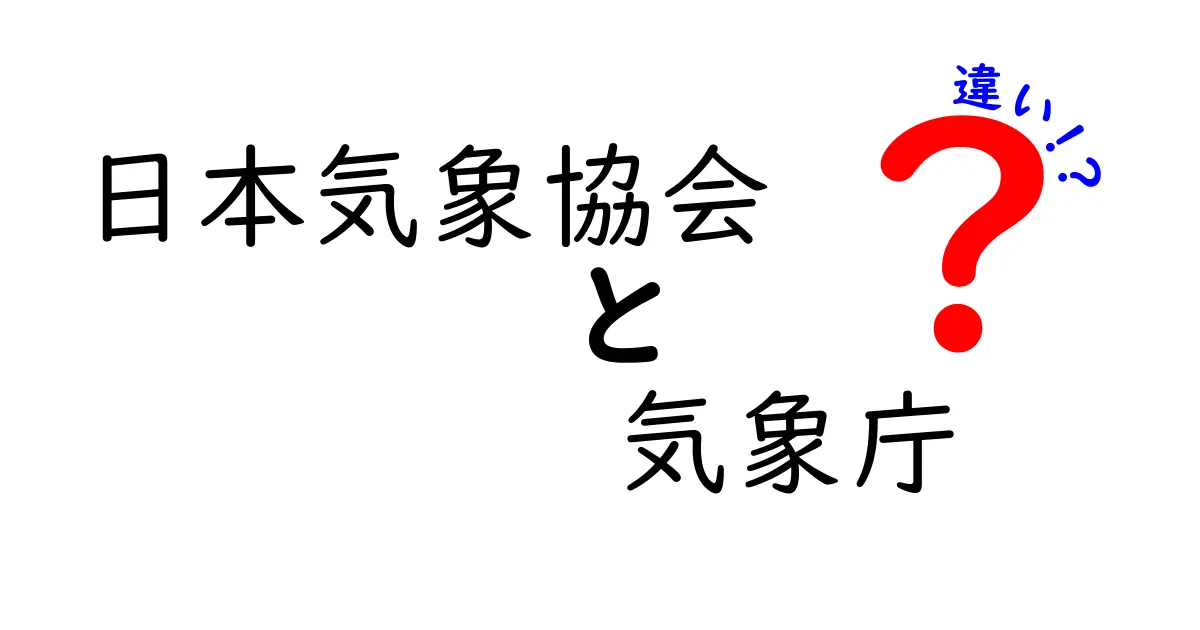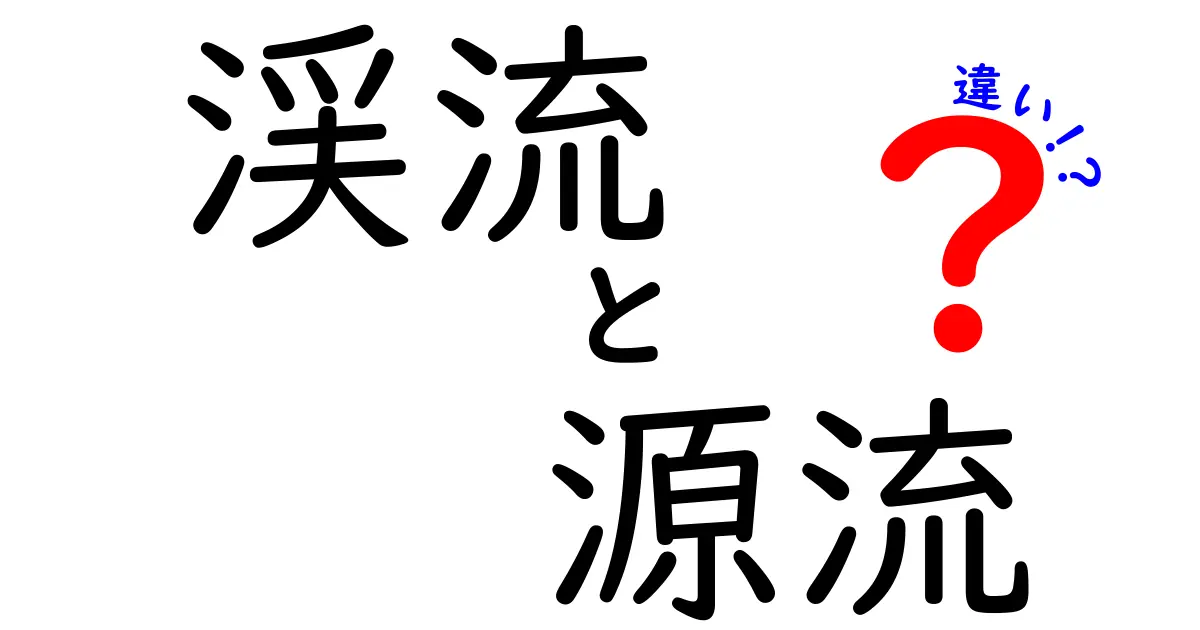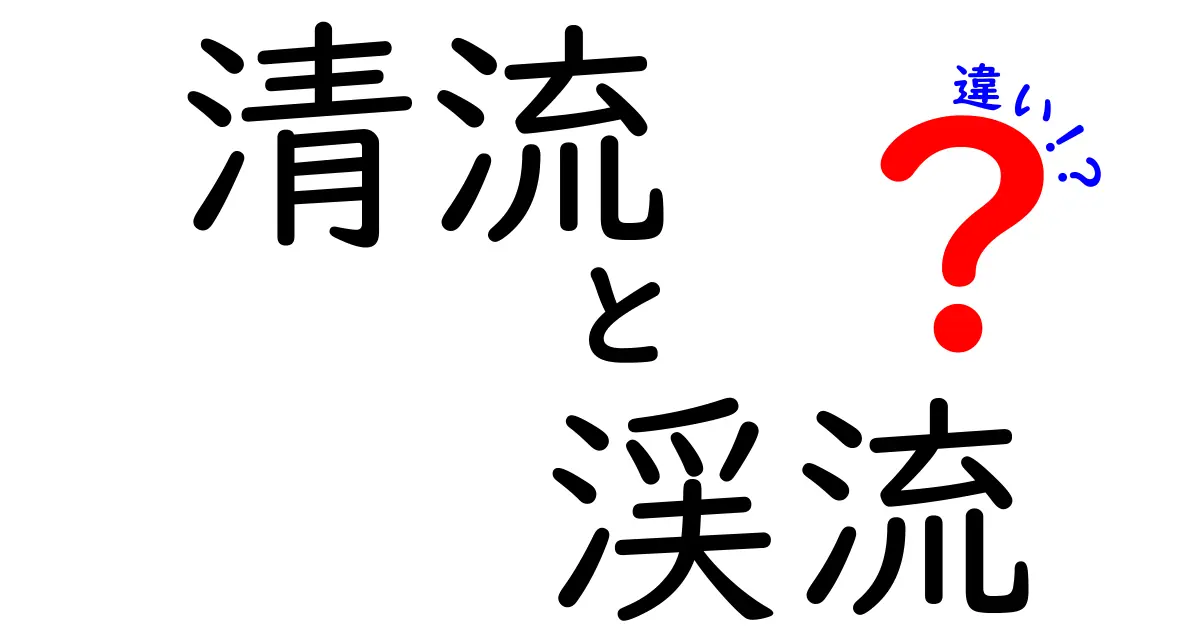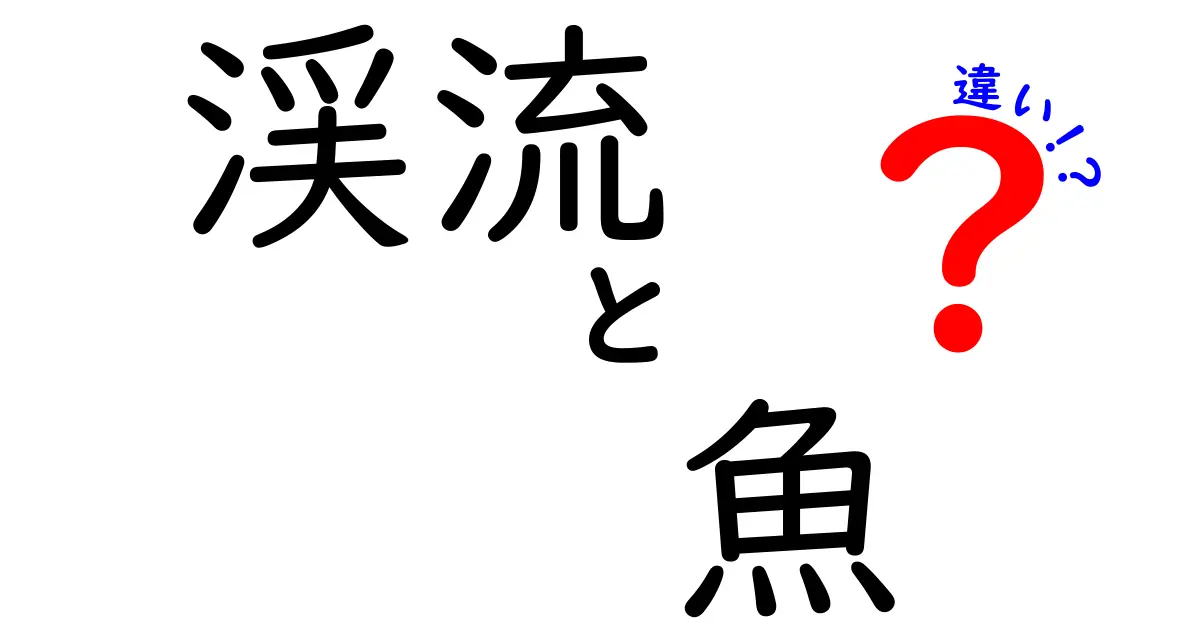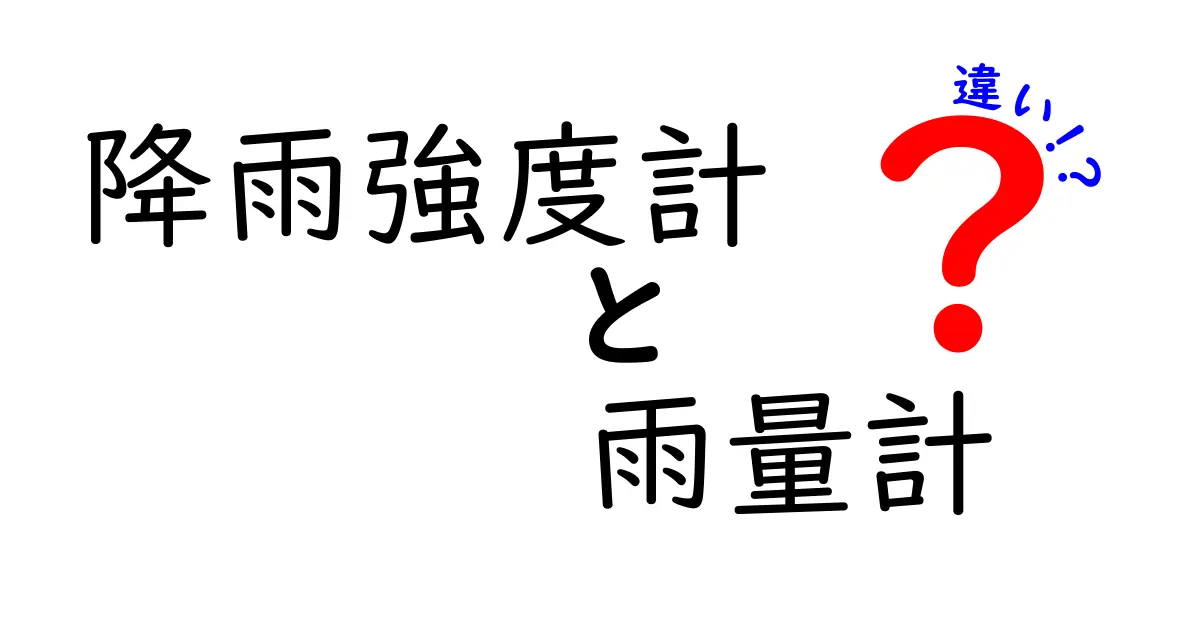

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
降雨強度計と雨量計の基本的な違いとは?
雨に関係する観測機器としてよく耳にするのが降雨強度計と雨量計です。どちらも雨を測る機器ですが、その役割や測定内容は異なります。
簡単に言うと、雨量計は一定期間に降った雨の総量を測定します。一方、降雨強度計は短時間あたりの雨の降り方の強さ、つまり雨の強さを測る装置です。
つまり、雨量計は「この時間で何ミリ降ったか」を知るのに対し、降雨強度計は「1分間や10分間でどのくらい激しく降っているか」を詳しく知るための機器と言えます。これにより、災害の予防や水資源の管理に役立っています。
降雨強度計と雨量計の仕組みと特徴
雨量計には主に「自動式」「手動式」があり、一般的な自動雨量計は漏斗を通して雨水を計量容器に集め、浮きや電子センサーで量を測定します。
一方の降雨強度計は、主にレーダーや音波、光学センサーを用いて、降っている雨の粒の数や大きさ、落ちる速度を瞬時に捉え、雨の強度をリアルタイムで計算します。
雨量計が累積的な雨の量を測るのに対し、降雨強度計は雨の状態を細かく知ることができるため、例えば局地的な豪雨や急な雨の強まりを敏感に捉えることができる特徴があります。
降雨強度計と雨量計の使われ方の違い
雨量計は農業、気象庁、環境調査などで長期間にわたる降雨量の測定を目的としています。その成果はダムの水管理や農作物の水やり計画に使われています。
これに対し、降雨強度計は特に災害対策や都市の洪水予防で重要です。時間あたりの雨の激しさを測ることで、土砂災害や河川の急激な増水を早く察知し、警報を発することができます。
また、降雨強度は単に降った雨の量だけでなく、雨の勢いも反映するため、道路や建物の安全確保において重要です。
降雨強度計と雨量計の違いをまとめた表
雨量計は「雨の合計量」を測りますが、降雨強度計は「雨の降り方の速さ」を細かく教えてくれるんです。これにより、いきなり激しい雨が降ったときに早めにわかり、土砂災害などの危険を防ぐことができます。普段あまり意識しませんが、この違いで私たちの安全が守られているんですよ。例えば、大雨警報で『短時間に激しく降っています』と言われるのは降雨強度計のおかげなんです。
前の記事: « カルデラ湖と堰止湖の違いを徹底解説!自然が作る湖の秘密とは?
次の記事: 一目でわかる!ステートチャート図と状態遷移図の違いを徹底解説 »