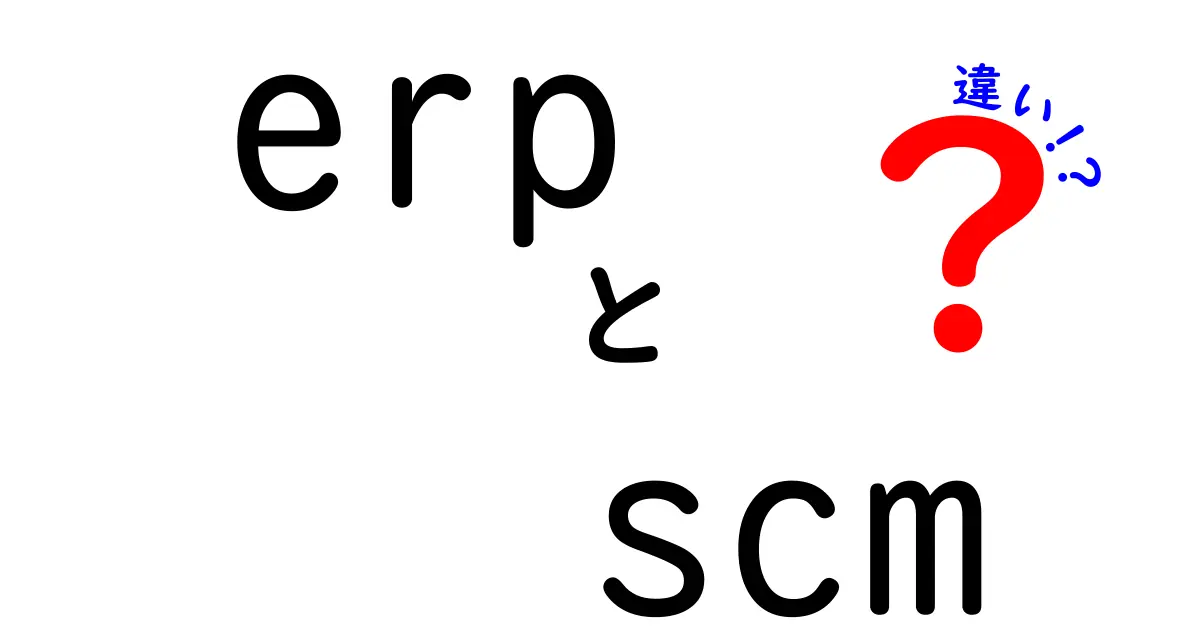

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ERPとSCMの基本的な違いとは?
ERPは企業資源計画の略で、会社の内部の資源(資金・人・材料・設備・情報)を一元的に管理する大きな仕組みです。主要モジュールには会計・購買・在庫・生産・人事・顧客管理などが含まれ、データは一つのデータベースで共有されます。これにより部門間の情報のズレを減らします。
一方SCMはサプライチェーンマネジメントの略で、製品が原材料の調達元から顧客の手元に届くまでの流れ全体を最適化する考え方です。外部の取引先、物流業者、顧客といった外部ステークホルダーも含めて、需要予測・調達・生産・物流・配送・返品といった段階を連携させます。
要はERPは内部の資源をどう回すかを決める設計図、SCMは外部の動きをどう調整して全体の納期・コストを下げるかを決める設計図のような役割です。
ERPとSCMはそれぞれの役割が異なるため、別々のシステムとして使われることもありますが、多くの場合は互いを補完する形で導入します。ERPが「何を」「誰が」「いつ動くか」を正しく把握できる状態を作ると、SCMは「外部の変化にも対応して納期を守る」ことができるようになります。
この組み合わせは特に製造業・小売業・物流業など、在庫と流れを同時に管理する場面で力を発揮します。
導入計画を立てる際には、経営戦略と現場の実務の両方を見渡せる人材が核となって推進することが成功のカギになります。
ERPとSCMの役割と現場での使い方
現場での使い方を考えると、ERPは「日々の業務を正確に処理し、透明性を高める」役割を担います。受注・発注・納品・請求といった一連の流れを一元管理することで、在庫の過不足を減らし、会計や原価計算をリアルタイムで正しく回せます。
一方SCMは「需要の変化や供給の不安定さに対して全体最適を目指す」役割です。需要の急増に応じて発注量を調整したり、納期の遅延を回避するための代替案を用意したりします。つまりERPが内部の“最適化”を担当し、SCMが外部の“連携最適化”を担当します。
この組み合わせは、特にグローバルに展開する企業で力を発揮します。部品の納期がずれると全体の組立ラインが止まる可能性があるため、SCMは代替サプライヤーや物流ルートの再設計を提案します。ERPのデータとSCMのデータを統合してリアルタイムに可視化することで、経営判断が遅れず、顧客サービスレベルを維持できます。
現場の担当者は、ERPの操作性とSCMの協調性を両方理解する必要があります。データの品質が低いと、両方のシステムで誤差が拡大し、意思決定が難しくなります。したがって、導入時にはデータクレンジングと標準化の作業が重要です。
「ERP」と「SCM」どう使い分ける?実例で解説
ある中規模の自動車部品メーカーを例に考えてみましょう。ERPは社内の在庫、購買、製造計画、会計、人事の各機能を統合して、日々のオペレーションを安定させます。原材料の発注から入荷、検品、在庫の回転までをリアルタイムで可視化します。SCMは海外のサプライヤー網と物流パートナーをつなぎ、部品がいつ、どのルートで届くかを最適化します。納期が逼迫している際には別ルートの検討や代替部品の選択、緊急の製造スケジュールの再構成を提案します。結果として、ERPが「内部の処理品質」を高め、SCMが「外部の供給安定性」を高めることで、全体の納期遵守率が向上します。
この実例から分かるのは、ERPとSCMは相互補完の関係にあり、どちらか一方だけでは完結しないということです。現場では、まずERPの土台を固め、その後SCMの外部連携を拡張する順序が取りやすいケースが多いです。
導入の流れとよくある誤解
導入の基本的な流れは、現状の業務プロセスの把握から始まります。現場のヒアリングを通じて、どのデータが最も価値を生むのかを特定します。次に、ERPとSCMのどちらを先に導入するべきかを判断します。多くの場合、内製化のためのリソースが乏しい企業ではERPの基盤を先に整え、内部のデータ品質を揃えるのが効果的です。そのうえでSCMの連携機能を追加します。
誤解として多いのは、ERPはSCMを置換できるという考えです。実際には両方を統合して初めて全体最適が達成されます。もう一つの誤解は、導入は一度で完結するというものです。現場の課題は時とともに変化します。最適化は継続的な改善プロセスであり、データ品質の維持、運用ルールの整備、教育訓練の実施が重要です。
この点を踏まえて、段階的な導入計画と定期的な評価会議を設けると成功率が高まります。
機能比較と実務上のポイント
この章ではERPとSCMの機能を比較し、実務上のポイントを整理します。
ERPの主な機能は会計、購買、在庫管理、生産計画、人事、顧客管理などです。これらは「内部の資源を最適化するための一連のデータと処理の集約」と言い換えることができます。
SCMの主な機能は需要予測、サプライヤー管理、調達、物流、配送、返品・品質管理などです。これらは「外部の供給網を滑らかにつなぐための連携と協調の機能」です。
実務では、ERPのデータがSCMの意思決定を支え、SCMの視点がERPの運用ルールを補完します。
以下の表で簡単に比較してみましょう。
この表から分かるポイントは、ERPは「内部の仕組みを整える」こと、SCMは「外部の動きを整える」ことを得意としているという点です。現場では、問題を見つけた時にまずどちらの視点から改善を始めるかを決め、その後両方の機能を統合していくと効率良く変化を生み出せます。
また、強いデータ品質と明確な責任範囲があると、ERPとSCMの連携はスムーズに機能します。データの整合性は全体のパフォーマンスに直結する要素なので、導入時のデータクレンジングと運用ルールの策定を優先する企業が多いのです。
あのね、ERPとSCMの違いを雑談風に深掘りするなら、朝の通学路の会話を思い出してみて。ERPは教室の机と椅子をきちんと並べて使えるようにする設計者みたいなもので、SCMは給食の配膳や机の移動順を決める運び屋さんみたいな役割。つまり、ERPが教室の内部を整える作業、SCMが外部の資源をスムーズに動かす作業。違いを混同すると、どちらかが空回りしてしまうけど、両方をバランス良く使えば、授業は始まり、昼休みにはスムーズに出欠がとれ、給食も時間どおり配られる。こんな感じで、実務でも“内部最適化”と“外部連携”を同時に意識するのが大切なんだよ。
前の記事: « epm erp 違いを徹底解説!中小企業が知るべき基礎と選び方
次の記事: 安全在庫と適正在庫の違いを理解して在庫コストを削減する秘訣 »





















