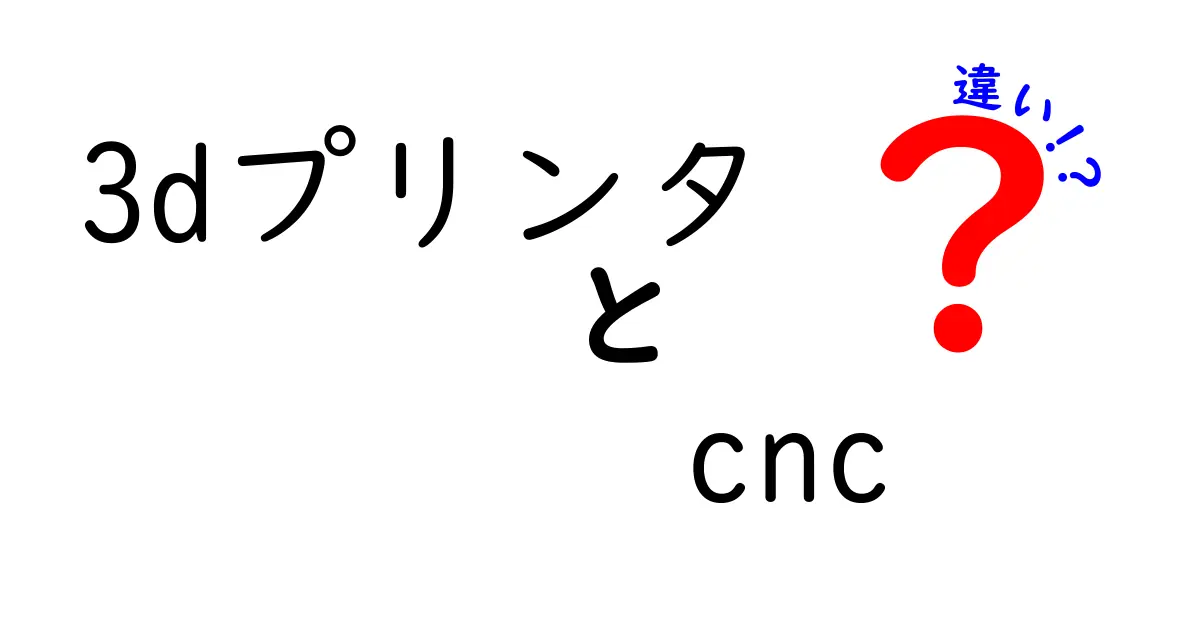

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
3DプリンタとCNCの違いを徹底解説!初心者が迷わず使い分けるポイント
ここでは「3Dプリンタ」と「CNC」の基本的な動作原理と、実際の使い分けのコツを、中学生にも分かる言い方で丁寧に説明します。まず大切なのは作る方法の違いです。3Dプリンタは材料を層ごとに積み重ねて形を作るadditive(付加)方式、CNCは材料を削って形を作るsubtractive(減算)方式という2つの根本的な考え方が根っ子にあります。仕上がりの質感や精度、使える材料、コスト、作業スペースの大きさなど、いろいろな点で差が出ます。ここからはその違いを、たとえば身の回りの身近な道具と比較しながら、やさしく見ていきます。
また、初心者が迷わず選べるように、実際の作業の流れや準備、注意点もセットで紹介します。
この知識は趣味の工作だけでなく、学習プロジェクトや小さな研究にも役立ちます。
最後に、簡単な比較表の代わりになるポイントも整理します。
それでは、まず基本の違いをしっかり理解しましょう。
1. 根本的な仕組みと材料の違いを知ろう
3Dプリンタは、材料を層ごとに積み重ねて形を作る性質が強いです。PLAやABSといった熱可塑性樹脂、または樹脂系のレジンを用います。使用方式は主に「フォトポリマー(樹脂)を紫外線で硬化させる方式」と「熱で樹脂を溶かして積層する方式」があり、選ぶ機材によって得られる表面の滑らかさや耐久性、熱の強さが変わります。対してCNCは素材を削ることで形を作るマシンで、木材・金属・硬質プラスチックなど、さまざまな材料に対応します。加工中の発生物は削りかすとして排出され、切削屑を処理するための換気や粉塵対策が重要です。
3Dプリンタは「層が積み重なる」こと自体が美しいコツであり、複雑な形状も比較的再現しやすい反面、強度を上げるには後処理が必要な場合があります。CNCは削る前の設計精度がそのまま仕上がりの精度につながり、素材の硬さが加工速度や工具選びに大きく影響します。
<強調ポイント> 材料選択と機械の特性は切っても切れない関係。あなたの作りたいものの形状・強度・表面の仕上がり・コストを総合して選ぶことが大切です。
また、付加的な作業としての段取りや治具の設計も重要で、CNCは治具の自由度が高い反面、治具作成に時間がかかることがあります。
ここでは、設計時にどちらの機械が適しているかを、具体例とともに理解していきましょう。
2. 作業の流れと現場での使い分け
3Dプリンタの場合、設計データを用意し、スライサーと呼ばれるソフトで「層の厚さ・充填率・サポート材」を決めます。次にプリンタにデータを送信して印刷を開始します。印刷中は機械の温度管理・ノズルの詰まり・材料の乾燥などに注意します。完成後はサポート材の除去、表面の仕上げ(サンドペーパーや化学的な仕上げ)を行います。全体の流れとしては「設計→設定→印刷→後処理」という順序で、部品の形状が複雑であればあるほどスライス時の設定が重要です。CNCは設計データをCAD/CAMソフトで作成し、工具路(ツールパス)を生成します。機械に材料を固定し、工具を回転させて徐々に形を削り出します。実際の加工では工具の種類(ドリル、エンドミル、バイト)や回転数、送り速度、切削深さなどを細かく調整します。加工中は切削音・振動・粉塵・冷却液の管理が重要で、適切なクーラントと換気を確保する必要があります。
3Dプリンタは初期投資が比較的低い機材が多く、教育現場や個人の学習には最適です。一方CNCは機材が大きくて高価になることが多く、金属加工への対応や航空機部品など高精度が求められる場面で活躍します。使い分けとしては、比較的小さく複雑な部品を量産しない場合は3Dプリンタ、耐久性が求められる部品や金属・高硬度の素材を扱う場合はCNCが適しています。
3. コストと学習曲線、初心者におすすめの使い分け
初期投資の観点から見ると、3Dプリンタは安価な機種が増え、家族でも手に入れやすくなっています。材料費もPLAなど手ごろなものが多く、教育現場の教材としても人気です。対してCNCは大型機械や高精度の工具、冷却システム、固定治具などが必要となり初期費用が高めです。ただし長期の運用コストは材料の削減分を考慮して判断する必要があります。学習曲線は3Dプリンタの方が入りやすい場合が多く、印刷設定の基本を覚えるだけで実用的な部品を作れるようになります。一方CNCは工具の選択や切削条件の理解、工具の寿命管理など学習項目が多く、最初は難しく感じるかもしれません。安全面では、3Dプリンタは高温ノズルへの接触など注意点が少なく、雨天でも安全に使用できますが、CNCは衝撃や切削時の飛散、粉塵の対策が重要です。
総合すると、趣味や学習用途には3Dプリンタが入り口として最適です。しっかりと基礎を身につけてから、必要に応じてCNCへステップアップするのが現実的な選択です。
最後に覚えておきたいのは、最良の結果は「目的に対して適切な道具を選ぶこと」です。形状・材質・量産性・完成までの時間など、さまざまな要因を考え、比較表のように頭の中で整理してから決めると失敗が少なくなります。
友達と放課後、3Dプリンタの話をしていたら、彼はこう言いました。『3Dプリンタっていうのは、材料を一度ずつ積み上げて形を作るんだよね。削っていくCNCとは違うんだ。』私は答えました。『そう、でも3Dプリンタにも裏側がある。設計が甘いとサポート材だらけになってしまうし、表面を滑らかにするには後処理が必要。つまり、用途と材料次第で最適解は変わるんだ。』この話題はただの雑談以上の学びに変わりました。彼と私は、使う材料の性質、仕上がりの段差、加工時間、費用、そして安全性について、熱心に語り合いました。結局、道具は目的を達成するための道具でしかない。使い方次第で、3Dプリンタは創造の翼になるし、CNCは実用的な部品を作る力になる。
次の記事: ターニングと旋盤の違いを徹底解説!初心者にも分かる基本と使い分け »





















