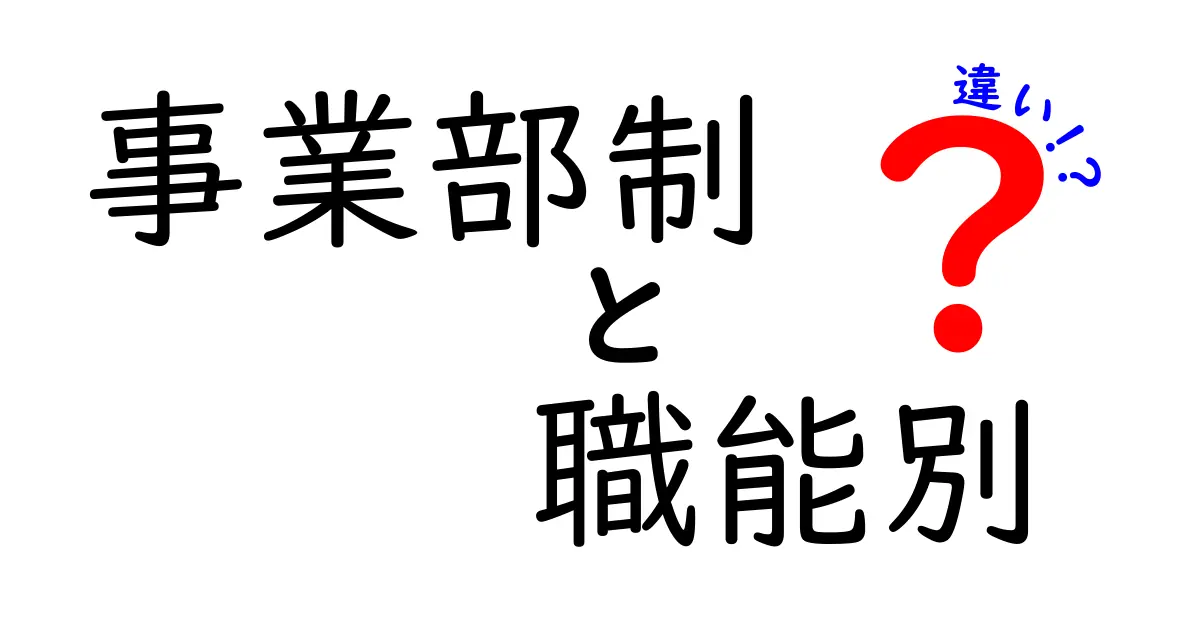

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
事業部制と職能別の違いをわかりやすく解説!
組織の形にはさまざまな考え方があります。事業部制と職能別は特に企業の成長や変化に大きく影響する二つの大きな枠組みです。事業部制は各部門が独立して責任を持ち、利益を出すための判断を自分たちで下します。職能別は機能ごとに専門家が集まり、協力して仕事を進めます。どちらを選ぶかで意思決定の速さ、資源の配分、評価の軸が大きく変わります。ここでは中学生にも分かるように、身近な例を使って違いを整理します。
まず知っておきたいのは目的が違うという点です。事業部制は新しい市場に挑戦したり新製品を育てたりする際に部門ごとに責任を持つことで動きが速くなります。
一方、職能別は専門家の技術や知識を最大限活かすことを重視します。
例えば製造部門、営業部門、経理部門などがそれぞれの専門の力を持ち寄って、全体の効率を高めようとします。
基礎知識:事業部制と職能別の成り立ち
まずこの二つの枠組みが生まれた歴史を知ることは、現場での使い方を理解する近道になります。事業部制は複数の事業を抱える企業が、それぞれの市場や顧客層に合わせて独立した判断をできるようにする考え方です。職能別は機能ごとに専門家を集め、専門性を高めつつ業務の効率化を図ります。両者の根底には「誰が何の責任を持つのか」という設計思想の違いがあります。歴史的には大企業が事業の多角化を進める過程で事業部制が採用され、専門性を重視する組織運営が求められる場面では職能別が主流となることが多いです。
この点を理解すると、なぜ同じ会社でも部署の働き方が大きく異なるのかが見えてきます。
実務に現れる違い:意思決定と専門性
意思決定の速度は組織設計の最も分かりやすい差です。事業部制では事業部が利益責任を担うため、戦略の判断が局所的に速く動く場面がありますが、部門間の連携が必要な案件では調整コストが増えることもあります。対して職能別では全体最適を目指す反面、横断的な調整が必要なときに時間がかかる場面もあります。
資源の配分はどのように予算を回すかという点で異なります。事業部制では各部門が自分の市場に合わせた投資を選択しやすく、失敗も部門単位で完結します。職能別では総務部門や人事など共通機能に資源が集まり、全社的な効率を狙います。
業績の評価はどの視点で見るかで変わります。事業部制では売上高や利益を部門別に評価します。一方職能別では部門横断の成果指標や、機能の効率改善を評価軸にすることが多いです。
比較表と事例
以下の表は特徴を要点だけ整理したものです。実務での判断材料として役立ちます。
導入のポイント
実際に導入を考えるときは、組織の規模、事業の性質、市場の変化速度、そして従業員のキャリア設計を総合的に考える必要があります。小さな会社では職能別の方が安定感があり、成長著しい分野では事業部制の方が変化に強い傾向があるでしょう。導入時には、責任の所在と評価方法を明確にし、部門間の協力体制をどう作るかを先に設計しておくことが肝心です。
まとめと活用のコツ
結局のところ大切なのは、組織設計は目的次第という点です。新規事業の拡大を最優先にするなら事業部制、既存のプロセスを最適化するなら職能別が適していることが多いです。現場では部門間のコミュニケーションを円滑にする仕組みづくり、評価の透明性、そして人材の交差研修によって、どちらの形態をとっても効果を高めることができます。最後に、現場の声を聞く仕組みを忘れず、失敗を学びとして次に活かす姿勢が組織の成長を支えます。
友達と話すとき、事業部制って“それぞれの部が自分のビジネスを持つ独立会社みたい”という例えをよく使います。たとえばお菓子メーカーが新しい味に挑戦する場合、味づくりを担当する部門と販売を担当する部門が別々に動くと、失敗しても全体の影響が最小限に済みます。だけど協力は必須。研究開発と製造、そして営業が協力しないと売れる商品にはなりません。そんな現場のつながりを、授業の課題のように整理するときには“誰が何をどう決定するのか”という点を先に決めるのがコツです。
次の記事: 事業譲渡と組織再編の違いを徹底解説!中学生にも分かる実務ポイント »





















