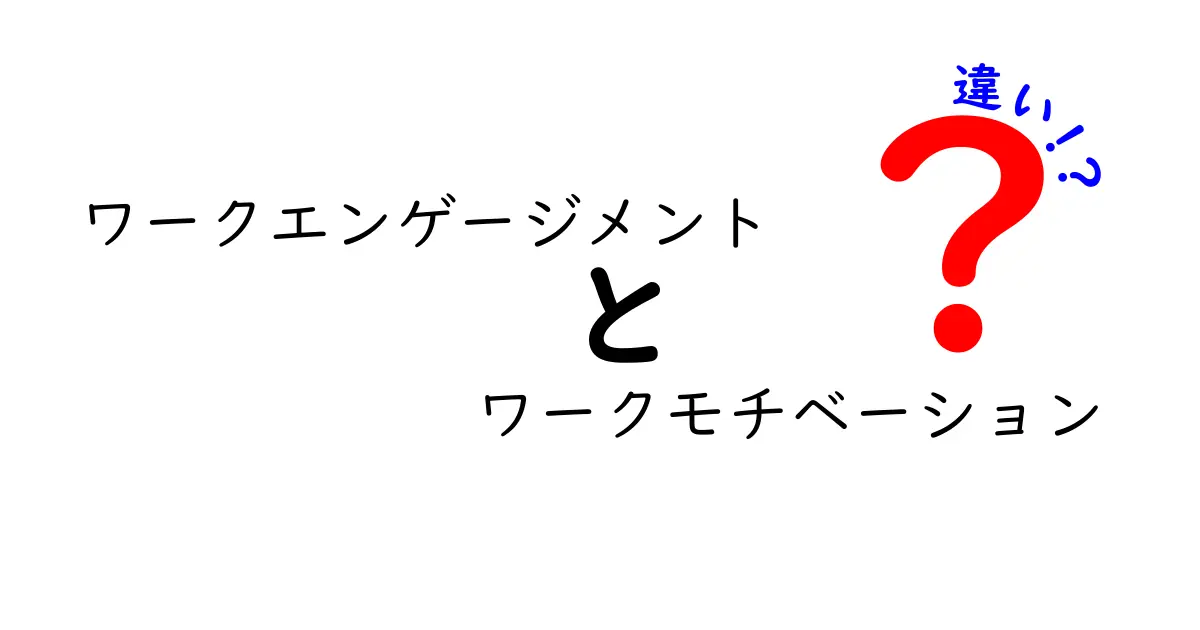

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ワークエンゲージメントとワークモチベーションの違いを理解する
ワークエンゲージメントとワークモチベーションは似ているようで、感じ方や影響する先が少し違います。まず、ワークモチベーションは内的・外的動機の組み合わせで生まれる心の状態です。やる気があるときには、達成感を感じたい、成長したい、報酬を得たい、周りの評価を上げたいといった欲求が原動力になります。これに対して、ワークエンゲージメントは日々の仕事の中で体感する心身の状態の総称を指します。簡単に言えば、モチベーションが心の中のスイッチのように点くかどうかに近いのに対して、エンゲージメントは職場環境と個人の関係性の総合的な状態です。
日常の観察が役立ちます。朝の出勤時に自分がどの程度元気に取り組めるか、難しい課題にぶつかったときの反応、協力的な雰囲気があるときの仕事への熱意、ミスを恐れて回避するのではなく挑戦する姿勢が出るかどうかなどを観察しましょう。
ワークモチベーションは個人の内面と外部報酬の組み合わせで揺れやすいのに対し、ワークエンゲージメントは長期的な職場環境の影響を受けやすい点が特徴です。つまり、転職や新しい仕事の話が出たときでも、エンゲージメントが高い人は職場の意味づけを見つけやすく、難題を乗り越える力が強まる傾向があります。
重要なのは、両者を別々に育てることです。モチベーションを高めることは短期の効果が出やすいですが、持続的なエンゲージメントを作るには適切な業務量、支援の文化、同僚との信頼関係、明確な目標とフィードバックが必要です。日々の工夫を積み重ねることが、長期的な成果につながります。
ワークエンゲメントの三つの要素と実感のつかみ方
ワークエンゲージメントの三つの要素は、活力と献身と吸収です。活力は仕事に取り組むときのエネルギーの強さを意味し、朝の準備や難題に向かう力を決めます。献身は仕事への心の関与度であり、自分の役割に意味を感じ、長期的な目標とつながっている感覚を表します。吸収は仕事に没頭して時間を忘れる状態であり、業務の細部に集中する力を表します。これらがそろうと、日常の業務は単なる作業ではなく意味のある挑戦として感じられます。
例えば難しいプロジェクトに取り組むとき、活力があれば疲れを感じにくく、献身があれば周囲との協力を自分ごととして捉え、吸収があれば新しい知識を積極的に吸収します。この三要素は互いに補い合い、全体としてのパフォーマンスを高めます。実務上は定期的なフィードバックと適切な難易度のタスク、休憩の取り方、仲間との信頼関係が三要素の発展を後押しします。
実践的な育て方としては職場設計が大事です。適度な難易度の仕事、明確な目標とフィードバック、同僚との信頼関係、そして自分が意味を感じる仕事の選択肢が組み合わさると、三要素が同時に高まります。これを支える仕組みには定期的な1対1の会話、業務量の見直し、成功体験の共有、達成感を認める文化が挙げられます。さらに個人レベルでは、自己の強みを活かせるタスクを選ぶ、短い休憩を活用してリフレッシュする、仕事の意味を言語化するなどの工夫が有効です。
今日は友達と放課後の会話をしていて、ワークエンゲージメントの話題が出ました。僕は彼に、エンゲージメントとモチベーションの違いを自分なりの例で説明したんです。例えば部活での練習を思い出してみると、モチベーションが高いときは“やる気が出る”瞬間はあるけれど、長続きしないことも多い。でもエンゲージメントは日々の練習の中で自然と力が湧いてくる感覚で、時間が経つのを忘れるほど集中できる状態だ、という話をしました。彼は最初は難しそうだと言っていましたが、実際の練習風景を観察すると、エンゲージメントが高い選手は責任感が強く、他の人と協力しながら困難を乗り越える姿勢が見えると気づいたそうです。私は、職場でも同じことが起きると信じています。強い動機だけでなく、周囲の支えと意味づけが揃うと、仕事への向き合い方が変わるのです。
次の記事: パワハラと叱責の違いを徹底解説!見分け方と実務での対応ポイント »





















