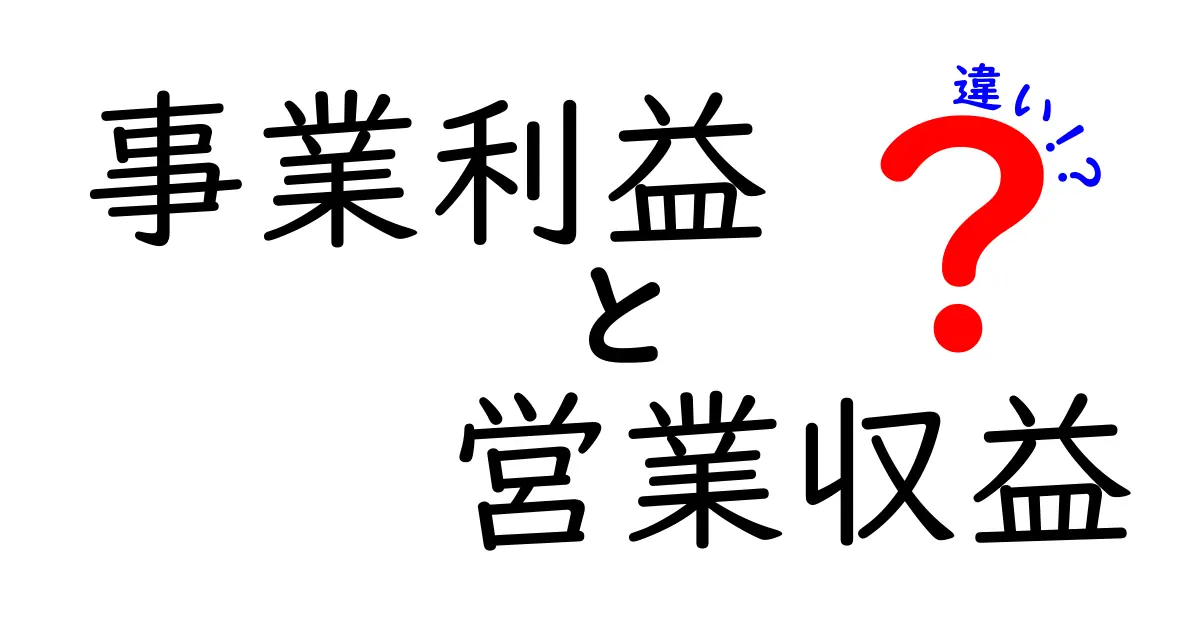

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
イントロダクション:なぜ「事業利益」と「営業収益」の違いを知る必要があるのか
現代のビジネスの現場では、財務の数値を正しく読む力がとても大切です。とくに「事業利益」と「営業収益」といった用語は、似た響きで混乱しやすい指標です。営業の現場では売上を上げることが重要ですが、経営の視点では売上だけではなくその後の利益の動きを知る必要があります。ここでは中学生にも分かる言い方で、2つの用語の意味と違いを丁寧に解説します。さらに実務での使い分けのコツも紹介します。読んだ人がすぐに現場の会計を読み解けるようになることを目指します。
まずは結論を先に伝えます。営業収益は主な事業から得られる売上の総額であり、数値の大枠を示す指標です。一方で事業利益はその売上から原価と費用を引いた後に残る、企業が本当に稼ぐ力の中心の数字です。
この違いを理解しておくと、部門の改善点を見つけやすくなり、社内の会計資料を読み解く力が上がります。
違いの基本を押さえる:用語の定義と計算の仕組み
ここでは具体的な定義と計算の流れを分かりやすく整理します。営業収益とは主な事業活動から得られる売上高の総額です。つまり売上高に相当する数字です。対して事業利益はその売上から売上原価と販管費(販促費や人件費、管理費など)を差し引いた後の利益です。つまり事業利益は実際に企業が機能している力を示す指標であり、購買・生産・販売といった一連の活動がどれだけうまく回っているかを映します。計算の順番としては、まず売上高を出し、次に売上原価を引き、さらに販管費を引くのが基本です。これを式で書くと、営業収益は売上高、事業利益は営業収益から売上原価と販管費を引いた値となります。なお売上総利益という概念もあり、これは売上高 minus 売上原価で算出され、そこから販管費を引くと事業利益になるという流れです。実務ではこの3つの段階を別々の勘定科目として管理することで、部門ごとの儲けを正確に把握できます。以下の表も参考にしてください。
また補足として売上総利益と事業利益の違いをよりイメージでつかむと良いです。売上総利益は「作る力の部分」、販管費を引くときに何が削れるのかが分かり、最終的に事業利益へとつながります。企業はこの連なりを月次や四半期ごと、部門別に分析して、どの活動がより利益を生むのかを判断します。ここまでの理解を実務に落とすときには数値の出所を明確にし、データの前提条件を揃えることが重要です。
具体的には、材料費が増えた時に売上が同じなら利益が落ちるのか、逆に販管費を見直してコスト削減が進んだか、といった点を数字で追います。
実務での使い分けと注意点
現場ではこの2つの指標を別々に見る利点があります。営業収益は売上の総量を把握する指標なので、マーケティングや販売戦略の効果を評価する際に役立ちます。たとえば販売キャンペーンを行った場合、売上が増えるかどうかをまず営業収益で判断します。一方、事業利益はコストを抑えて利益を増やす力を示すので、原価管理や費用削減の施策の成果を測るのに適しています。実務上のポイントとしては、原価管理の徹底、販管費の最適化、部門別の利益貢献度を揃えて定期的に比較することです。数字の読み方が分かれば、どの部門が効率的に働いているのか、どこを改善すれば全体の利益が伸びるのかが見えてきます。月次の決算資料を読み解くときには、前提となる会計処理の違いにも注意しましょう。ここではさらに実務に役立つポイントを三つ挙げます。第一は短期の売上と長期の利益のバランスを考えること。第二は部門ごとのコスト構造を理解すること。第三は真の利益を測る際の補助指標としてEBITDAや営業利益率も見比べることです。
よくある誤解と正しい読み方
誤解の一つは営業収益と売上高が完全に同じ意味だと思うことです。実務では用語の使い分けがあるので、資料ごとに定義を確認する癖をつけましょう。もう一つは事業利益が大きいほど良いと勘違いすること。もちろん高い方が良いですが、利益を押し上げるには売上高の成長だけでなく原価と費用の抑制が必要です。最後に表や決算短信を読むときには、前提となる会計処理の違いにも注意しましょう。
友達とカフェで雑談しています。彼が「事業利益って何だろう」と聞いてきたので、私はこう答えました。事業利益は売上高から原価と費用を引いた“実際に儲けた量”を示す数字で、会社がどれだけ効率よくお金を生み出しているかの目安になります。一方で営業収益は売上の総額、つまりどれだけ売れたかの合計のこと。売上が大きくても費用が多ければ最終的な利益は減ることもあるわけです。だから数字を並べて見比べる習慣をつけると、どのコストを削れば利益が伸びるのかが見えてくるようになります。こう考えると、決算資料を読んでも“なんとなく分かった”から“どこを改善すべきか”を具体的に指摘できる力が育ちます。





















