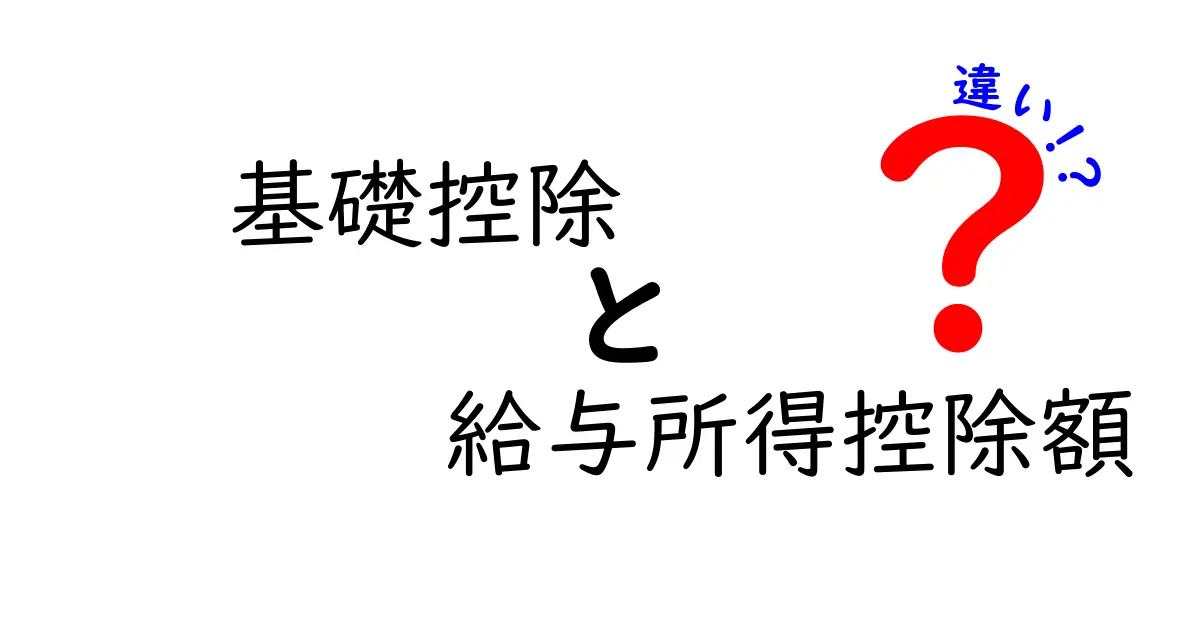

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
基礎控除と給与所得控除額とは何か?
税金の計算をするうえでよく耳にする「基礎控除」と「給与所得控除額」。どちらも所得税を軽減するための仕組みですが、その役割や適用される場面が違います。今回はこの2つの控除が何なのか、どう違うのかを中学生でも分かりやすい言葉で解説します。
まず、基礎控除とは所得に対して一律に適用される控除額のことです。これは所得の種類に関わらず、誰でも一定額を差し引いて税金の計算を行います。これに対して、給与所得控除額は給与所得者専用の控除で、給与収入の金額に応じて控除額が決まります。給与をもらっている人だけに適用される特別な控除です。
つまり、基礎控除は万人に適用される基本的な控除で、給与所得控除は給与所得者向けの控除ということになります。これらを理解すると、税金の計算の仕組みがより見えてきます。
基礎控除と給与所得控除額の具体的な違い
では、具体的にどう違うのか?ここでは両者の違いを表で比較してみましょう。
| 項目 | 基礎控除 | 給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 適用対象 | すべての所得者 | 給与所得者(会社員、パートなど) |
| 控除額の決まり方 | 一律48万円(2023年以降) | 収入金額に応じて変動(例:収入が増えると控除も変わる) |
| 控除の目的 | 税負担の軽減・最低限の生活保障 | 給与所得者の経費見合い(仕事にかかる費用相当分) |
| 計算時の使い方 | 課税所得全体から差し引く | 給与の収入金額から差し引いて給与所得額を算出 |
このように基礎控除はすべての人の所得税計算の基本となる控除で、給与所得控除額は給与収入を得るための必要経費とみなして計算する控除です。
例えば、給料が500万円の人の場合、給与所得控除額は約154万円(2023年基準)となり、この金額を差し引いて課税対象となる給与所得額を出します。そこからさらに基礎控除48万円が適用されて最終的な課税所得が決まります。
基礎控除と給与所得控除額を理解することのメリット
これらの違いを正しく理解すると、給与所得者でもそれ以外の所得者でも自分の税金がどうやって計算されているかが見えてきます。
特に給与所得控除額は、サラリーマンやパートの人にとっての年収の“手取り”を考える際の大切な要素です。給与所得控除額があるため、経費の心配をせずに収入から一定額が控除されるので安心して働けます。
一方で、フリーランスや自営業の人はこの給与所得控除は使えず、必要経費を自分で申告して税金を計算します。基礎控除は誰でも使えるので、最低限の税負担を守るためにとても重要です。
この2つの控除の違いを知ることで、将来自分が働き方を変えたり、副業(関連記事:在宅で副業!おすすめ3選!【初心者向け】)を始めたりするときの税金対策にも役立つでしょう。
まとめ
ここまで、「基礎控除」と「給与所得控除額」の違いについて解説しました。
- 基礎控除は全ての所得者に適用され、税金計算の最初に一律に差し引かれる控除です。
- 給与所得控除額は給与を得る人専用の控除で、収入に応じて控除額が変わり、給与所得を計算するために使われます。
両者を正しく理解しておくことで、税金の仕組みがよくわかり、正しい申告や節税を目指せるようになります。
ぜひこの機会に、基礎控除と給与所得控除額の違いを押さえておきましょう!
給与所得控除額は、サラリーマンなど給与をもらう人の"必要経費"のような役割を持っています。実は、実際の経費を細かく計算しなくても、国があらかじめ一定の控除額を設けてくれているんです。これによって給与所得者は自分で領収書を集めたり経費精算をしなくても節税できるので、とても便利な制度ですよね。逆にフリーランスは自分で経費を計算する必要があるので、働き方によって控除の仕組みが変わる点も面白い話です。





















