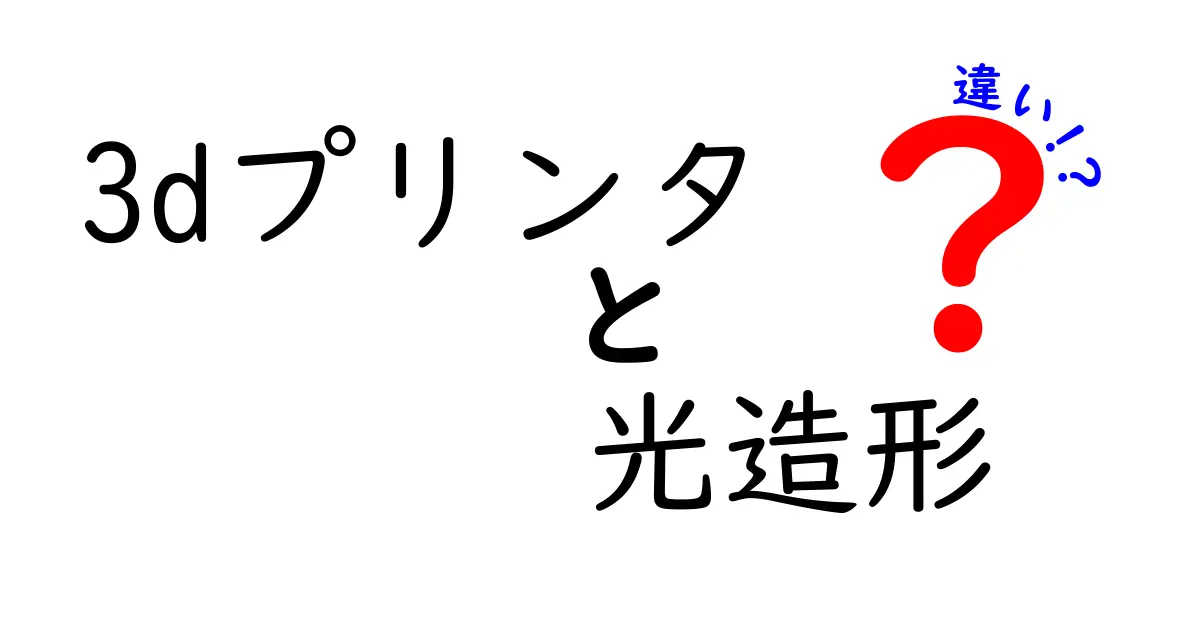

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
導入:3Dプリンタの基本分類と光造形の位置づけ
現代の3Dプリンタ市場には、FDM/FFF、SLA/DLPなどの光造形、金属3Dプリンタなど、複数の技術が混在しています。FDMは材料の溶融と押し出しによる積層で比較的安価に始められる一方、光造形は樹脂を紫外線で硬化させる方式で高い解像度と滑らかな表面を実現します。光造形は元々医療機器や精密部品、プロトタイプの段階で高い評価を得てきました。とはいえ、材料費が高く樹脂の取り扱いが難しい、サポート材の処理が手間といった欠点もあります。したがって、目的・予算・運用環境に応じて、FDMと光造形のどちらが適しているか判断することが大切です。本稿では、初心者の方にも「何が違うのか」を分かりやすく整理し、実際の選択や運用時のコツを紹介します。
まずは市場の現状を整理します。家庭での試作から産業用途まで、用途ごとに選ばれる傾向が変わります。FDMは強度を出しやすくコストも抑えられるため、箱ものや大きな部品の試作に向く一方、光造形は細かなディテール・滑らかな表面・高精度を求める場面で力を発揮します。光造形を使えば、曲面の連続性や細かな孔の再現性が高く、組み合わせた部品の動作検証もしやすいのが特徴です。ただし樹脂の収縮・反り、硬化時の収縮歪みといった問題には対処法があり、初期の段階で適切な設定を学ぶことが重要です。
光造形とは何か
光造形の核心は、紫外線を使って液体の樹脂を段階的に硬化させるところにあります。SLAやDLPといった方式があり、それぞれ光源や投影方法が異なります。硬化する速度は樹脂の成分に左右され、写真反応性のあるモノマーが多く配合されています。一般的には、樹脂は硬度と透明度のバランスを取りながら、用途ごとに選択します。初期投資としては機材の価格と樹脂の消費量が大きな要因になりますが、正しい使い方を覚えると、設計した形状を高精度で再現できる喜びが得られます。樹脂の種類には、透明性を重視したタイプ、耐久性を重視したタイプ、柔軟性を重視したタイプなど、用途に応じて多様な選択肢があります。
導入時には、機材の据え付けスペース・換気・安全対策・廃棄方法を事前に決めておくと、後のトラブルを避けやすくなります。
光造形と他の方式の違いを比較
光造形と他の3Dプリンタ方式を比較すると、まず「解像度と表面の美しさ」が顕著な違いとして挙げられます。光造形はミクロン単位の解像度を実現し、層の境界が目立ちにくい滑らかな表面を作りやすいのが大きな特長です。対してFDMは層の積み重ねが肉眼で分かる場合があり、荒い表面になることが多いですが、部品の強度や大きさの自由度は高い傾向があります。また、材料コストの違いも大きく、FDMではPLAやABSなどの低価格素材が利用されるのに対し、光造形では樹脂カートリッジの価格と消費量が全体コストに直結します。
用途の面では、光造形は複雑な内部形状や薄肉のディテールを正確に再現できるため、プロトタイピングや試作品、デザイン検証、最終部品の前段検証などに向きます。FDMは大型の試作や機械的な荷重を想定した部品、低コストの概算モデル作成に適しています。後処理の手間は、光造形の方がサポート材の除去や表面研磨、樹脂の硬化後の洗浄などのステップがある分大きくなることがあります。
材料の性質を比較すると、光造形樹脂は硬さ・柔軟性・耐薬品性・透明度など多様な特性を持つタイプがあり、設計の意図に合わせて選択します。FDM素材は強度と耐熱性のバランスを取りつつコストを抑える方向性が強く、家具や小物の部品、機械のプロトタイプなど幅広い用途に対応します。最後にランニングコストと保守性を見ていくと、光造形は樹脂の在庫管理・廃棄・洗浄剤の取り扱いなどで日常運用の労力が増えることがあります。一方FDMはフィラメントの保管やプリントベッドの清掃など、日常的なメンテナンス項目が比較的シンプルです。総合的には、目的・予算・運用環境を総合的に考慮して選ぶのが最も賢いアプローチになります。
材料・仕上がりの違い
材料と仕上がりの違いは、最終用途のイメージに直結します。光造形で使われる樹脂は、透明度・硬度・靭性・耐熱性の組み合わせが豊富であり、設計の要件に合わせて最適な樹脂を選ぶことが重要です。薄い壁や小さな穴、複雑な内部構造を正確に表現できる点は光造形の大きな強みです。ただし樹脂部品は脆性が高く、荷重を長時間受ける部品には向かない場合があります。したがって、耐久性が必要な部品は設計時に厚みを検討したり、鋼材などの金属代替案を検討することで安全性と耐久性を確保します。FDMは固体のプラスチックを積み重ねて作るため、耐荷重・耐温度の要件を満たす設計が比較的得意です。なお、表面仕上がりの美しさは光造形の方が優れていることが多く、玩具やコレクションモデル、デザインサンプルなどでその違いを実感しやすいです。
次にコスト面について触れます。光造形は材料費が高めで、樹脂の使用量と廃液処理のコストが発生します。FDMはフィラメント価格が比較的安価で、初期投資を抑えやすいという利点があります。ただし、部品の大きさが大きくなると材料費が膨らみやすく、設計の見直しや分解組みを検討する必要が出てきます。運用時間と後処理の手間を含めた総コストで比較すると、短期的な試作ではFDM、長期的な高精度の試作や量産前の検証には光造形が適してくるケースが多いです。
光造形を選ぶときのポイントと注意点
光造形を選ぶときは、まず用途と求める表面品質を明確にすることが大切です。高精度の部品や外観品質が重視される場合は光造形が適していますが、部品の荷重や耐久性が問題になる場合は設計の見直しやFDMとの組み合わせも検討します。樹脂選択や露光条件、サポート材の扱いなど、設計者の想いを形にするには、プリント前のデザイン段階で材料特性を反映させることが重要です。初期投資のコストだけでなく、運用時の材料ロス、清掃・廃棄方法、換気・作業環境の整備も忘れずに計画しましょう。
実務的なポイントとしては、樹脂の取り扱いは手袋と保護具の着用、換気の確保、保管温度の管理など、安全対策を徹底することが挙げられます。プリント後には洗浄・硬化・仕上げの順序を守り、表面を滑らかに整えるための研磨・コーティングの工程を取り入れると、完成度が大きく向上します。最後に、信頼できる樹脂ベンダーやサポート体制を持つメーカーを選ぶことは、長い目で見ればトラブルを減らし、学習効果を高める大きな要因になります。
ある週末、友人と部屋で自作の小さなフィギュアの話をしていました。友人は光造形に興味があり、私はFDM派。彼は「光造形は表面がすごく滑らかで、細かい穴や微細なディテールまできっちり再現できるんだ」と語りました。その一言がきっかけで、素材選びと設計の考え方が変わっていきました。結局、同じデザインでも露光時間や樹脂の種類を少し変えると、像が硬くなったり透明感が増したりするという話を聞くうちに、技術は道具以上の“設計の延長線”だと実感しました。デジタルで描く設計と、現実の材料がどう反応するかを同時に考えることで、創作の幅がぐんと広がるのです。そんな会話の中で、私たちは“失敗は成功の母だ”という言葉を再認識しました。試作を重ねるほど、どの樹脂・どの露光条件が最適かが体で理解できるようになり、次はどんな作品に挑戦するかを語り合う時間が楽しくなっていきました。
前の記事: « 2sと5sの違いを完全解説!写真・動画・日常で使い分けるコツ





















