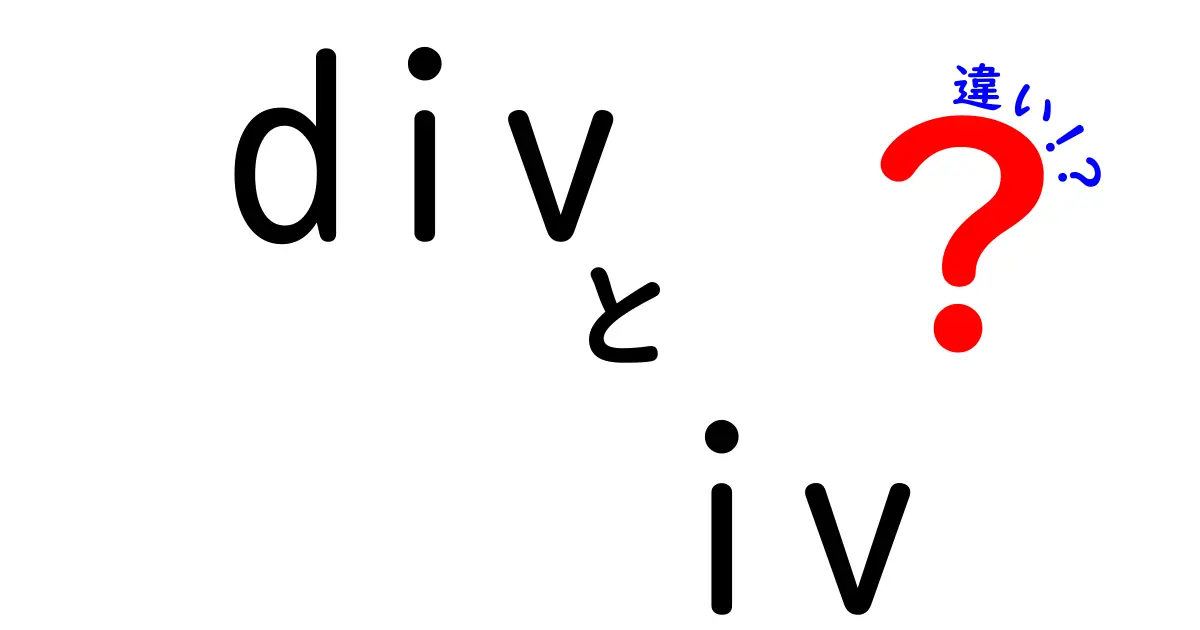

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
divとivの違いを理解する基本
ウェブページを作るとき、レイアウトを整えるための「箱」の役割を果たすのが div というタグです。divはHTMLのブロックレベル要素であり、他の要素の前後に新しい行を生み、幅や高さを CSS で自由に調整できます。
一方で iv という名前のタグは HTML には存在しません。ivは公式のHTMLタグではなく、見かけるときは多くがタイポ(誤字)か特定のフレームワークのカスタムタグの可能性 があります。表示の仕組みを理解するにはまず div の性質を覚えるのが近道です。div を使えば見出しのグループ、記事のセクション、サイドバーの領域など、「区切りの箱」を作れます。
ただし重要なのはこの箱が何を意味するかではなく、意味付けと構造をどう表現するかという点です。たとえば div の内部に見出しや段落を並べるときには 適切な意味的要素を選ぶことが大切です。下記の例と比較表を使って理解を深めましょう。
div は本来の目的としてレイアウトとグルーピングに向き、意味を兼ねる要素があるときには適切なセマンティック要素を使い分けます。
実際の使い分けとWeb開発での注意点
div の使いどころは、セクションやレイアウトの枠を作るときです。セマンティックな意味を意識する と、後の CSS や JS での操作が楽になります。
ただし狭い範囲のスタイルだけを当てたいときや、複数の要素をグループ化する必要がある場合には div によるラッピングが最適解になることが多い です。意味を持つ要素を使うべき場合には section, article, header などの要素を使ってください。
iv についての再確認としては、公式タグではないので混乱の原因になりやすいです。もしコード上で iv のような表現を見たら、それは タイポの可能性 や フレームワーク固有のカスタムタグの可能性 を疑い、ソースを確認してください。
ここからは実務的な注意点を挙げます。
- レイアウトを CSS の Flex あるいは Grid で組むときは div の活用度が上がります。
- アクセシビリティの観点からはセマンティック要素を優先し、スクリーンリーダーの読み上げ順を意識します。
- 目的がデータの意味付けにもあるなら strong などのタグを使い、可能なら aria による説明を付けます。
表の内容を踏まえると、現場では div を中心に使い分けつつ、意味を持つ要素へ置換する判断が大切です。
また新しいページを作るときは 可能な限りセマンティックな要素を優先して使い、SEO や accessibility の観点を忘れないようにしましょう。
ここでのポイントは、div自体は強力な道具だが意味の補填が必要な場面が多い、という点です。
div の話を深掘りする小ネタ 昨日友達と勉強会をしていて、 div の使い分けの話題になりました。友達は「 div ばかり使って CSS でしか形を整えない」と不安げでしたが、私は静かにこう言いました。
「div は箱を作る機能だけを担う。だからこそ意味を持つ要素を賢く使えば、後から CSS の見直しだけで大きなレイアウト変更が可能になるんだ」と。
実際、ニュースサイトのように見出しと本文を組み合わせる場合、div でグルーピングしておくと、後からセマンティック要素に切り替えるだけで構造がはっきりします。
つまり div は道具箱のような存在。使い方に正解はなく、目的に合わせて最小の意味を保ちつつ適切に使い分ける感覚が大切です。
前の記事: « 色校正と色見本の違いを徹底解説!初心者にも分かる色の世界





















