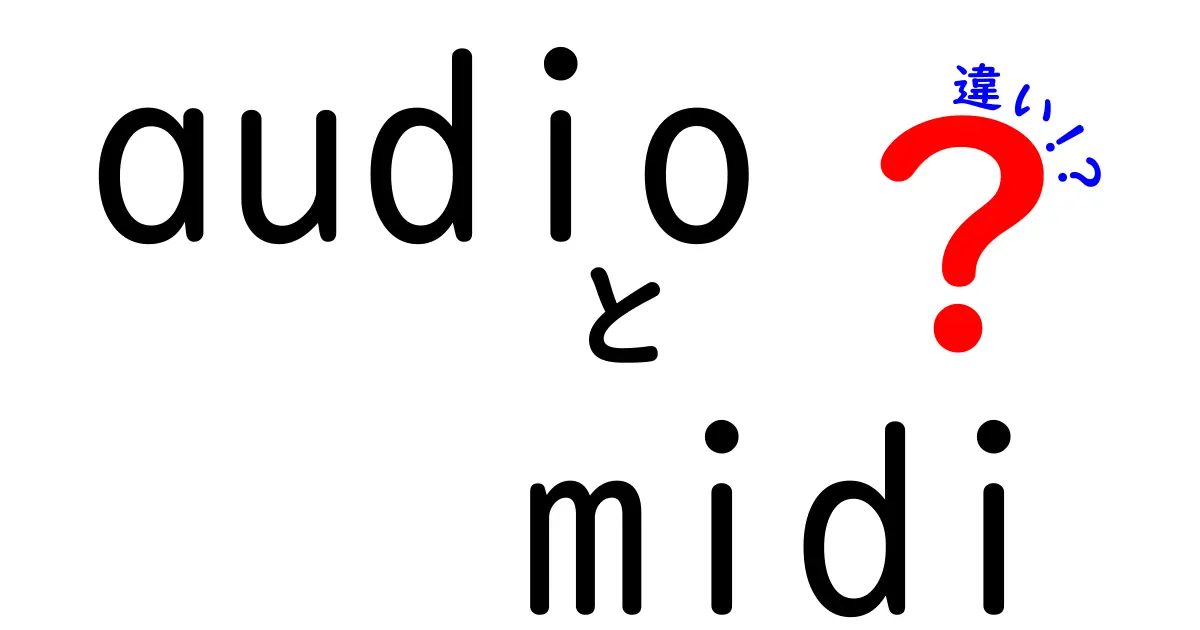

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
音声とMIDIの違いを理解するための完全ガイド
音声ファイルとMIDIデータは音楽制作の世界でよく登場しますが、初心者にとっては混同しやすい用語です。この二つは見かけが似ているように思える時もありますが、実は指し示しているものが全く違います。まず音声ファイルとは実際に聴こえる音そのものを保存したデータです。ノートの音階や楽譜の情報を別に持つわけではなく、私たちが耳で聴く音がそのままデータとして保存されます。これに対してMIDIデータは、音を鳴らす“指示書”のようなもので、どのノートをいつ鳴らすかといった演奏情報を伝える信号です。つまり音として鳴る仕組みが別物であり、取り扱い方も大きく異なります。
この違いを理解することは、音楽を作るときの戦略を決めるうえでとても大切です。音声ファイルは完成形としての聴感をそのまま伝えますが、編集の自由度はMIDIに比べると限定的なことが多いです。MIDIは演奏情報をいじれるので、同じメロディーでも楽器を変えたりテンポを変更したりするのが容易です。だから初期のデモ作成や楽曲のアイデア出しにはMIDIが適しており、完成版には素材の音声を足していくという作業フローを作れます。音声は最終的な演奏そのものとして聴かせることが多く、MIDIは作業の設計図として機能するケースが多いのです。
この記事では音声とMIDIの基本的な性質と、現場での使い分けのコツを中学生でも分かる言葉で丁寧に解説します。加えて、データの容量や編集の手間、再生環境の影響といった実務的なポイントも忘れずに伝えます。
音声ファイルとMIDIデータの基本的な違い
まず、音声ファイルは波形データです。波形データは連続した時間の音の振幅を数値として並べたもので、CDやスマホに入っている曲はこの形で保存されています。波形は耳で聴く音の実物そのもので、再生機器の性能や環境ノイズにも左右されます。データ量は基本的に大きく、音楽の長さが長いほど容量が増えます。もう一方の MIDIデータは、音そのものを鳴らす材料ではなく、どのノートをいつ鳴らすかを指示する情報です。つまりMIDIデータは楽器の演奏指示書のようなもので、音源によって同じMIDIを読んでも聴こえ方が変わることがあります。
この違いは作業上の自由度にも直結します。音声データは一度録音が始まると全体の調整は複雑で、EQやコンプなどのエフェクトをかけても音色そのものを変えるのが主な手段です。MIDIはノートの位置や長さ、ベロシティと呼ばれる発音の強さなどのパラメータを個別に動かせるので、同じ曲でも楽器を変えたりテンポを変えたりするのが容易です。だから初期のデモ作成や楽曲のアイデア出しにはMIDIが適しており、完成版には素材の音声を足していくという作業フローを作れます。音声は最終的な演奏そのものとして聴かせることが多く、MIDIは作業の設計図として機能するケースが多いのです。
実用シーン別の使い分けと注意点
実際の現場では、用途に応じて音声と MIDI を使い分けます。自宅の音楽制作なら、まずMIDIでアイデアを練ってから、後で実際の楽器音やボーカルを録音して完成させるという流れが多いです。ゲーム音楽や映画のサウンドデザインでは、MIDIで細かな演奏指示を管理しつつ、多様な音色を組み合わせることで時間とコストを節約します。音声ファイルは完成形としてそのまま配布しますが、MIDIは別の音源やアプリで再現性を調整できるため、長期的な保守性にも有利です。
注意点として、MIDIは機材やソフトウェアの対応に左右されやすい点があります。OSやDAWのアップデートで受ける影響、使用するVSTi(仮想楽器)の品質、サンプルレートやテンポの整合性などをきちんと管理しないと、意図した演奏と異なる音色になってしまうことがあります。逆に音声データは再生環境の差はあるもののその場の音として再現されやすく、聴く人に伝わる印象は安定します。こうした特性を理解して、制作の初期段階から適切なデータ形式を選ぶことが成功のカギになります。
MIDIデータを使って音楽を作るとき、まずノート情報を組み立てる工程が楽しいです。音の高さや発音の強さを微調整するたび、同じメロディーでも別の表情が生まれます。私は初めてMIDIを触ったとき、テンポを少し上げただけで印象が変わることに驚きました。MIDIはまるで設計図のように曲を書き換えやすく、別の楽器音源に差し替えれば新しい曲をすぐ試せます。とはいえ、最終的な聴感を作るには音声データとの組み合わせが大切で、MIDIだけでは伝わりにくいニュアンスもあるので、その点を忘れずに使うと良いでしょう。





















