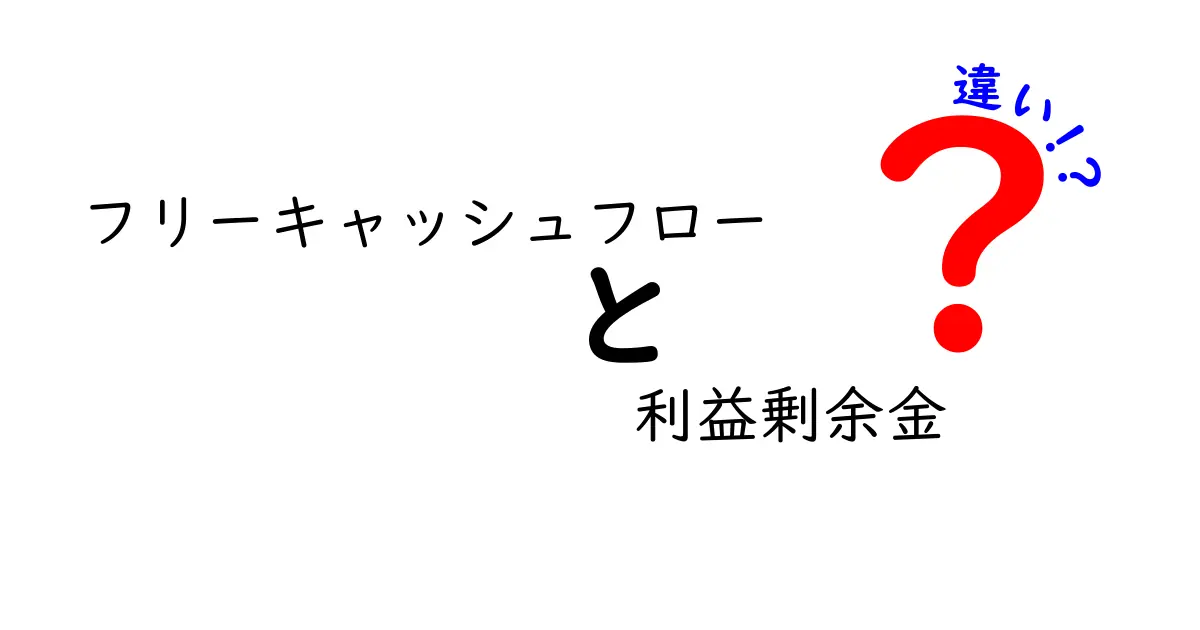

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:フリーキャッシュフローと利益剰余金の違いを知る重要性
財務用語は難しく見えるけれど、フリーキャッシュフローと利益剰余金は「企業のお金の使い方と貯め方」を示す基本的な指標です。
この2つを混同すると、会社の実力や経営判断を誤解してしまうことがあります。
まず、それぞれの意味を正しく押さえることが大切です。
フリーキャッシュフローは「現金が自由に使える状態」を示します。
利益剰余金は「過去の利益の蓄積」であり、資本として企業の財務諸表に積み上がる部分です。
この違いを理解すると、企業の現金創出能力と内部留保の性質が別物だと分かります。
本記事では、日常のニュースで見かける言葉の背景と、実務でどう使い分けるべきかを、中学生でも分かるように図と例で解説します。
最後には要点を表にまとめ、実務での判断に役立つ3つのポイントを提示します。
まずは基本を押さえ、混同を避けることが第一歩です。
違いを理解するための基本的な考え方と事例
では、具体的に両者の違いを整理します。
フリーキャッシュフローは企業が自由に使える現金の総量を示し、
資金繰りや投資余力、借入の返済力を判断する材料になります。
一方、利益剰余金は過去に積み上げた利益の蓄積であり、株主配当や自己資本の充実、将来の不測の事態に備える資本として企業の貸借対照表の内部で留保されてきました。
このように、現金ベースの“使えるお金”と、財務的な“資本の蓄え”は別物です。
実務では、プロジェクトの意思決定や資本政策を考える際に両者を混同せず、どの指標を見て何を判断したいのかを明確にすることが重要です。
次の表で、両者の定義・計算の違いを整理します。
友達とカフェでフリーキャッシュフローの話をしていたとき、彼は“現金が自由に使える状態って、どういうこと?”と尋ねてきました。私は「要は今すぐ投資や返済に回せる現金がいくらあるか」という現金の自由度の話だと答え、同時に利益剰余金は「過去の黒字を積み上げた貯金」だと説明しました。その後、ゲーム機を買う話と将来の設備投資を比較する雑談をしました。現金は動くが、留保は蓄える力。両者は同じ“お金”でも役割が違う、と私は話しました。会話が終わるころには、財務の話は机上の計算だけでなく日常の感覚と結びつく、という感覚を二人で共有できました。この体験は、現金と内部留保の違いを実務で意識する第一歩となりました。





















