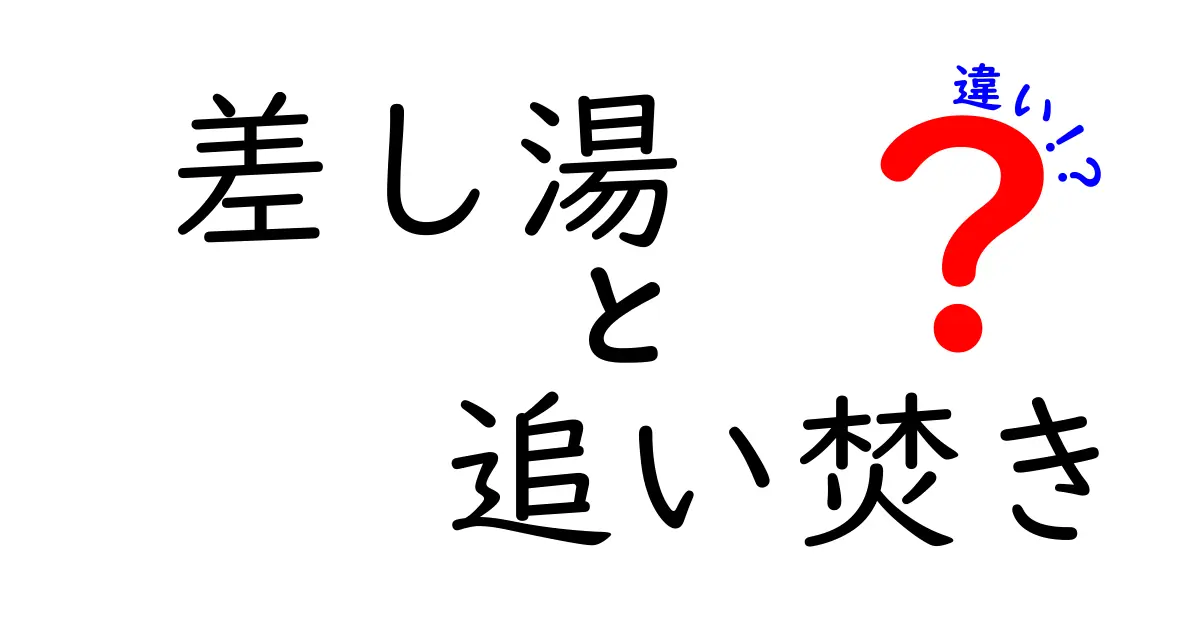

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
差し湯と追い焚きの基本
差し湯とは、浴槽の水温を適温に保つために別の湯を追加する行為を指します。家庭ではお風呂を沸かした後に湯温が下がることがあり、その場合には 水を足して温度を再調整します。差し湯は通常、熱湯をそのまま注ぐのではなく、温度が高すぎない範囲の温水を、少しずつ少量ずつ注ぐ方法が基本です。これにより、体が急激に温まるのを避け、湯のムラを減らす効果が期待できます。差し湯をする際には温度計で水温を測り、浴槽の温度と差が大きくならないよう慎重に調整します。
また、差し湯には水質の影響にも注意が必要です。長時間の使用や頻繁な追加は、湯の成分濃度を変え、浴槽の壁や排水口に結晶や沈殿を作ることがあります。特に硬水地域ではカルシウムやマグネシウムの沈着が起こりやすく、衛生面の管理が難しくなることもあります。したがって、差し湯は「温度を保つ」目的に絞って活用し、必要な時だけ行うのが安全です。さらに、浴槽の材質が木製や特殊な塗装の場合は、温度変化が材質にダメージを与えることがあるため、取扱説明書の指示を必ず確認しましょう。差し湯は最適化された入浴体験をつくる一つの工夫ですが、使い過ぎには注意が必要です。
日常生活では、洗面所の水質や給湯器の性能に合わせて差し湯の頻度を調整することが大切です。
ただし、公共の浴場や温泉施設では、衛生管理の都合から差し湯を禁止している場合があります。施設の規則に従いましょう。
実務の場面での違いと安全性
追い焚きとは、浴槽内の水を再度温め直す機能のことです。現在の多くの家庭風呂には、浴槽の水を循環させて温度を保つためのポンプとヒーターが組み込まれており、水を捨てずに温め直すことで節水にもつながります。追い焚きの使い方は機種によって違いますが、基本的には「自動運転モード」や「温度設定モード」を使い、浴槽全体を均一な温度に近づけることを目指します。
しかし、追い焚きは、水の循環による衛生リスクを伴う場合があります。長時間同じ水に留めておくと、残留塩素の変化や雑菌の繁殖が起こる可能性があり、衛生管理が重要です。定期的な清掃、浴槽内のカビ取り、蛇口周りの清潔、そして適切な水温管理が求められます。追い焚きの利点は、湯量を増やさずに暖かい風呂を長く楽しめる点です。寝る前のリラックスタイムや家族が同時に入る場合に便利で、給湯器の機能と組み合わせれば、快適さと節約のバランスを取りやすくなります。
一方で、差し湯と同様に、過度な追い焚きは水質悪化の原因になることがあります。温度が高すぎると肌への刺激が強くなるため、適温を定期的に確認することが大切です。対策としては、温度センサーを活用し、適正温度に自動制御する機能を選ぶこと、そして週に一度は浴槽の清掃と衛生管理を欠かないことです。追い焚きは、水を無駄にしない入浴の工夫として大きなメリットがありますが、衛生面の配慮を忘れず、適切なタイミングで活用することが重要です。
差し湯と追い焚きの違いを深掘りする小ネタです。私は友達と風呂の話をするとき、まず『差し湯は水を足して温度を整える作業であり、追い焚きは水をそのまま温め直す作業だよ』と説明します。差し湯は短時間の温度補正に向いていて、追い焚きは長時間の入浴や人数が多いときに便利です。とはいえ、差し湯で水質が変わることや、追い焚きで温度ムラが出ることもあり、それぞれのデメリットを知って使い分けることが大切です。





















