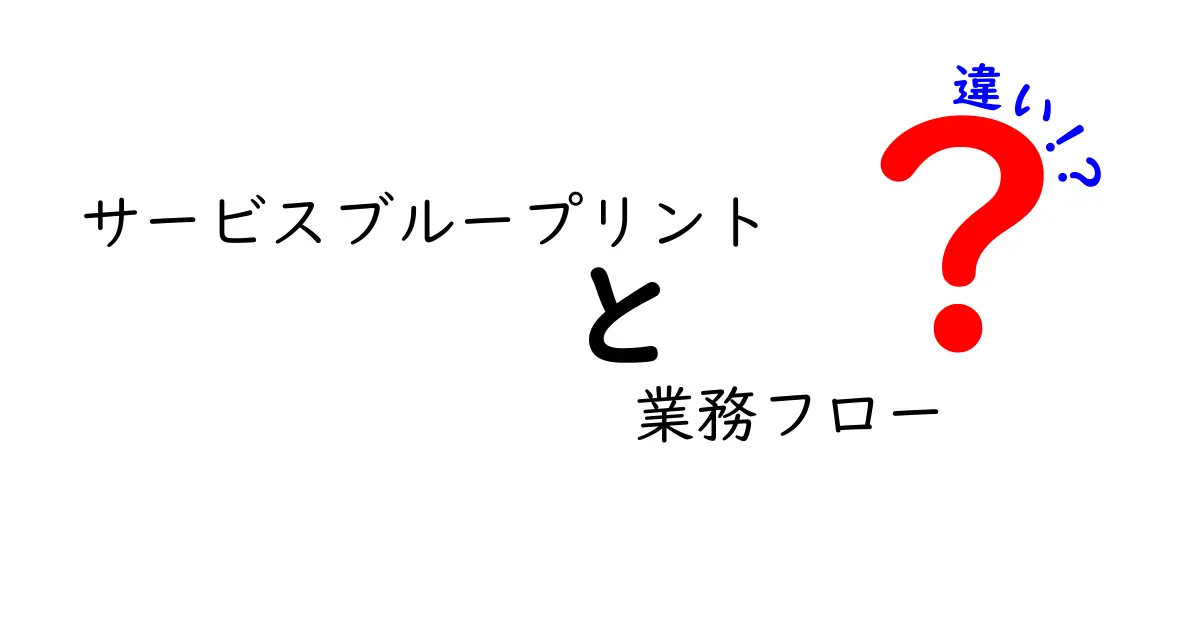

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
サービスブループリントと業務フローの基本を押さえよう
サービスブループリントとは、サービスを提供する現場の「体験」と、それを支える後ろの仕組みを同時に図にする設計ツールです。顧客が接触するポイント(オンステージ)と、裏で動く作業・システム・人の動きを一枚の図の中で結びつけるため、誰が何をどうするのかが一目でわかります。
この図を見ると、顧客が何を感じ、どの順番で接点を体験するか、そしてその体験を実現するためにどんな内部の動きが必要なのかが見えてきます。完成したブループリントは、プロジェクトの初期段階でのアイデアを整理し、関係者間の認識を揃えるのに役立つのです。
サービスブループリントの核心要素は、顧客アクション、オンステージの接点、バックエンドのプロセス、サポートの仕組み、そして物理的証拠(例:画面表示、紙の伝票、領収書など)を並べて示すことです。これにより、改善したいポイントを具体的に指摘でき、どの部門が協力すべきか、どの手順を変更すれば体験が良くなるかを全員が把握できます。さらに、責任の分担や情報の流れ、待ち時間の要因など、サービス全体の動きを時間軸で追える点が強みです。
一方で、業務フローは主に「業務の手順と流れ」を可視化します。顧客の体験よりも、内部作業の順序、入力・出力、役割、期限を整理するのに適しており、現場の作業を標準化し、ボトルネックを特定するのに役立ちます。
業務フローは、日常の運用を円滑化するための基礎設計であり、部門間の連携ミスを減らすための手掛かりを提供します。これを使えば、誰が次に何をするべきかがすぐに分かるため、新人教育にも効果的です。
実務での使い分けと違いのポイント
使い分けの目安は、目的とステークホルダーの観点で決まります。顧客体験を最優先に設計する段階ではサービスブループリントを選び、顧客の体験を裏で支える仕組みと人員の動きを一緒に描くのが有効です。実務での運用設計や改善案を現場の手順として確実に落とすには業務フローの作成が向いています。
また、作成の難易度と更新の頻度にも違いがあります。サービスブループリントは初期の設計に時間がかかることが多く、完成後に大きな変更がある場合は再度大きな修正が必要になることがあります。一方、業務フローは比較的更新が容易で、日々の運用の変化に合わせて頻繁に改良できます。現場の作業が複雑で、複数部門が絡む場合は、ブループリントと業務フローを組み合わせて使うのが効果的です。
実務の具体例として、ある小売店の「受注〜納品」プロセスを例に取ると、顧客の注文体験を改善したい場合はまずブループリントで顧客接点の不満点を洗い出せます。その後、日常の作業を標準化するために業務フローを作成し、責任者・期限・入力データの形式を明確にします。両方を併用することで、顧客に優しい体験を保ちつつ、内部の作業を効率化する道筋が見えてくるのです。
ねえ、サービスブループリントの話、深掘りしてみると意外とおしゃべりな道具なんだ。私は友達とカフェで注文の流れを思い浮かべて、この図を描いてみた。注文する人の動き、店員の反応、キッチンの連携、在庫の確認、そして会計の扉まで、すべての接点と背後の作業を一枚に置くんだ。すると、待ち時間の原因が“情報の伝わり方”だったり“同じデータが複数の場所で更新されていた”ことだったりと、びっくりするくらいシンプルに見えてくる。こういう発見が、現実の現場改善の第一歩になるんだよ。





















