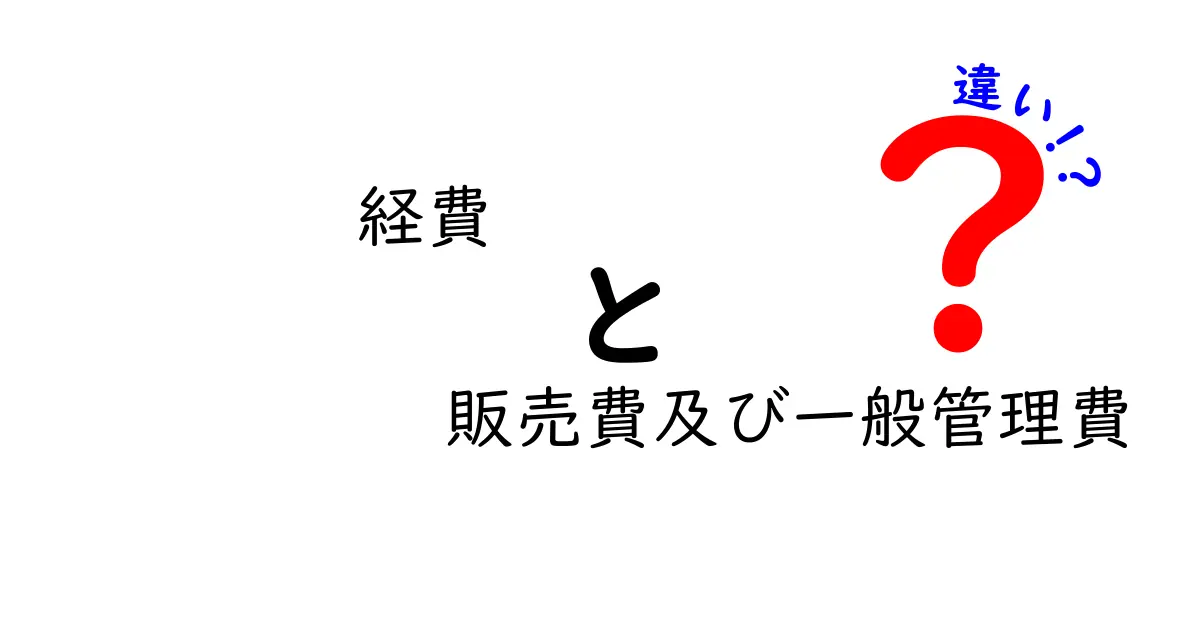

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに 経費と販管費の基本的な意味を知ろう
この章ではまず用語の基本を整理します。経費 とは日常の会話では費用という意味で使われがちですが、会計の世界ではもっと整理された意味があります。経費とは企業が活動を行ううえで発生する費用の総称です。大きく分けると、製造原価と販管費とに分類され、さらに販管費には販売活動に関する費用と一般的な管理運営費用が含まれます。これに対して販売費及び一般管理費、略して販管費は、財務諸表の中で直接的に「販売活動」と「一般的な事務・管理」に使われる費用の合計を示す特定の科目です。つまり経費の中の一部を指す、より具体的なカテゴリです。
例えば宣伝広告費や販売員の給与、オフィスの家賃や光熱費といった費用は、状況に応じて販管費として処理されます。一方で工場で働く人の給料のうち、製造を直接行う人の給与は製造原価に含まれることが多く、販管費には含まれません。ここが大きなポイントです。
企業の財務を読み解くためには、まずこの分類がどういう意味を持つのかを理解することが大切です。経費 と 販管費 の違いを意識すると、会社の利益がどのように生まれ、どの費用が最適化の対象になるのかが見えやすくなります。
現場での使い分けと具体例を見てみよう
日常の経理の現場では、費用の分類は予算管理と業績指標に直結します。販管費は「販売活動と一般管理の費用」という意味で、マーケティング部門の広告費、営業スタッフの給与、オフィスの賃借料、通信費、旅費交通費などを含みます。これに対して製造原価は工場での材料費、直接労務費、製造間接費など、製品を作るために直接かかった費用です。つまり 経費 という大きな枠の中に、販管費や製造原価といった細かい区分があるのです。
例えば、ECサイトの商品写真を撮影するカメラマンの費用は販管費の一部として扱われることが多いです。一方で、生産ラインの機械の修理費が発生した場合、それが製造原価に含まれるか販管費に含まれるかは、その修理が生産能力を維持する目的か、単なる事務作業の補助かで判断します。
さらに、給与の扱いも重要です。管理部門の人の給与は販管費ですが、現場の生産ラインを直接動かす技術者の給与は製造原価に近い性質を持つ場合があります。こうした微妙な判断は、会計のルールだけでなく、会社の方針や会計基準にも左右されます。
企業はこれらを正しく分類することで、実際の利益がどう出ているのかを正しく把握できます。正確な分類 は財務分析の精度を高め、投資家や経営者が意思決定をする際の貴重な情報源になるのです。
財務諸表での表示と注意点
財務諸表では、費用は大きく「売上原価」と「販管費」に分けて表示されます。販管費 はさらに細かく区分され、広告宣伝費、旅費交通費、通信費、地代家賃、給与・賞与、福利厚生費などが並びます。ここでのポイントは、製造原価と販管費の区別です。製造原価は製品を作るために直接かかった費用であり、販管費は製品を売ることや会社を運営するための費用です。したがって「経費」という広い言葉の中でも、販管費は売上計算や利益の見方を理解するうえで特に重要な区分です。
表を使って簡単に整理してみましょう。
例えば広告宣伝費は販管費の代表例、材料費は製造原価、オフィスの家賃は販管費、工場の設備維持費は製造原価または販管費のどちらに含むかは用途で決まります。
財務報告の際には、分類の一貫性 が求められます。会計方針を統一し、同じ基準で毎期比較できるようにすることが重要です。
最後に、中小企業 では予算に柔軟性を持たせることが多く、販管費の削減が利益率を大きく改善する場合があります。適切な管理と見直しを続けることが、堅実な経営につながります。
表の下には、混乱を避けるためのチェックリストも付けています。
電車で友人と会計の話をしていたとき、販管費って実際には何を指すのかを深掘りしてみた。彼女は広告宣伝費と事務の給与くらいしか思いつかなかったが、私は違いを深掘りした。販管費は売るための費用と会社を運営する一般管理費をまとめたもので、日常の経費の中でも特に「製品を作ること」に直接関係しない費用を含む。こうして会話を続けるうちに、経費という大枠の中で販管費がどのように利益の見方を支えるかが見えてきた。私たちは会計基準や分類の話題を膨らませ、実務の現場ではこのカテゴリ分けが予算や意思決定にどう影響するのかを想像してみた。結局、販管費は売上を生む活動だけでなく、会社を動かすための日常的な費用を網羅する枠組みであると理解した。





















