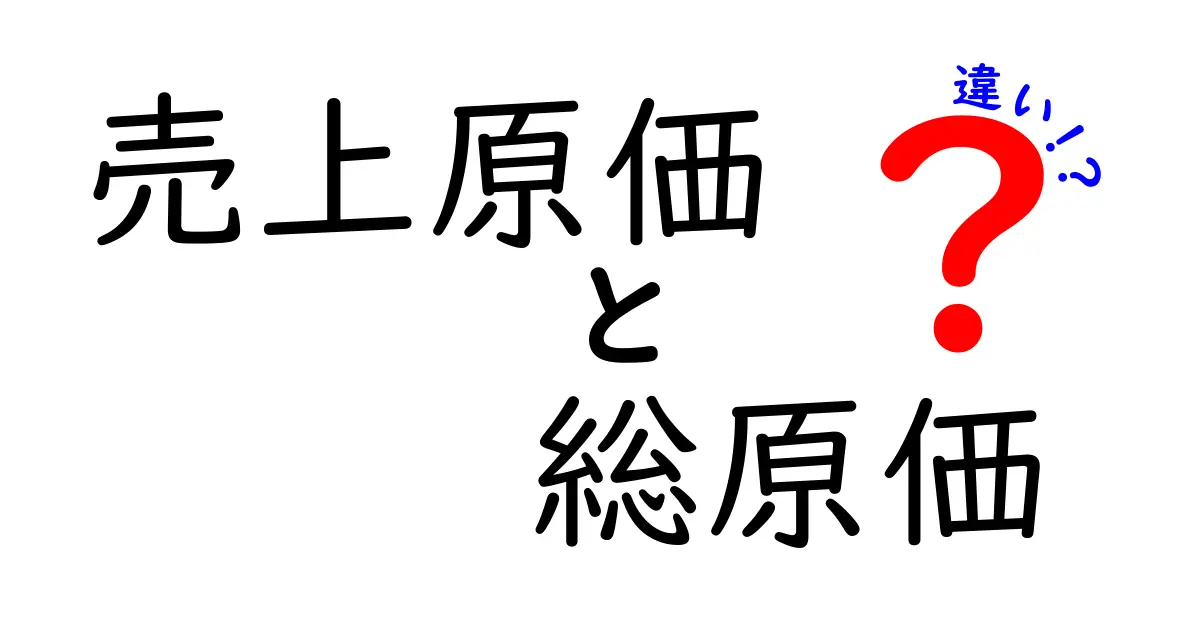

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
売上原価と総原価の違いを徹底解説:わかりやすく整理する9つのポイント
会計や経営の勉強を始めたばかりの人にとって、売上原価と総原価は似ているようで違いが分かりにくい言葉です。ここでは、売上原価と総原価の基本を、日常の生活にたとえるくらいわかりやすく解説します。まずは結論から言うと、売上原価は「商品を作るために直接かかった費用」で、総原価は「そのほかの費用も含めた全体の費用」です。これを覚えると、利益を正しく見る力がつきます。具合が悪い人を想像してみましょう。体の直接的な症状だけを見るのと、体全体の状態を見ようとするのでは、治療方針が変わります。企業も同じで、売上原価だけを追うと本当の利益が見えにくく、総原価まで含めて考えると、価格設定やコスト削減の方向性がはっきりします。
この二つの考え方を区別することは、決算書を読むときの第一歩です。売上原価は「売上を作るために直接かかった費用」、総原価は 「売上原価に販管費などの間接費を加えた全費用」 というシンプルな式で整理できます。これを理解しておくと、製品の利益率だけでなく、部門別の損益の見方も変わってきます。
なお、学校の成績表のように、数字だけを見るのではなく「どの費用がどこに入っているのか」を知ることが大切です。この記事では、以下のポイントを軸に詳しく解説します。1) 定義の違い、2) 計算の基本式、3) 実務での影響と活用例、4) よくある誤解、5) 実務での注意点。この5つを押さえれば、売上原価と総原価の違いがぐっと身近になります。
売上原価の定義と計算の基本
売上原価は、売上を生み出すために直接かかった費用のことです。具体的には材料費、直接人件費、仕入れに関わる費用、そして製品を作る工程で直接結びつく費用が該当します。飲食店なら材料費や料理を作る人の直接労務費、製造業なら原材料費と直接作業費が中心です。ここで「間接費」や「販促費」など商品づくりに直接関係しない費用は原価には含めません。売上原価の計算式は、一般的には 売上高に対して直接的にかかった費用の合計を指します。実務では、売上原価を正確に把握することで「この商品1つあたりの原価はいくらか」「どの工程が費用を増やしているか」を把握できます。
例を挙げると、ある小さなカフェで月の売上が100万円で、材料費が25万円、直接作業費が15万円、その他の直接費が5万円だったとします。ここで販促費や事務費は別扱いです。売上原価は material費 + 直接作業費 + 直接費 = 25万 + 15万 + 5万 = 45万円となり、売上原価率は 45万円 ÷ 100万円 = 45% となります。ここが「直接費の割合」が分かるポイントです。
このように、売上原価は「商品を作ることに直接関与する費用だけ」を集めたものだと覚えておくと、後で計算や比較が楽になります。
総原価の定義と計算の基本
総原価は、売上原価に販管費(販売費及び一般管理費)などの間接費を含めた全費用の総称です。販管費には広告費、営業費、事務費、管理部門の給与など、直接的に製品を作る作業には結びつかない費用も含まれます。つまり、総原価は「商品を作るのにかかった全費用」+「商品を市場で売るために必要な費用」をトータルで表す概念です。この点が売上原価と大きく異なる部分です。総原価の計算式の例としては、総原価 = 売上原価 + 販売費及び一般管理費がよく使われます。もし販管費が増えれば、同じ売上でも総原価は大きくなり、利益は下がります。反対に販管費を抑えることができれば、利益の見え方が良くなります。
ここに、実務での違いがはっきり現れる場面が出てきます。例えば、同じ商品が2か月間で売上高は同じでも、販管費の配分が変わると総原価が変動します。販促費を増やして短期的に売上を伸ばす戦略をとる場合、総原価は増え、利益率は一時的に下がることがあります。これを理解しておくと、「長期的に見た利益の安定性」を判断する材料になります。
以下の簡易表は、売上原価と販管費の位置づけを視覚的に整理したものです。項目 説明 売上原価 製品やサービスを作るために直接かかった費用 販管費 販促費・営業費・事務費などの間接費 総原価 売上原価 + 販管費
具体的な違いが企業経営に与える影響
売上原価と総原価の違いを理解することは、実務の意思決定に直結します。価格設定や利益計画、さらには toplineとbottomline の関係を正しく把握するためには、両者の区分が欠かせません。例えば、同じ売上高でも総原価が高い場合、粗利(売上高−売上原価)は大きくても、販管費が多いと純利益は小さくなります。つまり、「売上原価だけが減っても総原価が上がれば利益は減る」ことを忘れずに監視する必要があります。
また、部門別の損益を分析するときにも、この区分は役に立ちます。製造部門が効率化され、売上原価が下がっても、総原価の中の販管費が増えると、全体の profit margin が変わってしまうことがあります。そこで、経営者や管理部門は“どの費用が増減を引き起こしているのか”を特定し、どの費用を削減するか、あるいはどの費用を価値につなげるかを判断します。
このような分析は、決算期ごとの財務諸表を読み解く力を養ううえで重要です。売上原価と総原価を区別して理解することは、企業の健全性を測るうえで欠かせない基礎の一つです。特に中小企業やスタートアップでは、総原価を抑える取り組みが利益を守る鍵になる場合が多く、正確な原価管理が競争力の源泉になります。
実務での注意点とよくある誤解
実務では、売上原価と総原価の扱いを混同しやすい場面がよくあります。例えば、販管費を「原価」に含めてしまうと、粗利の指標が過大評価され、意思決定が的外れになることがあります。逆に、総原価だけを見て売上原価を軽視すると、製品の実際の採算性を見誤ることになります。重要なのは、どの費用がどの区分に入るかを常に確認することと、期間ごとに原価の構成を比較することです。期間を跨いで原価がどう変わるかを知ると、季節性や市場の変化にも対応しやすくなります。
また、表現の仕方にも注意が必要です。売上原価と総原価を混同しないよう、決算書上の表記を正しく読み解く癖をつけましょう。例えば、粗利率を伝える場合は「売上原価率」ではなく「売上原価 / 売上高」かどうか、また総原価の内訳を別に示すかどうかを確認します。これらの習慣は、社内外の人と話すときに誤解を減らす効果があります。
今日は売上原価についての小話風の解説です。友だちとカフェで「売上原価って何だろう」と話していたとき、私はこう答えました。売上原価は、商品を作るために直接かかった費用の総称で、材料費や直接人件費が中心です。一方、総原価は売上原価に販管費などの間接費を加えた全費用のこと。つまり、売上原価は“作るところまでの費用”を指し、総原価は“作る以外の費用も合わせた全体”を指します。これを区別しておくと、価格設定を決めるときや利益を正しく見積もるときに役立ちます。実際のビジネスでは、売上原価だけを見て安心してしまうと、販管費の増減で最終的な利益が大きく動くことに気づきにくくなります。私は友だちに、「総原価の中でどの費用が大きいか」を把握することが大事だと伝えました。これを知るだけで、コスト削減のヒントが自然と見つかります。初めは難しく感じても、費用の性質を分けて考える癖をつけると、材料費と人件費の違い、販管費の影響がすっきり分かるようになります。
次の記事: 総原価と製造原価の違いを徹底解説!初心者でもすぐ分かる実務ガイド »





















