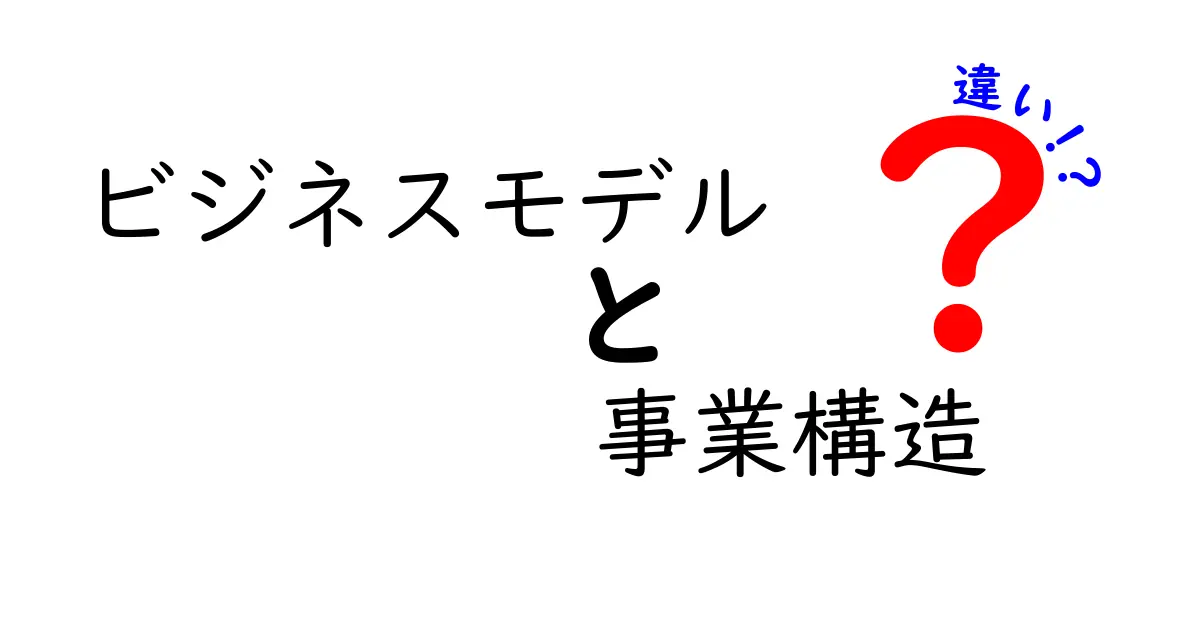

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:ビジネスモデルと事業構造を区別する理由
ビジネスモデルとは、「何を売り、誰に、どうやって、どのようにお金を生むのか」という設計図のことです。価値提案、顧客セグメント、チャネル、収益モデル、コスト構造などの要素を組み合わせて、企業が長期的に利益を生み出す仕組みを描きます。これに対して事業構造は、その設計図を実際に動かすための組織・人材・プロセス・資源の配置のこと。つまり、ビジネスモデルが「何をどう作るかの設計書」なら、事業構造は「それを現場でどう動かすかの組織図」です。
この二つは連動していますが、別の視点で語られることが多く、混同すると成長の機会を逃してしまうことがあります。たとえば、画期的なビジネスモデルがあっても、現場の仕組みが追い付かないと実際には拡大が難しくなることがあります。逆に、完璧な組織やプロセスを整えても、顧客のニーズに合わない収益の設計では長くは続きません。そこで本記事では、まずビジネスモデルの基本と実例を押さえ、その後に事業構造の基本と実例を詳しく解説します。
最後に、両者の使い分け方と実務で役立つコツをまとめますので、企業の現場で働く人はもちろん、起業を考えている人にも役立つ内容です。
ビジネスモデルの基本と具体例
ビジネスモデルの基本は、顧客にどんな価値を提供し、どのようにして対価を得るかという点にあります。ここには主に次の要素が含まれます。
・価値提案:顧客の課題をどう解決するのか
・顧客セグメント:誰に販売するのか
・チャネル:どう届けるのか(店舗、オンライン、代理店など)
・収益モデル:収益をどう生み出すか(販売、サブスク、広告、手数料など)
・コスト構造:どんな費用がかかるか
この五つの要素を組み合わせて、いくつかの典型的なパターンが生まれます。たとえばサブスクリプション型は定期的な収益を安定させ、広告型は無料で提供する代わりに広告収益を得る設計、プラットフォーム型は仲介機能を提供して手数料を稼ぐ設計です。実例として、動画配信サービスは価値提案を「多様なコンテンツで娯楽を提供すること」に置き、収益は月額課金と広告収益の両方で得るケースが多いです。
このように、ビジネスモデルは企業が「どのようにお金を生むのか」という根本的な設計であり、市場の変化に対応する柔軟性が成長の鍵になります。別の視点として、製品自体の価値だけでなく、顧客体験全体を再設計することで新しい市場を開拓できる点も重要です。
具体例をもう一つ挙げると、日用品のEC事業では価格競争力と配送の速さを武器にするビジネスモデルが成功することがあります。ここではリピート購買を促す仕組み、データに基づくレコメンド、カスタマーサポートの品質向上などが重要な要素です。ビジネスモデルは時に「何を捨て、何を優先するか」という意思決定にも影響します。したがって、企業は自社の戦略に最適な組み合わせを見つけるために、複数のビジネスモデル案を検討することが多いのです。
また、企業が新規事業を立ち上げる際には、既存のビジネスモデルと新規案を比較検討します。ここで重要なのは、市場適合性(Product-Market Fit)と収益性の両立です。市場が求める価値と、いくらで提供できるかを同時に評価し、長期的な視点で勝ち筋を描くことが求められます。結局のところ、ビジネスモデルは「顧客に価値を届ける仕組み」と「その対価をどう受け取るか」という二つの軸を結ぶ設計図であり、企業の成長を左右する最初の設計要素です。
事業構造の基本と具体例
事業構造は、前項のビジネスモデルを現場で実現するための組織・プロセス・資源の配置のことを指します。ここで大切なのは、設計図を実際に動かすための「現場の仕組み」を整えることです。具体的には、組織図と部門配置、業務プロセスと標準作業、サプライチェーンとパートナー、IT基盤とデータの流れ、さらには組織文化と人材育成が基本要素になります。これらを適切に設計すると、同じビジネスモデルでも実務のスピードと安定性が大きく変わるのです。
例えば、製造業で垂直統合を採用すると品質管理や納期管理がしやすくなり、安定した供給が可能になります。一方、アウトソーシングを活用すればコストを抑えつつ柔軟性を高められる場合があります。いずれの場合も、責任の所在を明確にし、情報の共有を徹底することが重要です。現場の意思決定スピードを上げるためには、権限委譲と意思決定ルールの整備が欠かせません。
また、事業部制やプロジェクト組織を取り入れると規模拡大時の機動力が維持されやすくなりますが、部門間の調整コストが増えるリスクもあります。そこで、組織文化の整備と、部門間の連携を支えるITツール・データガバナンスが鍵となります。これらの要素を総合的に整えることで、ビジネスモデルの実現性が高まり、長期的な成長が見込めます。
比較表:ビジネスモデルと事業構造の違い
| 観点 | ビジネスモデルの観点 | 事業構造の観点 |
|---|---|---|
| 焦点 | 価値の創出と収益源の設計 | 組織・プロセス・資源の配置と運用 |
| 時間軸 | 市場の変化に応じて更新・再設計が可能 | 日常業務の安定運用と継続性が重視 |
| 測定指標 | LTV、CAC、ARPU、顧客満足度 | KPI、部門効率、納期・品質・コスト |
| 変更の難易度 | 戦略的変更は難しくても柔軟性が高い | 組織再編・プロセス変更が必要になることが多い |
| 主な成果物 | 新規価値の提供と市場での差別化 | 組織の動きと運用の効率化 |
まとめと使い分けのコツ
結論として、ビジネスモデルは「市場に対して何をどう提供してお金を生み出すのか」の設計図であり、事業構造はその設計図を現場でどう動かすかの実装図です。新規事業を生み出すときは、まずビジネスモデルの仮説を複数用意し、それぞれの仮説について市場適合性と長期的な収益性を検証します。そのうえで、組織・プロセス・資源の配置を最適化する“実装”の段階へ進みます。実務では、両者の境界をはっきりさせ、互いの変化を互換的にとらえることが重要です。ビジネスモデルを更新する際には、事業構造も同時に見直す癖をつけましょう。こうすることで、変化に強く、長期成長を見据えた企業運営が可能になります。
最近、授業の話で『ビジネスモデルと事業構造は似ているようで違う』という言い回しをよく耳にします。私の解釈では、ビジネスモデルは“何を売り、どうお金を生むかの設計図”、事業構造はその設計図を現場で実現する“組織と手順の地図”です。例を挙げると、あなたがアイスクリームを売るとします。ビジネスモデルなら、新規性のある味を提供し、月額配送の形を取るか、スポット販売かを決めます。対して事業構造は、製造担当と販売担当をどう分け、原材料の調達と配送をどのように回すか、ITはどこでデータを管理するか、という現場の仕組みを組み立てることになります。つまり、設計と実装を分けて考えると、失敗の原因を見つけやすく、改善もしやすいのです。こうした視点を日常の課題解決にも活かしていくと、学校のプロジェクトでもビジネスの話題が身近に感じられるようになります。
前の記事: « 調達部と購買部の違いを徹底解説|企業の購買を成功に導く役割の差





















