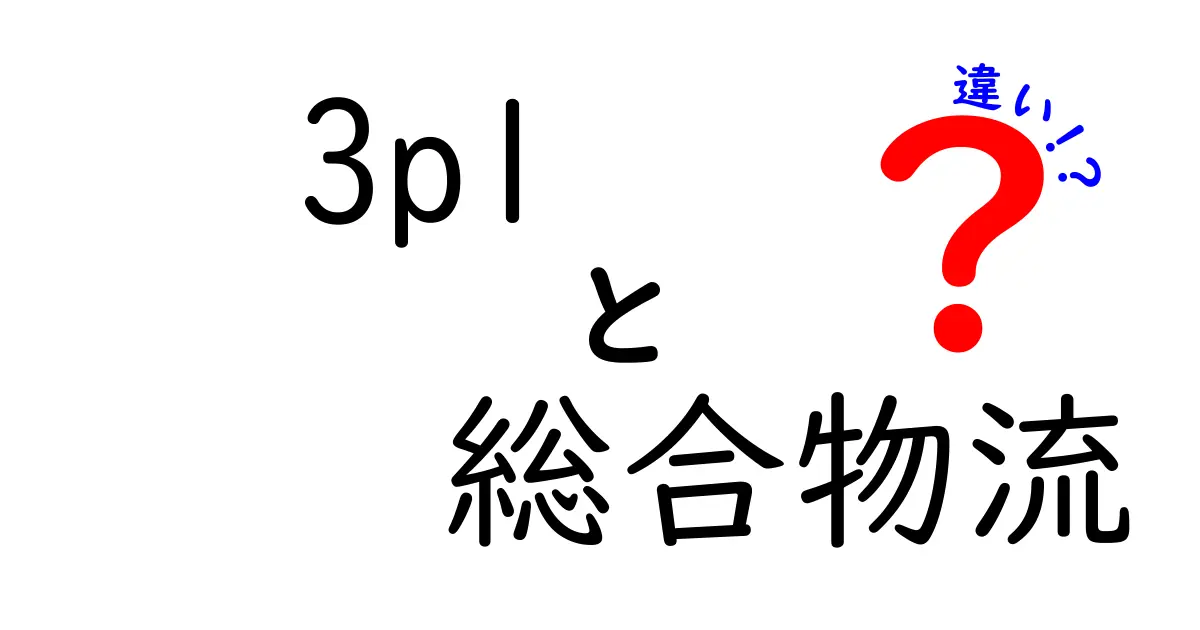

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
3plと総合物流の違いを理解する基礎
みなさんが日常で感じる物流の仕組みは、実はとても身近な話です。3PLは第三者物流の略で、企業が自社の倉庫や配送網を自分で持たず、物流の機能の一部または全部を外部の専門業者に任せる形を指します。これに対して、総合物流は「物流サービスを一つの窓口でまとめて提供する」という考え方を表すことが多いです。
つまり、3PLは外部委託の形を示す言葉、総合物流はサービスの範囲と一体化の設計を意味します。
この二つは似ているように見えますが、実務では使い方が違います。3PLを使うと、企業は自社の核となる業務に集中しやすく、倉庫の場所選びや配送手段の選定を専門家に任せられます。一方、総合物流は複数の機能を一つの窓口でまとめて提供することが多く、契約や連携もシンプル化されやすいです。
つまり、3PLは“外部の力を借りること”を意味し、総合物流は“一括で動く仕組み”を意味します。
自社の状況に応じて、どちらを選ぶかを判断するコツは自分たちの目的をはっきりさせることです。
コア業務に集中したいか、統合的な改善を一度に取り組みたいかを考えれば、適切な選択肢が見えやすくなります。
3plとは?役割と歴史
3plの基本は、物流の一部を外部の力に委ねることです。これにより企業は自分の商品の企画・開発・販売にもっと時間を使えます。歴史的には1990年代のグローバル化とECの拡大で需要が急増し、今では倉庫や配送のネットワークを持つ業者が増えました。3PLはWMS(倉庫管理システム)や配送ルートの最適化ツールを使い、在庫の見える化を支えます。
ただし、3PLは全ての場面で最適というわけではありません。自社ブランドの体験を大切にしたい場合には、配送や返品の対応を自分で管理したいと考える会社もあります。
その場合は、部分的に自社の力を残すハイブリッド型も選択肢としてあります。
実務での違いを比較して選ぶポイント
実務での違いを理解するには、まず費用の仕組みと提供される機能、契約形態を比べることが基本です。
3PLは通常、保管料・出荷料・配送費などを組み合わせた料金体系になります。総合物流はこれに加え、在庫の最適化、納期の改善、返品処理、品質管理といった機能まで一括して提供することが多く、全体的な効率と顧客満足の向上を期待できます。
導入前には、KPI(納期遵守率・在庫回転率・欠品率など)を設定し、段階的な導入計画を作るとよいです。短期のコストだけを見ると安く見えることもありますが、長期的には総合物流の方が大きな効果を生むことがあります。比較表を使って、それぞれの強みと弱みを並べると理解が深まります。
導入のプロセスは、現状の分析から要件定義、ベンダー選定、移行計画、安定運用の順で進みます。現状分析を丁寧に行うことが失敗を減らすコツです。現場の声を取り入れることも重要です。
また、データ連携の仕様、返品フローの対応、関係部門の協力体制、従業員教育などを事前に確認しておくと安心です。
費用・サービス範囲・契約形態の違い
費用は、3PLが基本的には変動費寄り、総合物流は固定費と変動費の組み合わせとなるケースが多いです。
サービス範囲の違いは、3PLが特定の機能を担当するのに対して、総合物流は在庫管理、配送、返品、品質管理など多くの機能を一括で提供する点にあります。契約形態は、3PLは部分的委託が多いのに対し、総合物流は一括契約で運用されることが一般的です。
導入のプロセスと注意点として、現状分析を丁寧に行い、SLAsを明確にすること、データ連携の整合性を最初に確かめること、移行期間のサポート範囲を確認することが重要です。小さなトラブルを想定して、試験運用を取り入れると安心です。
導入のプロセスと注意点
導入のプロセスは、現状分析→要件定義→ベンダー選定→移行計画→安定運用の順で進みます。現状分析を丁寧に行うほど、後のトラブルを避けられます。現状の問題点を数字で把握すると、改善点が見えやすくなります。注意点として、データ連携の仕様、返品フローの対応、関係部門の協力体制、従業員教育などがあります。
契約時にはSLAsを明確にし、成果指標とペナルティ、移行時のサポート範囲を確認しましょう。短期的なコストだけでなく、長期的な効果を考えることが大切です。
3plという言葉を耳にすると、難しく感じるかもしれませんが、案外身近な選択肢です。例えばオンラインショップの店長が自社で倉庫を増やさずに外部へ任せるのが3PLのイメージです。私は、3PLを選ぶときは“自社のブランド体験をどう守るか”を忘れないことが大切だと気づきました。外部に任せるメリットは在庫の見える化と納期の安定、デメリットはコントロールの一部を手放すことです。結局は自分たちの最も大切にしたい価値を明確にして、3PLか総合物流かを選ぶことが大事だと思います。
前の記事: « 3PLと4PLの違いを徹底解説:あなたの物流はどっちを選ぶべき?
次の記事: 2PLと3PLの違いがわかる!初心者にも伝える物流の基本 »





















