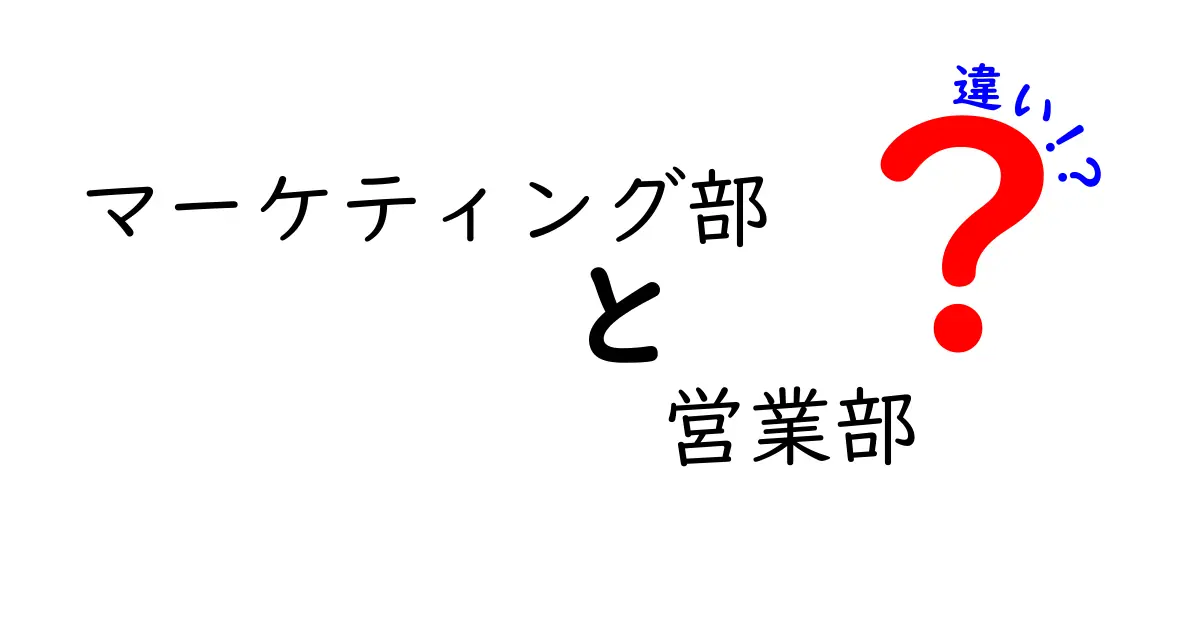

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
マーケティング部と営業部の基本的な役割を整理
ここでは「マーケティング部」と「営業部」の基本的な違いを、中学生にも分かりやすい言葉で解説します。
まず大切なのは目的の違いです。マーケティング部は「顧客がどんな人で、どんな情報を知りたいのか」を探ります。長期的な視点で認知を広げ、興味を引く材料を作ります。広告、記事、動画、SNSの投稿などを組み合わせ、ブランドの印象を形づくります。
一方の営業部は「今すぐ欲しい人、もしくはすぐに買ってくれる人」を見つけ、実際の取引を成立させることが目的です。電話や対面の商談、見積り作成、提案の最適化など、現場でのやり取りを中心に動きます。
このふたつは別の部門ですが、同じゴールを追います。最終的に売上を作るという点では共通していますが、アクションの性質とタイミングが違うだけです。
重要なのは「連携」です。情報を共有し、マーケティングが作るリードを営業が具体的な商談に変える。反対に営業が現場の反応をマーケティングに伝えることで施策を改善する。ここが“違い”であり“強さ”になるのです。
具体的な業務と日常の流れ
マーケティング部の業務は多岐にわたります。市場調査、顧客像の設定、ブランド戦略、コンテンツの作成、データ分析、広告運用、イベント企画など、幅広い活動で「認知の拡大」や「需要の創出」を狙います。
ペルソナ設定とは、理想の顧客を具体的な人物像として描く作業で、年齢、職業、趣味、悩み、解決したい課題などを細かく決めます。これにより、どんな情報をどう伝えると響くのかが見え、広告予算の使い道も具体的になります。
また、リードを育てるためのメール、ニュースレター、動画、セミナー案内などの施策を計画し、反応をデータで確認します。ここで重要なのは「長期的な関係づくり」です。短いキャンペーンで終わらせず、関心を持ち続けてもらうための情報提供を続けます。
営業部の業務は、獲得したリードを現実の商談へとつなぐことです。リードの背景を深掘り、課題と予算感を把握し、製品やサービスがどう解決できるかを丁寧に伝えます。見積り作成、提案資料の作成、デモンストレーション、価格交渉、契約手続きなど、対面またはオンラインでの対話を中心に進みます。
現場の声をマーケティングへ伝える役割も大切で、リードの質を高めるためのフィードバックを集め、次の施策に生かす循環をつくります。
営業は「即効性のある成果」を出す責任がある一方で、顧客との信頼関係を長期的に育てる力が求められます。
KPIと成功指標の違い
マーケティング部のKPIは「認知度の向上」「リード獲得数」「ウェブサイトの訪問者数」「リードの質」など、長期的な市場の反応を測る指標が中心です。
リードの質とは、どのリードが実際に購買につながりやすいかを示す指標で、マーケティングの施策がどれだけ効いているかを評価します。
一方、営業部のKPIは「成約数」「受注金額」「平均受注サイクル(商談開始から契約までの期間)」「商談化率(リードから商談へ進む割合)」など、短期的な成果を数字で追う指標が中心です。
この違いは、部門間の連携をどう設計するかに直結します。良い連携は、マーケティングが作るリードを営業が効率的に商談へ変えることです。
例えば、マーケティングが提供するリードスコアリングの基準を営業が使える形に整え、商談に繋がらないリードを原因分析して施策を修正する。反対に、営業が現場の声をマーケティングに伝えて、次のキャンペーンやコンテンツの企画に反映させる。
この循環が回ると、両部門の指標が同時に改善され、組織全体の業績アップにつながります。以下の表は、代表的な違いを簡潔にまとめたものです。 項目 マーケティング部 営業部 主な目的 認知と需要の創出 成約と売上の最大化 主な指標 リード獲得数、リードの質、ブランド指標 成約数、受注金額、商談化率 活動の典型 キャンペーン、コンテンツ作成、データ分析 商談対応、提案、契約手続き ble>成果のタイミング 中長期的な影響 短期・中期の成果
この表を見れば、両部門の役割がどう違い、どう協力するべきかが一目で分かります。
ただし、実務ではこの境界線は曖昧になることも多く、部門横断のプロジェクトや共通のSLA(サービスレベル合意)を設定するケースが増えています。
ここが、マーケティングと営業の違いを単なる“擦り合わせ”から“戦略的な連携”へと引き上げるポイントです。
マーケティング部と営業部の連携のポイント
連携を強化するには、情報の共有の仕組みと、共通のゴール設定が不可欠です。
最初のポイントは「リードの定義をそろえる」ことです。たとえば、マーケティング側では“MQL”と呼ぶ指標を使い、営業側では“SQL”として実務に落とすなど、同じ言葉を使いながら意味を合わせます。
次に「SLAを設定する」こと。どのタイミングでマーケティングがリードを渡すのか、渡した後に営業がどのくらいの時間でフォローを開始するのか、成果はどう評価するのかを事前に決めておくと、無駄な待機や重複が減ります。
三つ目は「コミュニケーションの質を高める」ことです。単に数値を追いかけるのではなく、現場の声を日常的に共有するミーティングを設け、リードの反応や商談の難しさを互いに理解します。
最後に「学習を繰り返す」こと。失敗や成功の原因を振り返り、次の施策に活かすサイクルを作ると、改善が連続的に進みます。
このような連携の工夫が、現場の実感とデータを両輪で回す鍵となり、最終的な成果を高めます。
リードという言葉を、マーケティングと営業の現場でどう扱うかを友達同士の雑談風に深掘りします。Aはマーケティング担当、Bは営業担当。Aは「リードは名前リストではなく、何かしらの関心を示してくれる人のこと」。Bは「リードをただ集めるだけではなく、どう動くかが勝負。初回の連絡で信頼を作ることが大事」と返します。リードの段階での情報共有、興味の示し方、反応の違いをぶつけ合いながら、二人は最適なコミュニケーションの型を模索します。結論はシンプルで、リードをどう育て、どう実際の商談につなげるかという連携の設計が成功の鍵、という雑談です。





















