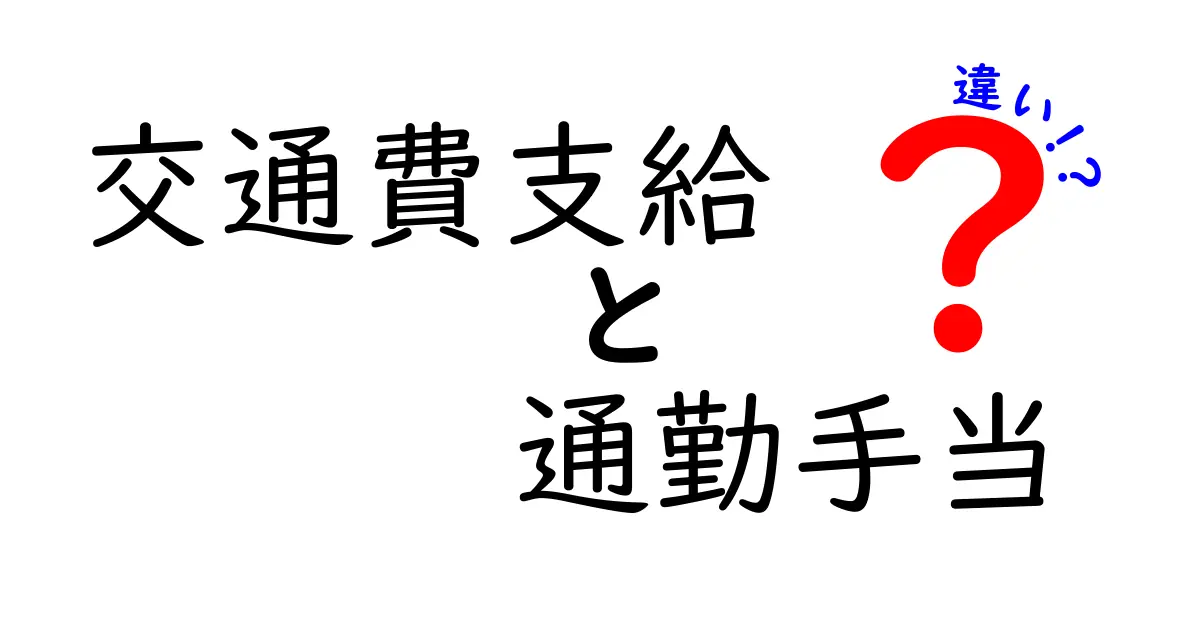

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
交通費支給と通勤手当の基本的な違いとは?
まずは「交通費支給」と「通勤手当」の言葉の意味を理解しましょう。
交通費支給は会社が社員に実際にかかった通勤費用を後から払うことを指します。例えば切符代やバス代、自転車のパンク修理代など実際に交通機関や通勤に使った費用全般が対象になります。
一方、通勤手当は会社が一定のルールに基づいて、あらかじめ決められた金額を毎月支給するもの。実際にいくら使ったかに関係なく会社の規定に合わせた金額が交通費として渡されます。
つまり、交通費支給は実費清算型、通勤手当は定額支給型と考えるとわかりやすいです。
この違いは会社ごとに採用している支給ルールや給料明細の表記にも関係してくるので、まずはここを抑えましょう。
なぜ会社は交通費支給と通勤手当を使い分けるの?メリットと注意点
通勤手当を導入する会社が多い理由は、事務処理が簡単でお互いに負担が少ないためです。毎回実費の領収書を集めたりチェックする手間が省けて、給与計算がスムーズになります。
ただし決められた額を超えた実費があっても差額を補填しないことが多いので、利用者側は注意が必要です。
一方、交通費支給は実際の利用に応じた金額を払うため、社員は無駄なく正確な費用の補填を受けられます。しかし毎月の細かい領収書管理や申請が必要になるため、会社にとっては負担になるケースもあります。
そのため、多くの会社は通勤手当の形を採用していますが、特別な事情のある場合は交通費支給と併用されたり、状況に応じて変わったりします。
交通費支給と通勤手当の税金面での違いと注意ポイント
給与として支払われる交通費や通勤手当には、税金面での違いがあります。
まず通勤手当には「非課税限度額」が設定されていて、その範囲内であれば所得税や住民税がかかりません。具体的には1ヶ月あたり15万円(2024年現在)が目安です。
しかし交通費支給の場合は、実費清算が基本とはいえ、会社の方針や支給の形態によって課税対象となる場合もあります。
この非課税の範囲を超える金額が支給された時は、超過分に対して税金がかかるので注意が必要です。
特に副業(関連記事:在宅で副業!おすすめ3選!【初心者向け】)や兼業で複数の勤務先から通勤手当をもらう場合、合算して非課税限度額を超えないように気をつけましょう。
まとめると、給与明細の「通勤手当」と「交通費支給」の内訳をよく確認し、税務面でも適切に理解しておくことが大切です。
交通費支給と通勤手当の違いを表で比較!わかりやすい一覧
| ポイント | 交通費支給 | 通勤手当 |
|---|---|---|
| 支給方法 | 実際にかかった費用を申請して支給 | 会社が決めた一定の金額を毎月支給 |
| 申請手続き | 領収書や乗車証明が必要 | 乗車券や領収書不要(会社規定による) |
| 税務扱い | 非課税になる場合もあるが会社方針次第で課税される場合あり | 非課税限度額内なら所得税・住民税がかからない |
| メリット | 実費を正確にカバーできる | 手続きが簡単で管理コストが低い |
| デメリット | 申請手続きに手間がかかる | 実費をカバーできないこともある |
いかがでしたか?今回のポイントは交通費支給は使った分だけ支給、通勤手当は定額支給という違いがあること。
そして税務面でも非課税範囲などルールが異なるので、会社の給与明細をよく確認したり、疑問があれば経理担当に相談することが大切です。
この知識があれば、働く人が自分の給与や手当を正しく理解しやすくなりますし、会社側とのコミュニケーションでも役立ちます。
ぜひ参考にしてください!
「通勤手当」って聞くと、会社が決めた一定のお金が毎月もらえるイメージだけど、実はこの金額には税金の非課税枠があるんだよ。なんと、1ヶ月に15万円までなら所得税や住民税がかからないから、お財布にやさしい制度なんだ。でももし複数の会社から通勤手当がある人は合算して15万円を超えないか注意が必要。税金の話ってちょっと難しいけど、こんな小さなルールを知っていると得した気分になるよね!





















