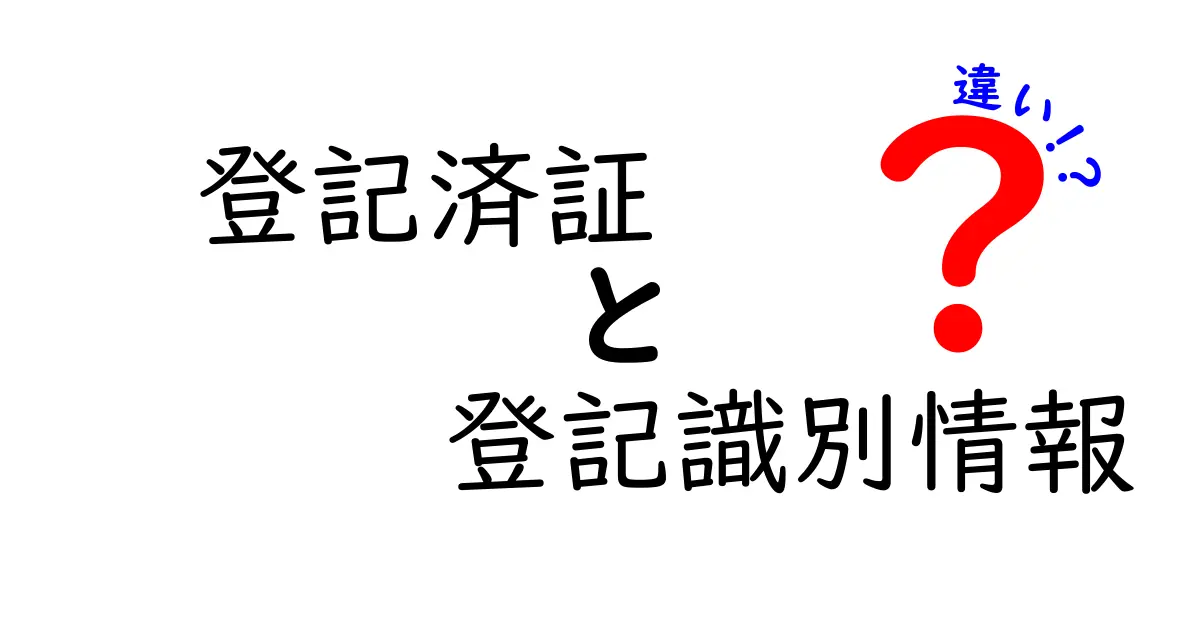

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
登記済証と登記識別情報の違いとは?
不動産の権利を登記する際に、大切な書類として「登記済証」と「登記識別情報」があります。この2つ、名前は似ていますが意味も扱い方も大きく異なります。簡単に言うと、登記済証は昔の"権利証"としての書類で、登記識別情報は現在の"暗証番号"のようなものです。
昔は登記手続きが完了すると「登記済証」という紙の証明書を渡されました。これは土地や建物の所有権があなたに移ったという証拠でした。しかし、平成17年頃から制度が変わり、紙の証書を持つ代わりに「登記識別情報」という12桁のパスワードのような番号で管理する形になったのです。
この制度変更によって紛失のリスクが減り、手続きがスムーズになるというメリットがあります。では、より詳しく2つの違いを見ていきましょう。
登記済証の特徴と利用方法
まずは登記済証についてです。登記済証は、所有権の移転や抵当権設定などの登記完了時に法務局から交付される「紙の証明書」です。
昔はこれがいわゆる"権利証"と呼ばれていて、不動産の売買やローンの設定時に必要不可欠な書類でした。
しかし、登記済証は紙なので紛失のリスクが高く、紛失すると再発行ができません。紛失した場合は面倒な本人確認手続きが必要になることもあります。
登記済証には登記時の情報が記載されており、これがあることでその不動産の登記内容が確かであることを示します。
しかし制度変更で、現在は登記済証は新しい登記手続きでは発行されなくなっています。
登記識別情報の特徴と利用法
次に、登記識別情報です。これは平成17年(2005年)に導入された「電子的な不動産登記の本人確認方法」として普及しました。
登録申請が終わると、法務局から12桁の英数字の番号で構成される登記識別情報が通知されます。
この番号は暗証番号のようなもので、譲渡や抵当権の設定解除、抵当権抹消などの手続きをする際に必要になります。
つまり、紙の登記済証の代わりに、この番号を本人確認の手段として用いるわけです。
登記識別情報は紙の通知書として渡されることもありますが、この番号自体が重要で、紛失すると手続きに影響が出るため大切に保管しましょう。
また、登記識別情報は復元や再発行ができないため、管理には注意が必要です。
登記済証と登記識別情報の違いまとめ
| 項目 | 登記済証 | 登記識別情報 |
|---|---|---|
| 提供方法 | 紙の証明書 | 12桁の番号での通知 |
| 制度開始時期 | ~平成17年頃 | 平成17年~現在 |
| 主な役割 | 権利証としての証明 | 本人確認のための暗証番号 |
| 紛失時の対応 | 再発行不可、本人確認手続きが必要 | 再発行不可、重要な番号として保管が必要 |
| 利用場面 | 登記完了後の証明 | 登記手続きの本人確認 |
このように、登記済証と登記識別情報は、不動産の登記に関わる大切なものですが、その内容や役割はかなり違っています。特に平成17年以降は登記識別情報が主流なので、不動産の売買や抵当権設定の際にはこの番号に注目してください。
何かのタイミングで登記関係の話を聞いた時は、この2つの違いを思い出せば、手続きも理解しやすくなりますよ。
「登記識別情報」という言葉、実は不動産取引の中でとても重要ですが、なかなか日常で出てこない単語ですよね。登記識別情報は"12桁の秘密の番号"のようなもので、これがなければ売買手続きなどで本人だと認められません。
面白いのは、この番号、昔の"権利証"という紙の代わりに登場した、言わば"紙のない権利証明"なんです。もし紛失したらかなり厄介なので、銀行の暗証番号以上に大切に扱う必要があります。
でも逆に言えば、この番号があればネット時代にぴったりのスマートな不動産管理が可能になります。
ちょっとした秘密の合言葉みたいですね!
前の記事: « 【図解でわかる】CEOとCFOの違いとは?役割や責任を徹底解説!





















