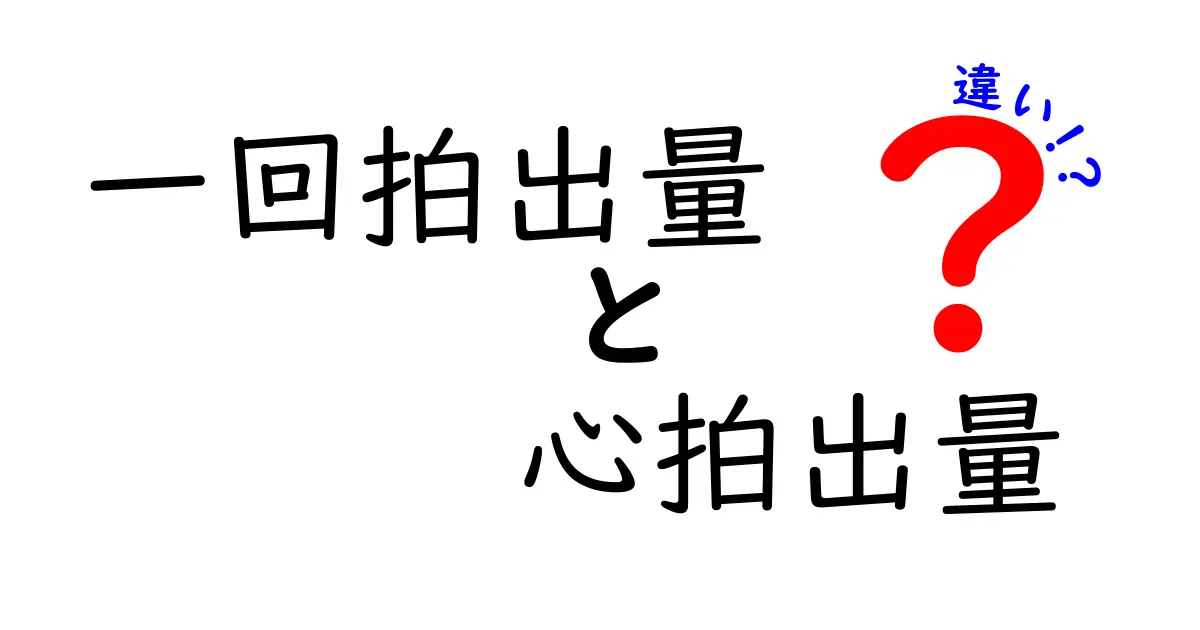

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
一回拍出量と心拍出量の違いを図解でサクッと理解!心臓の働きをやさしく解説
はじめに:一回拍出量と心拍出量の基本を押さえよう
この章では一回拍出量(SV)と心拍出量(CO)の意味を、日常の体の動きの中でどう分かれて働くのかを紹介します。私たちの心臓は休んでいるときでもわずかに動いていますが、運動をするときにはもっと強く拍動します。ここで大切なのは、SVは「一回の拍動で送り出す血液の量」、COは「1分間に送り出す血液の総量」という基本的な定義を覚えることです。
SVとCOは別の数値ですが、互いに影響し合い、健康状態や運動能力を表す重要な指標になります。
SVが増えるとCOも増え、HRが上がるとCOも増えますが、その関係は単純ではありません。
ここからはSVとCOの基本をもう少し詳しく見ていきましょう。
例えば運動を始めると心拍数が上がり、同じSVでも CO は大きく増えることがあります。反対に、脱水や出血で前負荷(心臓に戻ってくる血液の量)が減ると、SVが下がり、COも低下します。
一回拍出量(SV)とは何か?
SVは「1回の心臓の拍動で送り出される血液の量」です。SVは左右の血管に血液を送る力の大小を示す指標で、体の大きさや筋肉の状態、血管の硬さなどに影響されます。
安静時のSVは体格にもよりますが、だいたい60〜70 mL程度です。運動をすると筋肉が働き、返回血管が広がることで前負荷が変化し、SVは変化します。
SVの変化は、心臓の「収縮力」(心筋の力強さ)と「前負荷・後負荷」(戻ってくる血液の量と血管の抵抗)によって決まります。
健康な人はトレーニングを重ねるとSVが安定的に高い状態を保てるようになります。
このため、同じ心拍数でもSVが高い人はCOが高く、体を速く動かすことができます。
心拍出量(CO)とは何か?
COは「1分間に心臓が送り出す血液の総量」です。COはSVとHR(心拍数)の積で表されます。COが高いほど血液が全身に多く届けられ、酸素や栄養を運ぶ力が高くなります。
COは運動時だけでなく安静時にも変化します。健康な成人の安静時COは約4-5 L/min程度ですが、体の大きさや状態で4〜8 L/minの範囲に収まるのが普通です。
COが高い人は血管を広げて血液を効率よく循環させる体の適応を持っています。トレーニングを重ねると安静時COが少し下がり、運動時のCOが大きく増える「心血管の柔軟性」が高まることが多いです。
違いを日常の例で理解する
日常の例で考えると、SVは「1回の水道の蛇口から出る水の量」に近い感覚です。蛇口をひねる回数(心拍)が同じでも、水の量(SV)が多ければ1分間に流れる総水量(CO)は多くなります。別の例として、同じ人数の列車が走る場合、列車1両あたりの人数(SV)が多いと、列車の本数が同じでも車両を走らせる力(CO)は強くなります。しかし、体が要求する酸素量が変わると、HRを上げてCOを増やす必要が出てきます。
このようにSVとCOはセットで働き、私たちの体が動くための“燃料配分”を決めています。臨床的には、SVやCOの値を測ることで心臓の機能や血液量の状態、脱水や出血、薬の影響などを推測します。私たちの体は、運動時と安静時でこのバランスを微妙に調整しているのです。
臨床での意味と健康への影響
SVとCOは体の健康状態を読み解く手がかりになります。低SVや低COは心不全や脱水、出血などのサインになることがあるため、体調管理やスポーツのトレーニングを進める際にはこの数値を意識します。反対にSVが十分に高い人は、同じ心拍数でもCOが安定して高く、日常生活の動作やスポーツでのパフォーマンスが向上する場合があります。
若年層の運動選手では、定期的な心機能のチェックを通じてSVとCOの適応を見極め、無理のないトレーニング計画を立てることが推奨されます。
まとめと覚えるポイント
要点をまとめると、SVは「1回の拍動で送り出す血液の量」、COは「1分間に送り出す血液の総量」です。COは SVと心拍数の積で決まります。運動をするとSVとHRが変化し、COも大きく変化します。健康維持の観点からは、適度な運動と水分・塩分バランス、睡眠、栄養がSV・COの適切な評価と機能維持に役立ちます。日々の生活で「心臓がどのくらい力強く拍動しているか」を感じることは難しくありません。自分の体の変化に気づく習慣を持つことが大切です。
今日は放課後、友達と雑談風にSVとCOの話題を掘り下げてみました。最初は心拍数が上がるとCOも増えると思っていたけれど、実際にはSVが関係してくる場面が多いことに気づきました。例えば走り始めの時、心臓は速く打つ一方でSVがすぐに増えないとCOの増え方は控えめです。つまり「どれだけ強く心臓が収縮できるか」と「どれだけ戻ってくる血液があるか」が両方効いてくるのです。スポーツだけでなく、休息時の水分管理一つとってもSVとCOは影響し合います。自分の体の変化に敏感になると、体調管理がぐっと楽になります。雑談の中で友達に伝えたのは、SVとCOはセットだという基本理解を持つこと、そして運動を通じてこの二つをバランス良く育てることの大切さでした。





















