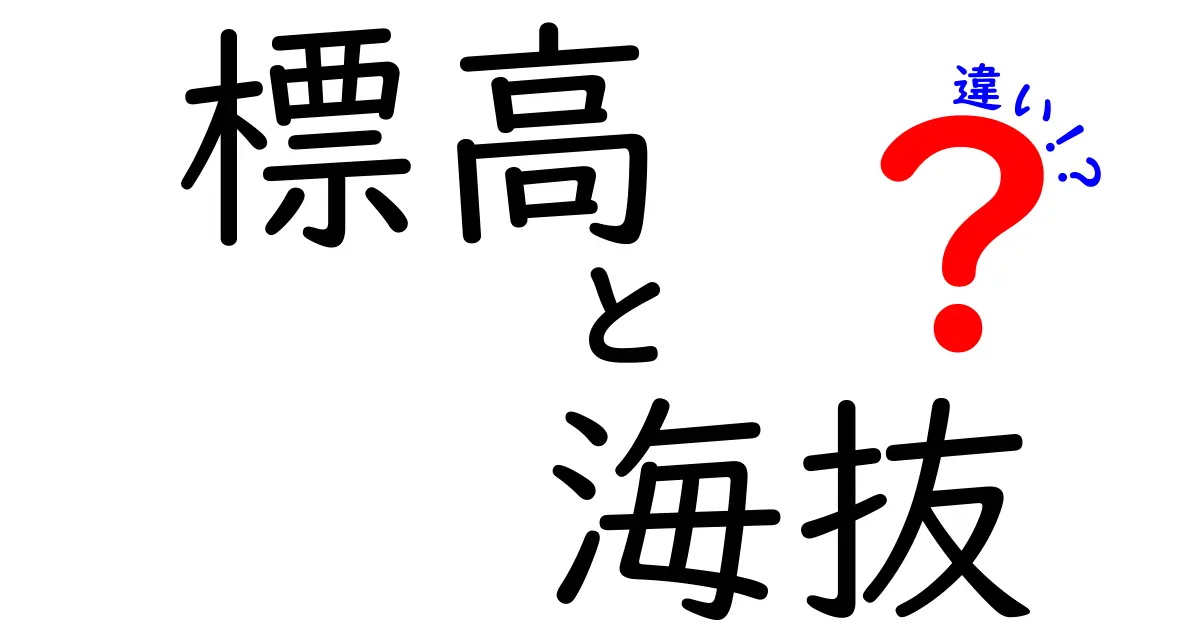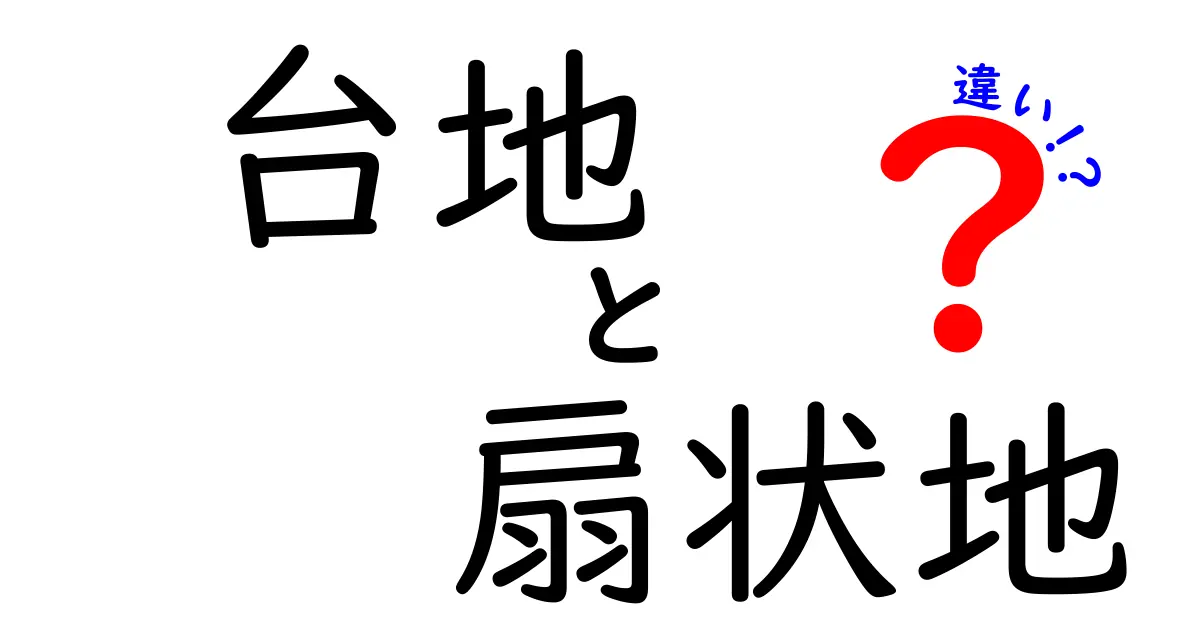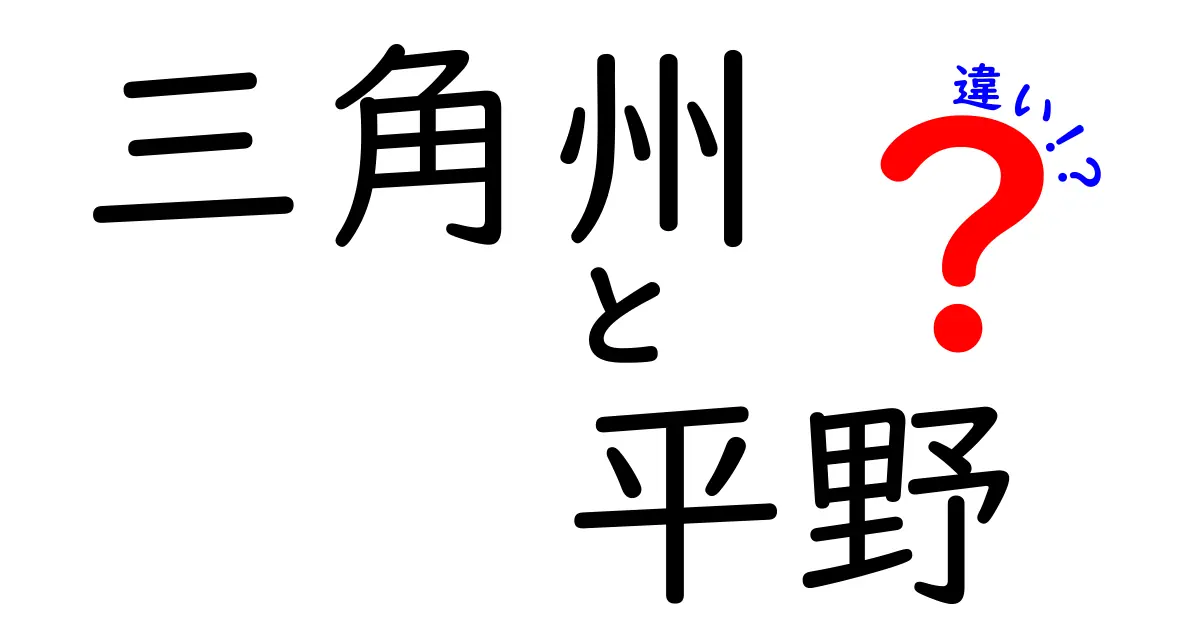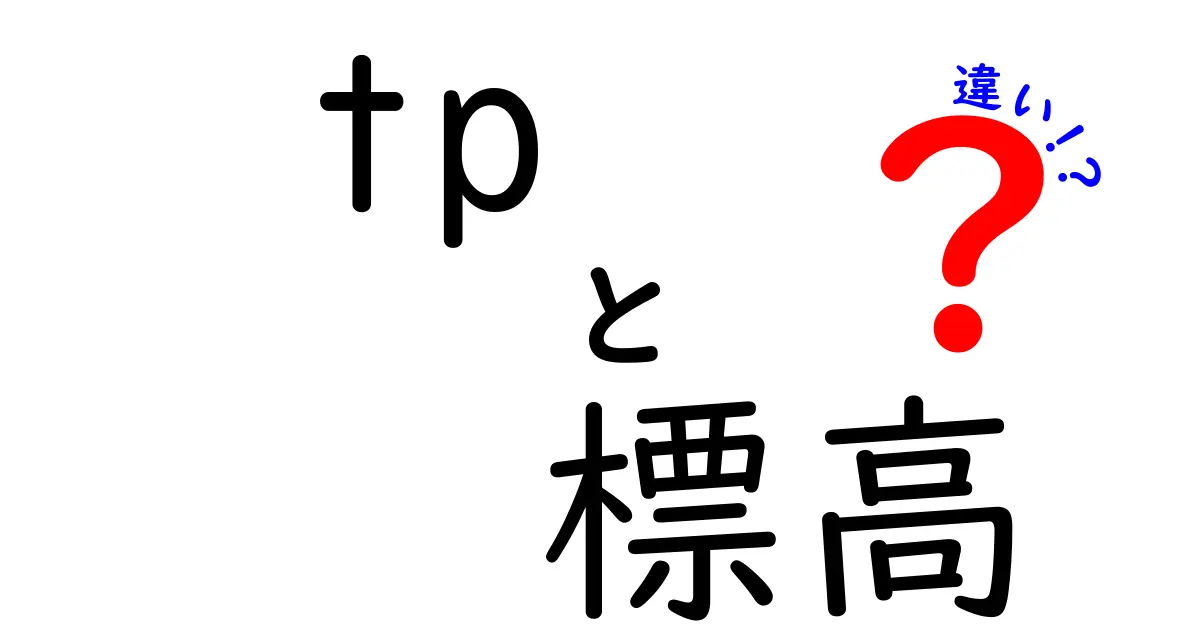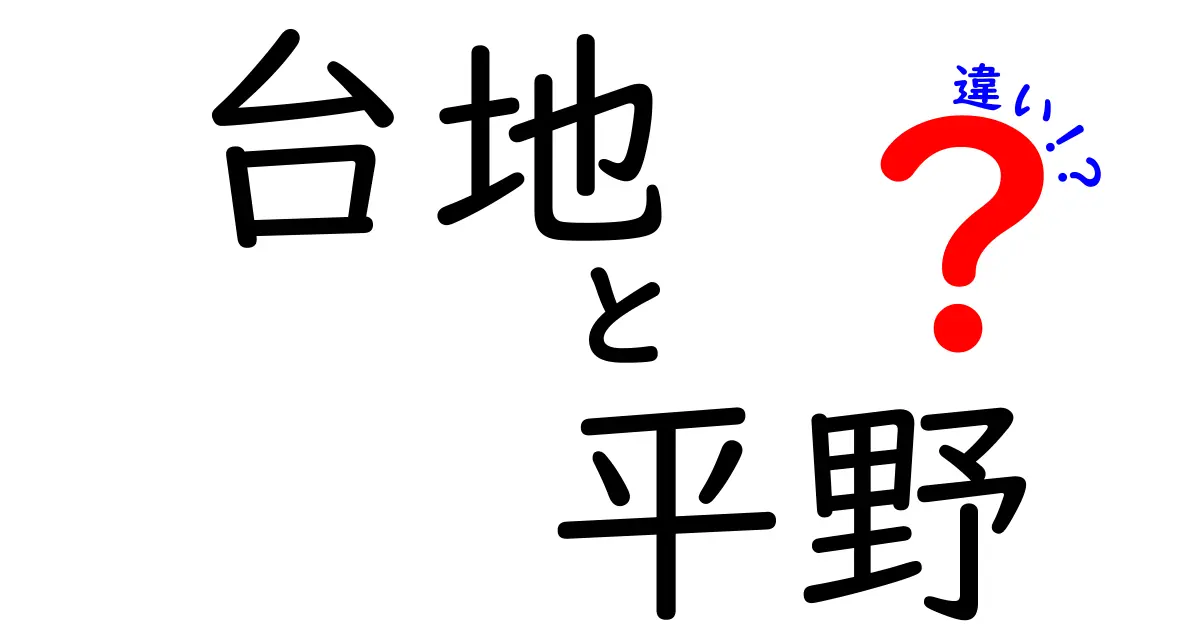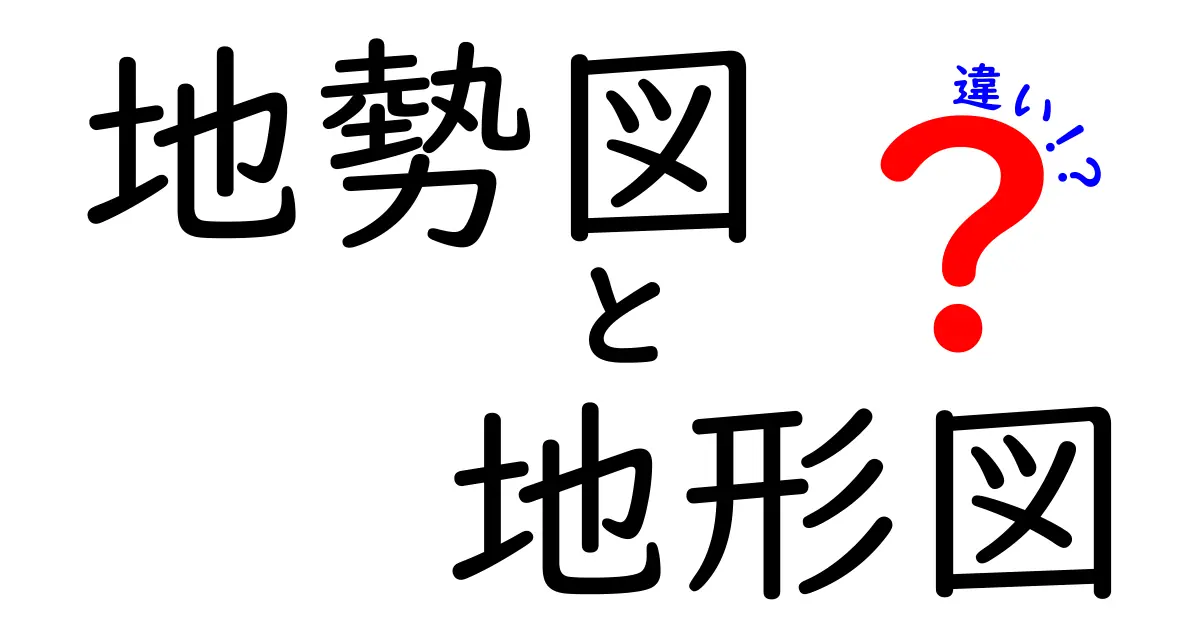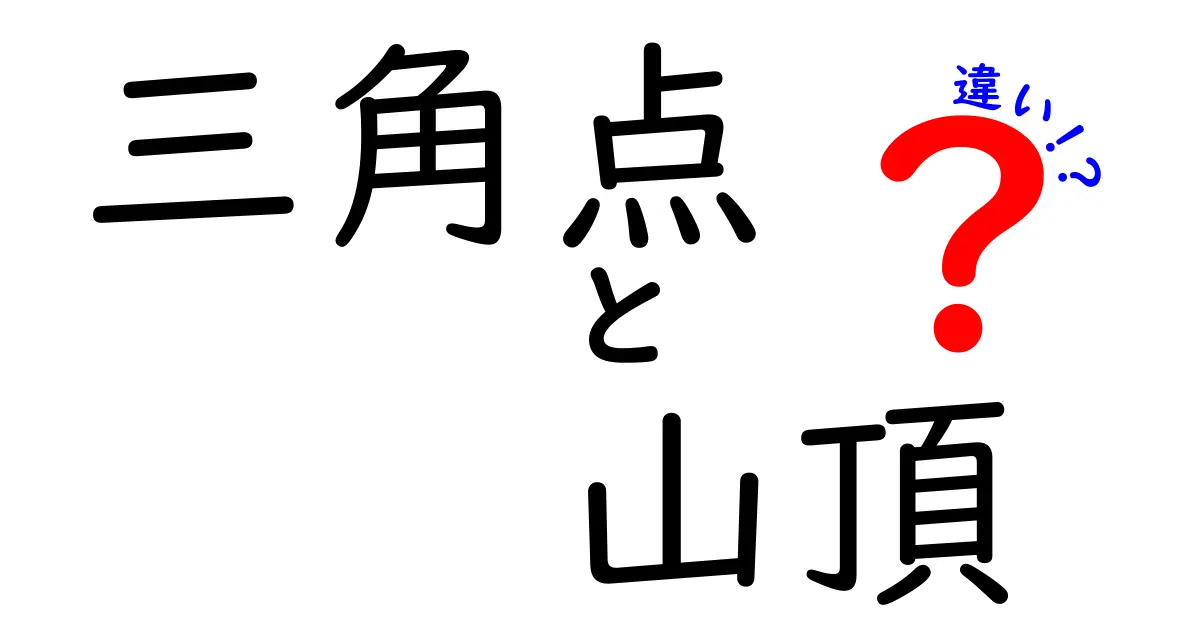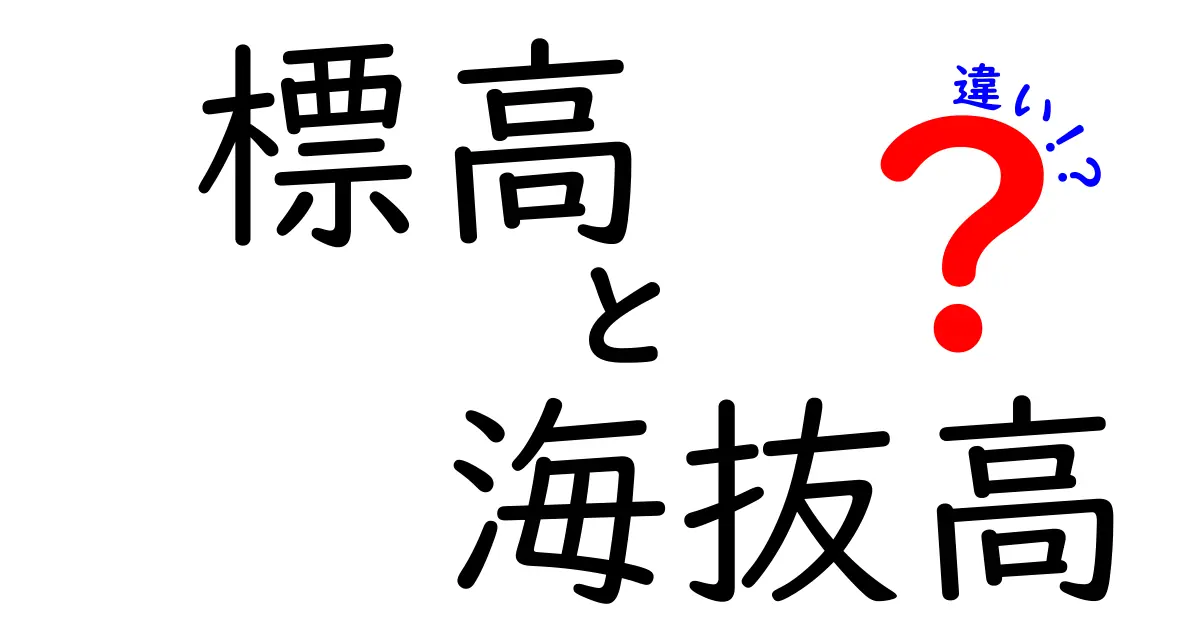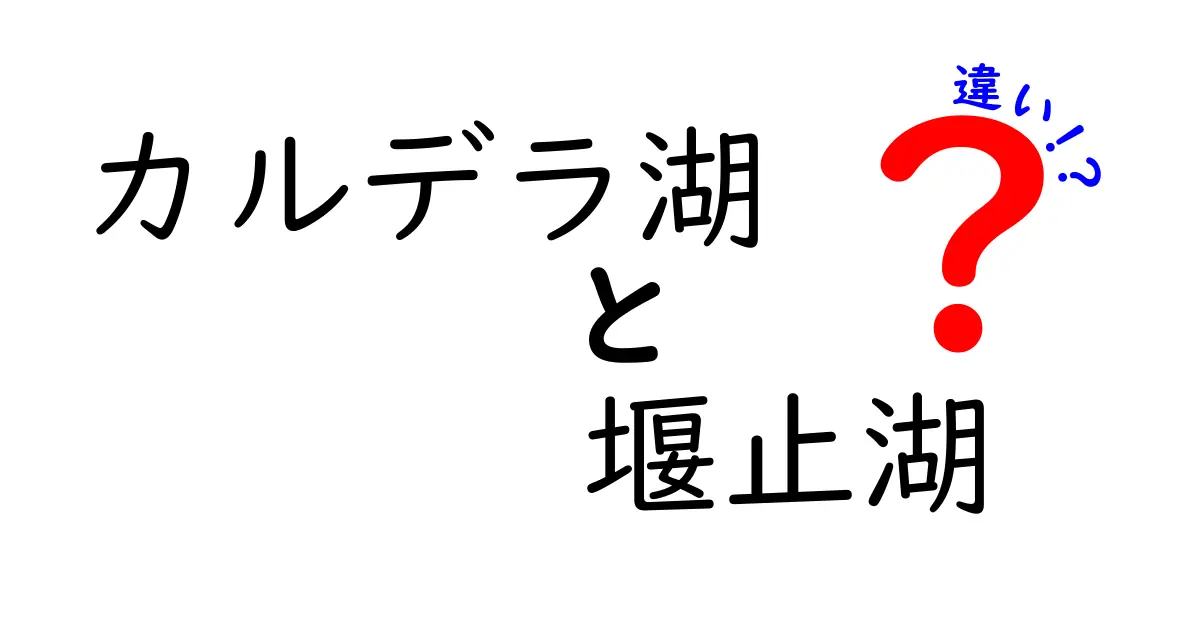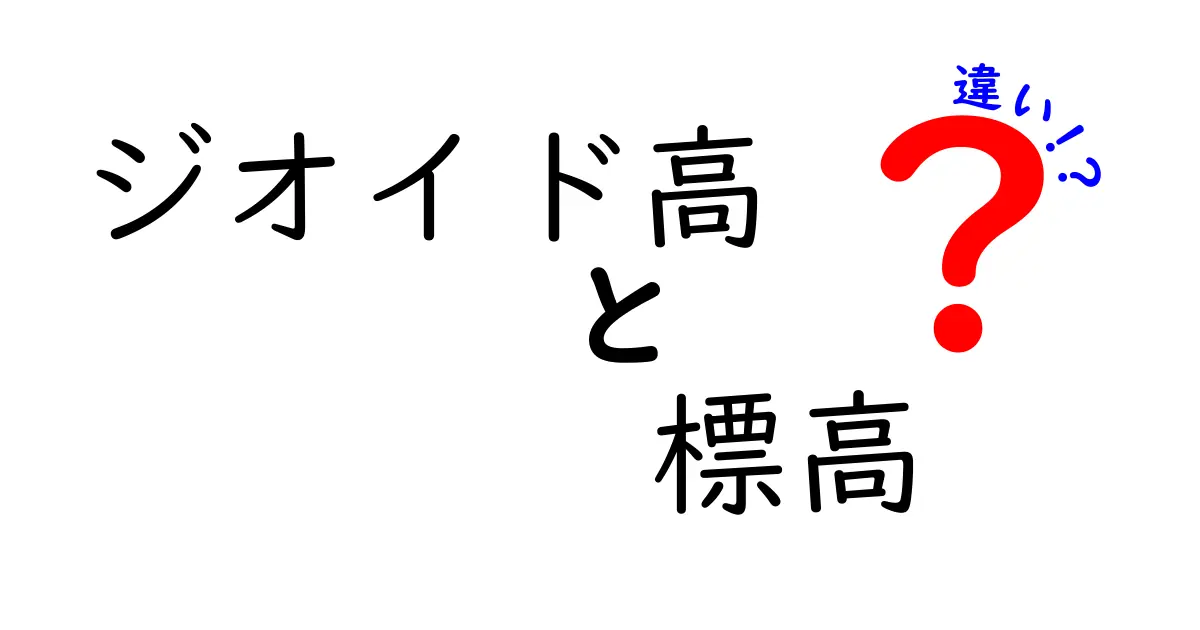

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ジオイド高と標高って何?その基本を知ろう
地図を見たり、山の高さを調べたりするときに使われる「ジオイド高」と「標高」。この二つは似ているようで、実は測り方や基準が違う特別な数値です。中学生でも分かるように、ジオイド高と標高の違いをしっかり説明します。
まず、ジオイド高とは地球の重力を基準にした高さのこと。地球の表面はただの球体ではなく、地球の重力や質量の分布によってちょっとだけ変形しています。この変形した地球の形を「ジオイド」と呼びます。ジオイド高は、そのジオイド面からの高さのことです。
一方、標高とは、海の平均水準面を基準にした土地の高さです。つまり、私たちが普段「山の高さは何メートル」と言うときの高さは、実はこの標高のことです。海の平均水準面は世界中どこでも同じではなくて、潮の満ち引きや地球の丸みなどで少しずつ違います。このため標高も正確には地域によって微妙に違うことがあります。
これら二つの高さの違いを理解することは、地図作成や建築、GPS技術の発展にとても重要です。
ジオイド高と標高の違いを具体例と表で比較しよう
ジオイド高と標高は、それぞれ基準となる面も意味も違うため、数値も異なります。
例えば、日本のある地点での
- ジオイド高が+20.0メートル
- 標高が100.0メートル
ジオイド面は完璧な平均海面ではなく、重力などによって凹凸があるため、標高との差が生じます。
以下の表で違いを分かりやすくまとめました。
ジオイド高と標高の違いが生活や技術で役立つ理由
ジオイド高と標高の違いは、GPS機器や測量技術の発展に欠かせません。
GPSは人工衛星を使って位置や高さを測る技術ですが、このとき使われるのは地球中心からの距離です。つまり、GPSの高さはジオイドではなく「楕円体高」と呼ばれる値です。この楕円体高から私たちが分かりやすい標高を求めるには、ジオイド高の情報が必要です。
また、建築や土木工事では正しい高さの基準を使わないと建物が傾いたり、水が流れにくくなったりする問題が起きます。そのため、ジオイド高を知らないと正確な標高を算出できず、工事の失敗につながることもあります。
さらに、気象データや海面変動の研究にもジオイド高の理解は重要で、地球の環境変化を正しくとらえるために役立っています。
このようにジオイド高と標高の違いを知ることは、私たちの日常生活だけでなく、科学技術の進歩にも大きく貢献します。
ジオイド高って一見難しそうですが、実は地球の“重力の波”を反映した高さなんです。
つまり、地球は完璧な球じゃなくて、重力の強さが場所ごとに違うから、それを基準に計ったのがジオイド高なんです。
だから、GPSで測った高さと実際の土地の高さが違う理由もここに隠れているんですよ。
ジオイド高を理解すると、地球ってやっぱり面白いなって思えますよね。