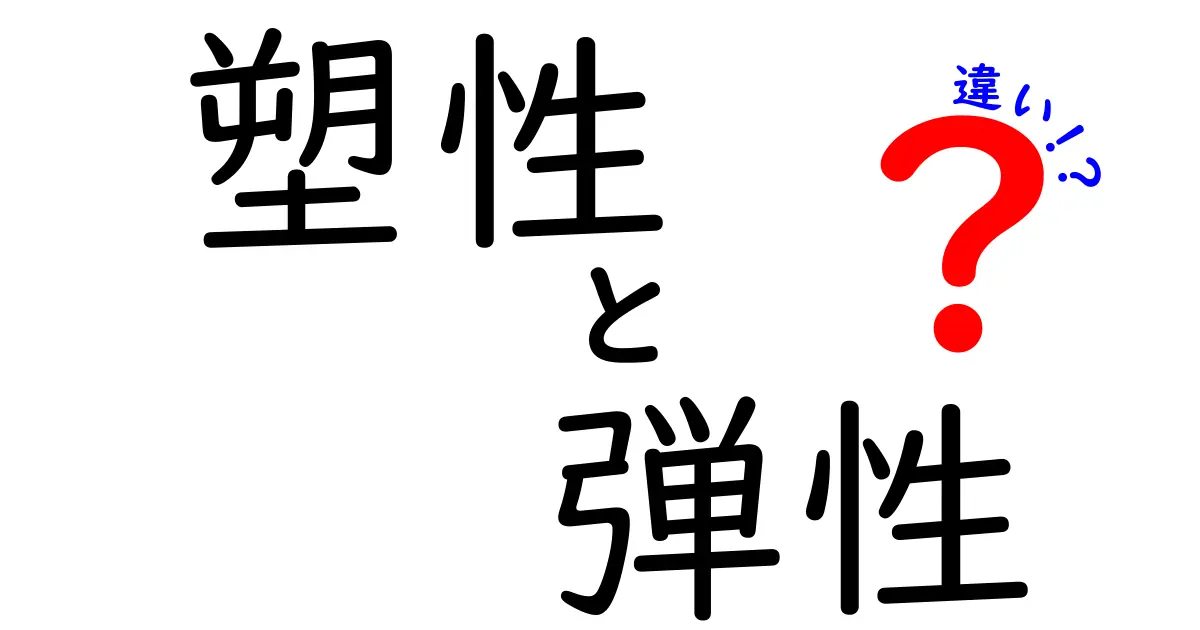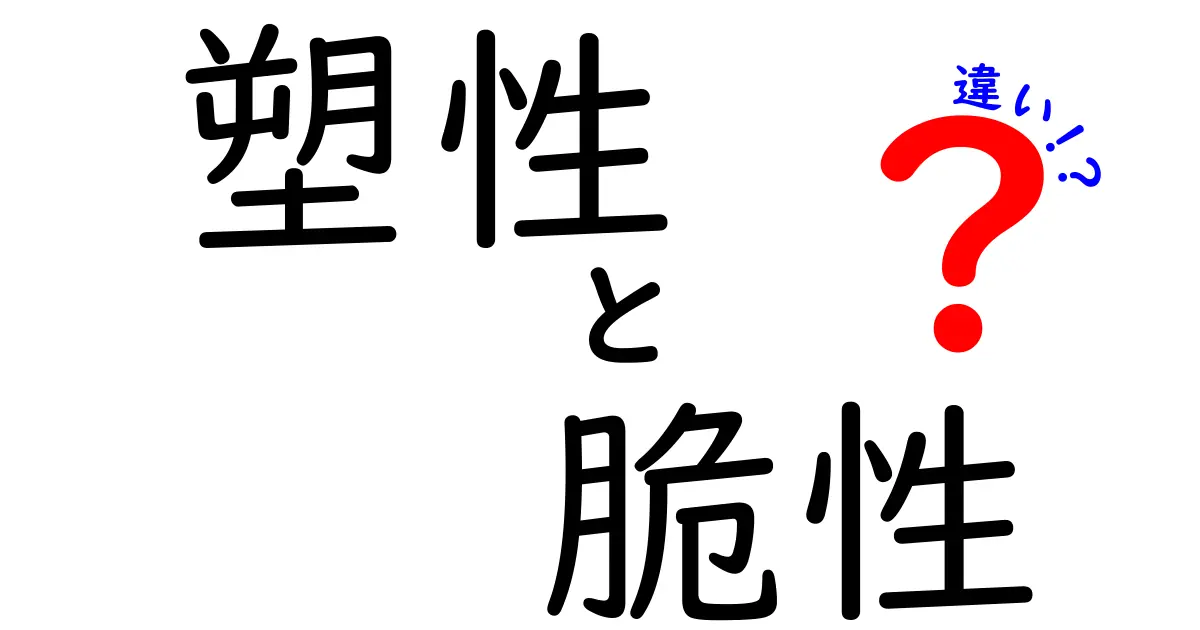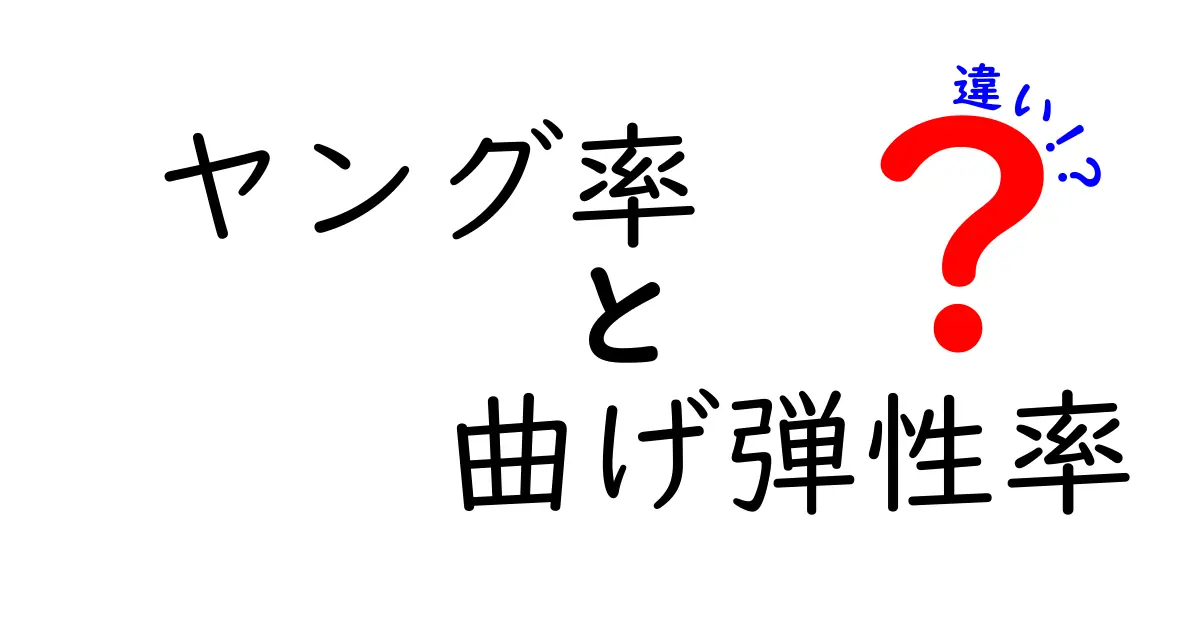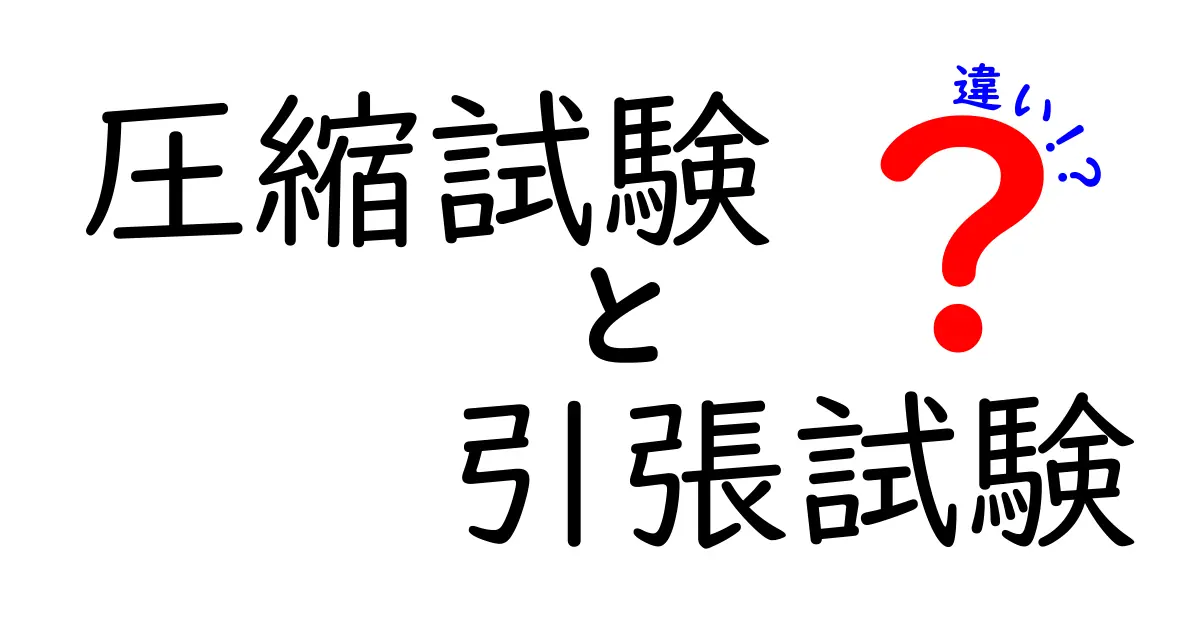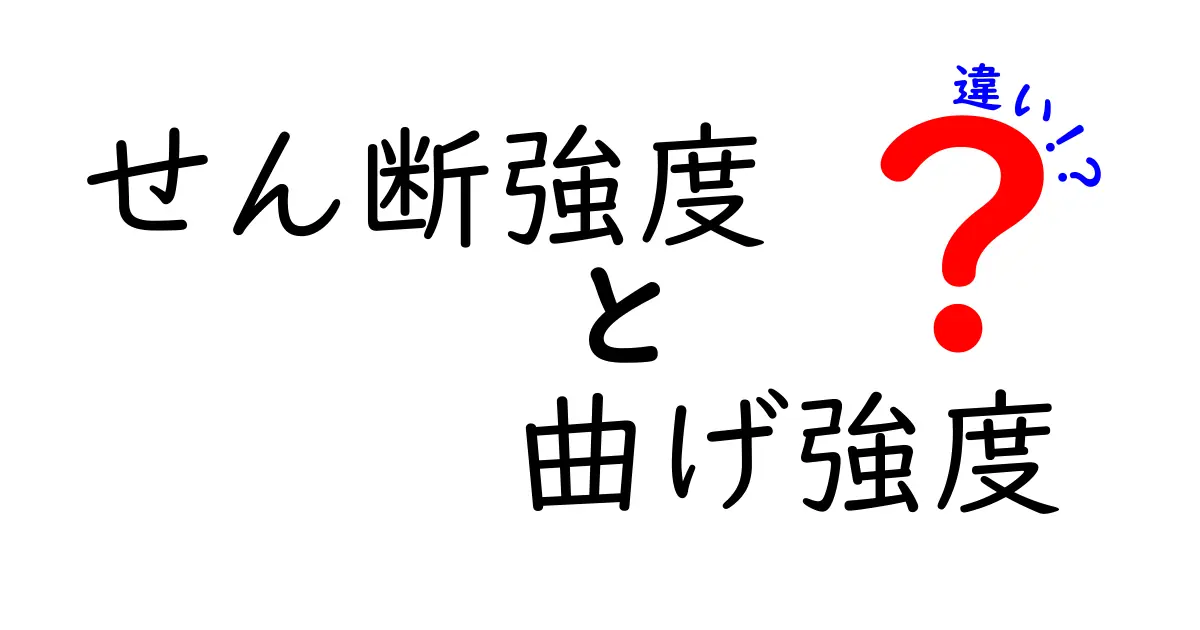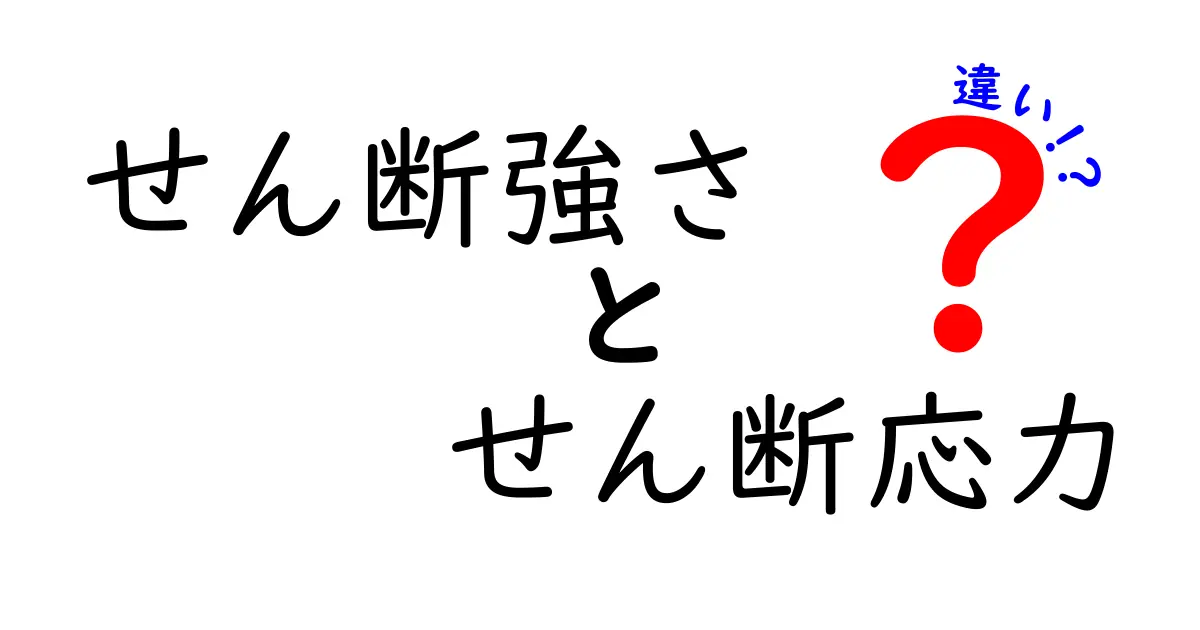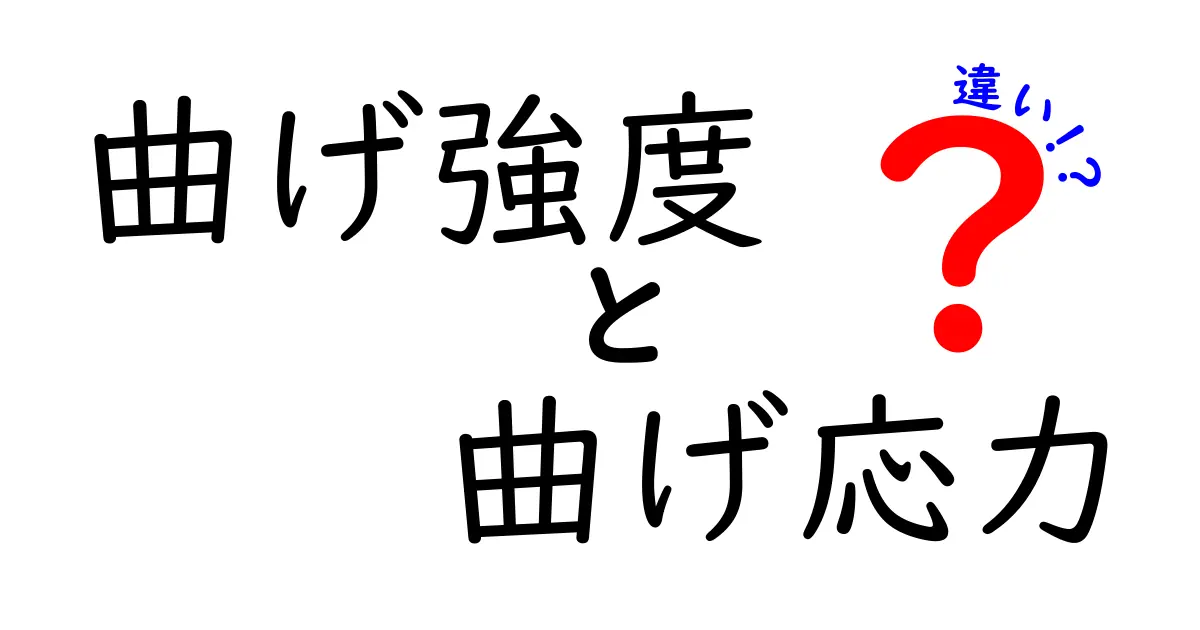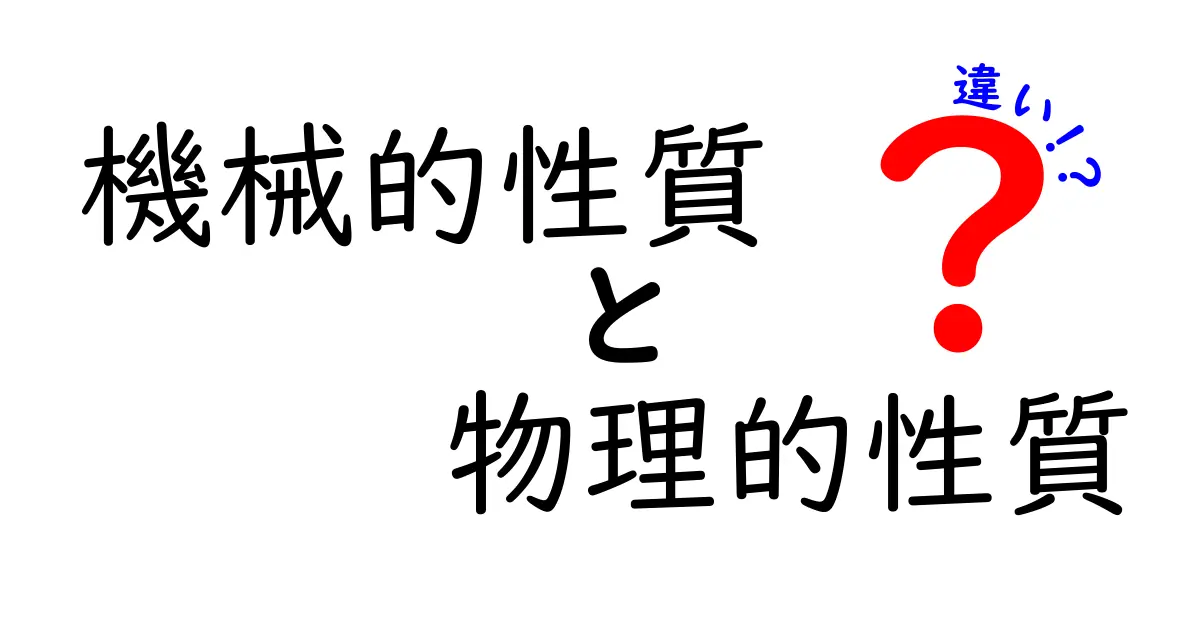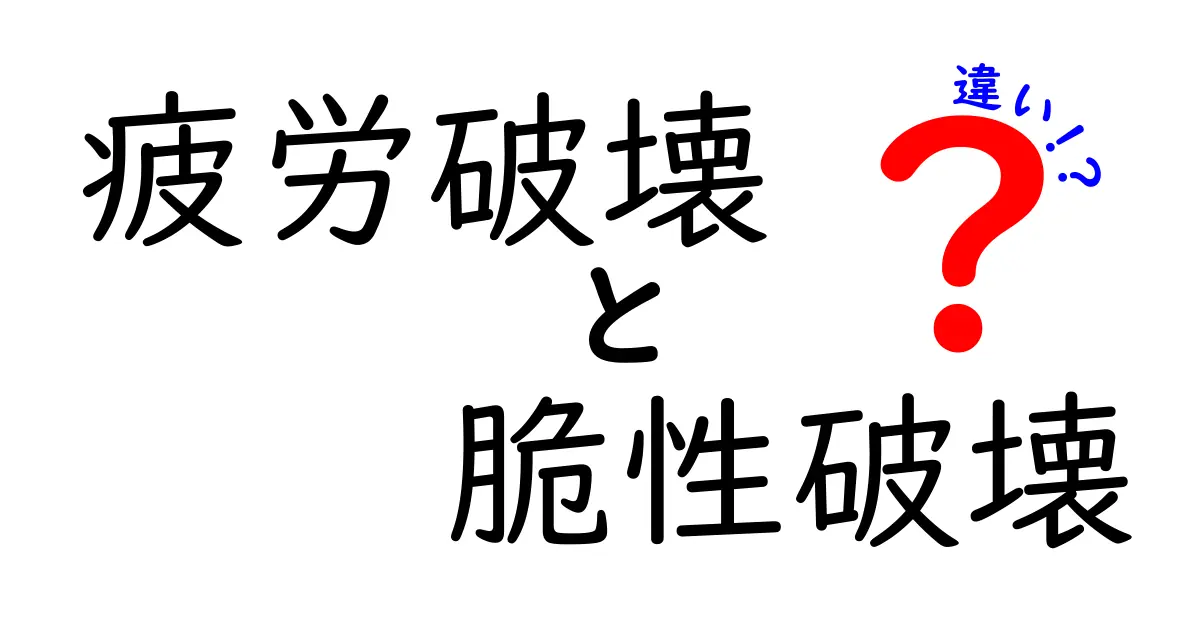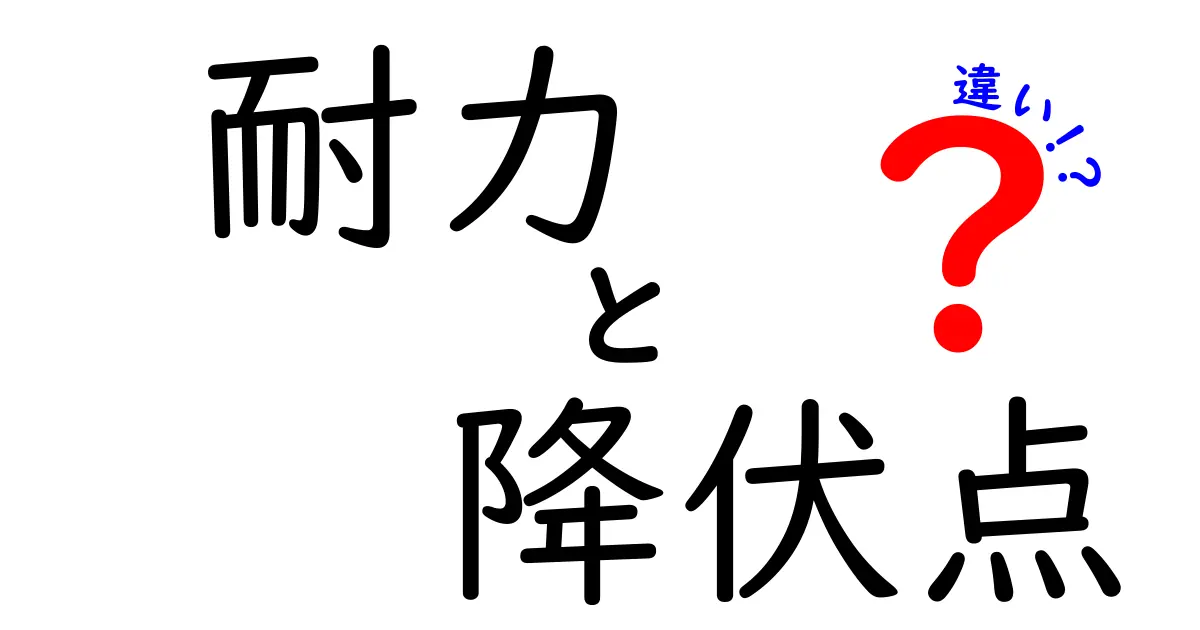

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
耐力と降伏点とは何か?基礎から理解しよう
材料の強さを表す言葉として「耐力」と「降伏点」はよく登場します。しかし、どちらも同じような意味に思えるかもしれませんが、実は明確な違いがあり、それぞれの役割や意味が違います。
まず、「耐力」とは材料が最大限に力に耐えられる数値のことです。具体的には、材料に引っ張りや圧縮の力を加えたとき、その材料が壊れる直前まで耐えられる強さを表しています。
一方、「降伏点」は、材料に力を加えた際に形が変わり始めるポイントのことです。つまり、力を加えると少しずつ変形していきますが、その変形が「元に戻らなくなる(塑性変形)」現象が始まる力の値を降伏点と呼びます。
この2つの言葉は材料の強さを判断するときに欠かせない指標なので、しっかり理解しておきましょう。
耐力と降伏点の違いを詳しく比較!表でわかりやすく解説
これらの違いをさらにわかりやすくするために、以下の表をご覧ください。
| 項目 | 耐力 | 降伏点 |
|---|---|---|
| 意味 | 材料が壊れる前の最大荷重や応力の値 | 材料が永久変形し始める応力の値 |
| 特徴 | 破壊の直前の強度 安全性を考える指標 | 形が元に戻らなくなる初期の応力 塑性変形の開始点 |
| 用途 | 設計時の最大許容強度の判断 | 材料の弾性限界の判断 |
| 測定方法 | 引張試験の最大応力値 | 応力-ひずみ曲線で急激な変形が始まる点 |
| 特徴 | 弾性 | 塑性 |
| 変形の戻り | 力を除去すると元に戻る | 元に戻らない |
| 内部の変化 | 一時的(原子の位置や状態は破壊されない) | 永久的(内部構造が変化) |
| 例 | バネ、ゴム、風船 | 粘土、曲げられた金属 |
| 利用例 | 弾むボール、伸縮バンド | 金属加工、成形品 |
日常生活での塑性と弾性の理解が役立つ理由
塑性と弾性の違いを理解すると、物質の扱いがよりわかりやすくなります。例えば、自転車のタイヤのゴムは弾性の性質を活かして変形しても元に戻り、走行を安定させます。
一方、家具の角にぶつかって凹んだ金属は塑性変形により凹みが残り、形が変わってしまいます。
このような違いを知れば、機械や道具の使い方がもっと理解しやすくなるでしょう。
また工業製品の設計や修理の際も、どちらの性質を活かすかで結果が変わるため、科学や物理の学びとしてもとても重要です。
弾性って聞くとゴムやバネのイメージが強いけど、実は私たちの体の筋肉や皮膚にも弾性があるんだよ。例えば、腕の筋肉を伸ばしても元に戻るのは筋肉の弾性のおかげ。だけど筋肉を使い過ぎると硬くなって、弾性が弱くなることもある。だから適度なストレッチが大事なんだね。
前の記事: « 塑性と脆性の違いとは?身近な素材の性質をやさしく解説!
次の記事: 耐力と降伏点の違いを徹底解説!中学生でもわかる強さの秘密 »