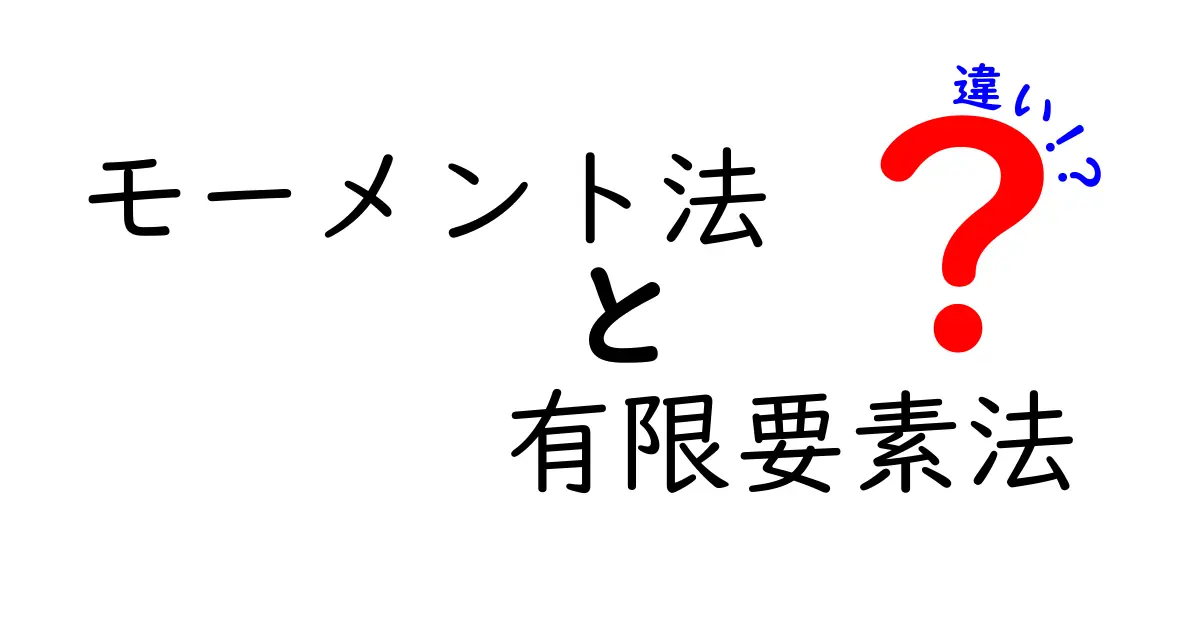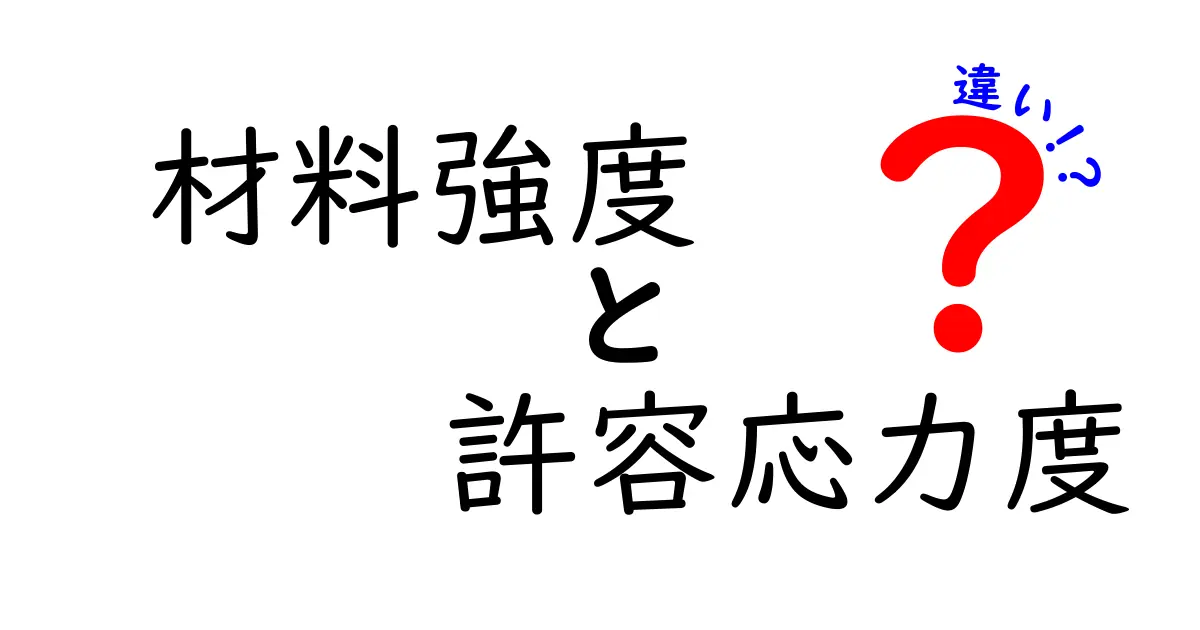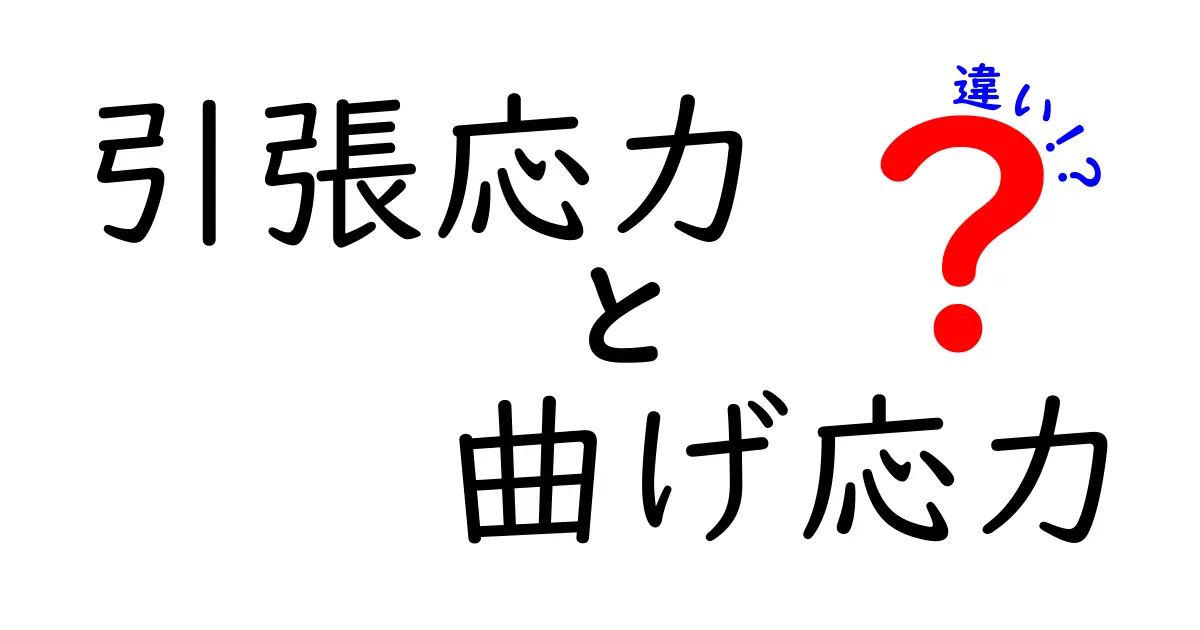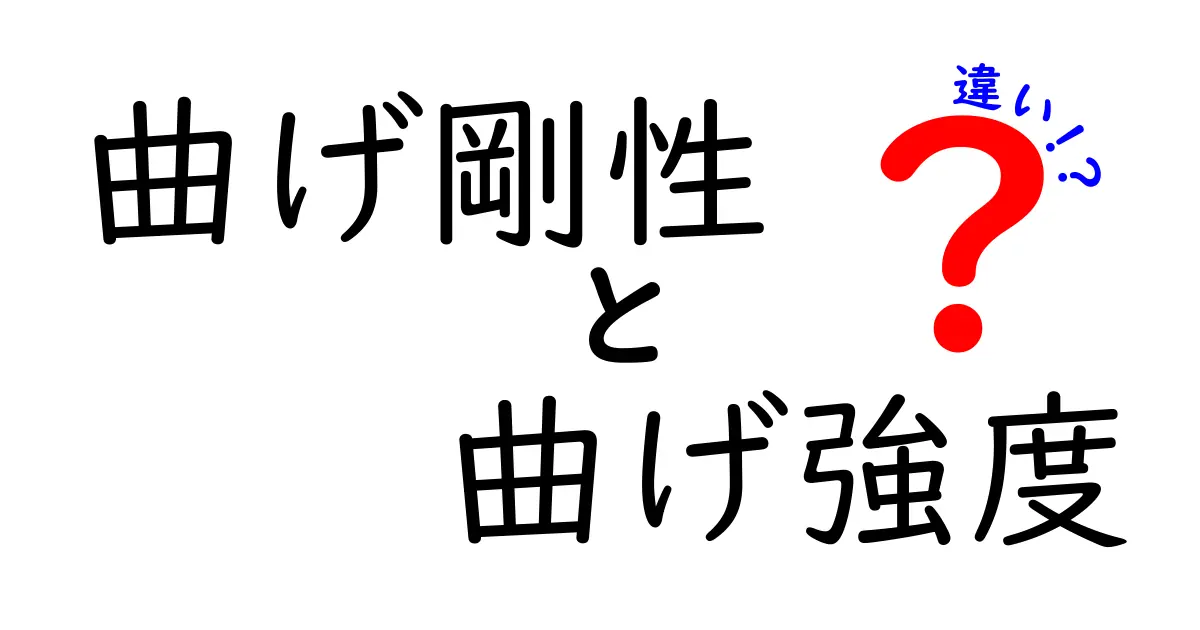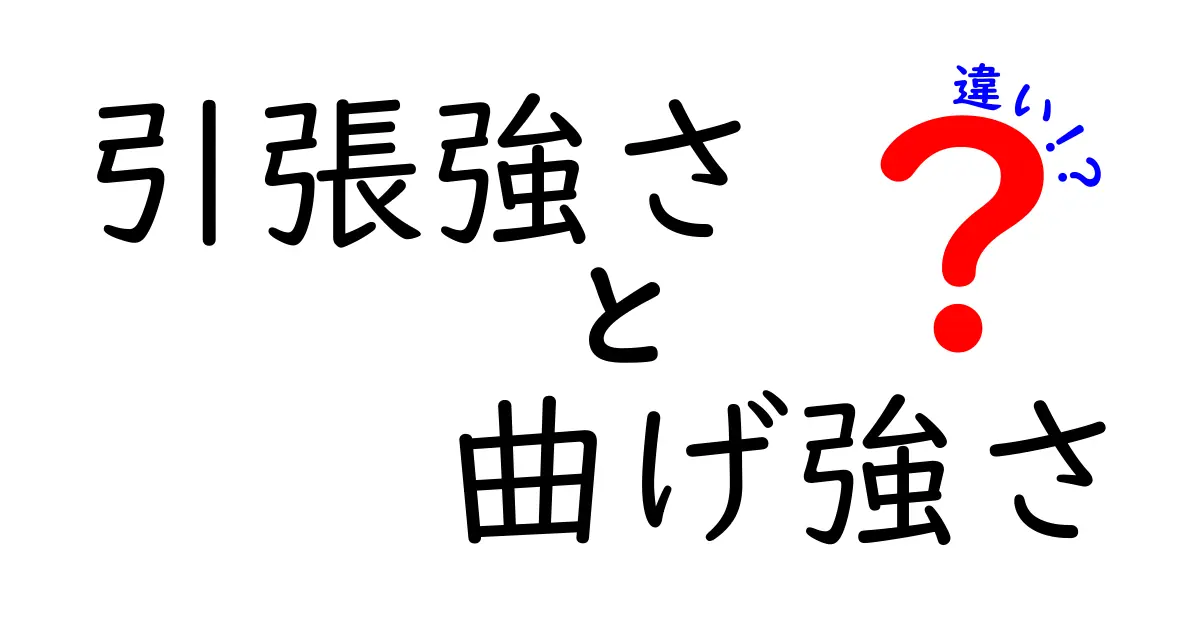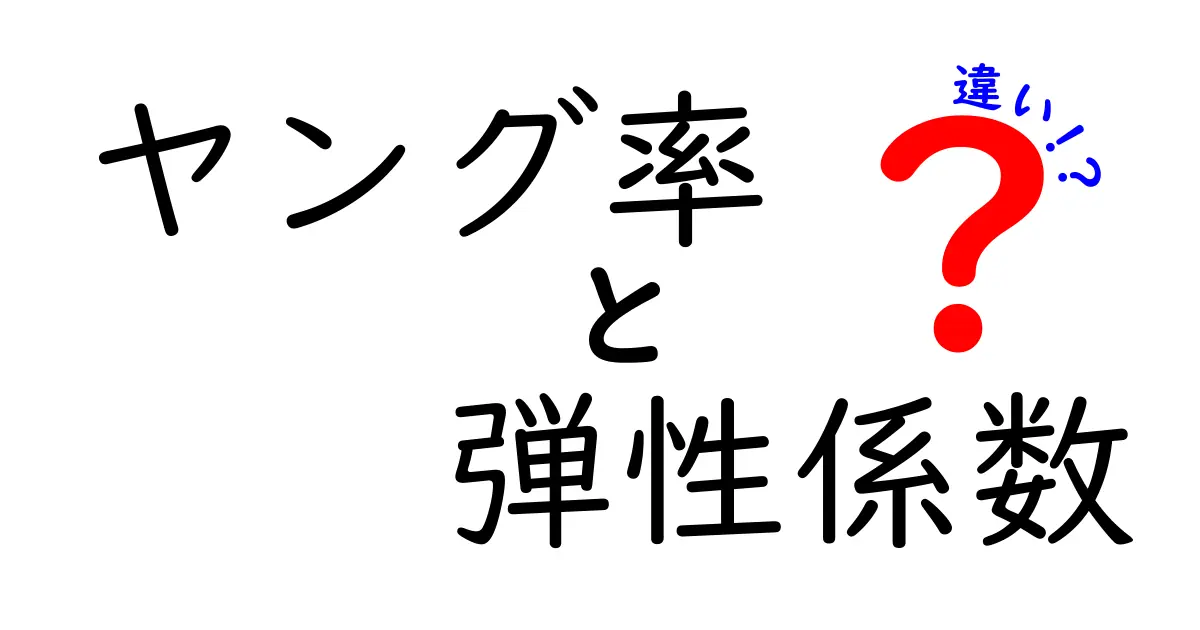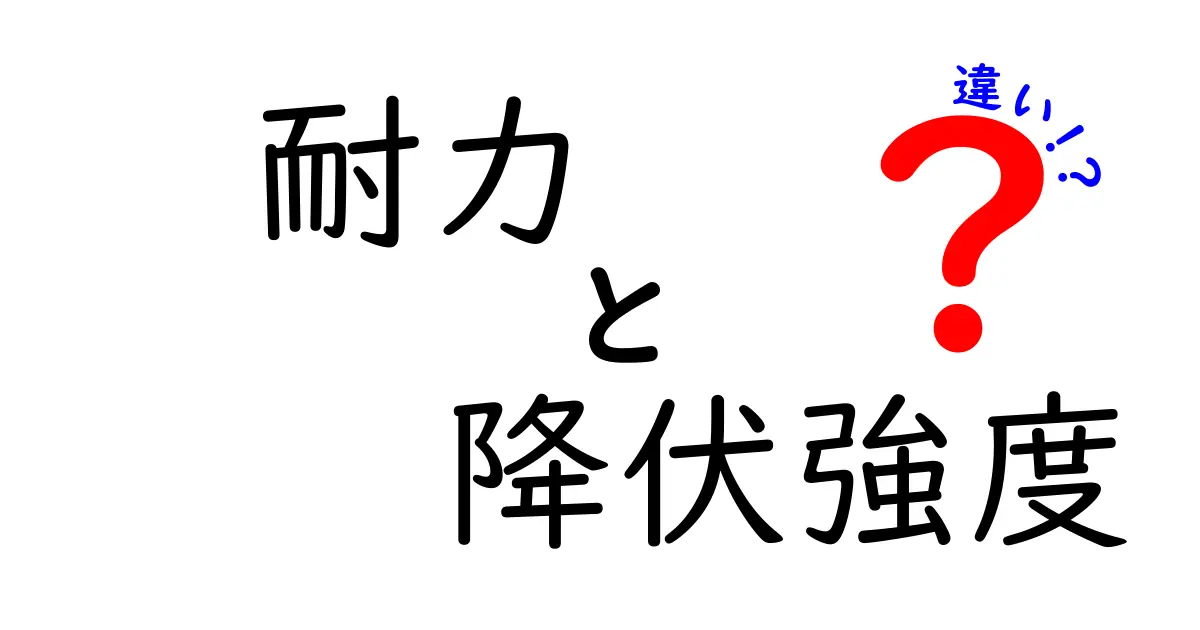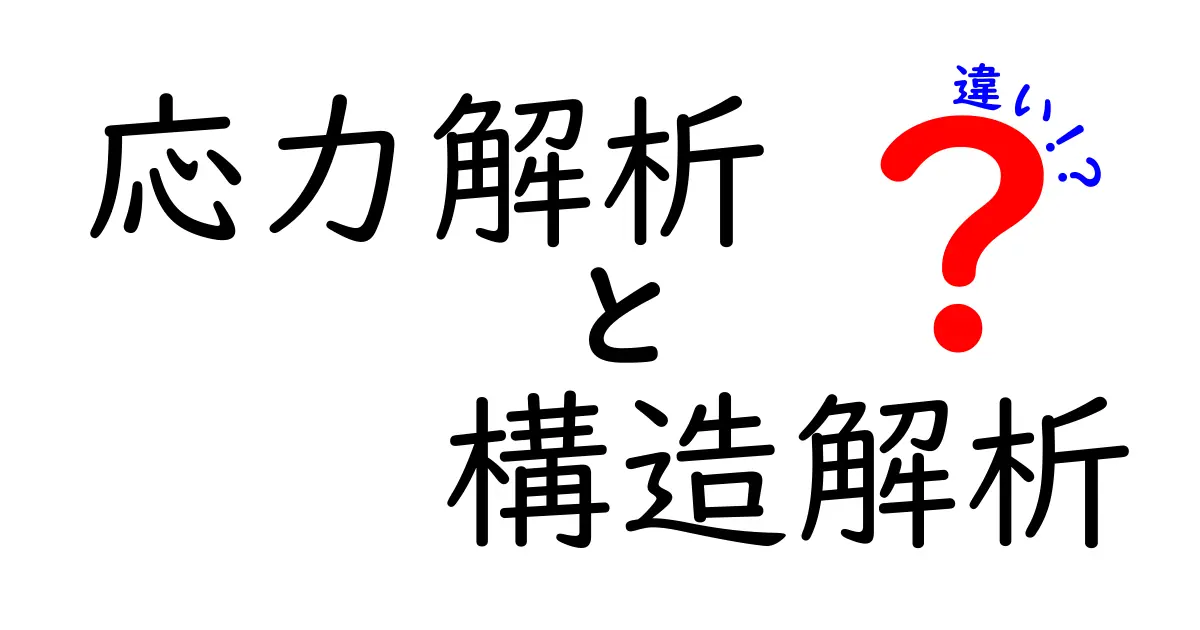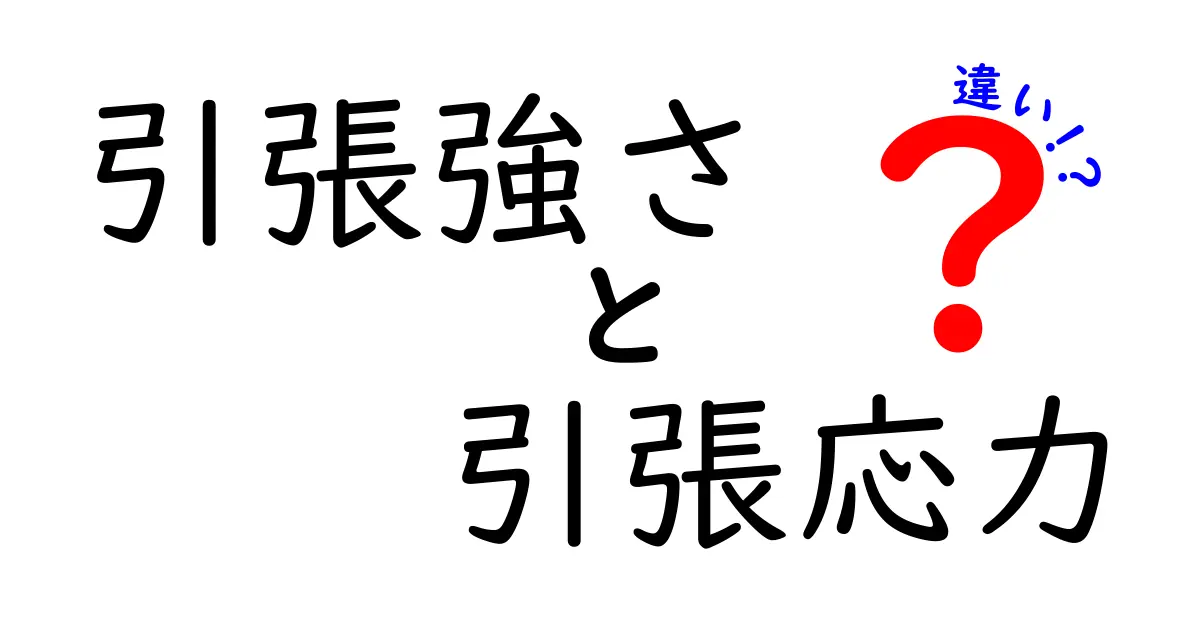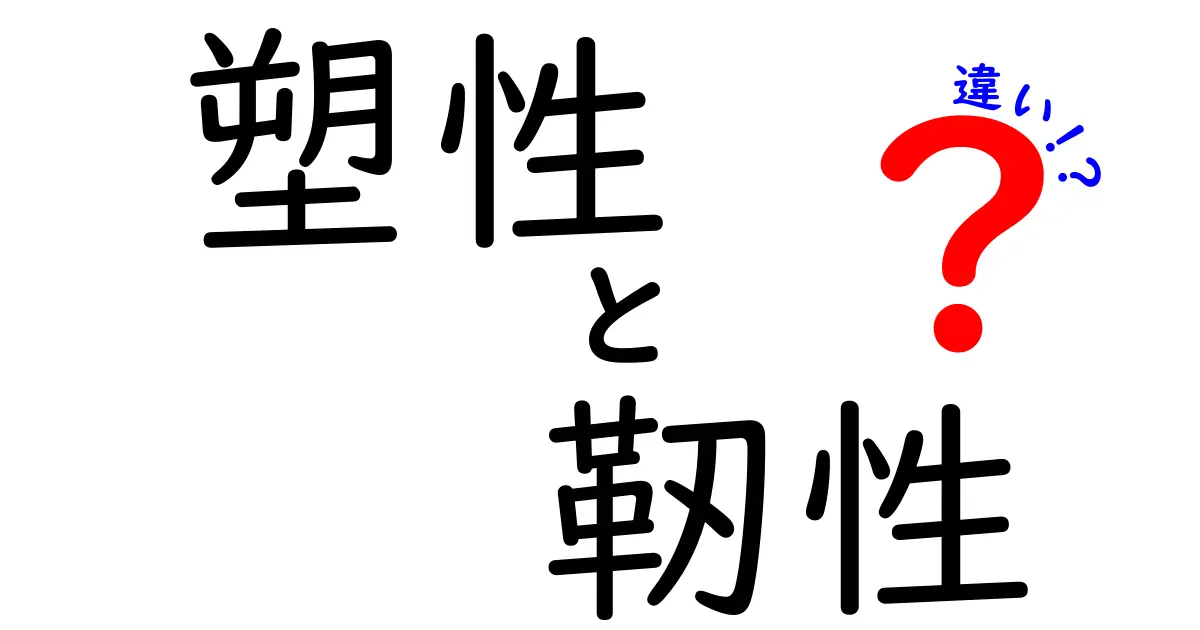

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
塑性と靭性とは何か?基本を理解しよう
まずは塑性(そせい)と靭性(じんせい)の意味から見ていきましょう。塑性とは、物質が力を受けたときに変形した状態を保持できる性質のことを指します。つまり、一度形が変わっても、元に戻らずにそのままの形状を保てるということです。例えば、粘土を押した時に形が変わり、その形がそのまま残るのが塑性の働きです。
一方、靭性とは物質が力を受けて割れたり壊れたりしにくい性質のことです。簡単に言うと、丈夫で折れにくいという特徴があります。靭性が高い材料は衝撃や圧力に強く、壊れたりひびが入りにくいため、建物の材料や車の部品などに使われます。
この2つは材料の重要な物理的な性質ですが、それぞれ役割や特徴が違うため混同しやすいものです。
塑性と靭性の違いを具体的に比べてみよう
ここでは、塑性と靭性の違いをわかりやすい表にまとめてみました。
| 性質 | 意味 | 特徴 | 例 |
|---|---|---|---|
| 塑性 | 変形を保持できる性質 | 力を加えると永久的に形が変わる。弾性とは違って元に戻らない。 | 金属の加工、粘土 |
| 靭性 | 壊れにくい性質 | 強い衝撃や力に耐えることができ、割れにくい。 | 鋼鉄、ゴム |
このように、塑性は形が変わる能力、靭性は壊れにくさを表しているのが大きな違いです。
たとえば粘土は塑性が高く、とても簡単に形を変えられますが、力を加えると割れやすく靭性はあまり高くありません。一方、ゴムはそのままの形を保ちやすいですが、強い力を受けてもびくともしない靭性の高さが特徴です。
日常生活や工業製品での塑性と靭性の利用例
塑性と靭性は私たちの身の回りにある多くのものに関係しています。
例えば、自転車のフレームや建物の鉄骨は靭性が非常に重要です。これらは強い力や衝撃に耐えなければならず、もし簡単に壊れてしまうと大事故につながります。だから高い靭性を持つ材料が使われるのです。
一方、金属を曲げたり形を変えたりするときには塑性が求められます。車のボディや家電製品は元の形を大きく変えるため、金属の塑性が不可欠です。
また、食品の加工でもこの考え方が活用されます。例えば、パン生地は適度な塑性と靭性を持っていて、こねたり伸ばしたりすることができます。硬すぎると形が変わらず、柔らかすぎると壊れやすくなってしまうのです。
このように塑性と靭性は、材料の使い方や性能を決める重要なポイントとなっています。
塑性という言葉を聞くと、何だか難しいイメージがありますが、実は日常生活でよく使われている考え方なんです。たとえば粘土遊び。粘土は力を加えると形が変わり、その形を保ちますね。これが塑性の働きです。面白いのは、金属も適度な塑性があるために、曲げたり叩いたりして形を変えられる点です。これは金属加工の基本で、車や家電の部品を作るときにとても大切なんですよ。粘土の柔らかさと金属の硬さ、どちらも塑性を持っているけど、その度合いが違うだけなんですね。そう考えると、塑性って身近で面白い性質ですよね!