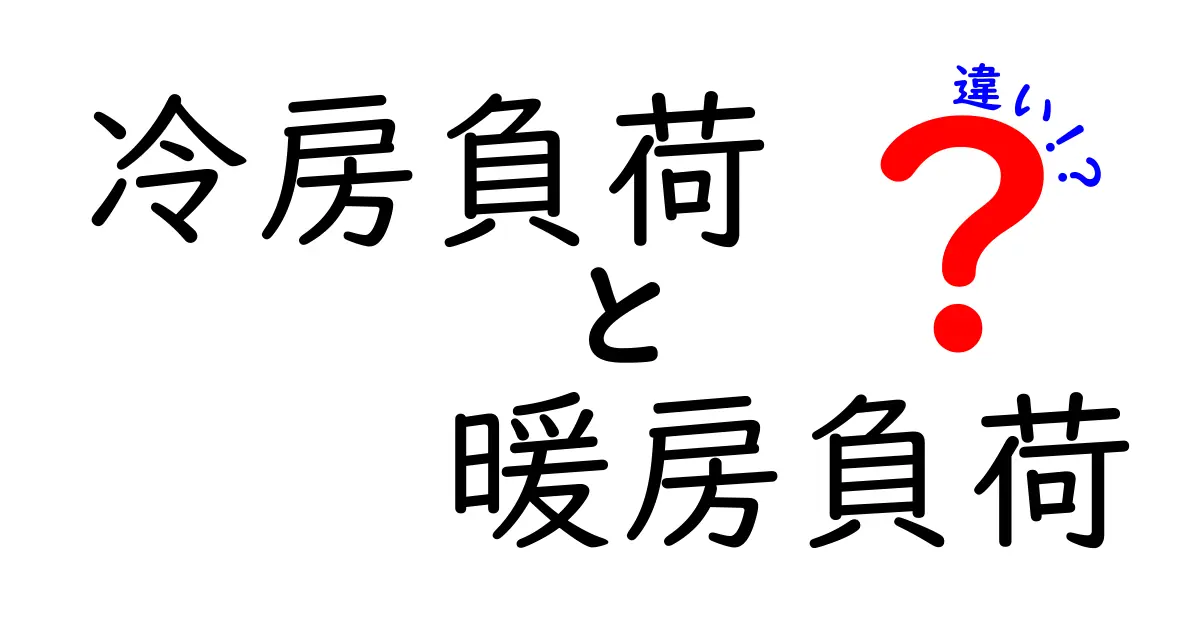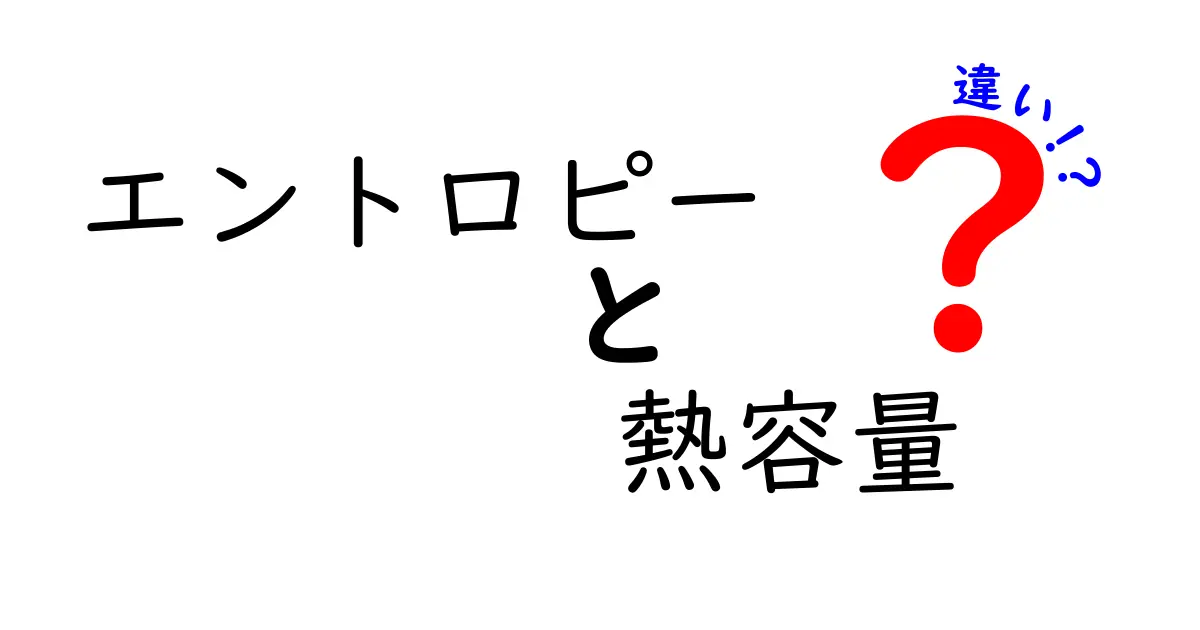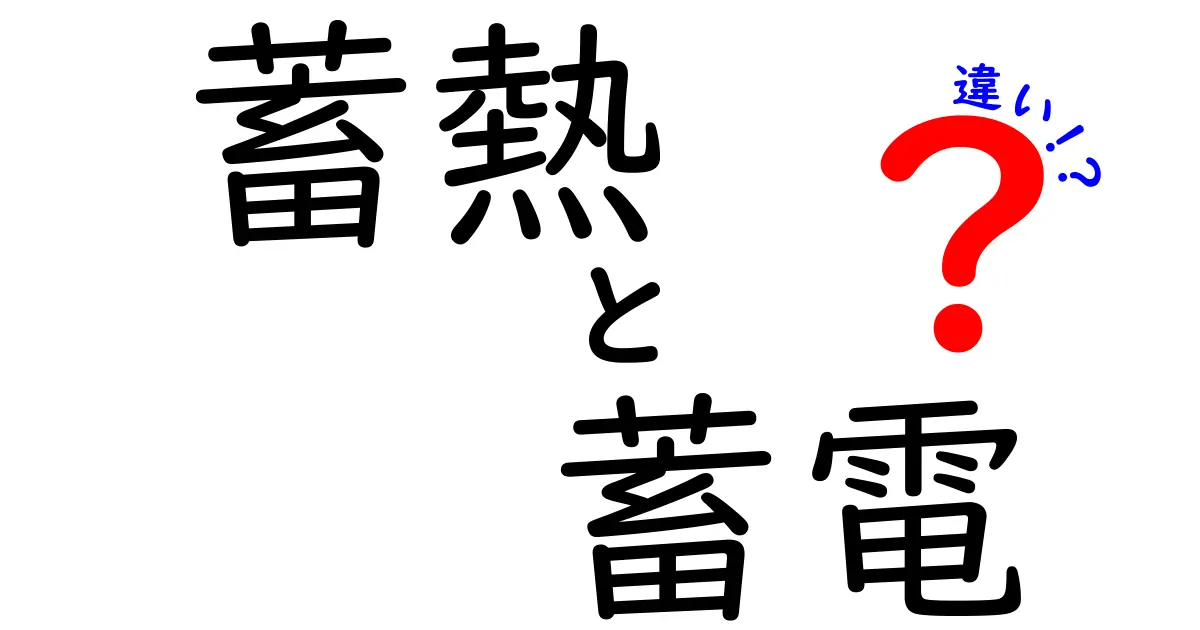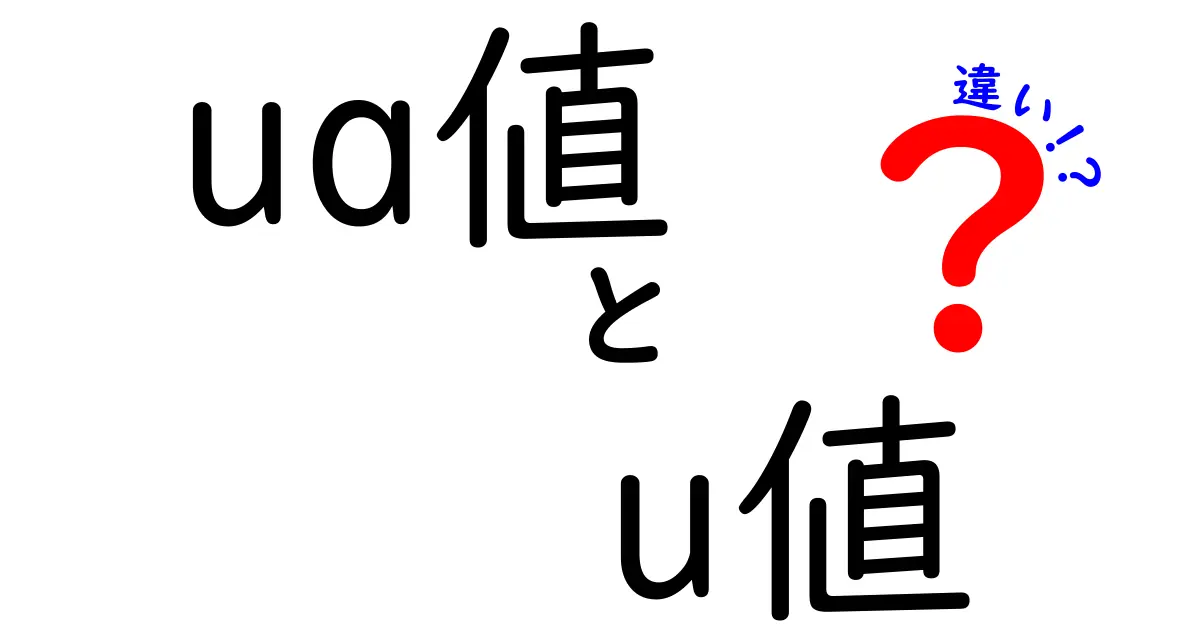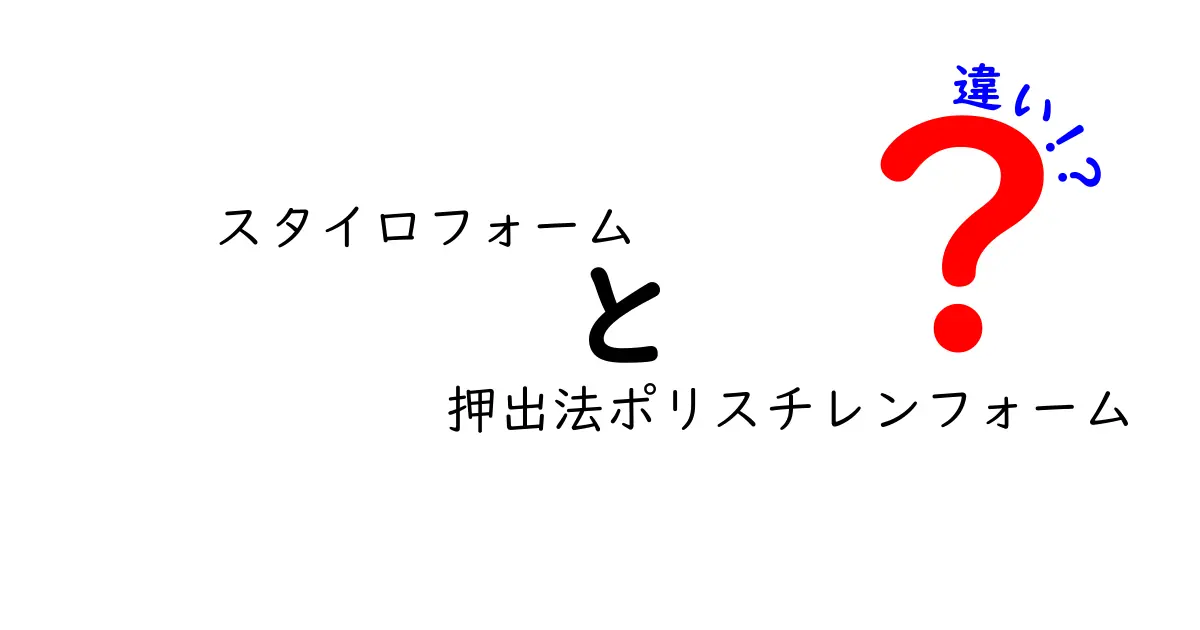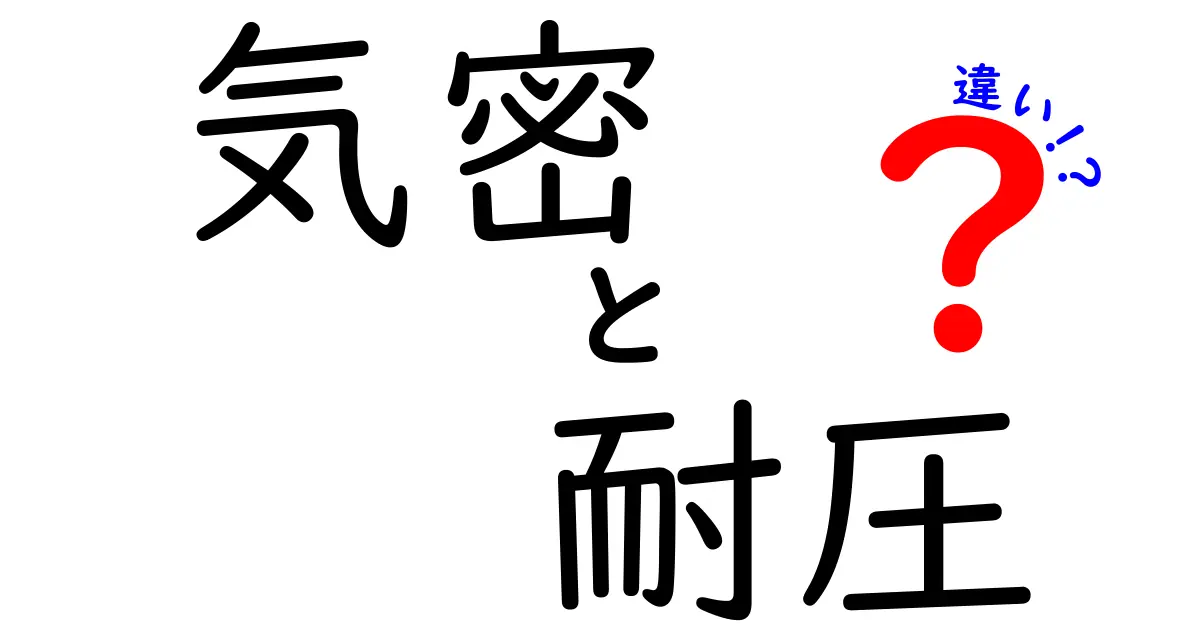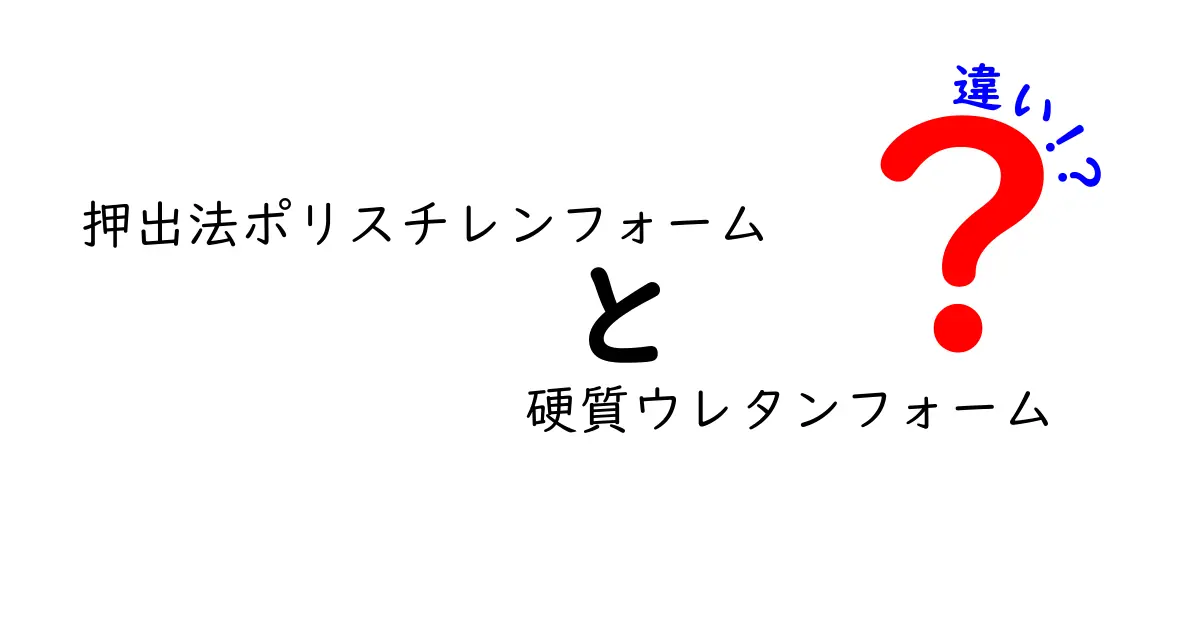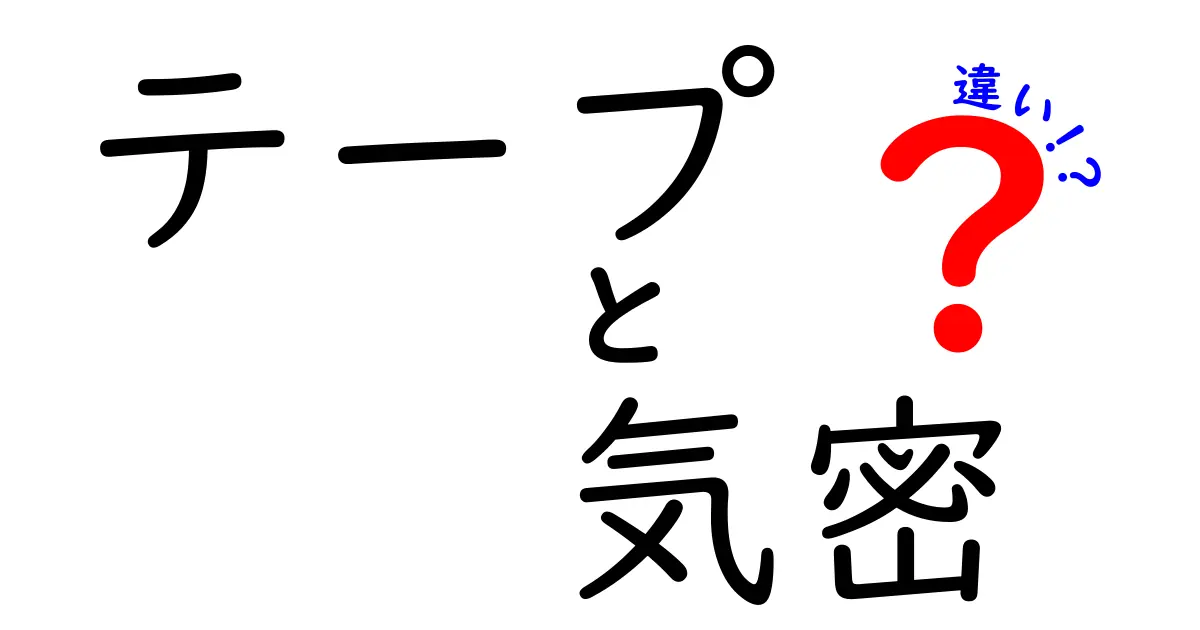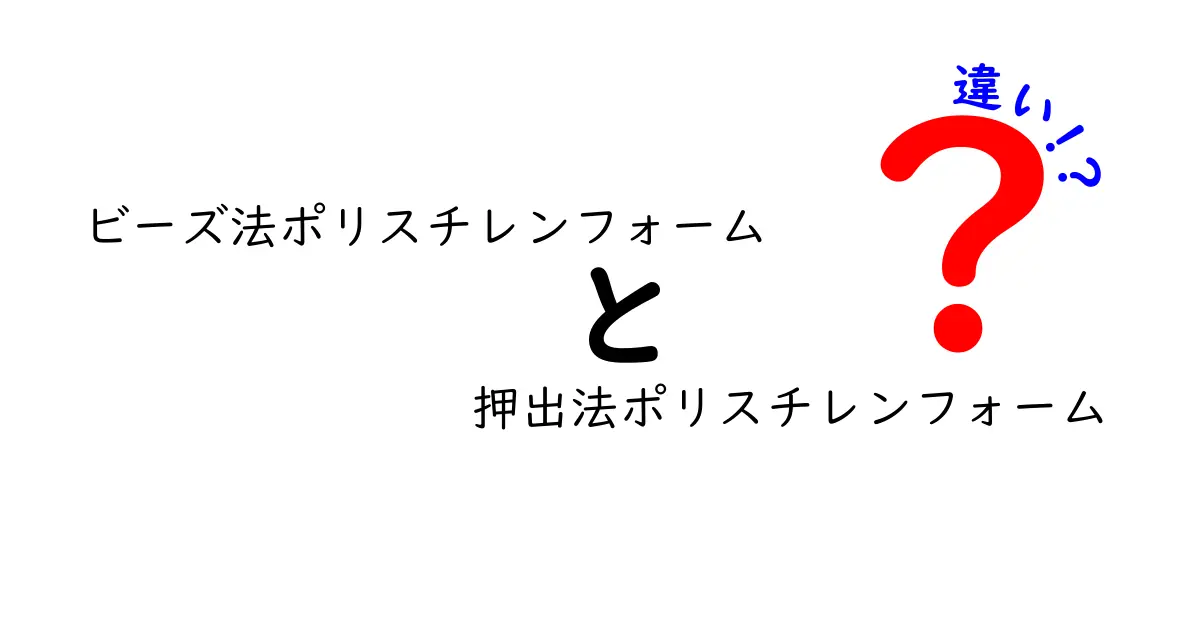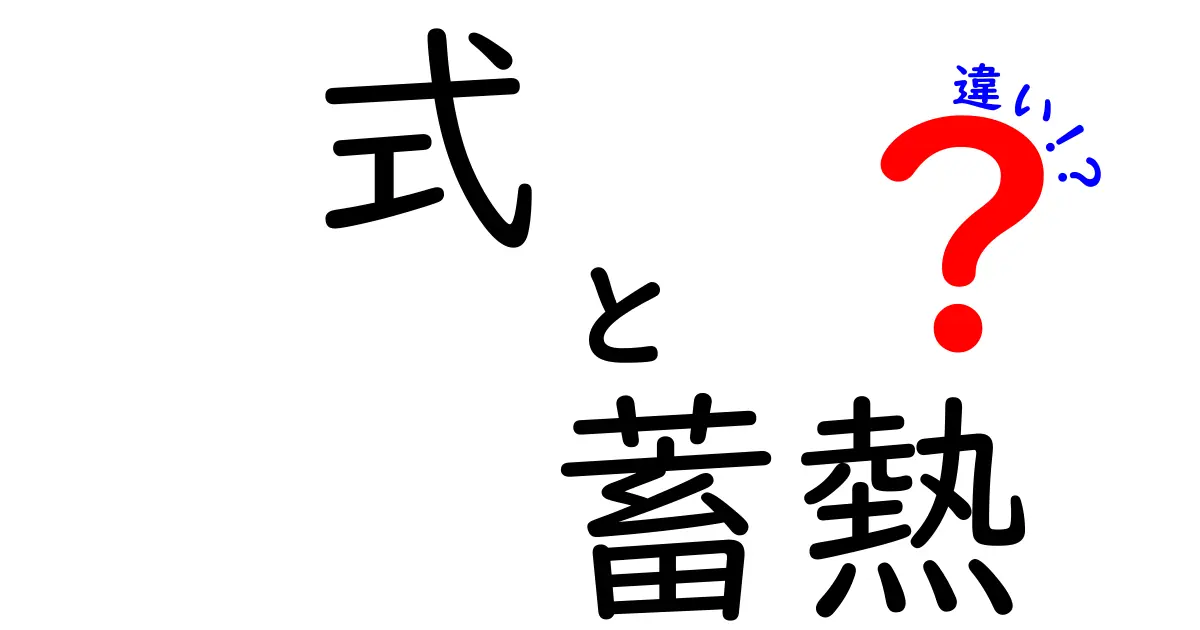

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
式とは何か?基本の説明
まず式という言葉には、いろいろな意味がありますが、ここでは物理や化学でよく使われる「計算式」や「数式」を指します。式とは、何かの関係性や法則を表すために数字や記号を組み合わせたものです。たとえば、速度を表す式「速度 = 距離 ÷ 時間」は、私たちがある距離をどれくらいの時間で移動するかを計算するためのルールです。
式は単なる言葉や説明よりも
詳しく言うと、式は問題を解くためのツールであり、物理の法則を数学的に示すために使われます。
このため、「式」は動作や現象の仕組みを簡単に理解し、計算する助けになります。
蓄熱とは?熱の貯め方・使い方について
蓄熱(ちくねつ)とは、熱エネルギーをためておくことを指します。私たちの生活の中でも、日の光や暖房で集めた熱をあとで使いたい時に役立ちます。
たとえば、昼間に太陽の熱を貯めておき、夜にその熱を利用する「蓄熱システム」は省エネや環境への配慮で注目されています。
蓄熱の仕組みは、熱をためる素材や構造によって変わります。石やコンクリート、水など、熱をよくうけとめる物質が使われることが多いです。
蓄熱は冷暖房や発電での効率アップに使われ、エネルギーを無駄なく使うための重要な技術です。
式と蓄熱の違いとは?わかりやすい比較
ここまで「式」と「蓄熱」について説明してきましたが、実はこの2つはまったく違うものです。
まず、「式」は計算や表現の道具であり、熱やエネルギーそのものではありません。
一方、「蓄熱」は熱エネルギーをためる物理的な現象や技術なのです。
簡単にまとめると、式は考えをはっきりさせるための言葉(数式)で、蓄熱は物質が熱をためておくという実際の行動という違いがあります。
以下の表で違いをまとめます。
このように、「式」と「蓄熱」は目的も使われ方も全く異なり、混同しやすい言葉ですが、覚えておくと便利です。
まとめ:式と蓄熱の違いをしっかり理解しよう
今回の記事では「式」と「蓄熱」の違いについてわかりやすく解説しました。
式は計算や表現のための数式、蓄熱は熱をためる仕組みや技術。
両者は性質や使われる場面が根本的に違います。
この違いを知ることで、科学や生活の中での熱の扱いについても深く理解できるようになります。
ぜひ、この機会に式と蓄熱の意味を覚えて、周りの話題にも自信をもって答えられるようになりましょう!
蓄熱という言葉は、ただの“熱を貯める”ことだけでなく、実はさまざまな種類があります。たとえば、水を使った蓄熱なら熱をためた後にゆっくり放出できるので、寒い夜に暖かさが続きます。
さらに、固体を使った蓄熱は建物の壁材として使われて熱を蓄え、日中の熱を夜間までキープ。こうした細かい仕組みを知ると、蓄熱がどれだけエコで便利かがもっと分かりますよね。蓄熱の世界は奥深いんです!
次の記事: 比熱と熱容量の違いとは?中学生でも分かる科学の基本を解説! »