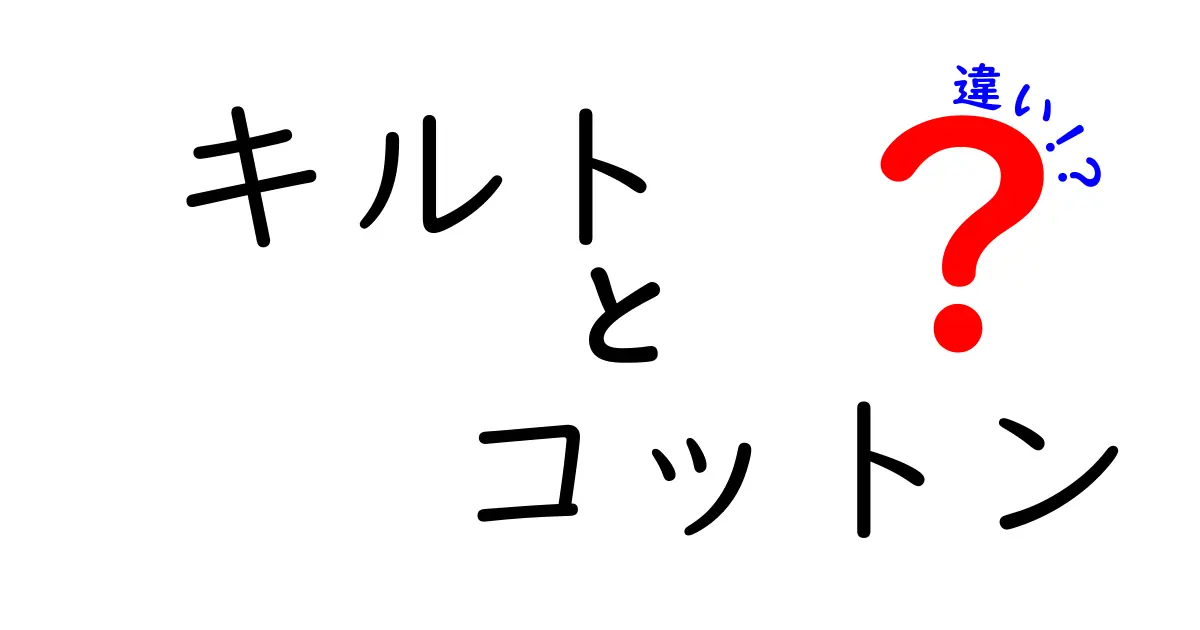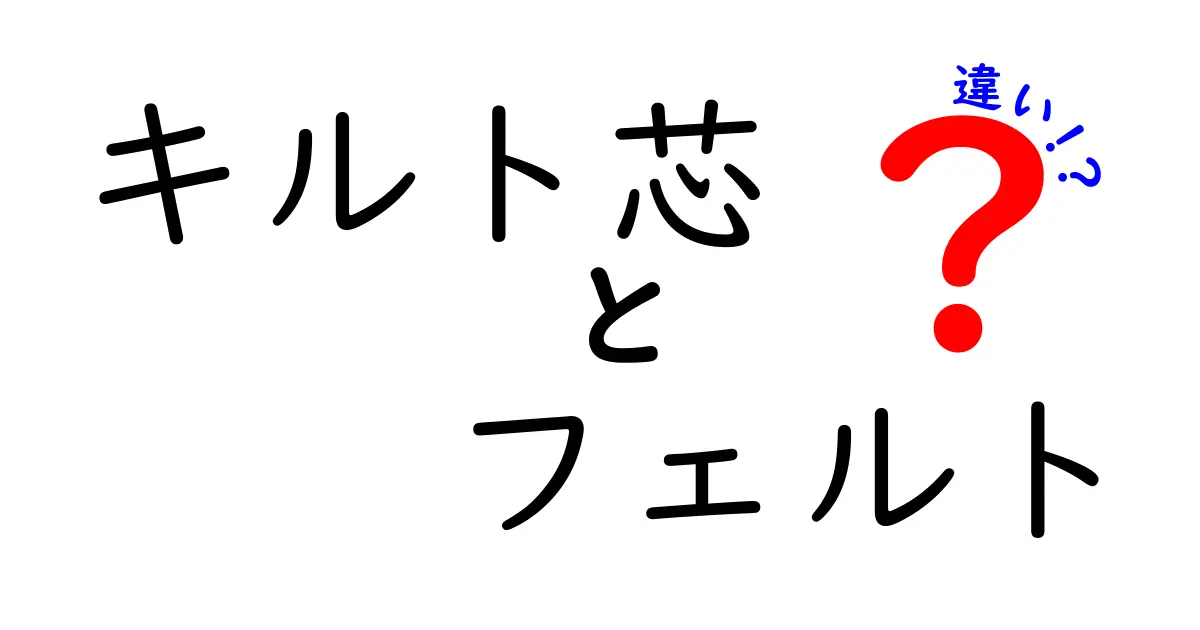

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
キルト芯とフェルトの基本的な違いを知る
キルト芯とフェルトは、名前は似ていますが性質が大きく異なります。キルト芯は主に布を重ねて縫い合わせるときの“芯”として使われる素材で、柔らかさと適度な厚み、そして張り感を作る役割があります。織物を縫う際には、断熱性や厚みを加え、縫い目を保護する目的で使われることが多いです。反対にフェルトは、 wool や合成繊維を圧縮して固めた“繊維が結合した布”のことで、結合力が高く、厚みそのものが形を作る素材です。これにより、布地を縫い合わせるよりも先に形や輪郭を作る力があります。
この違いを知ると、手芸の場面でどちらを選ぶべきかが見えてきます。例えば、布を縫って縫製する小物にはキルト芯の柔らかさが活きます。
ただし、キルト芯は水洗いするとへたることがあり、洗濯を前提とした作品には適さない場合があります。
一方、フェルトは洗濯耐性や形状の安定感が高い場面で力を発揮します。フェルトは水洗いにも比較的強く、裁断や縫製後の形を保つ力が強いのが特徴です。こうした違いを覚えると、作品の完成度が上がります。さらに学習する際には、素材ごとの表現力の違いも重要です。
たとえば、フェルトは毛の繊維が絡んでいるので、切り口がほつれにくく、端処理が楽という利点があります。逆にキルト芯は端がほつれやすい布地と組み合わせると、縫い代の処理が難しくなることがあります。
このようなポイントを踏まえて、最初は小さな作品から実際に手を動かして体感してみると理解が深まります。
用途別の使い分けと具体例
実際の製作現場では、作品の目的に合わせて素材を選ぶことが大切です。ミニポーチやクッションの中綿にはキルト芯が便利です。柔らかさと軽さを活かして、触り心地の良い仕上がりを作れます。布地の風合いを大切にしたい場合には、表地と裏地の間にフェルトを挟むことで立体感と強度を両立させる方法もあります。フェルトは形状を保つ力を活かして、立体的なモチーフやボタン留めの土台として使われることも多いです。
また、手作りのアクセサリーや小物は、縫い目の美しさよりも形の安定感が大切になる場面があり、そんな時にはフェルトの方が適しています。
ここで、素材選びの決定的なポイントを整理しておきましょう。まず、作品を水洗いする予定があるかどうか。水に弱い場合はキルト芯を避け、フェルトを選ぶのが安全です。次に、縫い合わせる布の組み合わせ。キルト芯は柔らかい布と相性が良く、フェルトは厚手の布地と組み合わせると安定します。
最後に、端の処理。フェルトはほつれにくい特性があるので、鋭角の形状や複雑なパーツの成形にも適しています。これらを踏まえて、下記の簡易表を参考にしてください。
この表を見れば、どちらを選ぶべきかの判断材料が明確になります。
手作りを続けるうちに、素材の性質に応じた作り方が身についてくるでしょう。
最終的には直感と経験が大きく作用しますので、実際に触れて作ってみることが一番の学びです。
フェルトの話題を友だちと雑談していたとき、ふとした疑問が湧きました。『フェルトって本当に“硬い布”みたいだけど、どうして形をこんなに保てるんだろう?』と。実はフェルトは単なる“布”ではなく、繊維が絡み合って結合することで作られる“固有の構造”なのです。羊毛フェルトなら熱と圧力、化学処理を経て繊維同士が絡み合い、縮んで塊のような形になります。だから裁断した後の端がほつれにくく、縫い代を少なくしても形が安定します。一方でキルト芯は布を縫い合わせるための“芯”として使われ、柔らかさと復元力を活かして、布地の風合いを損なわずに厚みをプラスします。こうした違いを知ると、工作の現場では“どの素材を主役にするか”がすぐに見えてきます。最近はフェルトを使って立体的なモチーフを作るのが楽しいのですが、同じ作品でも用途に合わせて素材を使い分けるのがコツだと実感しています。次に挑戦するときは、フェルトの厚みとキルト芯の厚みを組み合わせて、薄手の布地とどう相性が良いかを実験してみたいですね。