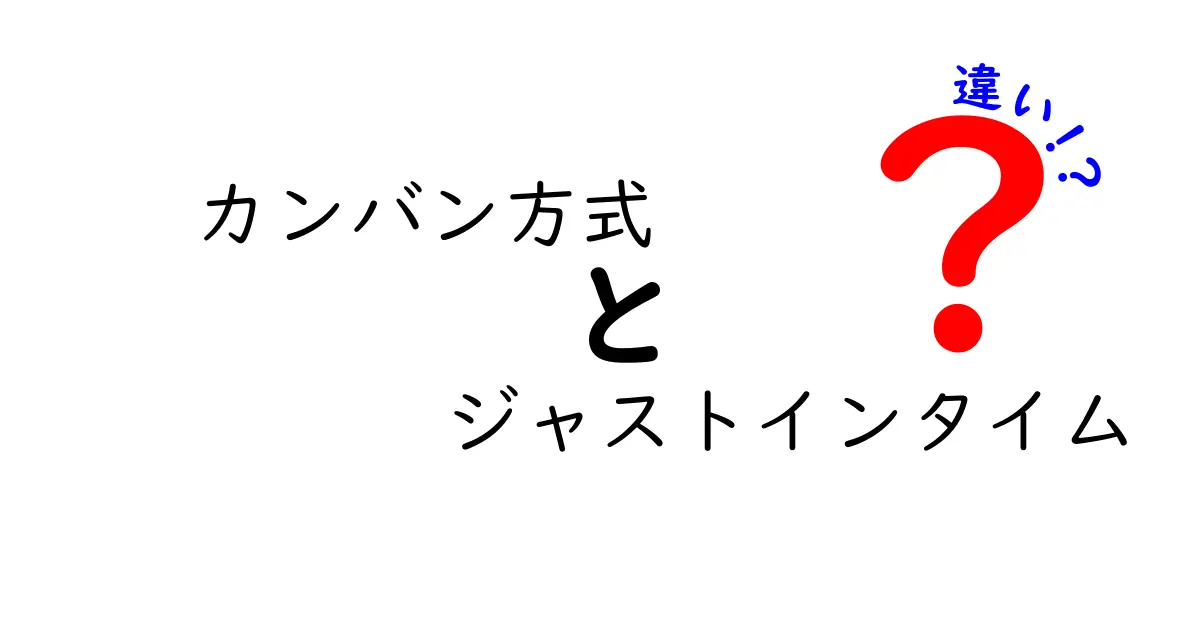

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
カンバン方式とジャストインタイムの違いを理解するための基本
まずは用語の意味を整理します。カンバン方式とは、作業の進行を「看板」と呼ばれる視覚的な指示カードで可視化し、次の作業を「引き出す」タイミングを調整する仕組みです。生産ラインの流れを妨げず、作業が終わるまで次の動作を始めない「プル型」の動きが特徴です。これに対してジャストインタイムは、必要なものを、必要な時に、必要な量だけ作ることを目指す思想で、在庫を最小化します。両者の共通点としては、無駄を減らすことと作業の流れを崩さないことが挙げられますが、アプローチの焦点が違います。
カンバンは「作業の見える化」と「ボトムアップの改善」を重視します。ジャストインタイムは「在庫の削減」と「供給の安定性」を重視します。これらを正しく組み合わせると、現場のムダを減らし、品質を保ちながらスピードを上げることができます。
では、どのような場面で適しているのでしょうか。 カンバンは複数のチームが同時に作業する環境や、変化の多い現場で力を発揮します。ジャストインタイムは部品や原材料の供給が安定しており、需要が比較的一定で在庫コストを抑えたい場合に効果的です。
次に表現の具体例を見ていきましょう。例えば製造現場では、カードに「次に必要な部品」「現在の在庫」「次の工程の要求量」などを書いて、各ステージで視覚的に確認できるようにします。これにより、誰が何をしているのか、どこで滞っているのかが一目で分かります。
この情報を基に、チームは協力してボトルネックを解消します。
また、現場だけでなくソフトウェア開発やサービス業にも応用され、タスクの優先順位や納期の見える化に役立ちます。
カンバン方式の実践のコツ
実践のコツとしては、まずWIP制限を設定することが大切です。これにより作業量が過剰にならず、ボトルネックを特定しやすくなります。次に、看板の運用ルールをチーム全員で共有します。役割を明確にした上で、定期的な見直しを行い、改善点をカードに書き込んで回します。最後に、組織全体の可視化を進めるために、物理的なボードだけでなくデジタル版の看板も検討します。デジタル化は情報の検索性を高め、リモートワーク時にも同期を取りやすくします。
ジャストインタイムの特徴とリスク管理
ジャストインタイムは「必要な時に必要な量だけ作る」という考え方で、在庫を最小限に抑えることを目指します。これにより保管コストが下がり、資金の回転が良くなります。ただし、在庫を減らすほどリスクも増えます。部品の欠品や納期遅延が生じると、生産ライン全体が止まる可能性が高くなります。したがってJITを実践するには、供給元の信頼性、品質の安定、リードタイムの短縮、そしてサプライヤーとの緊密な連携が不可欠です。
また品質問題が起きた場合の代替部品や予備計画を用意しておくことも重要です。これらの要素を総合的に整えないと、在庫を減らしたはずが別のコストを生む結果になりかねません。
現場の実践では、需要の変動を見越して安全在庫の設定や、供給元の評価を定期的に行うことが有効です。
このようにカンバンとJITは補完的な関係にあり、適切な場面で組み合わせることで現場の効率を最大化します。どちらか一方に偏りすぎず、組織の特性に合わせて導入することが成功の鍵です。
最後に覚えておきたいのは、いずれも「人と情報の流れを止めない」ことが目的であるという点です。見える化と連携を強化することで、ムダの排除と品質の安定を同時に達成できます。
ある日の放課後、友達とカンバンの話をしていた。僕はカンバンを「見える化の仕組み」と表現して、道具を使うのではなく情報の流れを整えることが大事だと語った。友達は「カードがなくてもいいんじゃないの?」と笑っていたが、実際にはカードの動きで誰が何をしているかが分かる。僕は、部活動の準備を例にして、道具の準備リストをカード化すれば、遅刻や欠席で混乱する場面が減ると説明した。雑談を続けるうちに、カンバンは単なる道具ではなく、日常の「作業の順番と連携」を整える考え方だと腑に落ちた。そんな話の中で、行動の見える化が人の協力を引き出す力になることを実感した。
前の記事: « ERPと基幹システムの違いを徹底解説|今すぐ使える選び方ガイド





















