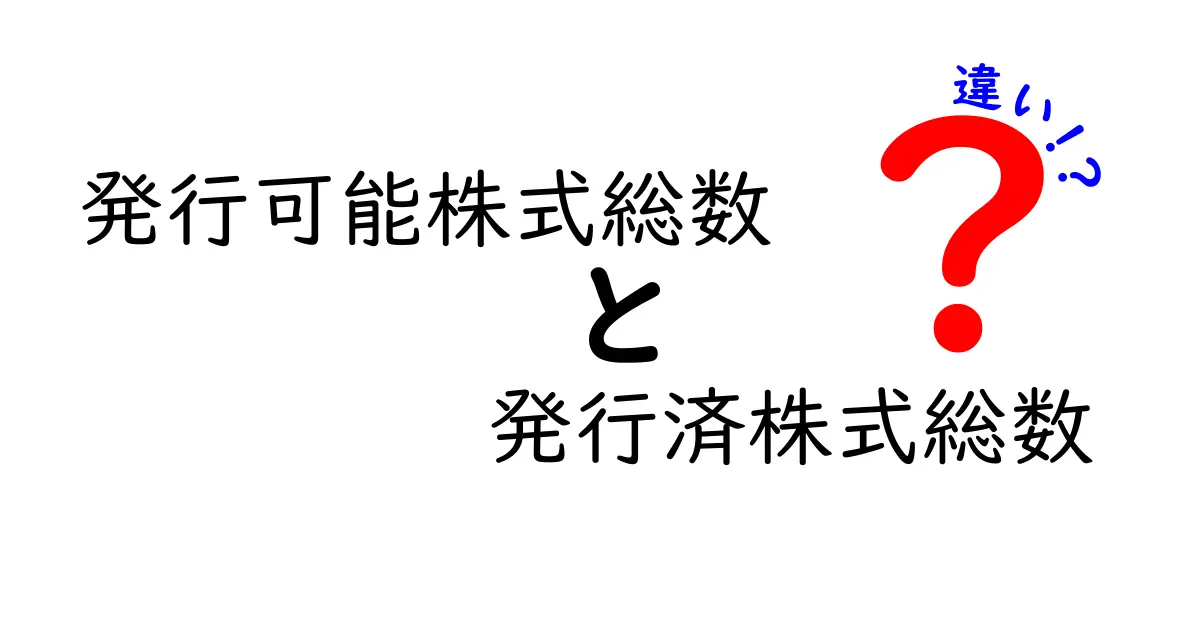

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
発行可能株式総数と発行済株式総数の違いを徹底解説|中学生にもわかる優しい図解
はじめに:株式の用語を整理する
株式の世界には難しい専門用語が多いですが、今日のテーマは「発行可能株式総数」と「発行済株式総数」です。これらは似ている言葉のようでいて、意味が全く違います。まずは前提として、会社には株式を新しく発行することができる量と、すでに市場に出ている株式の量という2つの数字が存在します。日常のニュースでも、株式数が増える話や希薄化といった言葉に触れます。これらの用語を正しく理解すると、会社の成長戦略や資金調達の仕組み、さらには株主の持ち分の影響までイメージしやすくなります。
本記事では、発行可能株式総数と発行済株式総数の意味を、難しい言い換えを避けて、身近な例と図解を使って丁寧に解説します。途中で表を使い、用語の関係を視覚的にも確認できるよう工夫します。中学生でも理解できるよう、できるだけ平易な日本語で述べます。結論を先に言えば、発行可能株式総数は「会社が新たに株を出せる可能性の総量」、発行済株式総数は「すでに市場に出ている株の実数」です。ここを押さえれば、株式の増減が意味することが段々と見えてきます。
この章では、いったん用語の定義と現実のイメージを結びつけるための基礎知識を整理します。株式の本質は「企業と株主の関係を数字で表す仕組み」だと考えると理解しやすくなります。発行可能株式総数は会社の成長計画が資金調達を使ってどう動くかを示す設計図のような役割を果たします。一方で発行済株式総数は現在の株主の持ち分割合を決める土台となります。これらの数字を組み合わせると、企業が市場にどう価値を届けようとしているのか、株主がどの程度の権利を持つのかが少しずつ見えてきます。
発行可能株式総数と発行済株式総数の違いを図解で理解する
次の図解は、現金の流れや株主の割合とどうつながるかを直感的に示しています。発行可能株式総数は会社の“未来の選択肢の量”であり、発行済株式総数は現在の“現実の株式の数”です。たとえば、A社が発行可能株式総数を1000万株、発行済株式総数を300万株と設定している場合、株を新たに発行して資金調達を行えば、発行済株式総数が増えることになります。発行可能株式総数が大きいほど、将来の資金調達の余地が広く、企業の成長戦略に柔軟性が生まれます。とはいえ、株をさらに発行すると既存の株主の持ち分が薄くなる可能性が出るため、慎重な判断が求められます。
以下の表は数字の意味を整理するのに役立ちます。表の読み方はとても簡単で、左が項目、真ん中が意味、右が日常生活のイメージです。表を見ながら、発行可能株式総数と発行済株式総数の関係が、どう株主の権利や会社の資金繰りに影響するかを思い出してみましょう。
株式の増減は企業の資金調達だけでなく、株主の権利にも影響します。例えば新株発行が増えると、既存株主の持ち分比率が低下する場合があり得ます。反対に、資金調達を適切に行えば、事業を拡大して売上を伸ばし、株価の基礎を強くする効果も期待できます。ここではそのバランスをとるための基準として、発行可能株式総数の上限は「会社の定款が決めた枠組み」であり、発行済株式総数は「実際に市場で流通している株の現実値」である、という点を特に強調しておきます。
実務上の注意点として、発行可能株式総数を増やすには株主総会の承認や法的手続きが必要です。透明性の高い情報開示と、株主に対する丁寧な説明が、信頼の基盤になります。資金調達の戦略がうまくいけば企業は事業を加速させ、投資家にとっての価値も高まる可能性があります。一方で過度な発行は希薄化リスクを引き起こし、株主の不満や株価の振れにつながることもあるため、適切な時期と量を見極めることが重要です。
実務上の影響と株主への影響
現場の観点から見ると、発行可能株式総数が大きいほど会社は資金調達の選択肢を持ちやすくなります。資金調達の目的はさまざまですが、研究開発の強化、設備投資、事業の拡大などが主な用途です。
ただし新株発行には希薄化のリスクが伴います。新株を発行して資金を得たとしても、発行済株式総数が増えれば既存の株主の株式価値は相対的に低下する可能性があるため、事前の説明責任や株主への影響の説明が重要です。企業側は発行のタイミング、発行数、価格設定、将来のリターンをどのように増やすかを明確に示す必要があります。
また発行可能株式総数を増やす前には、法的な手続きや取引市場の規則、株主総会の承認など、さまざまな工程が必要です。これらは一見難しそうですが、日常の学校生活で言えば「クラスの新しいルールを作る」というプロジェクトに似ています。新しいルールを作るには、みんなの同意と透明な説明が欠かせません。株式の世界も同じで、株主に対する情報開示と公正な方法で進めることが信頼につながるのです。
友だちと株の話をしていると、発行可能株式総数がどれだけ大きいかだけで会社の未来が変わるみたいな話が出てくる。僕は最初、それを聞いて“株ってそんなに単純に増えたり減ったりするの?”と驚いた。でも、よく考えると発行可能株式総数は“未来の選択肢の総量”であり、発行済株式総数は“現在の株の実数”だ。新株を出すと株価はどう動く?希薄化は何を意味するのか?そんな問いに、私は友人と白板に図を書きながら答えを探した。結局、最も大切なのは透明性と株主との対話だと気づいた。これを意識すると、株式のニュースを見ても“どういう仕組みで動いているのか”が見えやすくなる。





















