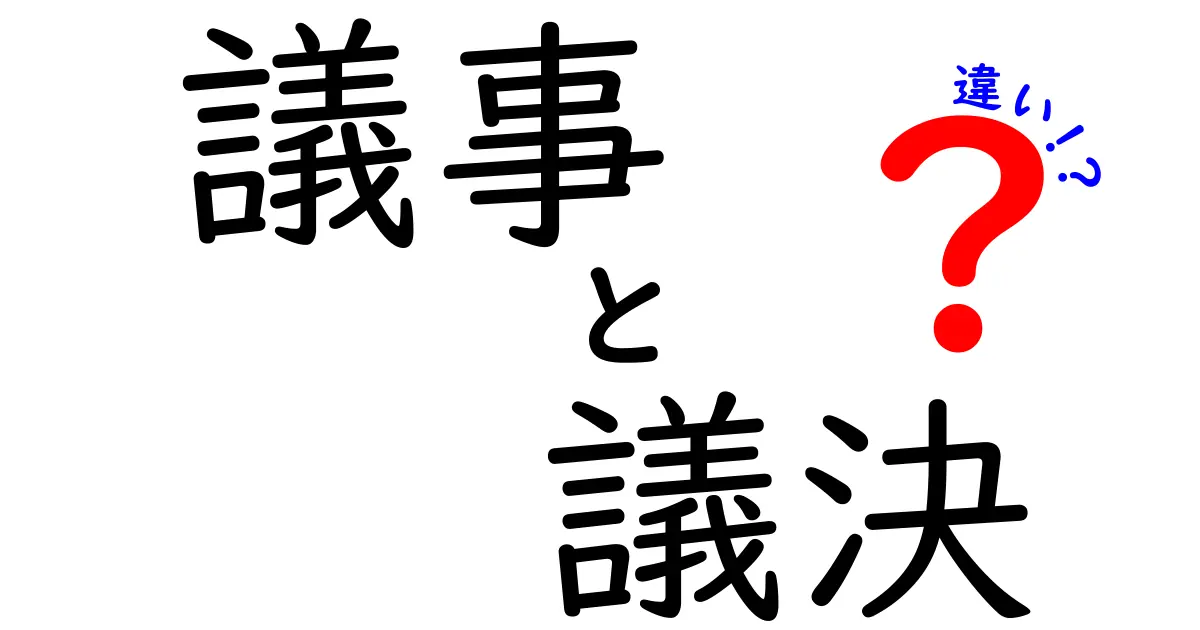

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
議事・議決・違いを徹底解説!会議の流れと意思決定のポイントを中学生にもわかる言葉で
この解説では三つの言葉の違いをわかりやすく説明します。議事とは会議の進行をつくる話し合いの流れのことです。
一方議決はその話し合いの結果として正式に結論を決定することを意味します。
つまり議事が「どう話すか」を決める作業なら、議決は「何を最終的に決めるか」を決める作業です。
この違いを理解すると学校や部活の活動、地域の集まりなどで手続きがスムーズになります。
このページでは具体的な場面と手続きの流れを順に紹介します。議事と議決の関係はつねにセットで考えると理解しやすいです。議事が不十分だと結論が出しにくくなり、議決だけが先走ると組織のルールを破ることにつながる可能性があります。
そのため会議ではまず発言の順序を整え、意見を聴取し、論点を明確化してから、最終的に全員の合意や多数決によって結論を決めるという流れを守ることが大切です。
この流れを知っておくと、あなたの意見を伝えるときにも適切な場を選べます。
議事と議決の基本を理解する
議事と議決の基本を理解するには日常の場面を思い浮かべるのが一番です。例えば学校の生徒会が新しいイベントを計画する場合、まず議題を決めて誰が何をするのかを決めます。これが議事の段階です。話し合いの中で予算の配分や日程の候補が出てくると、次は結論を出す必要があります。これが議決の段階です。結論とはイベントを実施するかどうかの決定であり、賛成か反対かの表明、もしくは条件つきの承認という形を取ります。ここで重要なのは議事は進行の手続き、議決は結論の正式な表明という点です。実際には賛否の投票や過半数の要件、定員の規定といったルールが関係してきます。これらのポイントを押さえると、誰が決定権を持つのか、そして決定の過程がどのように正当性を得るのかが見えてきます。
話をもう少し具体的に見ていくと、議事と議決の連携を理解するのに役立つ場面が増えます。たとえば部活の旅行計画では、最初に議題を出し意見を聴取します。ここが議事の場です。次に、旅行の可否と予算、日程などの条件を整理したうえで、実際に「実施します」か「中止します」といった結論を出すのが議決の場です。このように議事と議決は別々の役割ですが、連続して機能することで組織の意思決定を支えています。
この仕組みを理解しておくと、会議の場面で自分の意見を伝えるときにも、手続きの順序を間違えずに話を進められます。
違いを実務の場面で確認する
実務の場面ではこの違いを区別する訓練が役立ちます。学校の委員会や部活動の運営会議、あるいは地域の自治体の会合でも、議事と議決が混同されやすい場面があります。議事の段階で出された意見は仮の結論ではなく仮説の整理であり、議決はその仮仮説を正式に判断する行為です。賛成多数で承認されるケースが多いですが、場合によっては特別多数が必要な議題もあり、常にルールを確認しておくことが大切です。会議の最初に「この会議では何を決めるのか」という条項が明示されていると、全員が迷わず発言でき、後で混乱が生まれにくくなります。
実際の運用面では、議事録の作成も重要です。議事録には誰がどんな意見を出したか、最終的にどの結論に至ったか、結論に至るまでの条件が記録されます。これにより後日、決定の正当性を検証したり、同じ議題を再検討する際の基準として使えます。あなたが話し合いを主導する立場であっても、議事と議決を意識することで、無駄な混乱を避け、透明性のある意思決定が実現します。
表で比較してみよう
まとめとして、議事と議決の違いを表で確認すると理解が深まります。以下の表は要点を簡潔に整理したものです。
読み方のコツは、左から右へと流れを追うこと、そして結論が正式に表明されるのがどちらの段階かを区別することです。表をみると、議事は話し合いの過程を示し、議決は結論そのものを示すという点がはっきりしてきます。
この表を参照することで迷う場面が減り、どの段階で誰が何を決める権限を持つのかがはっきり分かるようになります。難しそうに見える用語も、実際には会議の実務で自然と使われる言葉です。焦らず、場面の区別を練習していきましょう。
議決という言葉を友だちと雑談していたときのこと。議決は会議の中でくだす正式な決定のことだけど、時には賛成多数で決まるだけじゃなく、反対意見を尊重して条件をつけることもあるんだよね。僕らの部活の新しい活動案でも、議事で十分な意見が出ていれば、最終的な結論はスムーズに決まる。ここで大事なのは、誰が決定権を持つのか、決定の過程はどう明記されるのか、という透明性だ。議決が正式な公認であることを理解すれば、意見を言う勇気も高まるはずさ。
前の記事: « 水溶液と溶液の違いを完全解説!中学生にもわかりやすい実例つき





















