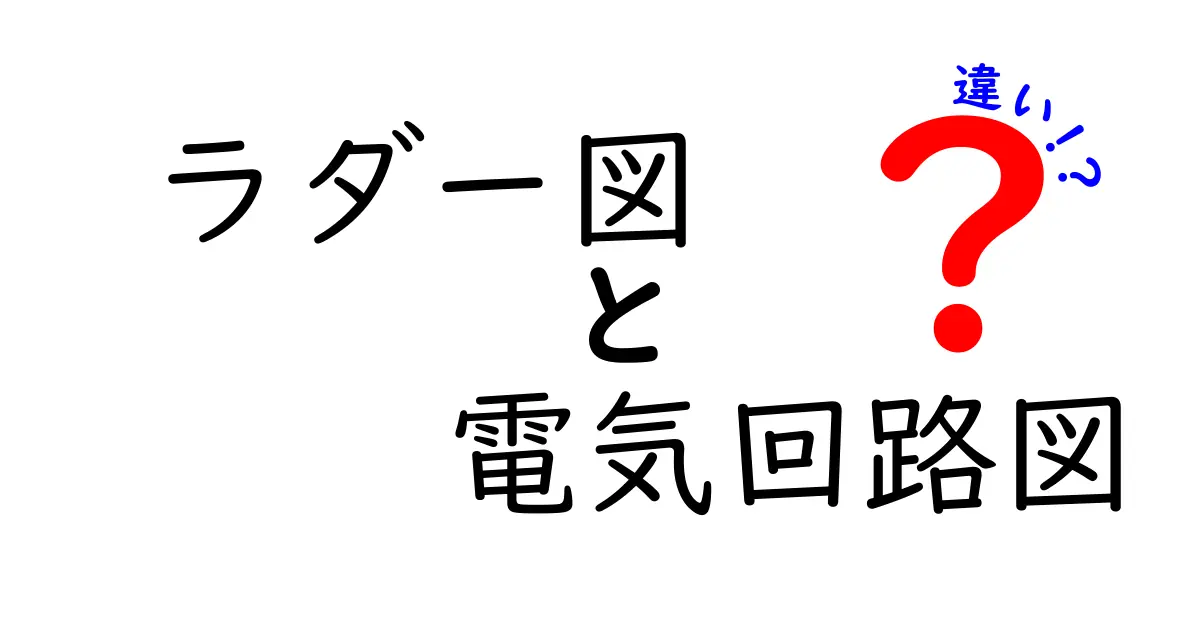

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ラダー図と電気回路図の違いを徹底解説:現場で使い分けるポイント
ここでは、ラダー図と電気回路図の違いを一緒に整理します。まず結論から言うと、ラダー図は「論理を表す設計図」で、電気回路図は「物理的な回路構成を示す図」です。ラダー図は PLC(プログラマブルロジックコントローラー)を使う自動化現場で主に用いられ、ボタンのON/OFFやセンサの信号を組み合わせて機械を動かす“動作の順序と条件”を描きます。対して電気回路図は、配線の実際の接続や部品の配置を表し、現場の電気工事や修理、設計時の部品選定に使われます。これらは同じ電気の世界にある道具ですが、視点が違います。
例えば、スタートボタンとストップボタンを組み合わせてモータを動かすとき、ラダー図では「この条件が成立したときモータをONにする」という論理を直感的に描きます。電気回路図では、モータへ電源を供給する経路、保護機器、導線の色分け、接続点の位置関係が一目で分かるように描かれます。
このように目的が異なるため、見方も読み方も変わります。ラダー図は“何を動かすか”を中心に、電気回路図は“どこへ電気をどう流すか”を中心に設計・理解されます。
ラダー図の特徴と現場での役割
ラダー図は、左から右へ“ rung”と呼ばれる横の段を流れる論理の流れを表します。主役は論理と信号の組み合わせであり、接点とコイルという基本部品を使います。接点はスイッチのON/OFFを表し、コイルは機械やモーターの動作を表します。
現場の工場では、PLCのプログラムを変更することで新しい動作条件を追加できます。例として「安全スイッチがOFFのときだけ動かさない」などの条件を、視覚的に理解しやすい形で表現します。
ラダー図の利点は、電気技術者と機械技術者の共通言語になる点です。図を見れば、配線の太さや色、接続の順序を気にせず“動作の論理”を読み取ることができます。教育現場でも、制御の考え方を学ぶ入門ツールとして広く使われています。併せて、機械がどのようなときに動くかを短い言葉で説明できる点も大きな魅力です。
電気回路図の特徴と現場での役割
電気回路図は、部品そのものの関係性を物理的な接続として表します。抵抗やコンデンサ、ダイオードなどの素子の配置、電源ラインの位置、アースの取り方、ベンチや現場の配線ルールなど、実際の電気工事や設計を支える基礎情報を含みます。
この図は“どこへ電気をどう流すか”を正確に示すことが求められ、保護機器の配置や安全距離、温度上昇の計算にも影響します。現場では、修理時にこの図を手掛かりに配線を追い、部品の故障箇所を特定します。教科書的には、部品ごとのシンボルや配線番号、電圧・電流の仕様を読み取る訓練が重要です。図面を正しく読み解ければ、設計ミスを早期に発見し、適切な部品選択と安全な施工につなげられます。
このように、現場での実務は「正確さ」と「再現性」が欠かせません。電気回路図はその核となる情報を一目で提供します。ラダー図と組み合わせて使うことで、機械がどう動くべきかというイメージを現実の回路構成と整合させることができます。
この表を見れば、どの図が何を伝えようとしているかが短時間で分かります。初学者は、まずラダー図の読み方を練習してから、実際の配線図へ移行すると理解が深まります。
また、現場の安全性を確保するためにも、図面は最新版を使い、変更履歴を追えるようにしておくことが大切です。
今日はラダー図の話を雑談風にしてみよう。実はラダー図って、子どもの頃に遊んだ“点と線の仕組み”みたいな感覚に近いんだと思う。接点がONになるとコイルが動く、それが連鎖して大きな動作につながる。自動機械の心臓みたいな PLC が、図の中の小さな回路を見つけては順序を決めていく。だから、「何を動かすか」と「どう動くか」を同時に考えられるこの図は、理系の会話を自然と盛り上げてくれる。時には難しい用語に出会うこともあるけれど、身近な例を思い浮かべれば理解の糸口が見つかるはず。私なら、ラダー図を“物語の設計図”みたいにとらえて、一つずつ接点とコイルの関係を読み解く練習をしていくと楽しくなると思うよ。
前の記事: « ガス給湯器と石油給湯器の違いを徹底解説!どっちを選ぶべき?





















