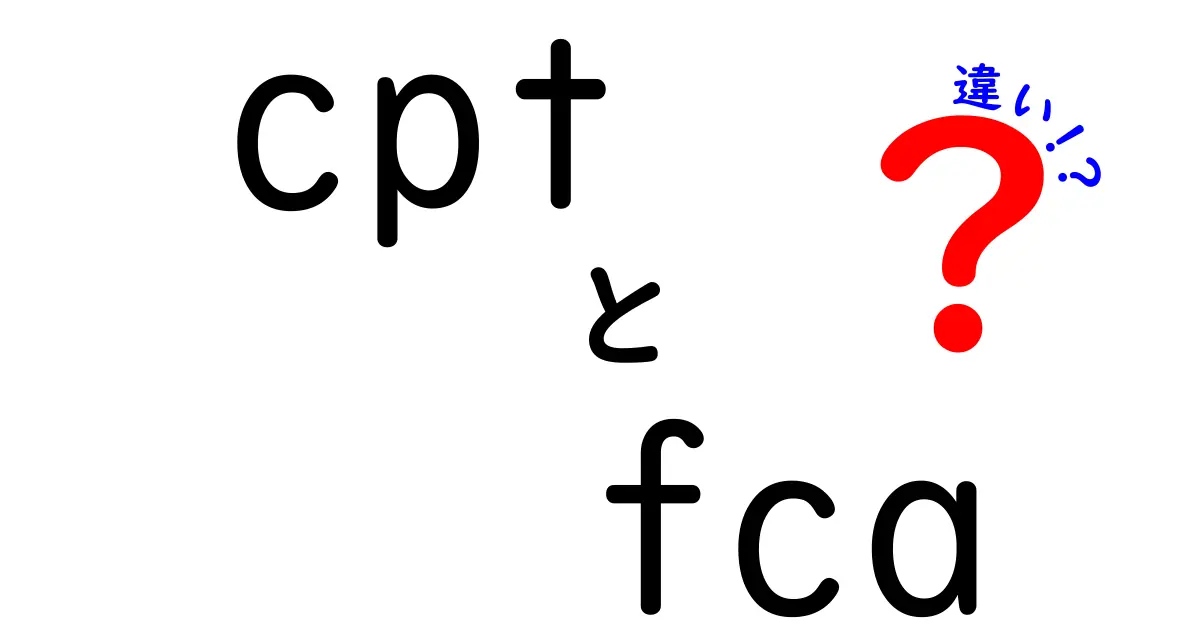

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
cpt fca 違いを徹底解説:輸出入の基礎を固める
これから輸出入の取引を学ぶ人にとって、CPTとFCAは避けて通れない重要な用語です。CPTはCarriage Paid To、FCAはFree Carrierというインコタームズの条項で、貨物を誰がどこまで運ぶのか、どの費用を誰が負担するのか、そしてリスクがいつ移るのかを整理します。最初に覚えるべきポイントは「リスクが移る時点」と「費用の負担範囲」です。
この2つがはっきりしていれば、契約書の条項を読んだときにも焦らず対応できます。なお、CPTとFCAはいずれも輸出者(売り手)が書類作成や出荷手続きを行い、輸入者(買い手)が主たる輸送の費用を負担する仕組みです。ただし、リスク移転のタイミングや適用場面には違いがあり、取引の性質によって最適な選択が変わります。
ここでは、初心者にも分かるように、基本の定義と実務での使い分け方を、具体例を交えつつ丁寧に解説します。
まず押さえるべきは「誰が何を負担し、どの時点でリスクが買い手に移るのか」です。CPTは運送費を売り手が負担して目的地まで輸送しますが、貨物が第一の運送人に引き渡された時点でリスクが買い手へ移ります。一方、FCAは名義指定の場所で貨物を運送人に引き渡した時点からリスクが移るので、リスク実務の取り扱いがやや厳密になります。これらの差を理解することが、国際取引をスムーズに進める鍵です。
CPTとFCAの基本の違いを押さえる
CPTとFCAは、どちらも「貨物が運送される際の責任と費用の分担」を明確にする条項ですが、具体的な適用方法には差があります。まず、最も大きな違いは「費用の負担範囲とリスク移転の時点」です。CPTは売り手が貨物を第一の運送人へ引き渡してから、到着地までの輸送費を売り手が負担します。つまり、輸送費用の負担が広く、最終的な配送費用の大半を売り手が支払う形になります。反対にFCAは、貨物を指定された場所で運送人へ引き渡した時点でリスクが移動します。ここが大きなポイントで、以降の輸送費用やリスクは買い手が負担することになります。
次に重要なのは「引き渡しの場所」です。CPTでは“named destination(指定された目的地)”までが売り手の責任範囲で、そこまでの運搬費用を負担します。FCAの場合は“named place(指定された場所)”で引き渡すことが求められ、ここがリスク移転の起点となります。どちらの条項を選ぶかは、取引のスピード感、輸送手段、保険の取り扱い方、さらには買い手側の物流能力に左右されます。
ここで覚えておきたいのは、保険の扱いは自動的には含まれない点です。インコタームズには保険を義務付ける条項(CIFや CIPなど)が別にあり、基本のCPT・FCAには保険は含まれません。必要なら別途保険契約を取り、貨物のリスク補償を自分で選ぶことになります。保険の要否は取引先の信用リスクと輸送経路、そして国内法規制にも左右されます。
さらに、適用分野にも違いがあります。海上輸送にも空輸にも適用できるのがCPTとFCAの特徴ですが、具体的なリスクや費用の分担が異なるため、実務では「どの場面でどちらを使うべきか」が大切な判断材料になります。
この段落の要点は、CPTは輸送費用の広範な負担を売り手が担うケースが多く、FCAはリスク移転のタイミングを重視して、発送地と引き渡し地の取り決めが明確に求められるケースが多い、という点です。
将来の契約書作成や交渉の際には、これらのポイントを踏まえて条項を具体化すると、誤解を減らしトラブルを避けやすくなります。
なお、以下の表は両者の主な違いをコンパクトに整理したものです。表だけでなく本文の説明と組み合わせて理解を深めましょう。
どんな場面で使い分けるべきか
実務では「買い手が輸送を自分で管理したい」「運送費をなるべく抑えたい」「出荷国の当局手続きにどれだけ関与したいか」などの観点で条項を選ぶことが多いです。以下の例で使い分けを考えると分かりやすいです。
1) 買い手が自社の物流網を使って輸送を確実にコントロールしたい場合: FCAを選ぶと、貨物を指定場所で引き渡して以降の運送を買い手が自由に手配できます。
2) 売り手が運送費用を負担して、指定 destination まで責任を持ちたい場合: CPTが適しています。売り手がファイナンス的にも支援をしたい場合にはこの選択が有効です。
3) 海外取引で、売買双方のリスクと費用を一定の形で分担したい場合: 条項を組み合わせることで、交渉時の折衝材料を増やすことができます。
4) 保険の取り扱いをどうするかで分かれるケース: どちらの条項でも自動的に保険は含まれません。保険の有無を契約書に明記しておくと、トラブルを未然に防げます。
5) 輸送手段が複数ある場合: 複合輸送(マルチモーダル)でも適用可能ですが、詳細な定義と責任範囲の明確化が必要です。
よくある誤解と正しい理解
よくある誤解の一つは「CPTとFCAには保険が含まれるかどうか」です。実際にはどちらの条項にも保険は自動付帯されません。保険が必要なら別途契約を結ぶ必要があります。もう一つは「リスク移転のタイミングが同じ」という誤解です。厳密には、FCAは指定場所で貨物を引き渡した時点でリスクが移動します。CPTは第一の運送人へ引き渡した時点がリスク移転の始まりですが、目的地までの輸送費用は売り手が負担します。この差を理解せずに契約を結ぶと、後で「責任の範囲が実務と異なる」というトラブルに発展します。
また、「CPTだから必ず海上輸送」という勘違いもあります。CPTは海上・航空・鉄道・道路といった様々な輸送モードに適用可能です。輸送モードに応じて、通関や保険の取り扱い、リスクの移転タイミングが微妙に変わる場合があるため、具体的な状況を踏まえて条項を選ぶことが重要です。
最後に、表現の揺れにも注意が必要です。契約書の言い回しが曖昧だと、実務での解釈が相手方と食い違う原因になります。例えば「FCA指定場所で引き渡す」など、場所の特定をはっきり書くことが、後々の争いを避ける最短ルートになります。
今日は CPT と FCA の違いについて、友達との雑談を交えながら深掘りします。CPT は売り手が運搬費用を負担して目的地まで運ぶイメージで、リスクは第一の運送人に貨物を渡した瞬間に買い手へ移ります。一方の FCA は、指定された場所で貨物を運送人に引き渡した瞬間からリスクが移ります。つまり、どこで引き渡すかが大事で、引き渡す場所が変わるとリスクの扱い方も変わります。保険はどちらの条項でも自動では入りません。だからこそ、契約書の一文一文を丁寧に読み、実務での負担とリスクをクリアにすることが大切です。身近な例で言えば、輸出者が港までの費用を全部負担してくれる CPT という選択は「費用は大幅に減るかもしれないけれど、リスクの移転時点が早い」点に注意、ということです。自社の物流体制や相手方の希望をよく聞き、どちらの条項が実務に合っているかを決めましょう。





















