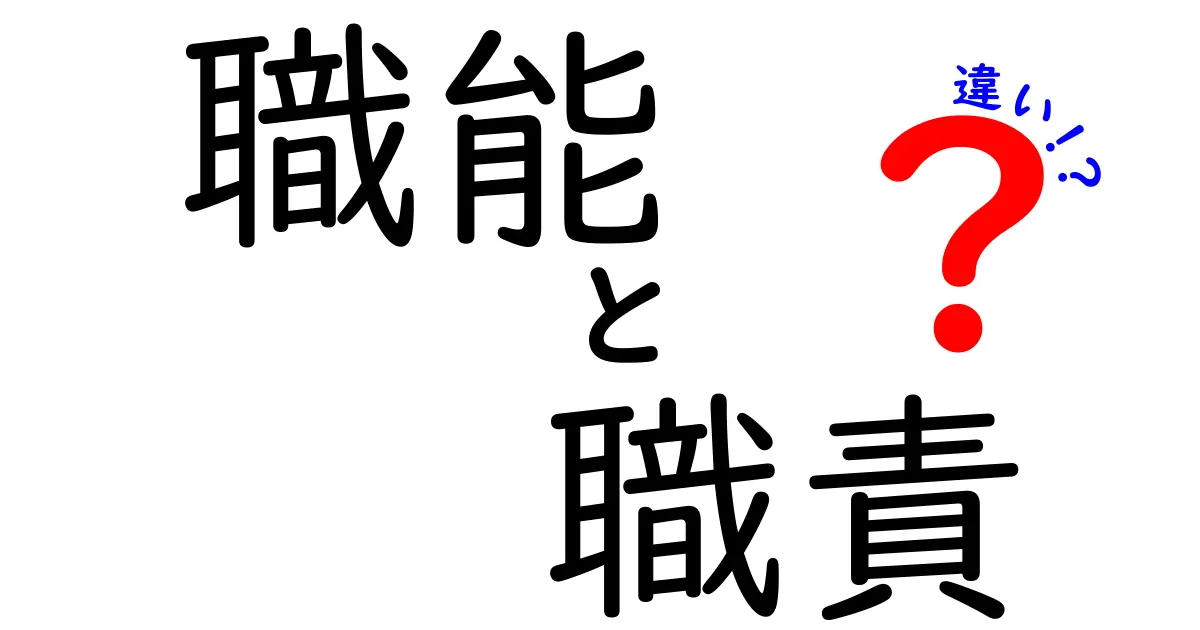

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
職能と職責の違いを理解するための基礎知識
この記事を読み進めるほど、職能と職責がどう仕事の現場で結びつくかが見えてきます。職能とは、組織が仕事を円滑に回すために求める“能力と機能の集合体”のことです。具体的には、専門知識、技術、判断力、問題解決力、コミュニケーション力、協働力、資料作成力、情報整理力など、多くの要素が含まれます。これらは個人の資質だけでなく、役割に必要な機能の組み合わせでもあります。つまり、同じ人でも担当する役割が変われば必要とされる職能も変わるのです。部活動や学校の課題でも、顧問の求める“成果を出すための手段”としての職能を理解することで、動き方が変わります。職能は“何をできるか”が中心の話であり、成果を出すための手段としての力の総称です。
この点を押さえておくと、後の節で出てくる例えが理解しやすくなります。
職能とは何か
職能とは、組織が仕事を成り立たせるために必要とする能力・機能の総称です。仕事を実際に進める力を指し、個人の性格や経験だけでなく、組織の評価基準や役割設計にも深くかかわります。たとえば、ソフトウェア開発の職能には「コードを書く技術」「設計を理解する能力」「チームで協力して作業を進める能力」「仕様を読み解く能力」「不具合を特定して修正する能力」などが含まれます。これらはすべて、業務を円滑に、正確に、効率よく進めるための道具箱のようなものです。実務では、職能が高い人ほど新しい課題に対応する力が増し、職能を組み合わせることで複雑な業務もこなせます。職能は学習と経験によって伸び、継続的なトレーニングが重要です。
また、職能は固定的なものではなく、役割や部署によって求められる組み合わせが変わる点も特徴です。例えば、同じ「技術者」という肩書きでも、研究開発と現場のサポートでは求められる技術や判断基準が異なるため、職能の重点が変化します。こうした理解は、個人のキャリア設計にも役立ちます。
職責とは何か
一方で職責は、ある役割に伴う責任と義務のことです。職責は所属する組織の中で“この人はこの役割を担い、この成果を出す責任がある”という外部に対する約束事です。具体的には、業務の遂行、期限の遵守、品質の確保、報告と連携、リスク管理、育成や後任の準備など、役職やポジションに応じて求められる範囲が決まります。部長であれば部門の方針を決定し、部下を指導・評価する責任、予算の適切な運用、部門間の連携の調整などが含まれることが多いです。中間管理職なら、目標の設定と進捗の確認、情報の透明性の確保、決定事項の伝達、トラブル時の対応などが職責として挙げられます。
このように職責は“成果の責任を誰が、どのように果たすか”を規定するものであり、評価の軸になりやすい特徴があります。職能と違い、個人の内在的な能力だけでなく、組織の目標達成に対する外部的な約束事である点が大きな違いです。
職能と職責の違いを実務で活かすコツ
職能と職責を現場でどう使い分け、どう組み合わせるかが、プロジェクトの成功を左右します。まずは、各人の職能を正確に把握して、適切な役割分担を行うことが基本です。役割に必要な職能を整理し、誰がどのタスクを担えるかを明確にします。次に、職責を共有することで、誰が何を報告し、誰が意思決定を行うのかを全員が理解します。こうすることで、会議の時間短縮や意思決定の遅延を減らせます。さらに、職能と職責の重なる領域を整理して、情報の流れと連携のルールを作ることが重要です。たとえば、コードの品質保証を担当する人の職責と、品質を評価する人の職能の間に適切な連携を設けます。最後に、状況に応じて職能の組み合わせを再配置できる余地を残すこと。新しい課題が出たとき、誰が主に対応するかを柔軟に決められる体制が、変化の激しい現代の仕事には不可欠です。
実務の現場では、職能と職責を分けて考え、互いを支え合う設計をすることで、混乱が減り、成果が安定します。
この表は、視点ごとに職能と職責の違いを視覚的に整理する助けになります。
ある日の昼休み、友達のユウと学校の課題について雑談していた。職能と職責、どちらが大事かを話していると、ユウは“職能は技術や知識のことで、職責は役割の責任を指すのかな?”と尋ねた。私は教科書の言い回しを引き合いに出しながら、こう答えた。職能は“この人が何をできるか”という能力の集合で、職責は“その人がその役割で果たすべき責任”という約束事。つまり、職能が道具箱、職責がその道具箱の使い方のルールだと説明しました。
前の記事: « 職位と職能の違いを徹底解説!混乱を解消する3つのポイントと実例





















