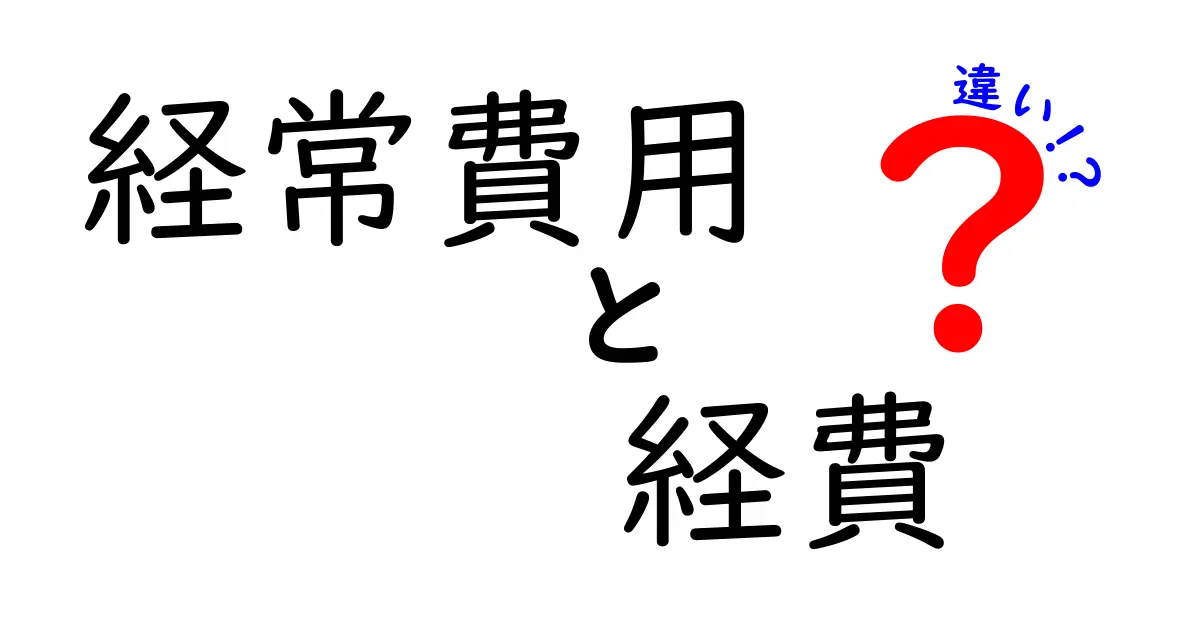

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
経常費用と経費の違いを正しく理解するための全体像
経常費用と経費は日常の会計でよく混同されがちですが、実は意味と使われ方が違います。
まず、経常費用とは日常の業務を回すために継続的に発生する支出を指します。たとえばオフィスの賃料、電気代、事務用品の購入、給与の一部、保険料などが含まれます。これらは毎月あるいは年々同じくらいの額で発生することが多く、企業の基本的な運営を支える“土台の費用”と呼ばれることがあります。
一方で、経費は支出を広く指す総称です。交通費、出張費、接待費、研究開発の備品購入など、用途が多様で一時的な支出も含みます。税務や会計の実務では、これらをどの科目に計上するか、どう区分するかがとても重要です。
結局のところ、経常費用は“日常の運営を支える費用”を意味し、経費は“支出全般の総称”として使われることが多いというのが実務上の共通認識です。
この違いを正しく理解しておくと、決算書の読み方が変わり、事業の強みや課題を外部の人に伝えやすくなります。
また、企業が成長していくと、経費の中にも戦略的な出費と非戦略的な出費が混在します。その見極めには目的・頻度・影響範囲を意識することが欠かせません。
この章の要点をまとめると、日常的な運営費は経常費用、広い意味での出費は経費として整理すると、後の財務管理が格段に楽になります。
ブレない区分をつくるためには、社内の会計基準を共有し、領収書の整理と科目の統一を徹底することが最初の第一歩です。
最後に押さえるべきなのは、費用の区分は決めつけず、用途と期間で判断することです。
これを守れば、決算を読み解く力が自然と身についていきます。
以上が経常費用と経費の基本的な違いと実務的な使い分けの土台です。
日常の場面での使い分けと具体例
実際の場面では、どう使い分けるのがよいのでしょうか。
例えば、事務用品を買うときは通常「経常費用」として計上しますが、出張費や交通費は用途や期間に応じて「経費」として扱うことが多いです。
ここでの肝心なポイントは、同じ出費でも会計上の処理が変わる場合がある点です。具体的には、短期間のものや特定の目的で発生した費用は経費として集計しやすい一方で、継続的に発生する費用は経常費用として分類する方が整理しやすいケースが多いです。
さらに資産性の高い支出は、資産として計上して減価償却の対象にするか、一定期間の費用として分割計上するかを決める必要があります。これらの判断は、社内の会計方針や税務の要件によって左右されます。
そのため、社内マニュアルと税務指針を事前に揃えることが重要です。
最後に、領収書の保存や科目の付け方の整合性が崩れると、見た目は正しくても数字の意味が薄くなってしまいます。
日々の業務で実践できるコツは、支出の用途を最初に明確に分類すること、そして月次で科目ごとの支出を見直すことです。
これを続けると、経営者にも従業員にもわかりやすい社内財務が作られていきます。
今日は小ネタです。経常費用と経費の違いを話すとき、友達との会話を思い浮かべてみると分かりやすくなります。友達Aが「この出費、経常費用に入れるべき?」と尋ねると、Bは「それは“日常の継続支出”かどうかで決まるよ」と答えます。例えば毎月同じ場所に払う家賃や光熱費は経常費用寄り。一回限りの出張費や接待費は経費として扱うのが普通です。会計では、出費の“用途と頻度”を確認して科目を決めるのが基本。結局、同じ現金の動きでも、文脈次第で見え方が変わるという小さな発見が、財務諸表を読み解く力を育てます。





















