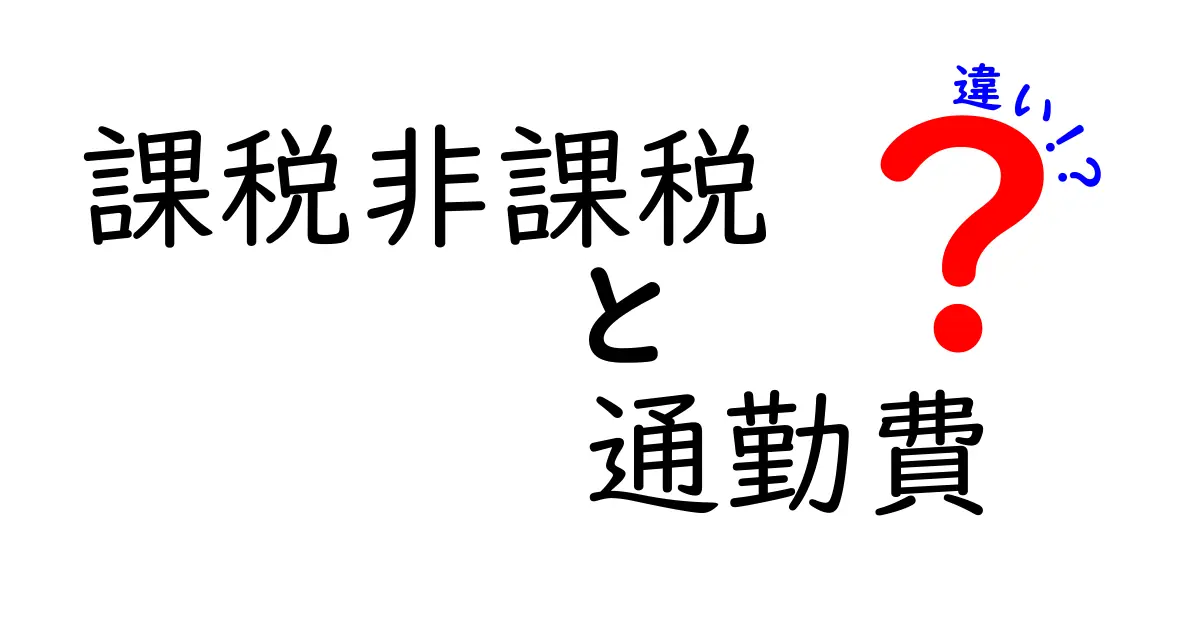

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
通勤費の課税と非課税の違いとは?
通勤費とは、会社が社員の通勤のために支給するお金のことを指します。
しかし、この通勤費には「課税されるもの」と「非課税となるもの」があります。
この違いを知らないと、所得税の計算で損をしたり余計な税金を払ってしまうことも。
課税されるか非課税かの区別は、「どのような形で支給されているか」が大きなポイントになります。
具体的には、「実費精算」か「定額支給」か、「交通費そのもの」か「通勤以外の目的も含むか」などが影響します。
ここではまず、その基本的な違いについて詳しく説明していきます。
通勤費が非課税となるケース
通勤費が非課税になるのは会社が社員の通勤にかかる実際の費用を補てんしている場合です。
例えば、電車やバスの定期券代、もしくは自動車のガソリン代や駐車場代のように、実際にかかった費用を申告して支給されるケースです。
また、通勤手当として一定の金額が支給される場合でも、国税庁が定める非課税限度額の範囲内であれば非課税となります。
2024年時点では片道の通勤距離などによって月額の非課税限度額が設定されています。
この非課税限度額を超えない範囲での通勤費は所得税がかからないのが大きな特徴です。
会社が社員の通勤負担を軽減するために認められたものなので、安心して受け取ることができます。
通勤費が課税されるケースとは?
一方で、通勤費が課税対象となる場合もあります。
例えば、現金で支給された定額の通勤費が国税庁の非課税限度額を超えた場合、その超えた分が課税されます。
また、会社が実際の通勤費とは関係なく、特別手当や福利厚生の一環として支給している場合も課税されます。
さらに、通勤以外の目的に使われる費用が含まれているケースも課税対象になるので注意が必要です。
つまり、通勤費として支給されていても使い道や支給方法によっては税金がかかることがあるのです。
課税の場合は給与と合算して所得税や住民税の計算に組み込まれますので、税負担が増す可能性があります。
通勤費の課税・非課税をわかりやすくまとめた表
ここで通勤費の課税・非課税の違いをわかりやすく表にまとめました。
ぜひご覧ください。
| 通勤費の種類 | 課税/非課税 | ポイント |
|---|---|---|
| 電車・バスの定期券代 | 非課税 | 実費支給かつ非課税限度額以内 |
| マイカー通勤のガソリン代・駐車場代 | 非課税 | 実費支給かつ非課税限度額以内 |
| 定額支給の通勤手当 | 非課税または課税 | 国税庁の非課税限度額内は非課税超過分は課税 |
| 特別手当や福利厚生費としての支給 | 課税 | 通勤以外の目的を含む場合も課税 |
このように、支給の目的や方法によって大きく違いが出ます。
正しく理解することで、無駄な税金を払わずにすみますのでぜひ覚えておきましょう。
通勤費が非課税になるかどうかは、実はとても細かいルールがあるんですよ。
例えば、定期券代を現物で支給する場合はわかりやすいけど、会社が現金で一定額を渡すときは注意が必要です。
なぜなら、国税庁が決めた非課税限度額を超えてしまうと、その超えた分には税金がかかるからです。
これって、通勤費の使い道は決まっていても、税務署は「もしかして違う使い方してるかも?」と考えるからなんですよね。
だから通勤費は単なるお金のやりとり以上に、ちゃんとルールを守ることが求められているんです。
次の記事: 単身赴任と赴任の違いとは?知っておきたい基本ポイントを徹底解説! »





















