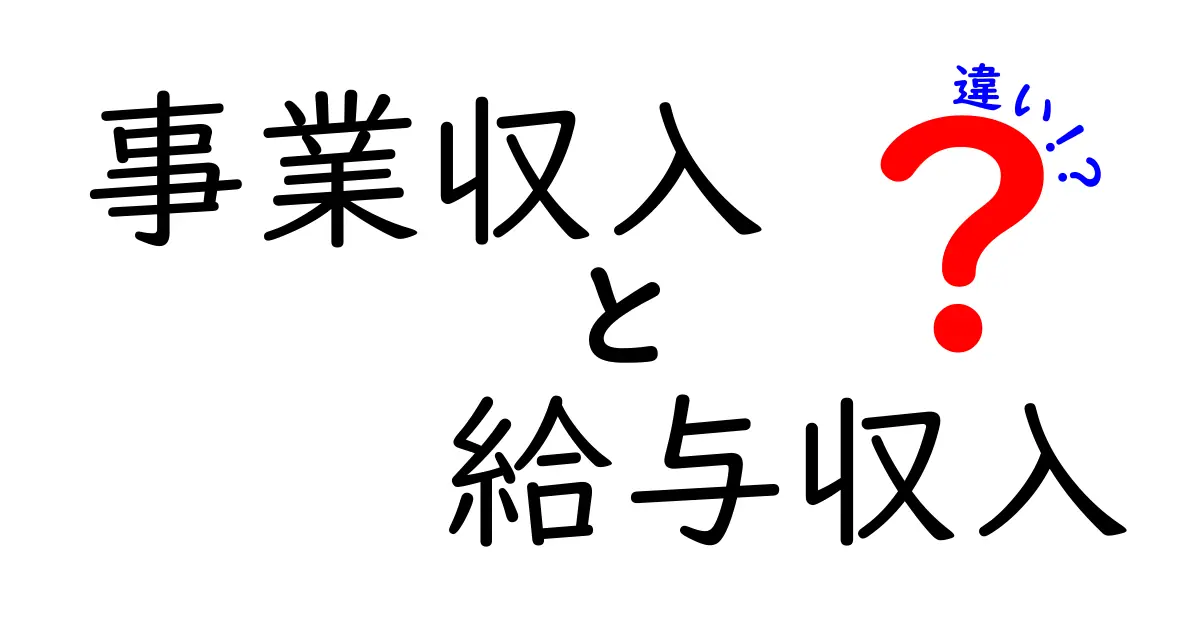

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに — 事業収入と給与収入の違いをわかりやすく解説します
みなさん、将来お金の話で困らないように、収入にはいろいろな種類があることを知っておくと役に立ちます。この記事では「事業収入」と「給与収入」という、似ているようで実は違う二つの収入について、やさしく、しかも丁寧に解説します。結論だけを先に言うと、事業収入は自分が行うビジネスの結果として生まれるお金で、給与収入は雇用主から働く対価としてもらうお金です。この違いが、税金のかかり方、社会保険の入り方、経費の計上の仕方、さらには生活の選択肢にまで影響します。たとえば「自分で店を開く」「フリーランスとして仕事を受ける」「会社で安定して働く」の三択は、それぞれにメリットとデメリットがあり、どちらを選ぶかで税金の支払い方や手取り額が変わってきます。これからの話を進めるとき、まずは基本を押さえ、次に身の回りの例を当てはめて考えると、勘違いしづらくなります。最後には、見極めのコツも紹介します。
さあ、はじめましょう。
ポイントの要点:個人が得る収入の源泉、税務の取り扱い、社会保険の加入の違いを軸に、混ざらないように整理します。
そもそも「事業収入」と「給与収入」とは何か?
まず大事なのは定義です。事業収入とは、個人が自分の事業を通じて得るお金のことを指します。サービスを提供したり、物を売ったり、オンラインでコンサルティングを行ったりといった活動の結果として得られる「売上」全体を含み、そこから必要経費を引いた残りが実際の利益になります。これを税務上の“所得”として計算します。対して給与収入は、雇用主から働く対価として受け取るお金です。給料や手当、ボーナスなどが含まれ、通常は源泉徴収され、年末には年末調整が実施されます。給与所得控除という仕組みがあり、これは働く年数や収入に応じて自動的に控除され、課税所得を決める大事な要素です。ここが大きく違う理由は、経費を自分で計上できるかどうかと、税務上の申告の仕方が違う点にあります。
たとえばイラストを依頼してもらうフリーランスの人は、パソコンの購入費用、通信費、事務用品、車両費など、仕事に直接使ったものを「経費」として計上できます。これにより所得が下がり、納める税金も少なくなることがあります。
一方、給与収入の場合は基本的に雇用主が経費を個別に負担する単純な構造ではなく、給与所得控除などの仕組みで税額が決まります。
| 比較項目 | 事業収入 | 給与収入 |
|---|---|---|
| 発生源 | 個人事業の売上・サービス提供 | 雇用主からの給与 |
| 経費計上 | 事業経費を差し引くことができる | 原則として経費計上は限定的、給与所得控除が適用 |
| 税務の計算 | 所得税+消費税等、青色申告/白色申告の選択 | 源泉徴収+年末調整、給与所得控除あり |
| 社会保険 | 任意選択で国民健康保険・国民年金に加入 | 雇用保険・健康保険・年金に加入 |
税務と社会保険の取り扱い
ここでは現実の手続きの流れを見ていきましょう。事業収入の場合、所得税の計算は「事業所得」として申告します。所得の額だけでなく、経費を差し引いた利益が課税対象になります。確定申告の有無は、所得の種類や副業の有無、給与所得の有無によって変わります。赤字が出た場合の繰越控除のタイミングや、青色申告特別控除などの制度を活用すると、納税額を減らすことが可能です。社会保険の扱いも大きく変わります。自営業の場合は国民健康保険と国民年金に自分で加入するケースが多く、保険料は所得に応じて変動します。反対に給与所得者は、会社が健康保険と厚生年金に加入させ、社会保険料は給料から天引きされる形になります。
税務と保険の管理を自分でどうするかは、将来のライフプランにも影響します。例えば、子どもの進学費用の準備や、長期的な資産形成を考えるとき、どの収入源を中心にするかで控除の額や保険の保障内容が変わってきます。
このように、税務と社会保険の取り扱いは、ただの数字の話以上に、“毎年の生活の重さ”を左右します。自分の立場に合わせて、必要な申告や保険の準備を前もって整えることが、安心した未来につながります。
実生活での影響と見分け方
日常生活で、事業収入と給与収入の違いを感じる場面はいろいろあります。まず手取り額の見え方が違います。給与所得者なら、毎月の給与から税金と保険料が引かれ、ボーナスの扱いも決まっています。一方、事業をしている人は、経費を自分で計算し、確定申告の時期に合わせて税額を自分で見積もる必要があります。次に、支出の仕方も変わります。事業を始めたばかりの人は、仕事道具の購入費用を「経費」として計上することで、税金を抑えるチャンスがありますが、それには証拠書類の整理が欠かせません。逆に給与収入だけの人は、生活費をコントロールする基本的な家計管理が重要になります。最後に、見分け方のコツとしては、収入の源泉と日常の経費の扱いをチェックすることが有効です。もし、毎月の収入が安定していて、経費の額がほとんどない場合は給与収入の可能性が高いです。反対に、売上の金額が月々変動し、経費が多い場合は事業収入の要素が強いことが多いです。
この見分け方は、家計の管理だけでなく、将来のキャリア選択にも影響します。自分でビジネスを展開したい人は、簿記の知識を少しずつ学ぶのがオススメです。基本的な領収書の整理、経費の分類、所得の計算方法を学ぶと、税務申告の際の不安がぐっと減ります。
また、学校の授業や部活動の経験も、計画性や責任感といった資質を高め、収入の管理に役立ちます。
友達と放課後の雑談で、税務の話を深掘りしました。『事業収入は自分のビジネスの成果、給与収入は働く対価』という基本を前提に、現実の場面を仮定してみると、なぜ経費を計上できるのか、社会保険の仕組みがどう違うのかがわかりやすくなります。もしも一日だけの副業で数千円の利益が出る程度なら、所得税の心配は少ないが、毎月数十万円の売上が続くようなら、青色申告の恩恵や控除を活かす価値が出てきます。最後には、将来的にどちらの道を選ぶかで“確定申告の難易度”や“保険の保障内容”が変わってくることを実感します。
前の記事: « 事業収入と営業収入の違いを徹底解説!中学生にも分かる実務の基礎
次の記事: 事業収入と所得の違いを中学生にもわかる言葉で徹底解説! »





















