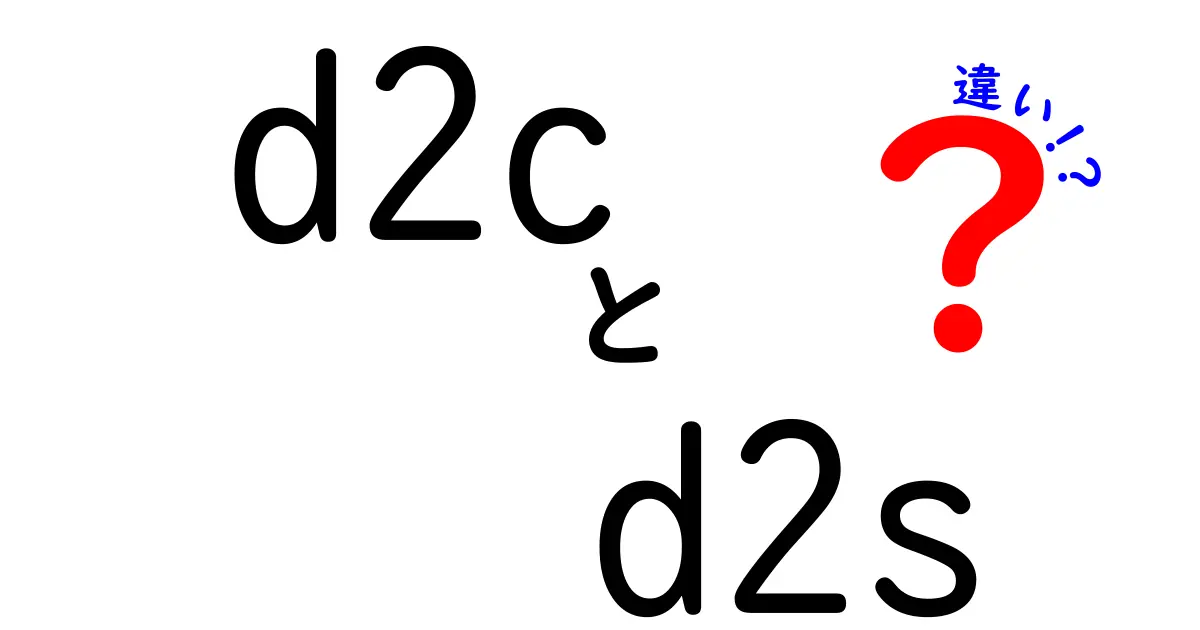

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに d2cとd2sの基本を押さえる
現代のビジネス用語の中でよく耳にする D2C と D2S は、直訳するとどちらも "Direct to" の意味ですが、指す相手や意味する関係が少し違います。D2C はブランドが消費者であるお客さんに直接商品を販売するモデルのことを指します。つまり広告費やショールームを使い、実店舗を介さずにオンラインストアなどを通して売ることが基本です。これにより、ブランドは顧客との接点を増やし、価格のコントロールや製品の情報伝達を自分たちで行います。一方、D2S は製造元が小売店へ直接商品を供給する形のモデルで、消費者とブランドの間に小売店という第三者の介在を置くことを意味します。直販ではなく店舗経由の販売になるため、在庫管理の複雑さや小売業者との契約条件、返品条件などのルールが重要になります。
この二つの違いを理解すると、どんな商品がどちらに向くのか、どのくらいの労力とコストが必要になるのかが見えてきます。ここから先では、D2C の特徴と D2S の特徴を順に詳しく見ていきます。ですから、読んでいるあなたが「自分のビジネスはどちらに近いのか」を考えるきっかけになるはずです。
まずは基本的な考え方を押さえ、次に実例と実務上のポイントへ進みましょう。
d2cとは何か
D2Cとは direct to consumer の略で、ブランドが 直接消費者へ商品を販売するモデルです。ここでの重要な点は「仲介者を減らす」ことにより、価格の透明性、顧客データの取得、ブランド体験の統一、そしてフィードバックループの短縮が実現される点です。
例えばオンラインストアを開設し、SNS で商品情報を発信し、購入までを自社で完結させる企業が多く見られます。D2C のメリットとしては、マージンの改善、ニーズの拾い上げの早さ、マーケティングの柔軟性があります。
一方デメリットは、全てを自分たちで抱える必要がある点です。ウェブサイトの運用、決済セキュリティ、配送、カスタマーサポート、広告運用、在庫管理など、やるべき仕事が山のようにあります。規模が小さいと人員や資金の制約が大きく、成長のスピードが遅くなることもあります。
この section では具体的な運用のコツを挙げます。まず顧客データを活用する仕組みを作ること、次にブランド体験を統一するデザインガイドラインを用意すること、そして物流の最適化を図ることが大切です。
また自社サイト以外のチャネルを使う場合にも、広告のROIを測ること、顧客サポートを拡充すること、リピート購入を促す仕組みを作ることが重要です。
d2sとは何か
D2Sは商品を直接消費者へ売らず、まずは小売店や取扱店舗へ供給するモデルです。小売店を介すことで、消費者の手元に商品が届くまでの距離が短くなり、実店舗での体験と接客による購買が促進されます。D2S のメリットは、在庫を分散する力が強く、地方や郊外の市場にも商品が並ぶ機会を増やせる点です。知名度が低い新規ブランドでも、百貨店や量販店の棚を使って認知を高められるメリットがあります。
また、販売チャネルが複数あることで、消費者が商品を見つける場所を拡張できます。
ただしデメリットもあり、小売店への卸値を設定しなければならず、マージンがD2Cより低くなることが多いです。さらに、店頭での販促や在庫管理、返品対応、プライスミリ mill など、取引条件をしっかり決めておく必要があります。
このセクションでは、店舗との契約形態、卸値の設定方法、棚割りの工夫、そして販促の協業のコツを紹介します。小売の顔となる店員さんへの教育も大切です。
どちらを選ぶべきかの判断ポイント
結局、d2c か d2s かは商品特性、ブランドの規模、資金力、そして狙う顧客体験によって変わります。
まず、製品の独自性が高く、ブランド体験が重要で、顧客データを武器に成長させたい場合は D2C が有利です。次に、地方市場で幅広く安定的に展開したい、在庫を分散させたい、あるいは話題性の高い商品を短期間で知名度を上げたいときは D2S が適しています。
また、資金が豊富で、ウェブサイトの運用と広告運用に自信があるなら D2C は大きなリターンを生む可能性があります。一方で、既に強い流通網がある、店舗での実演・体験が購買を後押しする商品なら D2S の方が現実的です。
この二つのモデルはお互いに排他的ではなく、実際には併用する企業も増えています。たとえば新製品を D2C で市場デビューさせ、人気が出たら D2S の流通を拡大して全国へ展開する、という戦略も有効です。
ねえ、D2Cって結局どういうことか分かる? 直販モデルだからブランドが直接お客さんとやり取りするんだ。オンラインで商品を紹介して販売までやるので、広告やSNSの力がすごく大事になる。でもその分、ウェブサイトの運用やカスタマーサポートも自分たちで頑張らないといけない。D2Sは小売店を通すので、棚に並ぶまでの道筋が長くなる分、店頭の人の説明力や地域の流通網が大事になる。どちらも一長一短だから、商品がどんな体験を提供したいかで選ぶのがいちばん大事なんだ。例えば新商品で話題性を作りたいときは D2C、安定した流通網で全国に広げたいときは D2S、という風に使い分けるといいよ。
前の記事: « btocとd2cの違いを徹底解説!初心者にも分かる3つのポイント





















