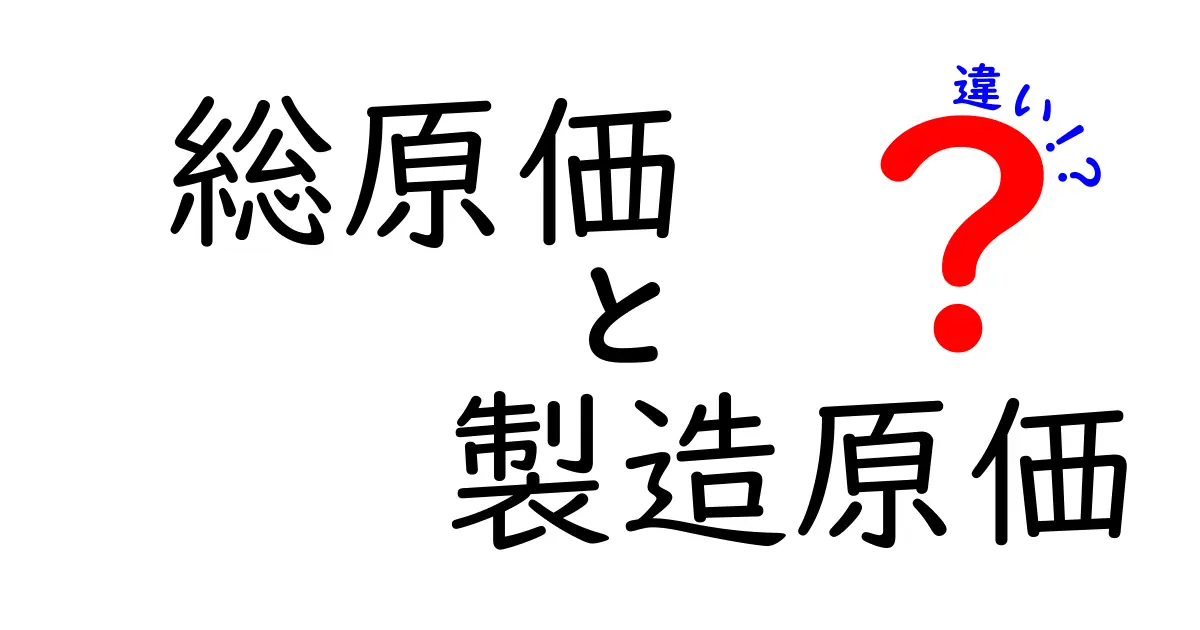

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
総原価と製造原価の違いを理解するための前提
総原価と製造原価は、会計や経営の世界でよく使われる用語ですが、学校の授業や現場では混同されやすい2つの考え方です。どちらも「コスト = 費用」の話ですが、対象の範囲と目的が異なります。総原価は企業が期間中に使ったすべての費用を含む概念で、製品だけでなく販売費、管理費、設備投資、減価償却などを含みます。これに対して製造原価は製品を作る過程で発生する費用に焦点を当て、原材料費・直接労務費・工場の間接費など、製造に直接結びつく費用を集計します。
この広い対象範囲は、経営判断をする際に「資金の使い道をどう配分するか」を決める土台になります。総原価の把握は、資金繰り、投資計画、部門間の資源配分の見直し、長期的な事業戦略の検討に欠かせません。
しかし、あまりに広い範囲を扱うと、個々の製品がどの程度の負担を抱えているかが分かりにくくなる難点があります。そこで通常は、総原価を使う際にも、製品別の原価と管理のための追加指標を併用します。
ここから先は、総原価と製造原価の本質を順を追って詳しく見ていきます。まず「総原価とは何か」を定義し、対象範囲を具体例で確認します。次に「製造原価とは何か」を、直接費と間接費の仕分けとともに考えます。最後に、実務での使い分け方と、実務上よくある混乱点を整理します。読者が学校の課題だけでなく、現場でも迷わないよう、できるだけ分かりやすい具体例と図解のイメージを添えて説明します。
この章を読むと、総原価と製造原価が別々の目的で使われる“道具”だと分かります。総原価は企業の全体像をつかむための視点、製造原価は製品の価値を測るための視点です。両者を正しく分けて使い分ければ、原価管理はより正確で、価格設定や意思決定がしやすくなります。つまり、財務諸表の読み解きだけでなく、日常の現場判断にも役立つ「使える知識」になるのです。
総原価とは何か?対象と考え方を詳しく解説
総原価とは、企業が一定期間に支出したすべての費用の総和を指す概念です。ここには製品の原価だけでなく、販促費、広告費、事務所の家賃、光熱費、役員報酬、減価償却、研究開発費、借入金の利息など、直接関係していないように見える費用も含まれます。
この広い対象範囲は、経営判断をする際に「資本の使い道をどう配分するか」を決める土台になります。総原価の把握は、資金繰り、投資計画、部門間の資源配分の見直し、長期的な事業戦略の検討に欠かせません。
しかし、あまりに広い範囲を扱うと、個々の製品がどの程度の負担を抱えているかが分かりにくくなる難点があります。そこで通常は、総原価を使う際にも、製品別の原価と管理のための追加指標を併用します。
総原価の実務上の扱い方のコツとしては、まず期間内の全費用を集計して“何にいくら払ったか”を把握すること、次に製品別の原価と結びつけるための分解を行うことです。これにより、「製品の価格にどの程度の販促費が含まれるべきか」「管理部門の費用をどう扱うべきか」といった、現場の意思決定に直結する情報を引き出せます。
また、総原価は財務諸表の分析にも使われ、会社の資金の健全性を判断する手掛かりになります。
製造原価とは何か?直接費と間接費の違いを整理
製造原価は、製品を作る過程で直接的に発生した費用と、工場全体の運営に関わる費用を合計したものです。ここには原材料費、直接労務費、直接経費といった“製品に直接紐づく費用”に加え、間接材料費、間接労務費、工場の家賃・光熱費・設備保守費など“製造過程全体にかかる費用”が含まれます。
この仕分けは、原価計算の基本となり、在庫評価や原価率、利益率の分析に直結します。
製品が売れる前の段階でどれだけのコストがかかるかを知ることで、価格設定の基礎を作ることができます。
製造原価の計算は、正確な配賦が求められます。直接費は製品ごとに追跡しやすいのですが、間接費はどの製品にどの程度配分するかが論点になります。配賦基準には生産量、作業時間、床面積、機械稼働時間などが使われ、これらを適切に選ぶことで公平で実務に適した原価を算出します。
また、製造原価は在庫評価の核となるため、期末の在庫が多いほど総原価と製造原価の差異が大きくなることがあります。この点も理解しておくと、決算時の解釈がスムーズです。
総原価と製造原価の明確な違いと実務での使い分け
総原価と製造原価の本質的な違いは、対象の範囲と目的にあります。
総原価は企業全体の費用を含む広い概念で、資金繰り、財務状態の把握、長期戦略の材料となります。対して製造原価は製品を作る過程に限定し、在庫評価・原価管理・価格設定の核となる指標です。
実務では、まず製造原価を正確に算出して、製品別の原価感覚を養います。その上で、販管費や管理費を含む総原価とセットで見比べ、全体の効率を評価します。この組み合わせにより、費用の無駄を減らし、利益を最大化する意思決定がしやすくなります。
また、変動費と固定費の区別も重要です。製造原価のうち変動費は生産量に比例して増減しますが、固定費は生産量に関係なく一定です。これを理解すると、販売の伸びに合わせた最適な生産計画を立てやすくなります。
総原価の話題で友だちとカフェにいたときの出来事を思い出す。店のコーヒー代や机のレンタル費、スタッフの給料、そして友だちが新しいノートを買ったお金まで、すべてを見渡して“総原価はその期間に使った全てのお金の総和”だと理解した瞬間、教室の黒板に書かれた式以上に実感が湧いた。製造原価は“作る過程の費用だけ”という点がカギだと気づく。こうした日常の場面が、難しい言葉を身近なものにしてくれるのだと感じた。





















