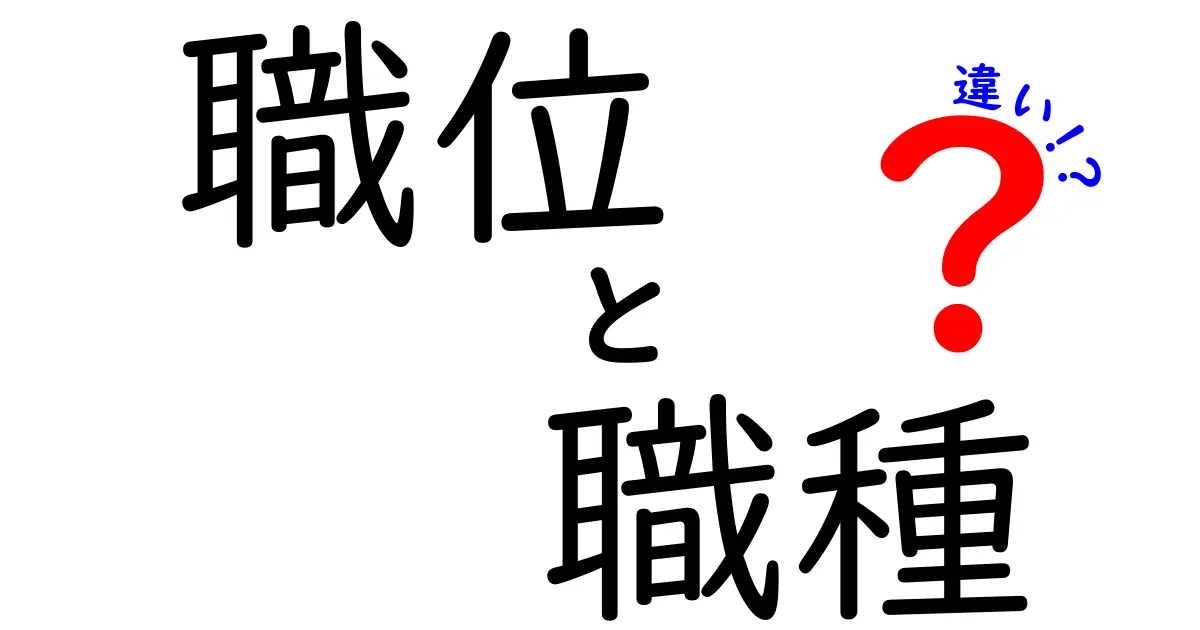

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに—なぜ「職位」と「職種」の違いを知るべきか
新卒の就活や中途採用のとき、履歴書にはよく「職位」や「職種」という言葉を見かけます。しかし、両者の意味は似ているようで異なります。職位は組織の中の地位・権限・階層を表し、職種はその人が日々何をする仕事の種類を指します。違いを理解していないと、応募先の求める人材像と自分のキャリアがズレてしまうことがあります。この記事では、中学生にも分かるように、具体的な例と比較、そして実務での使い分けのコツを紹介します。
まずは基本を押さえ、次に実務での活用法、そして就職活動時の具体的な見方へと進んでいきます。
職位は組織の中の階層と権限を示す指標であり、昇進や給与の決定にも影響します。例えば、部長、課長、係長などの名称は、誰が何を決められるかを表す境界線です。部長クラスは予算の承認や方針の決定など大きな裁量を持ち、部門の方向性を作ります。一方で同じ部門でも、職位が低い人は日々のルーティン業務やチームのサポート寄りの役割を担います。ここで重要なのは、職位が「誰が何を決めるか」という点に影響を及ぼすということです。
職種は日々の作業の内容を指す概念で、営業、開発、人事、経理など、具体的な業務の種類を表します。職種はスキル・知識・ツールの要件と直結しており、同じ部門でも職種が違えば現場の動き方や評価指標が変わります。例えば、同じ部門の営業と開発では求められる能力が大きく異なるのです。
このように、職位と職種は別々の軸でキャリアを語るものです。履歴書や職務経歴書を書くときには、次の3点を意識すると混乱を避けられます。1) 募集要項の職位と職種を分けて読み解く。2) 自分の強みがどの軸に合致するかを整理する。3) 転職時は昇進の機会や配置転換の可能性も考慮して、将来のキャリア像を描く。これらを意識するだけで、応募先の理解が深まり、面接時の自己PRも説得力を増します。
職位とは何か?その役割と例
ここでは職位の基本的な意味と、具体的な例を深掘りします。
前述のように、職位は組織内の地位・裁量・責任の度合いを示します。部長・課長・係長といった名称は、組織のとりまとめ役としての役割を表す「階層の標識」です。
この標識があることで、他のメンバーが誰に判断を委ねられているのか、誰が予算を決められるのか、どの程度の意思決定が可能かを理解しやすくなります。
具体的な例を見ていきましょう。部長は通常、部門全体の戦略と予算、人事の大枠の方針を決定します。課長は部門内の複数チームを統括し、日々の業務の進捗を管理します。係長はチームの現場での実務をコントロールし、後輩の育成も担当します。ここで重要なのは、同じ部門内でも職種が違えば現場の動き方や評価指標が変わる点です。
職位はまた、昇進の道筋と給与の設計にも影響します。昇進は通常、現行の職位より上位の職位へと移ることを意味しますが、同じ職位でも別の職種で働く場合は評価の観点が異なります。たとえば、営業部の課長と開発部の課長では、求められる成果指標が全く別です。これを理解しておくと、キャリアパスを描く際に現実的な目標を設定しやすくなります。
職種とは何か?その役割と例
次に職種の意味と、どんな仕事が該当するかを詳しく見ていきます。
職種は「どのような業務を担当するか」を表し、具体的な仕事内容や専門性に直結します。たとえば、営業は顧客と話をして商品を売る活動全般を指し、開発はソフトウェアやシステムを作る技術的な作業を意味します。
この違いがあるからこそ、同じ部門の人でも日々の業務内容や求められるスキルは大きく異なるのです。
職種は教育・研修・資格の有無、使うツールや言語、達成すべきKPIなど、評価の軸が多岐にわたります。職種ごとにキャリアパスの道筋が分岐し、転職市場での競争力にも影響します。たとえば、マーケティング、経理、人事、IT開発などがあり、それぞれのスキルセットや学習コスト、成長の速度が違います。ここで覚えておきたいのは、職位と職種が必ずしも同じ方向を向くとは限らないという点です。
キャリア設計では、この両軸を別々に、時には組み合わせて評価することが大切です。
最後に、実務での使い分けのコツを整理します。
・求人票や社内規程で「職位」と「職種」を別々に読み解く。
・自分の強みと将来の目標に合わせて、どちらを重視するかを決める。
・昇進・配置転換のイメージを描くことで、現職での学習計画を作る。これらのポイントを押さえると、将来のキャリア像が現実的に見えてきます。
また、実際の企業では、同じ職位でも部門や事業ごとに求められる能力が異なることを忘れずに。雇用契約や評価制度をよく読み解き、自分の希望と現実のバランスを取りながら進むことが重要です。
今日も友だちとキャリアの話をしていて、ふと職位と職種の違いにぶつかったんだ。友だちは「同じ部門の人なのに仕事の中身がぜんぜん違うね」と言い、その理由を私の方が説明する番。
私: 「部長って役職で、"誰に何を決める権限があるか"を指す。職種は"営業"や"開発"といった"仕事の中身"のことだよ。」と続けると、友だちは目を輝かせた。
結局、職位は組織の階層と権限、職種は日々の業務の種類というふうに、別の軸でキャリアを考えると理解が深まるんだ。
次の記事: 職位と職能の違いを徹底解説!混乱を解消する3つのポイントと実例 »





















